
・遺族年金と老齢年金どっちを選べばいい?
・老後の生活が不安…どうしたらいいの?
なんてお悩みではありませんか?
結論、遺族年金と老齢年金どっちを選べばいいかは、子どもの有無や収入・納付状況など、各人が置かれている状況によって異なります。
65歳以降は2つの年金を併給することもできますが、併給調整によって実際の受給額は減ることも。老後の生活費は年金だけでなく、自助努力でまかなう必要があります。
そこで本記事では、遺族年金と老齢年金どっちを選ぶかの判断ポイント、遺族年金と老齢年金どっちももらえる2つのケース、老後の資金形成が不安な人が取るべき対策を紹介します。
最後まで読めば、遺族年金と老齢年金の違い、どっちか選ぶ際の判断ポイントがわかりますよ!ぜひ参考になさってください。

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 遺族年金と老齢年金どっちか選べるのは60歳から65歳未満!選び方のポイントを解説
- 遺族年金と老齢年金を選べるのは60歳から65歳の間だけ
- 遺族基礎年金を優先した方がいい人
- 老齢基礎年金を優先した方がいい人
- 遺族年金と老齢年金どっちか迷ったらFPへの相談がおすすめ
- 65歳以降は遺族年金と老齢年金どっちももらえる?2つのケースを解説
- 老齢基礎年金と遺族厚生年金がもらえる人
- 老齢厚生年金と遺族厚生年金がもらえる人
- 遺族年金と老齢年金どっちを選んでも将来が不安な人が取るべき対策4つ
- ねんきん定期便をチェックし年金額を確認する
- 寡婦加算など制度の理解を深める
- iDeCoや新NISAなど自助努力で備える
- 働き方やライフプランを見直す
- 遺族年金と老齢年金の不安や悩みはマネーキャリアと解決してみませんか?
- 【まとめ】遺族年金と老齢年金は「どっちを選ぶか」より「どう備えるか」が大切
遺族年金と老齢年金どっちか選べるのは60歳から65歳未満!選び方のポイントを解説

遺族年金と老齢年金、どっちかを選んで受給するケースは少ないもの。
しかし、60歳~65歳の間には「遺族基礎年金」と「老齢基礎年金」のどちらかを選ぶ場面に迫られる方もいらっしゃいます。
どっちかを選ぶか検討する前に、まずは両制度の特徴を以下の表で把握しましょう。
▼遺族年金と老齢年金の違い
| 項目 | 遺族基礎年金 | 老齢基礎年金 |
|---|---|---|
| 受給資格 | 18歳到達年度の末までの子どもがいる 配偶者または子ども本人 | 60歳以上で保険料納付済期間などの 条件を満たした人 |
| 年額 (令和7年度) | 83万1,700円+子の加算あり (1人目・2人目:各239,300円) | 83万1,700円(満額) ※納付期間により減額あり |
| 併給可能な年金 | 遺族厚生年金と併給可能 | 遺族厚生年金と併給可能 (ただし65歳までは支給停止・65歳以降も併給調整あり) |
| 課税扱い | 非課税 | 課税対象(雑所得) |
遺族基礎年金と老齢基礎年金、どっちに特があるかは納付状況や働いてきた期間など、さまざまな要因によって異なります。以下で詳しく解説していきます。
- 遺族年金と老齢年金を選べるのは60歳から65歳の間だけ
- 遺族基礎年金を優先した方がいい人
- 老齢基礎年金を優先した方がいい人
遺族年金と老齢年金を選べるのは60歳から65歳の間だけ
60~65歳の間は、60歳以上で条件を満たした方が受け取れる「老齢基礎年金」、子どものいる配偶者(または子ども本人)「遺族基礎年金」、2つの年金の受給資格が発生します。
給付事由が異なる2種類の年金を同時に受けることはできないため、どっちかを選択しなくてはなりません。
遺族基礎年金を優先した方がいい人
18歳未満の子どもがいる(45歳前後で出産した)方は、遺族基礎年金を受け取れる可能性があります。
子どもの人数に応じて加算があるため、子どもが複数人いる方は遺族基礎年金の方が得が大きいでしょう。
さらに、遺族基礎年金は非課税、かつ遺族厚生年金と併給可能というメリットも。確定申告などの必要もありません。
老齢基礎年金を優先した方がいい人
老齢基礎年金は納付実績に応じて受給額が増えるため、未納などがなく納付状況に問題がない場合は特に有利です。
ただし、老齢基礎年金を60~65歳の間に受給するということは、繰り上げ受給する(特別支給を受ける)ということ。
この特別支給の間は受給資格があっても遺族厚生年金の支給が停止される点に注意しましょう。
遺族年金と老齢年金どっちか迷ったらFPへの相談がおすすめ

60~65歳の間は「老齢基礎年金」「遺族基礎年金」、2つの年金の受給資格を得る方もいらっしゃいます。ただし、支給要件の異なる年金は併給できないため、どちらかを選ぶことに。
すると、「自分はいくら受け取れるのか」「どっちを受け取った方が得が大きいのか」複雑な年金の仕組みに不安を感じる方も少なくありません。
とくに遺族基礎年金を受け取っていて子どもの独立後に年金額が大きく下がる方は、今のうちから備えが必要。
年金制度に関する疑問や受け取り方の戦略は、年金に詳しいFPに相談するのが確実です。

65歳以降は遺族年金と老齢年金どっちももらえる?2つのケースを解説

60~65歳の間は遺族年金と老齢年金、どっちかしか受給できません。しかし、65歳以降は2つの年金を併給できる場合も。
ただし、全額もらえるとは限らないため「併給調整」に注意が必要です。
- 老齢基礎年金と遺族厚生年金がもらえる人
- 老齢厚生年金と遺族厚生年金がもらえる人
老齢基礎年金と遺族厚生年金がもらえる人
自身で国民年金に加入していた方は、65歳から老齢基礎年金の受給が始まります。
また、自身に厚生年金の加入歴がなければ老齢厚生年金はもらえませんが、厚生年金に加入していた配偶者が亡くなった場合は、遺族厚生年金を受給可能。
この場合「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」を併給調整なしで満額受給できます。
老齢厚生年金と遺族厚生年金がもらえる人
ただし、遺族厚生年金に関しては自身の老齢年金の差額分だけ支給される「併給調整」が行われることとなります。
遺族年金と老齢年金どっちを選んでも将来が不安な人が取るべき対策4つ

遺族年金と老齢年金、制度上の縛りも多く、いずれを選んでも将来の生活に不安を抱える人は少なくありません。
老後資金は年金制度だけに頼るのではなく、自分で備える意識が大切。ここでは、具体的にできる4つの対策を紹介していきます。
- ねんきん定期便をチェックし年金額を確認する
- 寡婦加算など制度の理解を深める
- iDeCoや新NISAなど自助努力で備える
- 働き方やライフプランを見直す
ねんきん定期便をチェックし年金額を確認する
寡婦加算など制度の理解を深める
寡婦加算とは一定の条件を満たした遺族厚生年金の受給者に加算されるもの。40歳~65歳までの「中高齢寡婦加算」と65歳以降の「経過的寡婦加算」があります。
他にも児童扶養手当や生活支援給付など、支援制度を理解すれば他にもらえるお金がある可能性も。
自治体の窓口や年金事務所、FPへの相談を通じて自分が利用できる制度を確認しておきましょう。
iDeCoや新NISAなど自助努力で備える
運用益が非課税となる、所得税控除が受けられるといったメリットがあるほか、老後資金を自分で積み立てることで、「もらえるかわからない」不安を軽減できます。
特に非課税で長期運用できる新NISAは、老後資金づくりに大いに活用できるでしょう。
働き方やライフプランを見直す
たとえば、定年後も働き続けることで老齢年金を繰り下げたり、在宅ワークに切り替えることで支出を抑えるといった選択肢もあります。
家計・働き方・年金の受け取り方など、老後のお金の問題・ライフプランを整理するなら、資産形成のプロであるFPに相談するのが近道です。
遺族年金と老齢年金の不安や悩みはマネーキャリアと解決してみませんか?

遺族年金と老齢年金など、年金制度は大変複雑。独学で自分にとってのベストな選択をするのは至難の業です。
どっちを受け取るか決めあぐねているうち、子どもが独立するタイミングで遺族年金が減額されてしまい、不安を感じる方も多くいらっしゃいます。
老後へ向けた資産形成が不安なら、年金はもちろん、家計や働き方、今後の資産運用まで含めて相談できるマネーキャリアを利用してみましょう。
対応するのは年金や老後のお金に特化したFPのみ。ぜひご利用ください。
【まとめ】遺族年金と老齢年金は「どっちを選ぶか」より「どう備えるか」が大切
本記事では、遺族年金と老齢年金どっちを選ぶかの判断ポイント、遺族年金と老齢年金どっちももらえる2つのケース、老後の資金形成が不安な人が取るべき対策を紹介しました。
<結論>
60〜65歳の一部の方は、遺族基礎年金と老齢基礎年金、どっちを受給するか選ぶ必要があります。
65歳以降は2つの年金を併給ができますが、併給調整によって実際の受給額は減ることも。どっちが得かは、子どもの有無や収入・納付状況など、各人の事情によって異なります。






























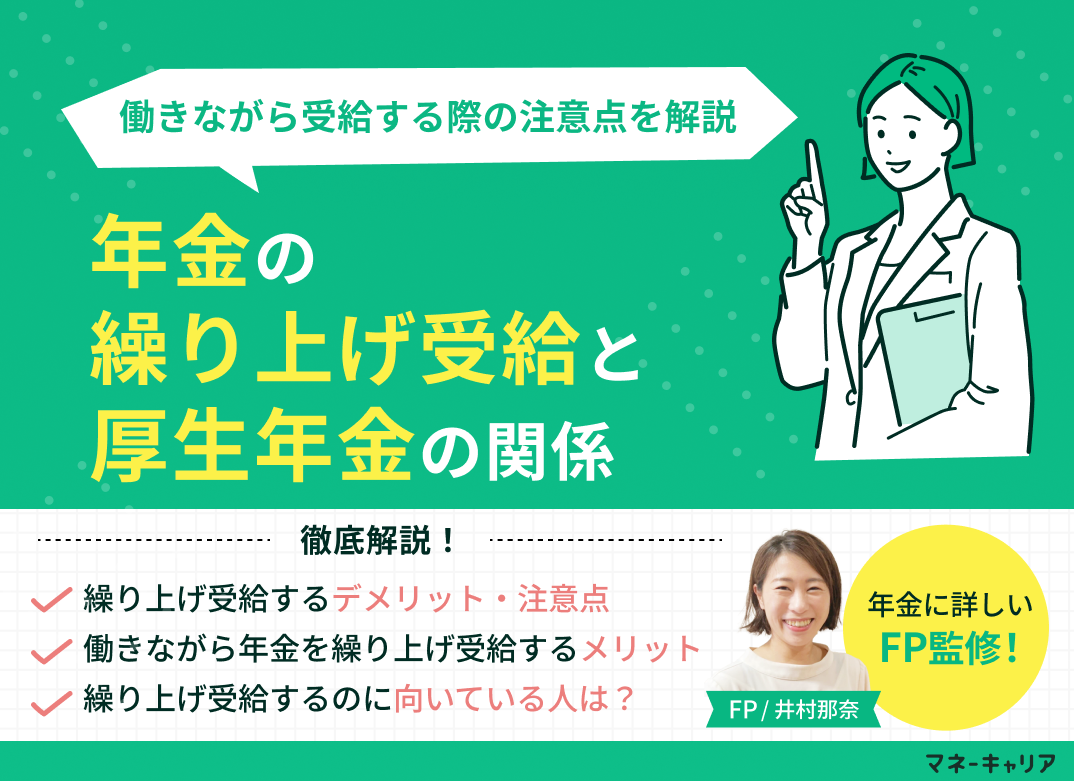
✔︎ 遺族年金か老齢年金、どっちを受け取るかプロと一緒に検討できる
✔︎ 自分に最適な老後の資産形成方法がわかる
✔︎ 相談満足度は業界高水準の98.6%
✔︎ 累計の相談申込件数100,000件突破
✔︎ FP資格取得率100%
✔︎ 3,500人以上のFPの中から厳選されたプランナーのみ対応
✔︎ 公式WEBサイトでFPのプロフィール、口コミ、経歴を確認できる
✔︎ LINEで気軽に予約・日程調整できる
✔︎ 土日祝日も相談OK
✔︎ オンラインか訪問か、都合のいい相談形式を選べる
✔︎ 何度でも無料で相談できる