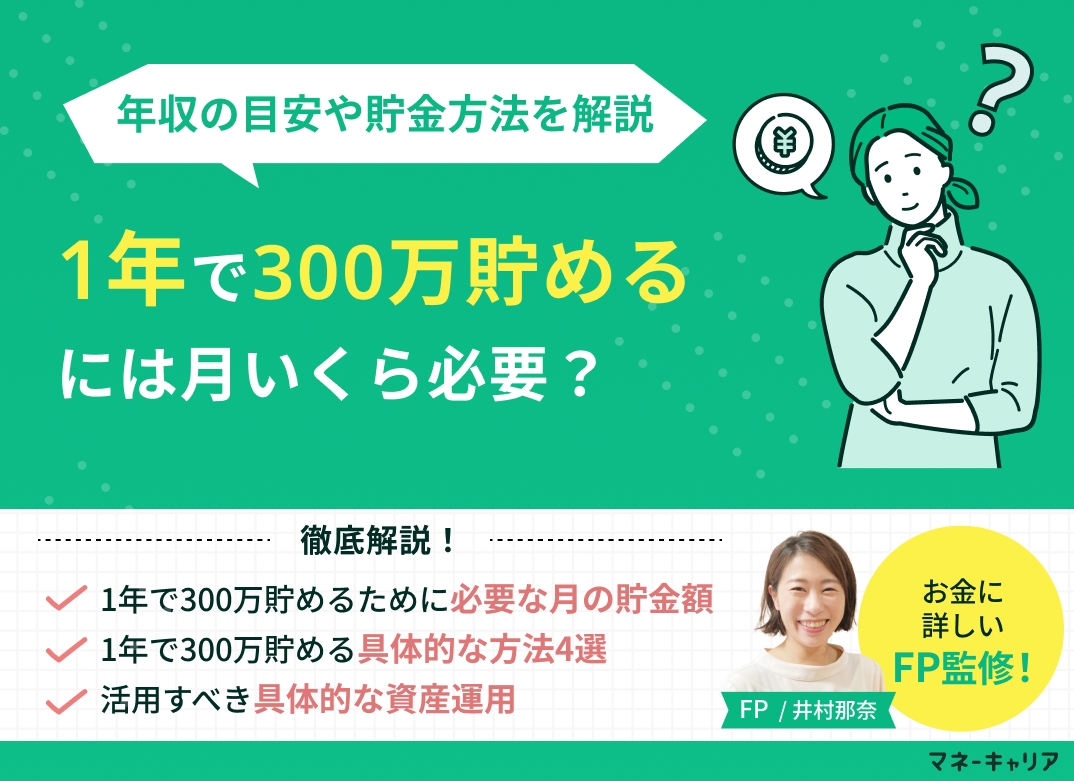「ふるさと納税って本当にお得なの?」
「仕組みが複雑で、ちゃんと控除されるか不安…」
そんな疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
結論、ふるさと納税は正しく利用すればお得な制度です。
自己負担額2,000円で返礼品を受け取れ、税金の控除も受けられるため、うまく活用すれば家計の節約につながります。
この記事では、ふるさと納税の仕組みや注意点、手続きの流れを詳しく解説します。
・「寄付できる上限額を知りたい」
・「手続きの流れを簡単に理解したい」
と考えている方は、本記事を読むことで、ふるさと納税を安心して活用できる知識が身につきます。
内容をまとめると
- ふるさと納税は自己負担2,000円で返礼品がもらえ、税金の控除も受けられる
- 正しい手続きをしないと控除されないため、申請が必須
- ふるさと納税を活用するには、寄付できる上限額の確認・手続きの流れの把握が大切
- マネーキャリアの無料相談を利用すれば、適切なふるさと納税の活用方法が分かる

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る
続きを見る
閉じる
この記事の目次
ふるさと納税は本当にお得?
結論からいうと、ふるさと納税は正しく利用すればお得な制度です。
ふるさと納税を活用すれば、寄付金の大部分が翌年の税金から控除されるうえに、地域の特産品を返礼品として受け取れます。
自己負担額は実質2,000円で済むため、家計への負担を抑えつつお得に特産品を楽しめるでしょう。
ふるさと納税の仕組み
ふるさと納税とは、自分で選んだ自治体に寄付を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分が所得税と住民税から控除される制度です。
例えば、年収600万円の給与所得者が30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。
寄付できる上限額は年収や家族構成によって異なるため、事前にシミュレーションを行うことが重要です。
ふるさと納税の注意点

- 寄付金額の上限を超えると自己負担になる
- 自分が住む自治体への寄付では返礼品が受け取れない
- 申請をしなければ税金の控除が適用されない
- 納税者本人の名義で寄付する必要がある
これらの注意点を押さえておかないと、期待するメリットを享受できない可能性があります。
各項目を詳しく見ていきましょう。
寄付金額の上限を超えると自己負担
寄付金額の上限を超えると、超過分は全額自己負担となります。
ふるさと納税には所得に応じた控除上限額があり、これを超えて寄付すると税金の控除対象にはなりません。
自分が住む自治体への寄付では返礼品がもらえない
自分が住んでいる自治体へ寄付しても、返礼品を受け取れません。
ふるさと納税の目的は、地方自治体の財政を支援することにあるため、寄付者が住民税を納めている自治体への寄付は優遇対象外です。
申請しないと控除されない
ふるさと納税をしても、申請をしなければ税金の控除は適用されません。
控除を受けるためには、確定申告をするか、ワンストップ特例制度を利用する必要があります。
納税者の名義で寄付する必要がある
ふるさと納税は、納税者本人の名義で寄付しなければなりません。
例えば、夫が寄付金控除を受けたいにもかかわらず、妻名義でふるさと納税を行った場合は、控除の対象外です。
ふるさと納税の手順

次に、ふるさと納税の基本的な流れを紹介します。
- 寄付できる限度額を調べる
- 返礼品を選んで寄付する税金控除の手続きをする
- 控除額を確認する
ふるさと納税は手順を誤ると、期待する控除が受けられない場合があります。
それぞれのステップを詳しく見ていきましょう。
寄付できる限度額を調べる
ふるさと納税には所得に応じた控除の上限があり、これを超えて寄付すると自己負担が増えます。
年収600万円の会社員であれば、独身か扶養家族がいるかによって控除額が異なるため、事前にいくらまで寄付できるのか確認が必要です。
返礼品を選んで寄付する
寄付上限額を確認したら、寄付できる金額内で返礼品を選びましょう。
自治体ごとに返礼品の内容は異なり、食品・家電・宿泊券など種類が豊富です。
税金控除の手続きをする
税金控除の手続きをしないと、寄付金の控除が受けられません。
控除を受ける方法は、確定申告とワンストップ特例制度の2種類があります。
控除額を確認する
最後に、寄付金控除をしっかりと受けられているか確認しましょう。
ワンストップ特例制度を利用した方は、6月頃に自治体から送付される、「住民税決定通知書」を確認してください。
摘要欄に記載されている金額が、「寄付した金額ー2,000円」になっていれば、正しく控除されています。
ふるさと納税が本当にお得か疑問な人のよくある質問
ふるさと納税が本当にお得か疑問な人のために、よくある質問を整理します。
特に多くの人が気にするのは以下のポイントです。
- 年収いくら以上ならお得?
- ワンストップ特例制度とは?
- 確定申告をする人はワンストップ特例制度を使えない?
それぞれの回答を見ていきましょう。
年収いくら以上ならお得?
年収いくら以上ならお得なのか、気になる人は多いでしょう。
基本的に、住民税と所得税を納めている人であれば、ふるさと納税による控除を受けられます。
ふるさと納税のメリットがある年収の目安は、おおよそ年収300万円以上です。
ワンストップ特例制度とは?
ワンストップ特例制度とは、確定申告をしなくても控除を受けられる便利な仕組みです。
この制度を利用すれば、自治体に申請書を提出するだけで、住民税から控除が反映されます。
オンライン申請に対応している自治体もあるため、簡単に寄付金控除の申請が可能です。
確定申告をする人はワンストップ特例制度を使えない?
確定申告をする方は、ワンストップ特例制度を使えません。
ワンストップ特例は、確定申告をしない給与所得者を対象とした制度です。
ふるさと納税を活用したいけれど不安な人は「マネーキャリア」に相談
ふるさと納税の仕組みや注意点、手続き方法について詳しく解説しました。
適切に活用すれば、自己負担2,000円で返礼品を受け取け取れるため家計の節約に繋がります。
ふるさと納税を始めるには、まず自身の寄付限度額を確認し、制度を正しく理解して適切な手続きを行いましょう。
とはいえ、自分の寄付上限額がわからない方や、寄付金控除の申告に不安がある方もいるでしょう。
「マネーキャリア」では、ふるさと納税の活用方法やそのほかの節税対策について、何度でも無料で相談できます。
プロのアドバイスを受けることで、お得な制度を賢く利用できるようになります。
ふるさと納税の活用に不安を感じる方は、一度マネーキャリアに相談してみてはいかがでしょうか。