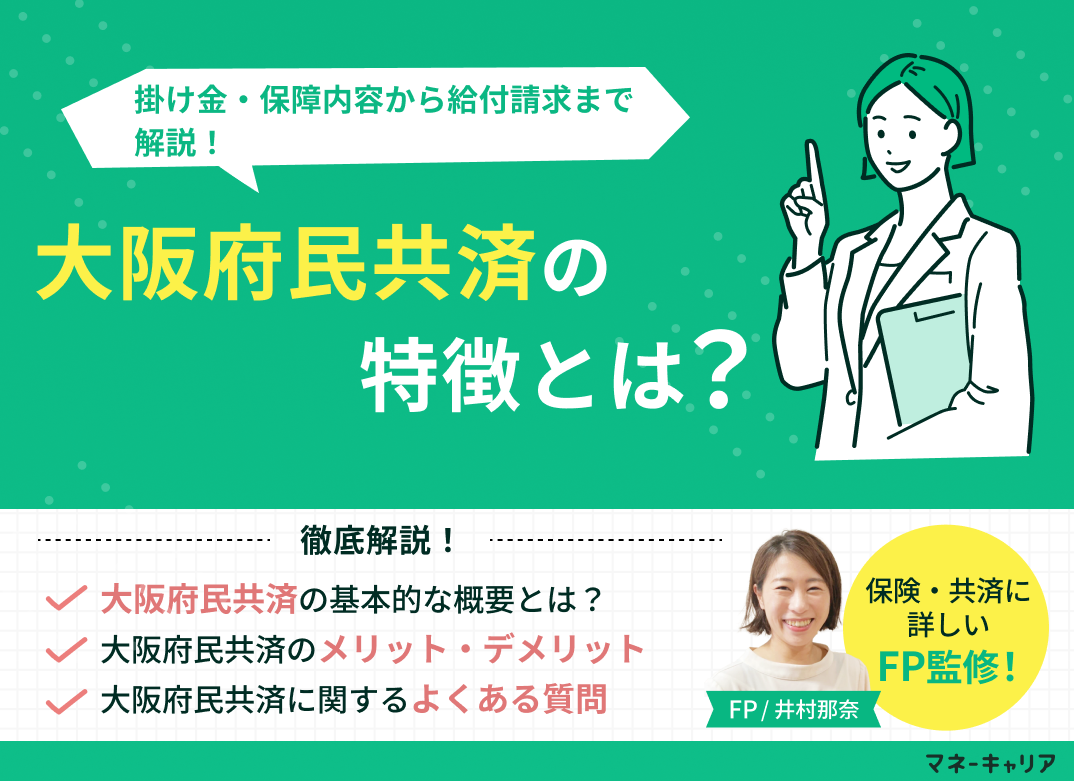「小規模企業共済の加入資格がなくなったらどうする?」
「小規模企業共済の代わりになる制度の詳細を知りたい」
とお悩みではないでしょうか。
結論、小規模企業共済の加入資格がなくなると解約手当金が支払われないことをはじめとしてさまざまなリスクがあるため、事前に対策や代わりの制度を知っておくことが重要です。
この記事では、小規模企業共済の加入資格や、加入資格を失った場合の影響やリスクについて解説します。
資格喪失後の対策や代替制度についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
内容をまとめると
- 小規模企業共済の加入資格は、個人事業主か会社役員かによって異なる
- 小規模企業共済の資格を喪失したあとは解約手付金が支給されないなどのリスクがある
- 解約する場合に受け取れる解約手付金の金額は人によって異なるのでシミュレーションが必要
- 小規模企業共済の代替制度には「iDeCo」「国民年金基金」「確定拠出年金」などがある
- 知識がないまま小規模企業共済の加入資格を喪失して後悔する人がいる
- そこで、相談満足度98.6%・相談実績100,000件以上のマネーキャリアに相談するのがおすすめであり、無料で何度でもオンライン相談が可能で、スマホで30秒で簡単に申し込み可能!

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 小規模企業共済の加入資格とは?
- 個人事業主としての条件
- 会社等役員の場合の要件
- 小規模企業共済の加入資格がなくなった場合
- 資格喪失のタイミングと必要手続きの全体フロー
- 資格喪失後に発生するリスクと影響
- 小規模企業共済資格喪失後の具体的対応策
- 解約や休止後の資金受取方法と注意点
- 加入資格復活や代替制度の検討ポイント
- 小規模企業共済の解約手当金はいくら?シミュレーションで確認
- モデルケースで見る具体的な戻り金額のシミュレーション
- 小規模企業共済の解約手当金は一括か分割か
- 小規模企業共済についてのよくある質問
- Q1.役員辞任したらどうなる?
- Q2.サラリーマン転職後に再加入できる?
- Q3.副業がバレるリスクは?
- 小規模企業共済の加入資格がなくなった場合の代替制度比較
- iDeCo
- 国民年金基金
- 確定拠出年金
- 小規模企業共済に関わる悩みを解消できる方法とは?
- 小規模企業共済の資格喪失後も慌てないための最終チェックリスト
小規模企業共済の加入資格とは?
ここでは、小規模企業共済の加入資格について解説します。
小規模企業共済に加入できるのは、大きくわけて以下の2種類の方です。
- 個人事業主
- 会社等役員
個人事業主としての条件
個人事業主が小規模企業共済に加入する条件には、主に以下のようなものがあります。
- 常時使用する従業員の数が要件を満たしている方
- 税務署に開業届を届け出て、事業所得を得ていて確定申告をしている方
- 会社との間で雇用関係が生じていない方(給与所得を得ていない)
- 固定給に近い報酬を得ておらず完全歩合制である方
- 社会通念上、事業者(個人事業主)と認められる方
| 営む事業の種別 | 従業員数の制限 |
|---|---|
| ・建設業 ・製造業 ・運輸業 ・不動産業 ・農業 ・サービス業(宿泊業、娯楽業に限る)等 | 常時使用する従業員の数が20人以下 |
| ・商業(卸売業・小売業) ・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く) | 常時使用する従業員の数が5人以下 |
会社等役員の場合の要件
会社等の役員の方が小規模企業共済に加入する場合、以下の条件を満たす必要があります。
- 常時使用する従業員の数が要件を満たしている方
- 役員登記し、事業に従事されている方
「常時使用する従業員の数」については、会社の役員なのか、組合等や士業法人の役員であるかによって以下のとおり変わります。
【会社の役員の場合】
| 営む事業の種別 | 従業員数の制限 |
|---|---|
| ・建設業 ・製造業 ・運輸業 ・不動産業 ・農業 ・サービス業(宿泊業、娯楽業に限る)等 | 常時使用する従業員の数が20人以下 |
| ・商業(卸売業・小売業) ・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く) | 常時使用する従業員の数が5人以下 |
【組合等・士業法人の役員の場合】
| 法人の種別 | 従業員数の制限 |
|---|---|
| 企業組合 | 事業に従事する組合員の数が20人以下 |
| 協業組合 | 常時使用する従業員の数が20人以下 |
| 農業の経営を主として行っている農事組合法人 | 常時使用する従業員の数が20人以下 |
| 弁護士法人、税理士法人等の士業法人 | 常時使用する従業員の数が5人以下 |
小規模企業共済の加入資格がなくなった場合
前述のとおり、小規模企業共済には個人事業主と法人等役員によって加入資格があります。
加入資格を満たさなくなったときは小規模企業共済に加入を続けられなくなるため注意が必要です。
ここでは、加入資格がなくなった場合にどのようなことが起こるのか、以下の2点から解説します。
- 資格喪失のタイミングと必要手続きの全体フロー
- 資格喪失後に発生するリスクと影響
資格喪失のタイミングと必要手続きの全体フロー
資格喪失のタイミングは、小規模企業共済の加入条件を満たさなくなったときです。
例えば、個人事業主として働いてきた事業が「法人成り」すると、個人事業主としての加入資格を喪失することになります。
また、個人事業主が事業を廃止して給与所得者(会社員)になった場合も、同様に加入資格を喪失します。
以下に、小規模企業共済の加入資格を喪失する理由をまとめました。
- 個人事業主が法人になる「法人成り」をした場合
- 個人事業主の事業が廃止になった場合
- 掛金を12ヵ月以上滞納した場合
- 会社の役員を退任して給与所得者に戻ったり、無職になったりした場合
- 契約者の自己都合で任意に解約した場合
- 契約者が死亡した場合 など
資格喪失後に発生するリスクと影響
小規模企業共済の加入資格を喪失した場合、共済を解約して解約手当金を受け取れる可能性があります。
ただし、資格を喪失したタイミング次第では以下のようなリスクがあるため注意が必要です。
- 解約手当金が支給されないリスク
- 解約手当金が元本割れするリスク
- 契約がさかのぼって取り消された場合には過去に受けた所得控除の修正申告が必要になるケースがある
小規模企業共済資格喪失後の具体的対応策
小規模企業共済の資格を喪失してしまったあとは、これまでのように資産形成や万が一の際に貸し付けを受けるなどのメリットを利用できなくなります。
資格が喪失することがわかったら、早急に今後の具体的な対策を考える必要があります。
ここでは、小規模企業共済の資格喪失後の具体的な対策として、以下の2点を解説します。
- 解約や休止後の資金受取方法と注意点
- 加入資格復活や代替制度の検討ポイント
解約や休止後の資金受取方法と注意点
小規模企業共済の解約や休止後に資金を受け取る方法には、いくつかの流れや注意点があります。
例えば個人事業を廃業する場合は「共済金A」を受け取れますが、「個人事業の廃業届」「印鑑登録証明書」「マイナンバー確認書類」「退職所得申請書」「共済契約締結証書」などの必要書類を準備のうえ、「共済金等請求書(様式小701)」を提出します。
共済契約を任意解約して解約手当金を受け取るには「解約手当金請求書(様式㊥401)」という書類に必要事項の提出が必要です。
添付書類と併せて登録取扱期間に提出することで、解約が受理されます。
解約手当金は中小機構に必要書類が到着したあと、書類に不備がない前提で10日~2週間程度で受け取ることができます。
実際に受け取れる金額は納付月数や解約理由によって異なるため、事前に把握することが大切です。
加入資格復活や代替制度の検討ポイント
加入資格を復活させることが可能で小規模企業共済への再加入を検討している場合、ほかにも個人事業主や役員が利用できる代替制度との比較検討を進めることが重要です。
一例として、小規模企業共済以外に個人事業主が加入できる制度には以下のようなものがあります。
- iDeCo
- NISA
リスクをとってより多くの資産形成を進めたい方にとって、仮に加入資格が復活しても代替制度に投資したほうが良いケースもあります。
自身のリスク許容度などから、自身に合う制度が何かを考えることが大切です。
小規模企業共済の解約手当金はいくら?シミュレーションで確認
小規模企業共済を解約することになった場合、解約手当金を受け取ることができます。
ただ、受け取れる解約手当金の金額は必ずしも払い込んだ掛金を上回るとは限らず、受取金額は人によって異なります。
支給される解約手当金の金額は「掛金合計×支給率」で計算され、支給率は掛金納付月数によって変動します。
掛金納付期間が20年(240ヵ月)だと掛金合計額と同額(100%)ですが、それ未満の場合は80%~99.25%など元本割れとなるため注意が必要です。
解約手当金の金額を把握するために、以下の2点について確認しておきましょう。
- モデルケースで見る具体的な戻り金額のシミュレーション
- 小規模企業共済の解約手当金は一括か分割か
モデルケースで見る具体的な戻り金額のシミュレーション
ここでは、4種類の掛金をモデルケースに、解約手当金の戻り金額をシミュレーションしてみましょう。
小規模企業共済の解約手当金は、加入月数に応じて以下のとおりに変動します。
| 加入月数 | 解約手当金の支給率 |
|---|---|
| 11ヵ月未満 | 0.0% |
| 12ヵ月~83ヵ月 | 80.0% |
| 84ヵ月~89ヵ月 | 80.5% 以下6ヵ月ごとに0.75%ずつ支給率が上がる 239ヵ月未満の場合は元本割れ |
| 240ヵ月~245ヵ月 | 100.0% |
| 246ヵ月~251ヵ月 | 100.25% 以下6ヵ月ごとに0.25%ずつ支給率が上がる |
| 720ヵ月以上 | 120.0% |
上記をもとに、「掛金が月1万円」だった場合の戻り金額を、加入年数5年・10年・20年で比較すると以下のとおりです。
| 加入期間 | 支給率 | 掛金の合計 | 解約手当金の受取金額 |
|---|---|---|---|
| 5年 | 80.0% | 60万円 | 48万円 |
| 10年 | 85.0% | 120万円 | 102万円 |
| 20年 | 100.0% | 240万円 | 240万円 |
小規模企業共済の解約手当金は一括か分割か
小規模企業共済の解約手当金は一括受け取りと分割受け取りから選択でき、それぞれ以下の控除が適用されます。
- 一括受け取り:退職所得控除
- 分割受け取り:公的年金等控除
小規模企業共済についてのよくある質問
ここからは、小規模企業共済に関してよくある質問を解説します。
今回紹介する質問は以下の3つです。
- Q1.役員辞任したらどうなる?
- Q2 サラリーマン転職後に再加入できる?
- Q3.副業がバレるリスクは?
Q1.役員辞任したらどうなる?
会社の役員を辞任した場合、小規模企業共済の「共済金」または「解約手当金」の受取事由になります。
小規模企業共済の掛金を180ヵ月以上積立て、65歳以上で役員を退任した場合には「共済金B」の老齢給付が受け取れます。
例えば毎月1万円の積立を10年続けた場合は掛金の合計金額は120万円ですが、共済金Bの受取額は126万800円になります。
また、役員を退任するのを機に小規模企業共済を解約した場合は解約手当金を受け取れますが、前述の条件では受け取れる金額が102万円にとどまります。
Q2.サラリーマン転職後に再加入できる?
サラリーマン(会社員)に転職した場合、小規模企業共済に再加入する資格は有していません。
小規模企業共済に加入できるのは、原則として「企業等の役員」「個人事業主」に限られます。
ただし、会社員であっても副業で個人事業主として事業所得を得ており、税務署への開業届を提出している場合は条件を満たしたうえで再加入が可能です。
サラリーマンになる場合は小規模企業共済の解約時に受け取れる解約手当金が最後になりますが、加入期間によっては元本割れする可能性があることを把握しておきましょう。
Q3.副業がバレるリスクは?
会社員が副業で個人事業主になっている場合は小規模企業共済に加入できる可能性はありますが、会社に副業がばれるリスクがあることは覚えておきましょう。
会社に副業がばれる原因は、基本的に「住民税」です。
年収が同水準のほかの社員よりも住民税が高いと、本業以外の手段で利益を得ていることが経理や総務の担当者にバレてしまう可能性があります。
副業で個人事業主をする場合、まずは会社の就業規則を確認して副業ができることを確認しておきましょう。
小規模企業共済の加入資格がなくなった場合の代替制度比較
小規模企業共済の加入資格を喪失したあと、老後に向けて別の資産形成の制度に加入することも検討してみましょう。
老後の資産形成に利用できる制度としては、以下のようなものがあります。
- iDeCo
- 国民年金基金
- 確定拠出年金
iDeCo
iDeCo(イデコ)は、個人型確定拠出年金の愛称で、個人が将来の年金の受取額を増やすための私的年金制度です。
毎月の掛金金額を5,000円以上1,000円単位で自由に選択でき、定期預金・保険・投資信託の中から任意に投資先を決めて毎月投資を行います。
小規模企業共済と同じく掛金が全額所得控除になるうえ、運用期間中に得た利益は全額が非課税になるため効率的に資産形成が可能です。
元本保証こそありませんが、運用結果によっては小規模企業共済よりも高額な老後資金をためられる可能性があります。
国民年金基金
国民年金基金は、自営業やフリーランスの方が年金を増やすための制度です。
以下の2つの条件を満たす方が加入できます。
- 国民年金の第1号被保険者の方
- 60歳以上65歳未満の方や海外居住者で国民年金に任意加入している方
確定拠出年金
確定拠出年金には前述した個人型の「iDeCo」以外に、企業型の確定拠出年金もあります。
掛金の上限は毎月55,000円で、その他の企業年金に加入している方は月額55,000円から他制度の掛金相当額を控除した金額まで拠出できます。
事業主が拠出する分の掛金は加入者が負担する必要はなく、加入者自身が拠出する掛金の全額が所得控除になる点はiDeCoと共通です。
事業主掛金は福利厚生として会社が拠出するため、社会保険料の算定基礎の対象外となります。
運用にかかる費用は企業が負担するため、iDeCoよりもコストをおさえやすいメリットもあります。
小規模企業共済に関わる悩みを解消できる方法とは?

共済に関するすべての悩みにオンラインで解決できる
マネーキャリア:https://money-career.com/
<マネーキャリアのおすすめポイントとは?>
・お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、共済や民間の生命保険に知見の豊富な、ファイナンシャルプランナーのプロのみを厳選しています。
・もちろん、共済や民間の生命保険だけではなく、資産形成や総合的なライフプランの相談から最適な解決策を提案可能です。
・マネーキャリアは「丸紅グループである株式会社Wizleap」が運営しており、満足度98.6%、相談実績も100,000件以上を誇ります。
<マネーキャリアの利用料金>
マネーキャリアでは、プロのファイナンシャルプランナーに「無料で」「何度でも」相談できるので、相談開始〜完了まで一切料金は発生しません。
小規模企業共済の資格喪失後も慌てないための最終チェックリスト
ここまで、小規模企業共済の加入資格や、加入資格を失った場合の影響やリスクなどをお伝えしてきました。
記事のポイントをまとめると以下のとおりです。
- 小規模企業共済に加入できるのは「個人事業主」「会社等役員」で、会社等役員の場合には従業員数や業種などによって加入資格が異なる
- 小規模企業共済の資格を喪失すると「解約手当金が支給されないリスク」「解約手当金が元本割れするリスク」などが心配される
- 解約手当金の金額は個人ごとに異なるがシミュレーションによって事前に把握が可能
- 資格喪失で小規模企業共済を解約したあと、「iDeCo」「国民年金基金」「確定拠出年金」など別制度に加入を検討できる