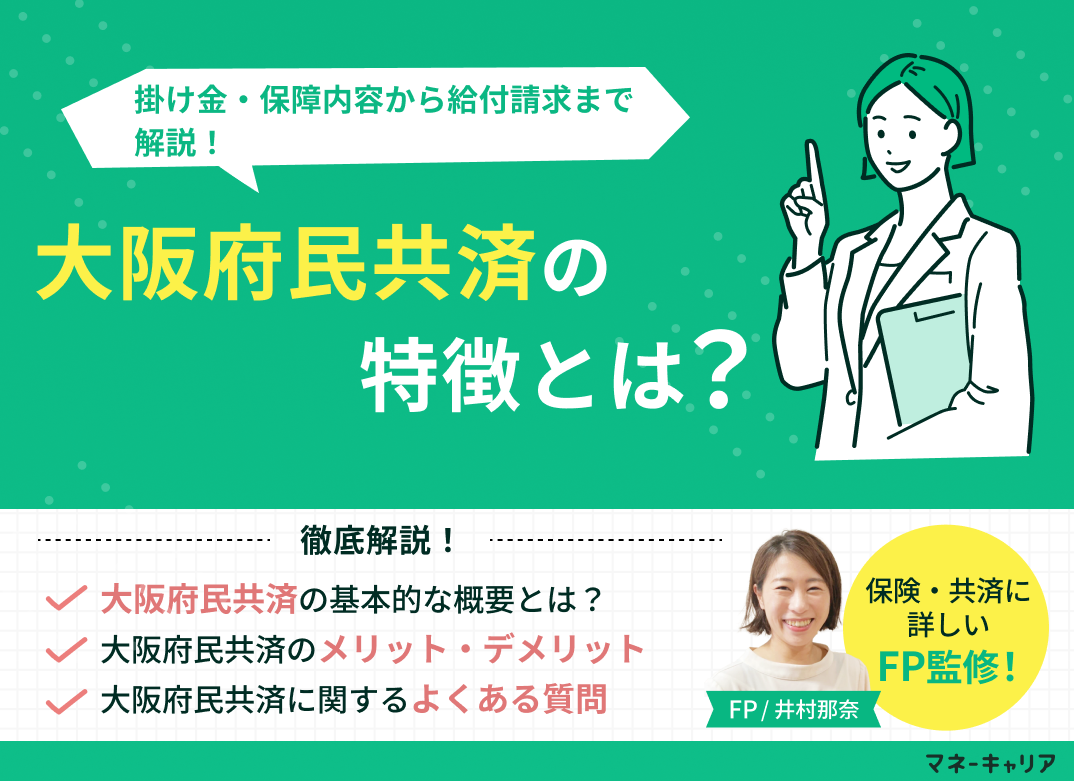「小規模企業共済は60歳から老齢給付を受け取れる?」
「65歳からの受け取るとどちらがお得?」
とお悩みではないでしょうか。
結論、小規模企業共済は条件を満たすことで60歳から老齢給付や解約手当金を受け取れる可能性があります。
ただし、どのくらいの金額を受け取れるかは人によって異なるため、後悔しないためには事前のシミュレーションが重要です。
そこで、小規模企業共済の共済金を60歳から受取を開始できる仕組みや、60~64歳の分割プランと65歳以降の一括・併用プランの比較結果を解説します。
内容をまとめると
- 60歳以上なら小規模企業共済の分割受取プランや老齢一括給付を受け取れる
- 60~64歳の分割プランと65歳以降の一括・併用プランで受給金額が異なる
- 小規模企業共済の単独加入とiDeCo・NISAの併用で節税効果が異なる
- 知識がないまま小規模企業共済の老齢給付や解約手当金の受給を決めて後悔する人がいる
- そこで、相談満足度98.6%・相談実績100,000件以上のマネーキャリアに相談するのがおすすめであり、無料で何度でもオンライン相談が可能で、スマホで30秒で簡単に申し込み可能!

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 小規模企業共済の60歳から受取が開始できる仕組み
- 仕組み1:分割受取プランで受取を開始する方法
- 仕組み2:一括給付で受取を開始する方法
- 60~64歳の分割プランと65歳以降の一括・併用プラン比較図解
- 小規模企業共済の60歳からの実例シミュレーション(掛金3万円×20年納付の場合)
- 小規模企業共済の解約手当金(60歳時点)
- 小規模企業共済の老齢給付額(65歳到達時)
- 小規模企業共済・iDeCo・NISAの節税効果を比較
- 小規模企業共済単独加入時の節税効果
- iDeCo・NISA併用でさらに増える節税メリット
- 小規模企業共済の60歳から受け取ることに関する疑問とは
- Q1.何歳から加入・受取できる?70歳加入は?
- Q2.一括受取と分割受取、どちらが得?
- Q3.税金・節税メリットはどうなる?
- 小規模企業共済における60歳からの全般の悩みを解決できる方法とは?
- 小規模企業共済を60歳から賢く受け取る方法
小規模企業共済の60歳から受取が開始できる仕組み
小規模企業共済は条件を満たすことで60歳から受け取ることができます。
分割受け取りと老齢一括給付の2つの仕組みを利用でき、それぞれ公的年金等控除、退職所得控除を活用できます。
60歳で受け取りを開始するための、以下の2つの方法を解説します。
- 仕組み1:分割受取プランで受取を開始する方法
- 仕組み2:一括給付で受取を開始する方法
仕組み1:分割受取プランで受取を開始する方法
小規模企業共済は個人事業の廃止や共同経営者としての退任、会社等の解散などの事由に該当すると「共済金A」を受け取れます。
共済金Aの受取方法は一括が原則ですが、以下の条件を満たすことで「分割受取り」および「一括受取りと分割受取りの併用」を選択できます。
- 共済金Aまたは共済金Bであること
- 請求事由が共済契約者の死亡でないこと
- 請求事由が発生した日に60歳以上であること
- 共済金の額が次のとおりであること
1.分割受取りの場合:300万円以上
2.一括受取りと分割受取りの併用の場合:330万円以上
一括で受け取る金額が30万円以上
分割で受け取る金額が300万円以上
仕組み2:一括給付で受取を開始する方法
共済金Aに関して、条件を満たすことで60歳未満でも一括給付で受け取りを開始できます。
共済金Aは個人事業の廃止や共同経営者としての退任、会社等の解散など「請求事由」に該当すれば中小機構に申請して受け取ることができます。
一括での受け取りは、分割での受け取りのような条件はついていません。
掛金納付月数が6ヵ月以上であれば請求できます。
60~64歳の分割プランと65歳以降の一括・併用プラン比較図解
60~64歳までに分割で受け取る場合と、65歳以降に一括・併用プランで受け取る場合を表にまとめると、以下のようになります。
| 60~64歳の分割 | 65歳以降の一括・併用 | |
|---|---|---|
| 受け取り開始年齢 | 60~64歳 | 65歳以降 |
| 共済金の最低額 | 300万円以上 | 330万円以上 ※分割:300万円以上 一括:30万円以上 |
| 受取途中での変更 | できない | できない |
| 適用される税制 | 公的年金等控除 | 一括:退職所得控除 分割:公的年金等控除 |
注意点として、「分割」「一括・分割の併用」のいずれの場合も、受け取りを決定したあとに例外を除いて分割払いから一括払いに変更できません。
分割払いから一括払いに変更できるのは「受給者が死亡した場合」「受給者が重度の障害や災害を受けた場合」に限られます。
小規模企業共済の60歳からの実例シミュレーション(掛金3万円×20年納付の場合)
小規模企業共済でいくらの給付を受け取れるのかは、受け取る給付の種類や毎月の掛金、納付期間によって異なります。
ここでは、掛金を月3万円で20年間納付した場合を例に、60歳からの給付金額のシミュレーションを解説します。
- 月掛金:3万円
- 納付期間:20年(240ヵ月)
- 掛金額合計:720万円(3万円×240ヵ月)
紹介するシミュレーションは以下の2つです。
- 小規模企業共済の解約手当金(60歳時点)
- 小規模企業共済の老齢給付額(65歳到達時)
小規模企業共済の解約手当金(60歳時点)
60歳になった時点で納付期間が20年あれば、小規模企業共済を解約して「解約手付金」を受け取ることが可能です。
加入期間が20年の場合、支給率(返戻率)は100.0%が基本です。
掛金額合計と同じ「720万円」の解約手当金を受け取ることができます。
ただし、掛金を途中で増額や減額をした場合には、上記の金額のとおりにはなりません。
特に「減額」をすると、減額した金額がその後に運用されなくなってしまうため、20年の納付期間があっても元本割れするリスクがあります。
小規模企業共済の老齢給付額(65歳到達時)
65歳以上で180ヵ月以上の納付期間があれば、65歳到達時に「共済金B」の老齢給付金を受け取ることができます。
参考までに、掛金月額1万円を20年間納付した場合、掛金合計240万円に対し、受け取れる共済金Bの金額は「265万8,800円」です。
掛金に対して25万8,800円をプラスで受け取ることができる計算です。
毎月3万円を積み立てた場合も支給率は同じであり、掛金合計720万円に対して受け取れる共済金Bの金額は797万6,400円(+77万6,400円)となります。
小規模企業共済・iDeCo・NISAの節税効果を比較
小規模企業共済は掛け金が所得控除されるため、将来のための資産形成を進めながら所得税や住民税を節税できます。
一方、以下の2つの制度も所得控除や非課税の恩恵を受けることができ、それぞれ節税が可能です。
- iDeCo
- NISA
小規模企業共済単独加入時の節税効果
小規模企業共済に加入した場合、毎月の掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、所得控除の対象になります。
例えば毎月7万円の掛金を支払っている場合、年間の掛金合計である84万円が所得控除されます。
課税所得が400万円の方の場合は所得税率20%と住民税率10%であり、84万円が所得控除されると所得税と住民税を併せて「84万円×0.3=25万2,000円」の節税効果があります。
一方、課税所得が1,000万円の方は所得税率33%、住民税率10%のため、「84万円×0.43=36万1,200円」の節税が可能です。
上記はあくまでも月7万円の掛金を拠出した場合の例ですが、小規模企業共済では月額1,000円~最高7万円の範囲内(500円単位)で掛金額を自由に設定できます。
余剰資金に合わせて柔軟に掛金を設定でき、掛金と「所得税率+住民税率」に見合う控除が受けられるのが小規模企業共済のメリットです。
iDeCo・NISA併用でさらに増える節税メリット
iDeCoやNISAといった非課税投資制度を併用することで、小規模企業共済に単独で加入するよりも大きな節税メリットを得られる可能性があります。
iDeCoは60歳以降に受け取れる私的年金を作るための制度で、毎月任意の掛金を拠出して定期預金・保険・投資信託などを運用して元金と利益を将来受け取れます。
小規模企業共済と同じく掛金の全額が所得控除であり、掛金の拠出による節税金額は小規模企業共済と同額です。
さらに、投資信託に投資することで元本保証がない代わり、小規模企業共済の老齢給付(掛金の最高120%)を大きく上回るリターンを獲得できる可能性があります。
運用で得た全額が非課税であり、利益の全額を再投資することでより効率的に資産運用が可能です。
NISAもつみたて投資枠を利用して毎月少額からの積み立てで投資信託への投資が可能です。
小規模企業共済やiDeCoと違って所得控除のメリットはありませんが、投資可能額が月10万円(年間120万円・上限1,800万円)と大きく、運用期間中は利益の全額が無期限で非課税というメリットがあります。
小規模企業共済・iDeCo・NISAはどの組み合わせでも併用できます。
小規模企業共済にiDeCoやNISAを併用することで、所得控除による節税+運用益非課税のメリットを最大限活用できるでしょう。
小規模企業共済の60歳から受け取ることに関する疑問とは
ここでは、小規模企業共済を60歳から受け取ることに関して、よくある質問と回答を解説します。
今回集まった質問は以下のとおりです。
- Q1.何歳から加入・受取できる?70歳加入は?
- Q2.一括受取と分割受取、どちらが得?
- Q3.税金・節税メリットはどうなる?
Q1.何歳から加入・受取できる?70歳加入は?
小規模企業共済の加入について、年齢制限はありません。
個人事業主や企業の役員であるなどの加入条件を満たせば、70歳からでも加入できます。
分割受取や一括・分割の併用で共済金を受け取る場合、受取開始時期は、原則として60歳以上です。
ただ、老齢給付金を受け取るには年齢が65歳以上に達しているだけでなく、掛金納付月数が180ヵ月以上であることも条件に含まれるため注意が必要です。
Q2.一括受取と分割受取、どちらが得?
一括受取と分割受取のどちらがお得かは、人によって異なります。
まず、節税メリットを最大限に利用したい方や、若いうちに高額を一気に受け取りたい方は、一括受取がお得です。
一括受取では「退職所得控除」が適用され、分割受取の際に適用される「公的年金等控除」よりも大きな控除を受けられる可能性があります。
一方の分割受取は税負担こそ一括受取よりも大きくなる可能性がありますが、長期的に共済金を受け取れることで老後の生活が安定しやすい点がメリットです。
Q3.税金・節税メリットはどうなる?
小規模企業共済を利用すると、以下の2つの税金・節税メリットを得ることができます。
- 掛金の全額所得控除
- 受取時の税制優遇
小規模企業共済における60歳からの全般の悩みを解決できる方法とは?

共済に関するすべての悩みにオンラインで解決できる
マネーキャリア:https://money-career.com/
小規模企業共済を60歳から賢く受け取る方法
ここまで、小規模企業共済の60歳から受取が開始できる仕組みや、60~64歳の分割プランと65歳以降の一括・併用プランの比較結果などをお伝えしてきました。
記事のポイントをまとめると以下のとおりです。
- 小規模企業共済は条件を満たすことで一括または分割で60歳から受け取ることができる
- 解約手当金(60歳時点)では納付した掛金の100%、65歳以上の老齢給付金では100%以上の支給率で受け取れる
- iDeCo・NISAは運用益が非課税という小規模企業共済にないメリットがあり、組み合わせることでより大きな節税メリットを得られる可能性がある
- 一括受取と分割受取のどちらがお得なのかは人によって異なる