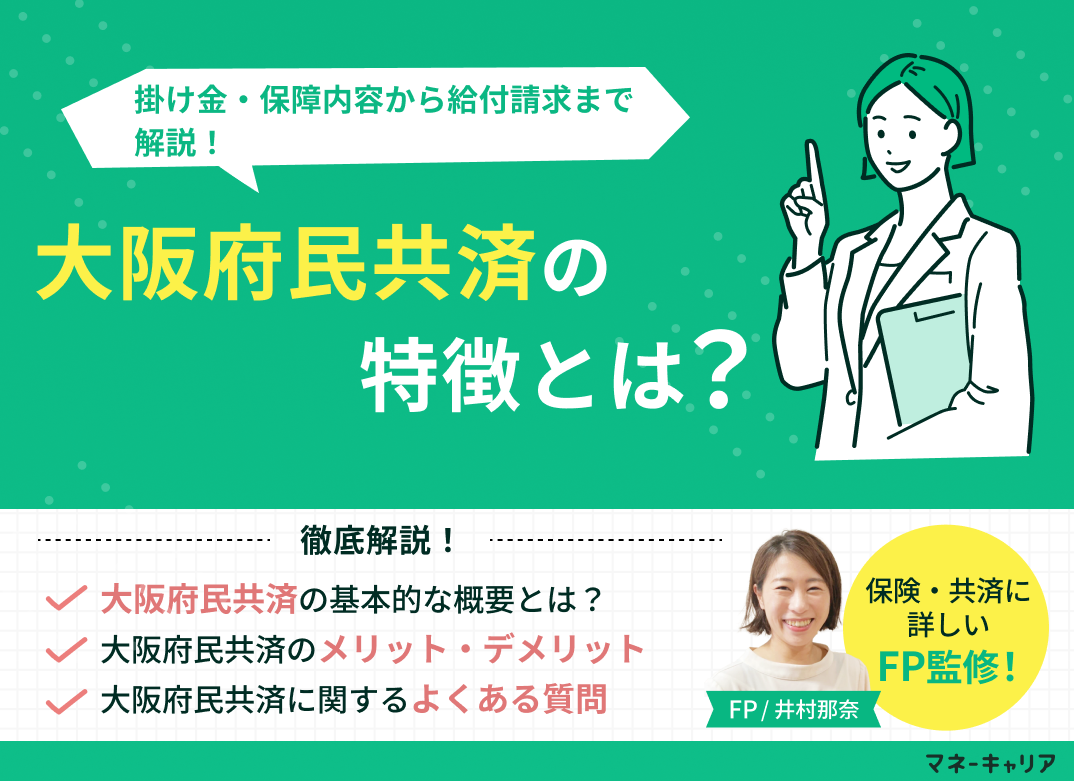障害共済年金は、地方公務員や教職員などの共済加入者が障害を負ったときに受け取れる年金で、退職後も引き続き受け取れる制度として知られています。
しかし実際には、「退職したら支給が止まるのでは?」「再就職したらどうなるの?」といった不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、障害共済年金が退職後も受け取れる条件や注意点、支給停止のリスク、必要な手続きまで詳しく解説します。
・退職後も障害共済年金が継続して受け取れるのか不安な方
・働き方や生活の変化に合わせた年金制度の正しい理解を深めたい方
この記事を読むことで、退職後も安心して障害共済年金を受け取るための知識がわかり、準備ができるようになります。
内容をまとめると
- 障害共済年金は退職後も原則として受給可能であるが、再就職や収入状況により支給停止となるケースがある。
- 受給には障害等級や初診日などの条件、保険料納付要件を満たす必要がある。
- 退職後の手続きや審査対応を正しく理解することで、不支給リスクを回避しやすくなる。
- マネーキャリアを活用すれば、制度に詳しい専門家に無料で相談でき、自分に合った年金の受け取り方を安心して選べる。
障害共済年金は退職後も受給可能ですが、就労状況や申請手続きによって支給停止となる場合があります。退職後に障害共済年金を受け取り続けるには、障害等級や初診日、保険料納付の要件を満たし、必要書類を正しく準備することが重要です。

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 障害共済年金は退職後も受け取れる?
- 原則として退職後も受給は可能
- 再就職や働き方で支給停止になることもある
- 障害共済年金の退職後に必要な受給条件
- 障害等級や初診日の要件
- 保険料納付期間のルール
- 障害共済年金の退職後に起こり得る支給停止・不支給のリスク
- よくある支給停止・不支給理由
- 支給継続のために必要な対応
- 障害共済年金の退職後の審査と審査請求について
- 審査の流れと通過のポイント
- 審査請求(不服申立て)の方法
- 障害共済年金の退職後に必要な手続きを解説
- 申請に必要な書類一覧
- 提出のタイミングと相談窓口
- 障害共済年金に関するよくある質問
- Q1:退職したら年金は自動的に止まりますか?
- Q2:職域加算はいつまで支給されますか?
- Q3:障害共済年金と他の年金は同時にもらえますか?
- 障害共済年金の退職後に関する悩みを解決する方法とは?
- 障害共済年金の退職後の制度を理解して安心して受給するためのまとめ
障害共済年金は退職後も受け取れる?
障害共済年金は、地方公務員や教職員などが加入する共済制度に基づく障害年金で、障害の状態が継続していれば退職後も受給できます。
ただし、再就職の内容によっては支給が停止されるケースがあるので注意が必要です。
- 退職後も受給は継続される
- 再就職や収入次第で支給停止の可能性がある
原則として退職後も受給は可能
障害共済年金は、地方公務員や教職員など、共済組合に加入していた方が在職中や退職後に一定の障害状態となった場合に受け取れる年金です。
原則として、受給要件を満たしていれば退職後も支給は継続されます。
要件には、初診日が在職中であることや、障害等級の基準を満たしていることなどが含まれます。
そのため、退職したからといって自動的に年金が止まることはありません。
むしろ、退職後の生活を支える大切な収入源となる場合も多いのが障害共済年金です。
再就職や働き方で支給停止になることもある
障害共済年金は、原則として退職後も受給できますが、再就職の内容や障害の状態によっては、年金の全部または一部が支給停止となる場合があります。
以下のようなケースでは注意が必要です。
- 再就職先が共済組合に加入する職場(公務員等)の場合
→ 在職中は、職域加算部分が全額支給停止となります。さらに、障害の程度や勤務の実態によっては、基本年金(基礎部分)も支給停止となる可能性があります。 - 民間企業などで厚生年金に加入して働く場合
→原則として障害共済年金の支給は継続されますが、労働の実態や障害の状態によっては支給停止となることがあります。なお、「給与と年金の合計額によって支給停止される」という在職老齢年金の仕組みは、障害年金には直接適用されません。 - 障害の状態が改善し、障害等級に該当しなくなった場合
→障害等級に該当しないと判断されたときは、障害共済年金の支給は停止されます。
このため、退職後に働き方や収入が変わる場合は、支給条件や収入基準について事前に確認しておくことが重要です。
障害共済年金の退職後に必要な受給条件
障害共済年金は、退職後でも条件を満たしていれば受け取れる制度ですが、すべての人が自動的に受給できるわけではありません。
受給には、障害の程度や初診日が共済組合加入中であることなど、いくつかの要件があります。
- 障害の重さや初診時期に関する基準
- 共済組合への加入期間や納付実績の条件
障害等級や初診日の要件
保険料納付期間のルール
障害共済年金を受給するためには、障害等級や初診日の要件に加え、保険料納付要件を満たす必要があります。
この要件を満たしていない場合、障害の程度が重くても年金は支給されません。
- 初診日の前日において、初診日のある月の2か月前までの被保険者期間(共済組合員期間も含む)のうち、保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あること
- または、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
障害共済年金の退職後に起こり得る支給停止・不支給のリスク
障害共済年金は、一度受給が認められてもその後の健康状態や就労状況の変化により、支給が停止または打ち切られることがあります。
制度の仕組みを十分に理解していないと、将来、予期せぬ形で収入が途絶えてしまう可能性もあるため注意が必要です。
- 状況の変化による支給停止や打ち切り
- 支給を継続させるための必要な対応
よくある支給停止・不支給理由
障害共済年金は一定の条件を満たせば退職後も継続して受給できますが、状況の変化によって支給が停止、または打ち切られることもあります。
実際に、以下のような理由で支給が止まるケースがよく見られます。
▼支給が止まるケース
- 労働能力が回復し障害等級に該当しなくなった場合
- 更新時の診断書提出が遅れたり、適切な書類が揃っていない場合
これらの要因は、受給者にとって予測しにくく、思わぬ支給停止につながります。
支給を継続するためにも、制度の変更や手続き内容を定期的に確認し、不安な点があれば早めに共済組合に相談することが重要です。
支給継続のために必要な対応
障害共済年金の受給を継続するためには、以下のような対応が必要です。
- 定期的な更新手続き
障害の状態を継続的に確認するため、共済組合からの案内に従って、診断書や調査書など必要書類を期限内に提出しましょう。 - 医療情報の正確な提出
診断書の記載に不備がある、または期限を過ぎて提出した場合、支給が停止される可能性があります。 - 再就職時の報告
就労状況によっては支給の見直し対象となるため、雇用形態や勤務内容、収入などを共済組合へ速やかに報告することが必要です。
障害共済年金の退職後の審査と審査請求について
障害共済年金を受け取るには、退職後であっても必ず共済組合による審査を経る必要があります。
また、万が一申請が却下された場合には、不服を申し立てる審査請求という手段も用意されています。
- 年金審査の手順と注意すべきポイント
- 不支給になった場合の再申請手続きの方法
審査の流れと通過のポイント
障害共済年金を受け取るためには、共済組合による障害認定の審査を通過する必要があります。
審査は書類ベースで行われるため、正確で詳細な診断書や必要書類の提出が求められます。
▼審査の流れ
- 必要書類(診断書、初診証明書など)の準備
- 共済組合への提出
- 医療専門家による障害等級の判定
- 審査結果の通知(受給可否)
審査請求(不服申立て)の方法
障害共済年金の申請が却下された場合でも、不服があるときは審査請求を行い、再審査を求めることができます。
これは正式な不服申立ての手続きであり、審査機関に再度判断を仰ぐ制度です。
▼審査請求の流れ
- 却下通知を受け取った日の翌日から3か月以内に、所定の審査請求書を提出
- 必要に応じて追加資料や医師の意見書などを添付し、不支給理由を踏まえて主張内容を補強
- 審査会が再評価を行い結果が書面で通知
注意点として、初回申請と同じ内容・書類だけを再提出しても結果が変わる可能性は低いため、不支給理由をしっかり確認し、必要な情報や証拠を追加することが重要です。
障害共済年金の退職後に必要な手続きを解説
退職後に障害共済年金を受け取るには、一定の条件を満たすだけでなく、必要な書類を準備して正しく手続きを進めることが大切です。
ここでは、申請に必要な書類の内容や提出のタイミング、手続きの流れを解説します。
- 申請に必要な書類一覧
- 提出の期日と困ったときの相談先
申請に必要な書類一覧
障害共済年金を退職後に受け取るためには、必要書類を正確に揃えて提出することが重要です。
書類が不足していたり、内容に誤りがあると審査に時間がかかってしまい不支給となる可能性もあります。
▼必要となる書類
- 障害共済年金裁定請求書(指定の様式)
- 医師の診断書(共済組合が指定する様式)
- 初診日を証明する書類(カルテ、紹介状、受診状況等証明書など)
- 被共済者であったことを証明する書類(年金手帳や加入証明書など)
- 収入状況を確認できる書類(再就職時や就労中の場合)
提出のタイミングと相談窓口
申請書類は、退職後に共済組合から送付されるのが一般的です。
多くの組合では、退職後に届く年金請求書を受領し、必要書類を揃えて60日以内に提出する必要があります。
また、各地の公立学校共済組合では、担当支部や年金グループに電話で相談することも可能で、書類の形式や記入について詳しくアドバイスが受けられます。
退職後は退職届書や年金待機者登録通知書の提出も必要な場合があるため、住居変更や働き方の変化がある場合には速やかに手続きを行うことが重要です。
障害共済年金に関するよくある質問
障害共済年金には、受給に関してわかりづらい点が多く制度の内容や手続きに戸惑う方もいます。
不安や疑問を放置してしまうと、必要な手続きが遅れて年金が受け取れなくなる可能性もあるので疑問点を解決しましょう。
- 退職したら年金は自動的に止まりますか?
- 職域加算はいつまで支給されますか?
- 障害年金と他の年金は同時にもらえますか?
Q1:退職したら年金は自動的に止まりますか?
いいえ、退職しただけで障害共済年金が自動的に停止されることはありません。
共済組合の支給要件を満たしている限り、退職後も年金の支給は原則継続されます。
ただし、再就職などで状況が変化した場合や、年金更新時に提出すべき書類が不足している場合などは、一時的に支給が止まる可能性があるため注意が必要です。
継続受給のためには、診断書の提出や就労状況の報告など、共済からの連絡や案内にきちんと対応することが大切です。
Q2:職域加算はいつまで支給されますか?
職域加算は、障害共済年金に上乗せされる給付で年金の受給資格がある限り支給されます。
ただし、再び共済組合員として働く場合や、年金自体が支給停止となった場合は、職域加算も同時に停止されます。
制度内容は変更されることがあるため、最新の条件は所属していた共済組合に確認してください。
Q3:障害共済年金と他の年金は同時にもらえますか?
障害共済年金は、他の公的年金と原則として同時に満額で受給することはできません。
制度上、同じ性質(老齢・障害・遺族)の年金どうしは併給できないため、どちらか一方を選択する必要があります。
ただし、異なる性質の年金については、条件を満たせば併給が認められることもあります。
- 障害基礎年金と老齢厚生年金:年齢にかかわらず、両方の受給要件を満たしていれば併給可能。
- 障害基礎年金と遺族厚生年金:年齢に関係なく、併給が認められている。
一方で、 障害共済年金と老齢共済年金のように、同じ種類(共済)の異なる性質の年金どうしであっても原則はいずれか一方の選択が必要です。
障害共済年金の退職後に関する悩みを解決する方法とは?
ここでは、退職後の障害共済年金に関する悩みを解消するための方法をご紹介します。
障害共済年金は制度が複雑で、退職後の申請や再就職との関係、併給可否など不安を抱える方も多いです。
また、手続きや審査でつまずくと、本来受け取れる年金を逃してしまうこともあるので、こうした悩みを解決したい方におすすめなのが、「マネーキャリア」での無料相談です。
公的年金や共済年金に詳しいファイナンシャルプランナーが、個別の状況に応じて最適なアドバイスを行います。
何度でも無料で相談できるため、納得のいくまでじっくり話せるのが特徴です。

共済に関するすべての悩みにオンラインで解決できる
マネーキャリア:https://money-career.com/
<マネーキャリアのおすすめポイント>
・マネーキャリアでは、これまでの相談実績や満足度の高さをもとに独自の評価を行い、共済や民間保険に詳しい信頼できるファイナンシャルプランナーを厳選しています。
・保険の相談だけでなく、資産づくりや家計の見直し、将来設計などライフプラン全体のご相談にも対応しています。
・サービスを提供するのは丸紅グループの「株式会社Wizleap」で、これまでに10万件以上の相談実績があり利用者の満足度は98.6%と高評価です。
<マネーキャリアの利用料金>
・マネーキャリアでは、専門知識をもつファイナンシャルプランナーに何度でも無料で相談できます。
障害共済年金の退職後の制度を理解して安心して受給するためのまとめ
ここまで、障害共済年金が退職後も受け取れる仕組みや、受給に必要な条件、注意すべき手続きや支給停止のリスクなどを解説してきました。
記事のポイントをまとめると以下のとおりです。
- 障害共済年金は、退職後であっても一定の条件を満たせば原則として継続して受け取れる制度
- 支給を受けるには、障害等級・初診日・保険料納付期間といった要件をクリアする必要がある
- 再就職後の収入や障害の回復、書類不備などが原因で、年金の支給が停止される可能性もある
- 制度に不安がある場合は、マネーキャリアのような専門家の無料相談を活用することで、安心して手続きや将来設計を進められる