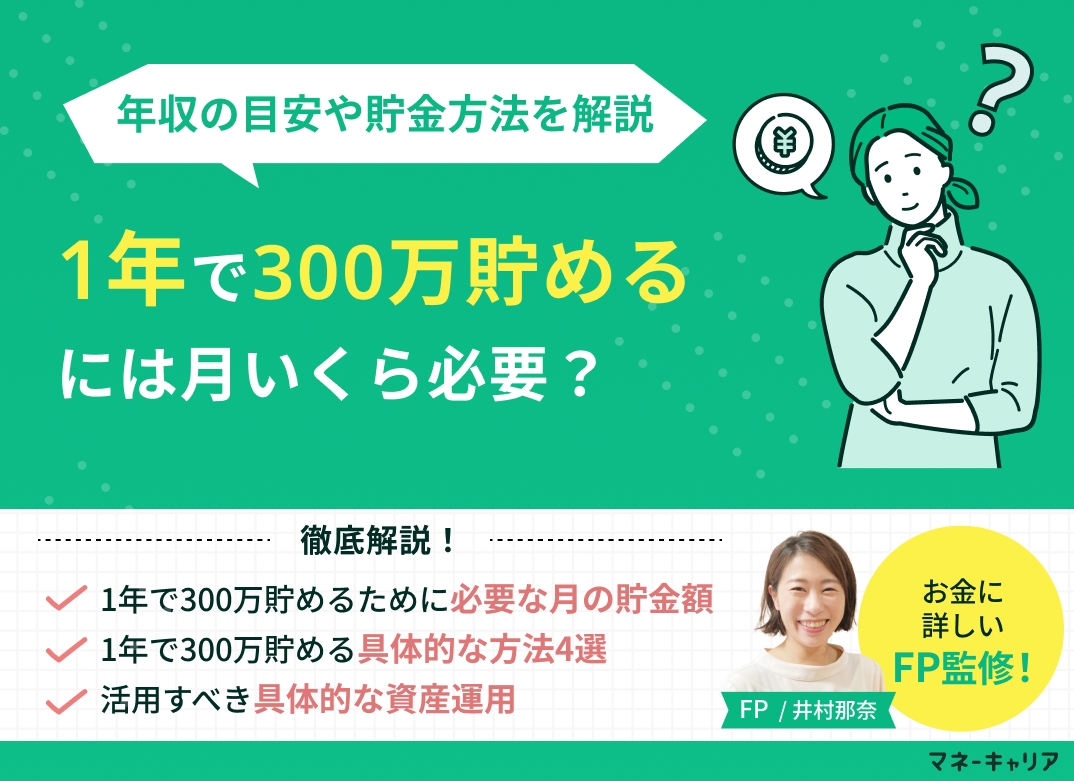内容をまとめると
- 所得税の課税最低限(103万の壁)が160万円に引き上げられたことで、税負担が軽くなり、パートやアルバイトでも収入を増やしやすくなります。
- 一方で、社会保険料や住民税の発生など、103万円(改正後160万円)以外にも注意すべき年収ラインがあり、事前に把握することが重要です。
- 配偶者控除や特定扶養控除も見直されたため、家計全体の税負担の変化を把握し、働き方の調整を再検討する必要があります。
- 制度の変化を踏まえ、収入計画を整理したい方は、相談実績10万件超・満足度98.6%超のマネーキャリアで、専門家に家計や働き方を相談することが有効です。

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 103万の壁はどうなった?基礎知識を解説
- 103万円の壁は所得税の壁
- 103万の壁が160万に引き上げられた背景
- 103万の壁が160万の壁に変わるメリット
- シフト調整のストレスが減る
- 月収が増えて生活にゆとりが生まれる
- 正社員・フルタイム勤務にも減税メリットがある
- 103万の壁が160万の壁に変わると手取りはいくら増える?年収別の減税額を解説
- 103万の壁が160万の壁に変わる際の注意点
- 社会保険の106万・130万の壁が残る
- 住民税が発生する可能性がある
- 配偶者控除・扶養控除に関わる103万の壁の改正内容
- 配偶者控除の壁も103万から123万に引き上げ
- 親が受けられる特定扶養控除も103万の壁を150万に引き上げ
- 103万の壁はどうなった?関連するよくある質問
- 103万円の壁はいつから廃止されますか?
- パートで1番損する年収はいくらですか?
- 103万の壁の改正内容を理解して損しない働き方を選ぼう【まとめ】
103万の壁はどうなった?基礎知識を解説
103万の壁の基礎知識について、2つ解説します。
紹介する内容は以下のとおりです。
- 103万円の壁は所得税の壁
- 103万の壁が160万に引き上げられた背景
位置づけや改正の理由を理解することで、制度を正しく把握し、本記事全体の理解がしやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
103万円の壁は所得税の壁
103万の壁は“所得税の壁”と呼ばれ、収入を抑える目安の一つでした。
従来は年収103万円を超えると、超えた部分に対して所得税が課税されました。
例えば、年収が113万円の場合は、103万円を超えた10万円の部分に5%の税率がかかり、約5,000円の負担になります。
しかし、令和7年度の税制改正により、この基準が160万円に引き上げられました。
そのため、従来であれば所得税が発生していた年収113万円などの方でも、今回の改正後は年収160万円以内であれば、所得税がかからなくなります。
この改正により、年収を103万円以上に増やしても、手取りが減る心配は少なくなります。
103万の壁が160万に引き上げられた背景
年収の壁が160万円に引き上げられた背景には、複数の事情があります。
政府は国民生活を守るため、物価上昇への対応を重要な課題と位置づけていました。
また、東京都の生活保護基準や最低賃金の水準なども、見直しの判断材料とされています。
こうした背景をふまえると、年収の壁は時代にあわせて変化していることがわかります。
103万の壁が160万に引き上げられた背景を知ることで、制度全体の理解が深まるでしょう。
※1参照:基礎控除の特例の創設について|自民党
103万の壁が160万の壁に変わるメリット
103万の壁が160万の壁に変わるメリットを、3つ解説します。
紹介するメリットは以下のとおりです。
- シフト調整のストレスが減る
- 月収が増えて生活にゆとりが生まれる
- 正社員・フルタイム勤務にも減税メリットがある
それぞれの特徴を知ることで、手取りや税負担の変化を見通しながら、自分に合った働き方を選びやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
シフト調整のストレスが減る
シフト調整のストレスが減るのが、103万の壁が160万の壁に変わるメリットの一つです。
非課税枠が広がり、「これ以上働くと損するかも」と不安に感じる収入の上限が引き上げられたからです。
これまで103万円を意識してシフトを減らしていた方も、安心して働く時間を増やしやすくなるでしょう。
また、人手不足の業界では、柔軟に働ける人が増えることで、労働力確保につながると期待されています。
年収の壁にとらわれず、自分のペースで働けるようになるのは、大きなメリットといえるでしょう。
月収が増えて生活にゆとりが生まれる
月収が増えて生活にゆとりが生まれることは、103万の壁が160万に変わるメリットの一つです。
これまで年収調整のために働き控えていた分まで働けるようになり、手取りが増えやすくなるからです。
例えば、週に数時間の残業や、月に数日間の勤務日を追加することで、家計に少し余裕を持たせることができます。
特に、扶養内で働く方にとっては、生活の安定感や気持ちの余裕を実感しやすくなるはずです。
正社員・フルタイム勤務にも減税メリットがある
正社員・フルタイム勤務にも減税の恩恵が広がる点が、103万の壁が160万の壁に変わるメリットの一つです。
令和7年度税制改正では、基礎控除や給与所得控除が拡大されたので、正社員などの方にとっても収入が同じでも課税対象が小さくなり、税負担が軽くなる可能性があります。
103万の壁の改正は、扶養内パートの話に見えがちですが、正社員やフルタイム勤務の方にも恩恵があるのが特徴です。
年収に応じて節税効果が得られることから、実質的に手取りが増える可能性があります。
具体的な年収別の減税額については、次の章で紹介します。
103万の壁が160万の壁に変わると手取りはいくら増える?年収別の減税額を解説
103万の壁が160万の壁に変わると、手取りは実際にいくら増えるのでしょうか。
政府が示した、単身の給与所得者を想定した年収別の減税額(所得税のみの試算)は、以下のとおりです。
| 給与収入 | 減税額 |
|---|---|
| 200万円 | 2.4万円 |
| 300万円 | 2.0万円 |
| 400万円 | 2.0万円 |
| 500万円 | 2.0万円 |
| 600万円 | 2.0万円 |
| 800万円 | 3.0万円 |
| 850万円〜2,545万円 | 2.0〜4.0万円 |
| 2,545万円超 | 0円 |
これにより、多くの人は年2〜4万円(月換算で約1,670円〜3,300円)の手取り増が見込めます。
特に、年収200万円前後の方にとっては、日々の家計へのうれしいあと押しとなるでしょう。
今回の改正では、全体の約8割以上の納税者が、減税メリットを受けられる見込みです。
また、高所得者だけが得をすることのないように、減税額の平準化も図られています。
103万の壁が160万の壁に変わる際の注意点
103万の壁が160万の壁に変わる際の注意点を、2つ解説します。
紹介する注意点は以下のとおりです。
- 社会保険の106万・130万の壁が残る
- 住民税が発生する可能性がある
あらかじめ注意点を押さえておくことで、損を防ぎながら自分に合った働き方を選びやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
社会保険の106万・130万の壁が残る
103万の壁が160万に変わっても、社会保険の“106万・130万の壁”は依然として残っている点に、注意が必要です。
106万円の壁とは、一定の条件を満たすパート・アルバイトの方が、社会保険への加入を義務づけられる年収基準のことです。
具体的には、従業員51人以上の企業で週20時間以上働き、月収8.8万円以上などの要件をすべて満たすと、106万円を超えた時点で社会保険(厚生年金と健康保険)の加入対象となります。
一方、従業員が50人以下の職場では、年収が130万円を超えると配偶者の扶養から外れ、国民健康保険や国民年金に加入する必要が出てくることが多いです。
ちなみに、社会保険料の負担は年収の約15%です。
例えば年収106万円の場合だと、年間で約15万9,000円が差し引かれます。
住民税が発生する可能性がある
住民税が発生する可能性がある点にも、注意が必要です。
所得税は“160万円の壁”を超えない限り発生しませんが、住民税はそれより低い年収でもかかることがあります。
多くの自治体では、年収110万円が課税対象になる基準です。
例えば年収120万円の場合、所得税はかかりません。
しかし、住民税は目安として、年間で約1万5,000円の負担が見込まれます。
収入が増えても手取りが減るケースを防ぐため、住民税の基準も事前に確認しておくと安心です。
配偶者控除・扶養控除に関わる103万の壁の改正内容
配偶者控除・扶養控除に関わる103万の壁の改正内容を、2つ解説します。
紹介する改正内容は以下のとおりです。
- 配偶者控除の壁も103万から123万に引き上げ
- 親が受けられる特定扶養控除も103万の壁を150万に引き上げ
それぞれの改正内容を知ることで、収入と控除のバランスを見直しやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
配偶者控除の壁も103万から123万に引き上げ
令和7年度の税制改正では、配偶者控除の適用条件が従来の年収103万円以下から、123万円以下へと変更されました。
配偶者控除とは、妻の収入が一定額以下であれば、夫の課税所得から最大38万円が差し引かれ、所得税が安くなる制度です(もちろん、夫婦の立場が逆の場合でも同様に適用されます)。
この改正により、夫が配偶者控除を受けるために、働く時間をセーブして収入をおさえていた方も、より自由に働きやすくなります。
ただし、妻の収入が123万円を超えると、段階的に控除額が減っていく“配偶者特別控除”の対象となり、夫の税負担が少しずつ増える仕組みです。
控除額が急にゼロになることはありませんが、手取りへの影響を考慮して、収入の調整を検討しておくと安心です。
親が受けられる特定扶養控除も103万の壁を150万に引き上げ
令和7年度の税制改正では、親が受けられる特定扶養控除の上限が、従来の子の年収103万円から150万円へと引き上げられました。
特定扶養控除とは、大学生年代(19歳以上23歳未満)の子どもの収入が一定以下である場合に、扶養している親の所得から63万円が差し引かれる制度です。
これまでは子どもの年収が103万円以下であることが条件でしたが、新たに上限が150万円となり、より働きやすくなりました。
さらに、"特定親族特別控除"が新設され、子の年収が150万円を超えても188万円までは、控除額が段階的に減る仕組みが整えられています。
この改正により、学生アルバイトの収入が増えても、扶養者の手取りが急に減る心配が少なくなりました。
103万の壁はどうなった?関連するよくある質問
103万の壁に関連するよくある質問を、2つ解説します。
紹介する質問は以下のとおりです。
- 103万円の壁はいつからなくなりますか?
- パートで1番損する年収はいくらですか?
改正のタイミングや損を避ける収入ラインを知っておくことで、今後の働き方や収入の目安を検討しやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
103万円の壁はいつから廃止されますか?
所得税の基礎控除額が引き上げられたことにより、いわゆる“103万円の壁”と呼ばれる所得税非課税ラインは、2025年(令和7年)から160万円へと実質的に引き上げられました。
これは、物価や最低賃金の上昇をふまえ、税制全体の見直しが行われたためです。
改正後は、年収160万円までは所得税がかからなくなります。
非課税枠が大きく広がることで、これまでより働く時間を調整しやすくなるでしょう。
今後の収入計画を立てる際は、この新しい基準を意識しておくことが大切です。
パートで1番損する年収はいくらですか?
パートで手取りが最も減りやすい年収ラインのひとつは、おおむね130万円です。
この金額を超えると、配偶者(夫)の扶養から外れてしまい、自分で健康保険や年金などの社会保険料を支払う必要が出てきます。
その結果、手取りが大きく減りやすくなる点に注意が必要です。
社会保険料の負担額は、年収の約15%が目安で、130万円の場合は年間で約19万5,000円が給料から差し引かれます。
働く時間や収入を決めるときは、手取りベースでの損得やライフスタイルに合った年収設定を意識するとよいでしょう。
103万の壁の改正内容を理解して損しない働き方を選ぼう【まとめ】
103万の壁の改正内容を理解しておくことで、自分に合った損しない働き方を選びやすくなります。
今回の改正では、非課税となる年収の上限が160万円に引き上げられ、配偶者控除や特定扶養控除の見直しも行われました。
関連して、住民税や社会保険の負担に関する注意点も確認しておきましょう。
こうした制度の変化を正しく把握することで、将来を見据えた安定的な収入計画を立てやすくなります。
とはいえ、複雑な年収ラインを一人で整理し、最適な選択をするのは簡単ではありません。
税負担の変化や控除に不安を感じる方や、どの働き方を選ぶべきか迷っている方は、専門家(FP)への相談をおすすめします。