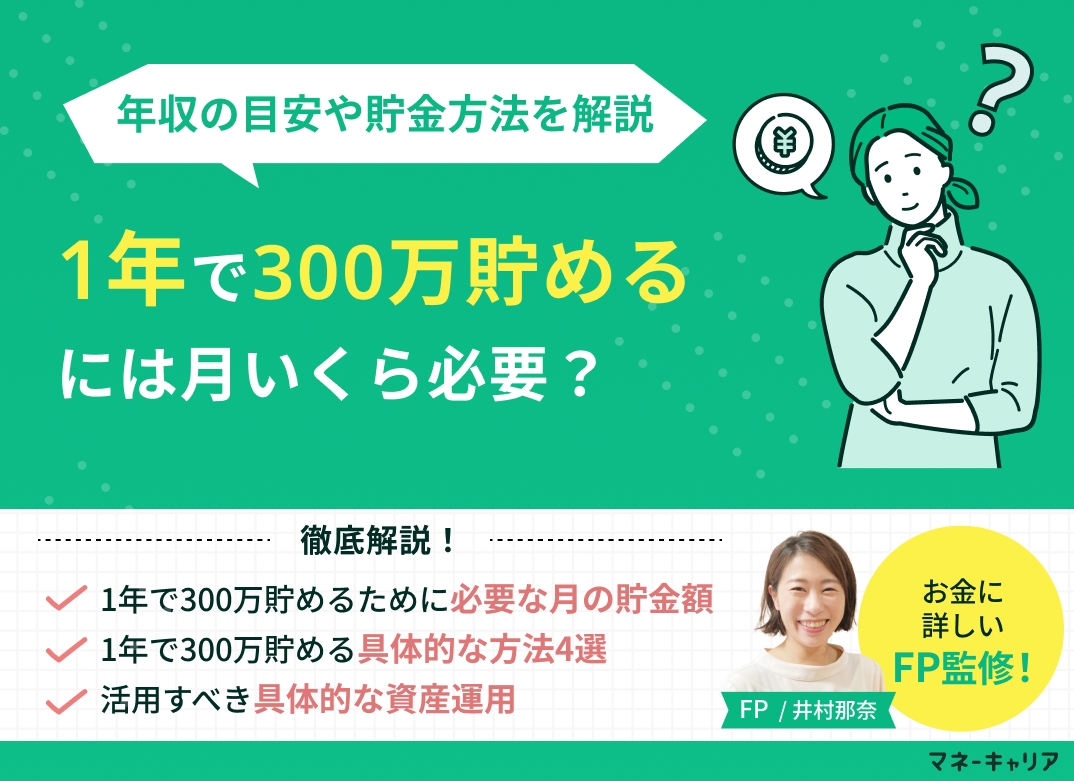内容をまとめると
- 離婚せず別居する際の生活費(婚姻費用)には分担義務がある
- 生活費が支払われないトラブルもあるため注意が必要
- FPに相談すれば家計の見直しや将来設計についてアドバイスが得られる
- マネーキャリアは相談実績10万件以上でお金の悩みを解決できる
- 家計の見直しや将来設計に関する相談ならマネーキャリアがおすすめ

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 離婚せず別居する際の生活費(婚姻費用)はどうする?
- 生活費(婚姻費用)は夫婦で分担義務がある
- 生活費(婚姻費用)には何が含まれる?
- 離婚せず別居する際の生活費(婚姻費用)の相場
- 離婚せず別居する際の生活費(婚姻費用)の決め方
- 夫婦間で話し合って決める
- 養育費・婚姻費用算定表をもとに金額を算出する
- 話し合いで合意できない場合は調停や審判を利用する
- 離婚せず別居する際の生活費(婚姻費用)が不足するときの対処法
- 婚姻費用の増額を相手に請求する
- 実家への引っ越しを検討する
- 一時的な収入源を確保する
- 家計を見直して支出を抑える
- 離婚せず別居する際の生活費(婚姻費用)が支払われないときの請求方法
- 内容証明郵便で支払いを求める
- 家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てる
- 支払いがない場合は強制執行を申し立てる
- 離婚せず別居する際の生活費(婚姻費用)の注意点
- 勤務先の手当が受け取れなくなる可能性もある
- 別居の理由や経緯によっては婚姻費用が認められないこともある
- 婚姻費用だけに頼る生活設計は危険
- 離婚せず別居する際は生活費(婚姻費用)は事前にしっかり話し合おう【まとめ】
離婚せず別居する際の生活費(婚姻費用)はどうする?
離婚せずに別居する場合、生活費(婚姻費用)をどのように負担するのか、どのような費用が含まれるのかを事前に把握しておくことは大事です。
トラブルの回避にもつながります。
- 生活費(婚姻費用)は夫婦で分担義務がある
- 生活費(婚姻費用)には何が含まれる?
生活費(婚姻費用)は夫婦で分担義務がある
離婚が成立するまでは、たとえ別居していても法的に婚姻関係が続いているため、夫婦には生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。
民法第760条では、夫婦は婚姻に伴う生活費や必要な費用を互いに負担する責任が定められています。
そのため、別居しているからといって「生活費を支払わない」「将来的に離婚するかもしれないので支払いたくない」といった理由は通用しません。
例えば、夫が働き妻が専業主婦の場合は夫が生活費をすべて負担し、共働きの場合は収入に応じて適切に分担するのが一般的です。
離婚が成立していない限り、別居中でも生活費(婚姻費用)の負担義務があることを理解して、具体的な金額や支払い方法について早めに話し合うことが大切です。
※参照:民法 | e-Gov 法令検索
生活費(婚姻費用)には何が含まれる?
生活費(婚姻費用)には、一般的に次のような項目が含まれます。
・食費
・日用品費
・衣服費
・水道光熱費
・住居費
・医療費
・子どもの生活費や教育費
・出産費用
・冠婚葬祭費
・交際費
・娯楽費
・交通費など
このように、日常生活に必要な費用だけでなく、子どもの養育や家族としての社会的な関わりに必要な費用も、婚姻費用に含まれます。
生活費(婚姻費用)の金額は、夫婦の話し合いで決めることもありますが、婚姻費用算定表をもとに算出するのが一般的です。
離婚せず別居する際の生活費(婚姻費用)の相場
離婚せず別居する際の生活費(婚姻費用)の相場を知っておくことは大切です。
相場を知っておけば、相手との話し合いや今後の資金計画が進めやすくなります。
以下では、裁判所が基準として用いている「婚姻費用算定表」にもとづき、代表的なケースをもとに生活費(婚姻費用)の目安を算出しています。
| 世帯構成 | 夫の年収 | 妻の年収 | 月の生活費目安 |
|---|---|---|---|
| 夫婦のみ | 600万円 | 200万円 | 6万〜8万円 |
| 800万円 | 300万円 | 8万〜10万円 | |
| 1,000万円 | 専業主婦 | 16万〜18万円 | |
| 夫婦+子ども1人(0〜14歳) | 600万円 | 200万円 | 10万〜12万円 |
| 800万円 | 300万円 | 12万〜14万円 | |
| 1,000万円 | 専業主婦 | 20万〜22万円 | |
| 夫婦+子ども2人(15歳以上と0〜14歳) | 600万円 | 200万円 | 12万〜14万円 |
| 800万円 | 300万円 | 14万〜16万円 | |
| 1,000万円 | 専業主婦 | 22万〜24万円 |
※給与所得者の場合
※夫が義務者(払う方)、妻が権利者(もらう方)の場合
養育費・婚姻費用算定表の金額はあくまで目安で、必ずしもその通りに決まるわけではありませんが、参考として活用することができます。
※参照:養育費・婚姻費用算定表|裁判所
離婚せず別居する際の生活費(婚姻費用)の決め方
離婚せずに別居する場合、生活費(婚姻費用)の取り決めはとても大事です。
主な方法としては、以下の3つがあります。
- 夫婦間で話し合って決める
- 婚姻費用算定表をもとに金額を算出する
- 話し合いで合意できない場合は調停や審判を利用する
夫婦間で話し合って決める
離婚せず別居する場合の生活費(婚姻費用)は、夫婦でしっかりと話し合って決めることが大切です。
生活費(婚姻費用)には、衣食住にかかる基本的な生活費に加え、子どもの教育費なども含まれます。
そのため、必要な金額や分担の内容について話し合い、お互いが納得できる金額を決めましょう。
金額を取り決めたあとは、口約束のままだと後にトラブルへ発展する恐れがあります。
トラブルを防ぐためにも、婚姻費用に関する合意内容は書面に残し、公正証書として正式に作成しておくことが大事です。
また、金額だけでなく、「いつからいつまで支払うのか」「どのような方法で支払うのか」といった具体的な取り決めもしておきましょう。
養育費・婚姻費用算定表をもとに金額を算出する
生活費(婚姻費用)を決める際に多く利用されているのが、裁判所が基準としている「婚姻費用算定表」をもとに金額を算出する方法です。
養育費・婚姻費用算定表では、夫婦それぞれの年収や子どもの人数、年齢などを考慮して、月々の婚姻費用の目安が示されています。
一定の基準にもとづいた金額により、公平な金額を導き出すことが可能です。
また、婚姻費用算定表は誰でもインターネットで閲覧できるため、話し合いの前に目安を確認しておくと、スムーズな交渉につながります。
※参照:養育費・婚姻費用算定表|裁判所
話し合いで合意できない場合は調停や審判を利用する
夫婦間の話し合いだけでは合意に至らない場合は、家庭裁判所を通じて調停や審判を申し立てる方法があります。
相手との関係がこじれている場合でも、第三者(裁判所)が関与することで、冷静かつ客観的に話し合いを進めることが可能です。
調停では、調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら合意点を探っていきます。
それでも折り合いがつかない場合は、裁判所が婚姻費用の金額や支払い方法を最終的に決定します。
離婚せず別居する際の生活費(婚姻費用)が不足するときの対処法
離婚せず別居する場合の生活費(婚姻費用)が不足する場合、次のような対策を検討することで、状況を改善できることがあります。
- 婚姻費用の増額を相手に請求する
- 実家への引っ越しを検討する
- 一時的な収入源を確保する
- 公的支援制度の活用を検討する
- 家計を見直して支出を抑える
婚姻費用の増額を相手に請求する
別居中の婚姻費用を決めた後でも、事情により生活費が不足する場合には相手に増額を求めることができます。
例えば「勤務先を解雇されて収入が途絶えた」「子どもが私立に進学して教育費が増えた」など、生活環境の変化や予期せぬ事情が発生した場合には、すでに取り決めた金額では対応できないこともあります。
このような場合には、夫婦間で話し合い、合意に至れば金額を変更することが可能です。
また、夫婦間で合意に至らなくても、増額を求める正当な理由があれば、調停や審判を通じて金額の変更が認められる場合もあります。
実家への引っ越しを検討する
離婚せず別居する際に生活費(婚姻費用)が不足する場合の対策として、実家に戻るのも一つの方法です。
実家に戻れば、家賃や光熱費といった住居関連の支出を大幅に抑えられるため、家計に余裕ができる可能性が高くなります。
また、親からのサポートを受けられることで、食費や日用品費などの負担も軽減できる場合があります。
ただし、実家に戻る際は、親との生活リズムの違いやプライバシーの問題に注意が必要です。
特に子どもが思春期の場合は、親としっかり話し合い無理のない環境づくりを心がけることが大切です。
一時的な収入源を確保する
離婚せず別居する際に生活費(婚姻費用)が不足した場合は、一時的な収入源を確保することも対処法の一つです。
例えば、専業主婦がパートを始めたり、派遣社員が掛け持ちの仕事をしたり、正社員が副業に挑戦するなど、新たな収入を得ることで家計に余裕が生まれる可能性があります。
また、スキマ時間を利用したバイトや在宅ワークなら子育てとの両立もしやすく、効率的に収入を増やすことが可能です。
家計を見直して支出を抑える
離婚せずに別居している中で生活費(婚姻費用)が足りないと感じたら、まずは家計の見直しを行い、支出を抑える工夫をしましょう。
食費や光熱費、通信費、交際費といった日常の支出を見直すことで、家計にゆとりを持たせることができます。
また、税金対策を行い税負担を軽減するのも効果的です。
家計の見直しに不安がある場合は、FPへの相談がおすすめです。
FPに相談すれば、家庭の状況やライフスタイルに応じた家計の見直し方法や、節約・節税に関してアドバイスを受けられます。
離婚せず別居する際の生活費(婚姻費用)が支払われないときの請求方法
離婚せずに別居している中で、生活費(婚姻費用)が支払われない場合は、次のような手段で相手に支払いを求めることができます。
- 内容証明郵便で支払いを求める
- 家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てる
- 支払いがない場合は強制執行を申し立てる
内容証明郵便で支払いを求める
離婚せずに別居している中で、生活費(婚姻費用)が支払われず、話し合いも進まない場合は、内容証明郵便を使って相手に支払いを求める方法があります。
内容証明郵便とは「いつ・誰が・誰に・どのような内容の文書を送ったか」を公的に証明してくれるサービスです。
後に調停や裁判に発展した場合にも、内容証明郵便は証拠として有効です。
内容証明郵便には相手に一定の心理的プレッシャーを与える効果があるため、支払いに応じなかった相手が対応してくる可能性があります。
家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てる
内容証明郵便を送っても生活費(婚姻費用)の支払いがなされない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てるという方法があります。
裁判所が間に入り、生活費(婚姻費用)の問題を整理・解決する手続きです。
裁判所という第三者が関与することで、相手に対するプレッシャーや法的な意識が高まり、これまで支払いを拒んでいた場合でも合意に至る可能性が高くなります。
調停で合意が成立すると調停調書が作成され、相手の支払いが滞った場合には強制執行も可能になります。
支払いがない場合は強制執行を申し立てる
調停で合意に至ったにもかかわらず、生活費(婚姻費用)が支払われない場合は、裁判所を通じて強制執行を申し立てることが可能です。
強制執行が認められると、相手の財産が差し押さえられ、その中から未払い分の生活費(婚姻費用)が回収されます。
強制執行を進める際には専門的な知識が必要となるため、できるだけ早い段階で弁護士などの専門家に相談することが大切です。
離婚せず別居する際の生活費(婚姻費用)の注意点
離婚せず別居する際の生活費(婚姻費用)について、次の点に注意が必要です。
- 勤務先の手当が受け取れなくなる可能性もある
- 別居の理由や経緯によっては婚姻費用が認められないこともある
- 婚姻費用だけに頼る生活設計は危険
勤務先の手当が受け取れなくなる可能性もある
別居することで、勤務先から支給されている各種手当が受け取れなくなる可能性もあるため、事前の確認が必要です。
例えば、扶養手当や家族手当、住宅手当などは、家族と同居していることを支給条件としている企業もあります。
そのため、別居によって条件を満たさなくなると、手当の支給が停止される場合があります。
手当がなくなることで収入が減り、生活費(婚姻費用)にも影響が出る恐れがあるため注意が必要です。
別居により手当が停止される場合は、支出を調整するなどしてバランスを取るようにしましょう。
別居の理由や経緯によっては婚姻費用が認められないこともある
別居の原因や経緯によっては、生活費(婚姻費用)の請求が認められないケースがあるため注意が必要です。
例えば、自身の不貞行為などが原因で別居に至った場合は「有責配偶者」とみなされ、婚姻費用を請求できない可能性があります。
また、正当な理由なく一方的に家を出て別居した場合も、請求が認められないことがあります。
生活費(婚姻費用)の請求が可能かどうか不安がある場合は、事前に自治体窓口や弁護士などに相談してみましょう。
婚姻費用だけに頼る生活設計は危険
生活費(婚姻費用)は、思っていたより少ない金額になることもあれば、相手が支払わない可能性もあるため、婚姻費用だけをあてにした生活設計では家計が破綻する恐れもあります。
より安定した生活を送るためには、在宅ワークやアルバイト・パートなどで収入を得たり、家計を見直して支出を抑えたりすることが大事です。
突然の出費などに備えるためにも、家計には余裕を持たせておくよう心がけましょう。
離婚せず別居する際は生活費(婚姻費用)は事前にしっかり話し合おう【まとめ】
離婚せず別居する場合、夫婦には生活費(婚姻費用)を分担する義務があるため、金額や期間、支払い方法などについて事前に取り決めておく必要があります。
ただし、生活費(婚姻費用)が希望通りの金額になるとは限らず、支払いが滞るリスクもあるため、アルバイトなどで収入を補ったり、家計を見直して支出を抑えたりといった工夫も大事です。
法的な不明点がある場合は自治体の窓口や弁護士に、お金に関する不安がある場合はFPへの相談を検討してみましょう。
トラブルリスクを回避して、安心して生活を送るためにも確かな知識を持って進めていくことが重要です。