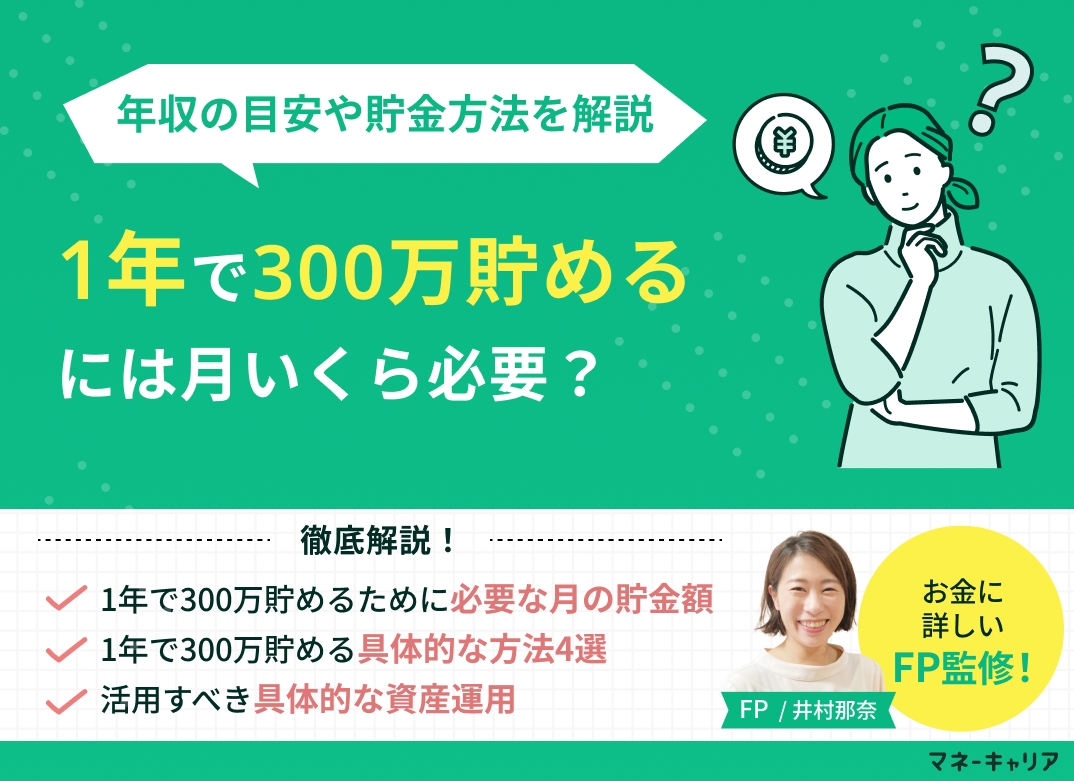内容をまとめると
- 親の介護で退職して生活費が不足しそうな場合は早めの対策が大切
- 介護のことを福祉事務所やケアマネージャー、お金のことはFPに相談
- FPに相談すれば家計の見直しや将来設計についてアドバイスが受けられる
- マネーキャリアは相談実績10万件以上でお金の悩みを解決できる
- 家計改善、節約、資産形成に関する相談ならマネーキャリアがおすすめ

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 親の介護で退職した場合に生活費はいくらかかる?
- 親の介護費用
- 退職後の生活費
- 親の介護で退職した場合に生活費を確保する方法
- 退職前に計画的に貯金して備える
- 在宅ワークやアルバイトで収入を得る
- 親の年金や貯金を生活費に充てる
- 失業手当(失業保険)を活用する
- 自治体の支援制度や独自サービスを活用する
- 親の介護で退職して生活費が不足したときの対処法
- 公的支援・負担軽減制度を活用する
- 生活保護の申請を検討する
- 持ち家を担保にしてお金を借りる
- 施設入居を検討して再就職をする
- 自治体の窓口やケアマネージャーに相談する
- お金の専門家(FP)に相談する
- 親の介護で退職した場合に生活費を支える公的支援・負担軽減制度
- 家族介護慰労金
- 高額介護サービス費
- 高額医療・高額介護合算療養費制度
- 居宅介護住宅改修費
- 親の介護で退職した後の生活費も踏まえて今後の行動を考えよう【まとめ】
親の介護で退職した場合に生活費はいくらかかる?
親の介護のために退職した場合、生活費がどの程度かかるのかを把握しておくことは大切です。
費用の目安がわかれば、今後の資金計画も立てやすくなります。
ここでは、以下の2つの費用について目安を紹介します。
- 親の介護費用
- 退職後の生活費
親の介護費用
公益財団法人 生命保険文化センターの調査によれば、介護にかかる費用は平均で月額9万円となっています。
要介護度ごとの平均的な介護費用は、以下のとおりです。
- 要支援1:月5.8万円
- 要支援2:月7.0万円
- 要介護1:月5.4万円
- 要介護2:月7.5万円
- 要介護3:月8.5万円
- 要介護4:月12.4万円
- 要介護5:月11.3万円
- 公的介護保険の利用経験なし:月4.0万円
また、介護の平均期間は平均55.0ヶ月(4年7カ月)となっています。
月に9万円の介護費用で55ヶ月介護を行ったとすれば、495万円かかることになります。
ただし、家庭によって介護費用は異なり、月に15万円以上かかるケースもあるため、事前にシミュレーションを行い、資金計画を立てておくことが大切です。
退職後の生活費
総務省統計局の調査によると、世帯人数別の平均的な生活費は以下のとおりです。
| 生活費の平均 | |
|---|---|
| 二人以上世帯 | 月30万243円 |
| 単身世帯 | 月16万9,547円 |
上記のとおり、退職して介護に専念する場合、二人以上の世帯で生活費のすべてをまかなう必要があると、1ヶ月30万243円程度の支出が目安となります。
その際は、親の年金や自身の貯金、アルバイトによる収入などを組み合わせて生活費をカバーする必要があります。
一方、自身の生活費のみを負担すればよい状況であれば、単身世帯の平均である月16万9,547円程度が目安となり、その金額を収入や貯金で補うことが必要です。
どのようにして生活費を負担するのか、早めのタイミングで計画を立てておくことが大切です。
親の介護で退職した場合に生活費を確保する方法
親の介護のために退職した場合に生活費を確保する方法として、次のような選択肢があります。
- 退職前に計画的に貯金して備える
- 在宅ワークやアルバイトで収入を得る
- 親の年金や貯金を生活費に充てる
- 兄弟姉妹と生活費を分担する
- 失業手当(失業保険)を活用する
- 自治体の支援制度や独自サービスを活用する
退職前に計画的に貯金して備える
親の介護で退職を検討している場合は、退職前に計画的に貯金を進めておくと安心です。
退職後の生活費を事前にシミュレーションして、その結果をもとに、退職までの期間を有効に使って貯金を積み立てていきましょう。
現役で働いている間は収入が安定しているため、比較的お金を貯めやすい時期です。
できるだけ多くの貯金をしておくことで、退職後の経済的な不安を軽減できます。
また、家計を見直して無駄な支出を削減することで、手元に残るお金が増えて貯金額をさらに増やすことが可能です。
在宅ワークやアルバイトで収入を得る
親の介護で退職した後も、生活費を確保する手段として在宅ワークやアルバイトで収入を得る方法があります。
介護が1日中必要でない場合は、空いた時間を活用して仕事に取り組むことで、一定の収入を得ることが可能です。
最近では、クラウドソーシングやスキマバイトなど柔軟に働ける仕事が増えており、収入を得やすい環境が整っています。
令和6年度の全国平均の最低賃金は1,055円で、地域によって差はありますが、週5日・1日5時間程度働けば、月に10万円以上の収入が見込めます。
また、在宅ワークやアルバイトを通じて外部の人との関わりを持つことは、精神的なリフレッシュにもつながるため、介護生活を続ける上でも大切なことです。
親の年金や貯金を生活費に充てる
親の介護を理由に退職した場合、生活費を確保する手段の一つとして、親の年金や貯金を生活費に充てる方法があります。
例えば、次のような状況ではこの方法を検討してもよいでしょう。
・1日中介護が必要な状況で外出が難しい
・アルバイト・パートができない環境にある
・親自身が年金や貯金の活用を勧めてくる
ただし、親の年金や貯金が十分でなければ、生活費を安定してまかなうのは難しくなります。
参考までに、厚生労働省の調査によると、令和5年度における年金受給額の平均(厚生年金を含む)は月額14万6,429円です。
アルバイトが見つかるまでの一時的な手段として活用するなど、状況に応じて取り入れることが大切です。
失業手当(失業保険)を活用する
親の介護で退職して生活費の確保が難しくなった場合には、失業手当(失業保険)を活用するのも一つの方法です。
退職前の1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があるなど、一定の条件を満たし、親の介護を理由にやむを得ず離職した場合は「特定理由離職者」として失業手当を受給できる可能性があります。
受給資格の有無や支給額、手続きの流れなどについては、早めにハローワークで確認しておくと安心です。
自治体の支援制度や独自サービスを活用する
自治体によっては、介護にかかる費用や負担を軽減するために、さまざまな独自サービスを提供している場合があります。
例えば、介護に伴う住宅リフォーム費用の助成、配食サービス(食事の宅配)、通院や買い物のための外出支援、訪問介護や見守りサービスなどがあります。
これらのサービスによって、介護にかかる経済的・精神的な負担を軽減し、その分を生活費を生活費に回すことが可能です。
自治体によって独自サービスの有無や内容は異なるため、早めに確認しておきましょう。
親の介護で退職して生活費が不足したときの対処法
親の介護で退職して生活費が足りなくなったときは、次のような方法で対処できます。
- 公的支援・負担軽減制度を活用する
- 生活保護の申請を検討する
- 持ち家を担保にしてお金を借りる
- 施設入居を検討して再就職をする
- 自治体の窓口やケアマネージャーに相談する
- お金の専門家(FP)に相談する
公的支援・負担軽減制度を活用する
親の介護で退職して生活費が不足したときは、公的支援制度や負担軽減制度を活用する方法があります。
家族介護慰労金や高額介護サービス費、高額医療・高額介護合算療養費制度など、介護や医療にかかる費用を軽減するための制度が複数用意されています。
例えば、家族介護慰労金は、一定の要件を満たす場合に自治体から年間で10万〜12万円程度支給される制度です。
これらの制度を利用することで、経済的な負担を抑え、限られた生活費の中でも安心して介護生活を送ることが可能です。
制度の内容や対象条件に関して、早めに地域の窓口で確認しておきましょう。
生活保護の申請を検討する
介護のために退職して、収入が途絶えた上に貯金などの余裕もなく、安定した生活を送ることが難しい場合には、生活保護の利用を検討するのも一つの選択肢です。
生活保護は、生活に困窮している人が最低限度の暮らしを維持できるよう支援する公的制度です。
支給額は、国が定めた「最低生活費」から、給与や年金、仕送りなどの収入を差し引いた不足分が支給される仕組みです。
また、住宅費を補助する「住宅扶助」や、医療・介護にかかる費用を支援する「医療扶助」「介護扶助」なども受けることができます。
審査があるため、誰でも必ず受けられるわけではありませんが、生活が厳しい場合は早めに福祉事務所やケアマネージャーに相談しましょう。
※参照:生活保護制度|厚生労働省
持ち家を担保にしてお金を借りる
親や自分が持ち家を所有している場合、持ち家を担保にしてお金を借りる「リバースモーゲージ」を検討する方法があります。
リバースモーゲージは、契約者が生きている間は利息のみを支払い、死亡後に担保としている自宅を売却することで返済する仕組みです。
また、自宅を一度売却した上で、賃貸としてそのまま住み続けられる「リースバック」という方法もあります。
まとまった資金を得ることができ、住み慣れた家で暮らし続けられる点がメリットです。
このように、持ち家を活用して資金を確保して、生活費を補うことも可能です。
施設入居を検討して再就職をする
生活費が不足したときの対処法として、親に介護施設へ入居してもらい、自身は再就職して収入を確保するという方法があります。
施設に入居することで費用はかかりますが、在宅介護で生じる精神的・身体的な負担が減り、働く時間も確保できる点がメリットです。
特に、次のような状況にあてはまる場合には、施設への入居を検討できます。
- 親自身が介護施設への入居を希望している
- 在宅介護の負担が大きく心身ともに限界を感じている
- 介護によって収入が絶たれ今後の生活が立ち行かない
- 他の家族の協力があり分担ができる
入居可能な施設や費用、介護保険の利用条件などを事前に確認し、家族とも相談しながら進めることが大切です。
自治体の窓口やケアマネージャーに相談する
親の介護で退職して生活費が不足している場合は、早めに自治体の窓口やケアマネージャーに相談することが大切です。
相談することで、家計を支えるための公的支援や自治体独自の補助制度などについて具体的な情報や提案を受けられます。
また、日々の介護に関する悩みや不安について、専門的な視点からアドバイスをもらえるため、精神的な負担を軽減することにもつながります。
特に悩みや不安がある場合は、早めに相談しておくことが大事です。
お金の専門家(FP)に相談する
退職後の生活費が不足しそうなときは、FPに相談してみましょう。
FPに相談することで、家計の見直しや今すぐ実践できる対策について、具体的なアドバイスを受けることができます。
固定費や変動費の削減、税金対策によって支出を抑えることができれば、生活費にゆとりを持たせることも可能です。
親の介護で退職した場合に生活費を支える公的支援・負担軽減制度
親の介護で退職した場合、生活費を支えるために利用できる公的支援や負担軽減制度には、次のようなものがあります。
- 家族介護慰労金
- 高額介護サービス費
- 高額医療・高額介護合算療養費制度
- 居宅介護住宅改修費
家族介護慰労金
家族介護慰労金は、要介護4〜5の認定を受けている方を介護保険サービスを利用せずに在宅介護している家族に対して支給される制度です。
対象は市民税非課税世帯など、一定の条件を満たす必要があります。
支給額は自治体によって異なりますが、おおむね年間10万〜12万円程度です。
家族介護慰労金を受給するためには、自治体の窓口で所定の申請書を提出する必要があります。
高額介護サービス費
高額介護サービス費とは、1ヶ月間に支払った介護サービスの自己負担額が一定の上限を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。
例えば、市町村民税非課税世帯の上限額は1万5,000〜2万4,600円、生活保護受給者は1万5,000円、どちらにも該当しない場合は3万7,200円が上限です。
高額介護サービス費を利用すれば、家計の負担を軽減できるため、生活費に余裕を持たせることが可能になります。
高額医療・高額介護合算療養費制度
高額医療・高額介護合算療養費制度は、介護保険と医療保険をどちらも利用する世帯の経済的負担を軽減するための制度です。
1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、所得や年齢に応じた上限額を超えた場合に、超過分が払い戻されます。
上限額は年齢や世帯の所得状況によって異なり、19万〜212万円で設定されています。
居宅介護住宅改修費
居宅介護住宅改修費は、自宅で介護リフォームを行う際に支給される補助金です。
要介護者が暮らしやすい環境を整えるため、次のような改修工事が対象となります。
- 手すりの取付け
- 段差の解消(スロープ設置など)
- 扉の引き戸への交換
- 和式トイレから洋式トイレへの交換
- 滑り防止や移動をしやすくするための床材変更
補助額の上限は20万円です。
制度を利用する際は、事前に自治体へ申請書類を提出して承認を受けてから工事を行うことが必要です。
工事完了後に領収書などを提出することで、補助金が支給されます。
親の介護で退職した後の生活費も踏まえて今後の行動を考えよう【まとめ】
親の介護で退職を考えている場合は、事前に貯金を増やしたり、在宅ワークやアルバイトに取り組むなどして、退職後も生活を維持できるよう準備しておくことが大切です。
生活費が不足しそうな場合には、生活保護の申請や再就職の検討など、状況に応じて早めに行動することが重要です。
また、FPに相談すれば、家計の見直しや将来設計について具体的なアドバイスが受けられるため、退職後の生活費の備えや不足時の対策としても有効です。
介護を理由に退職する可能性がある方は、早い段階で必要な生活費や介護費用をシミュレーションして、資金準備や利用できる制度の情報収集を行い計画的に進めるようにしましょう。