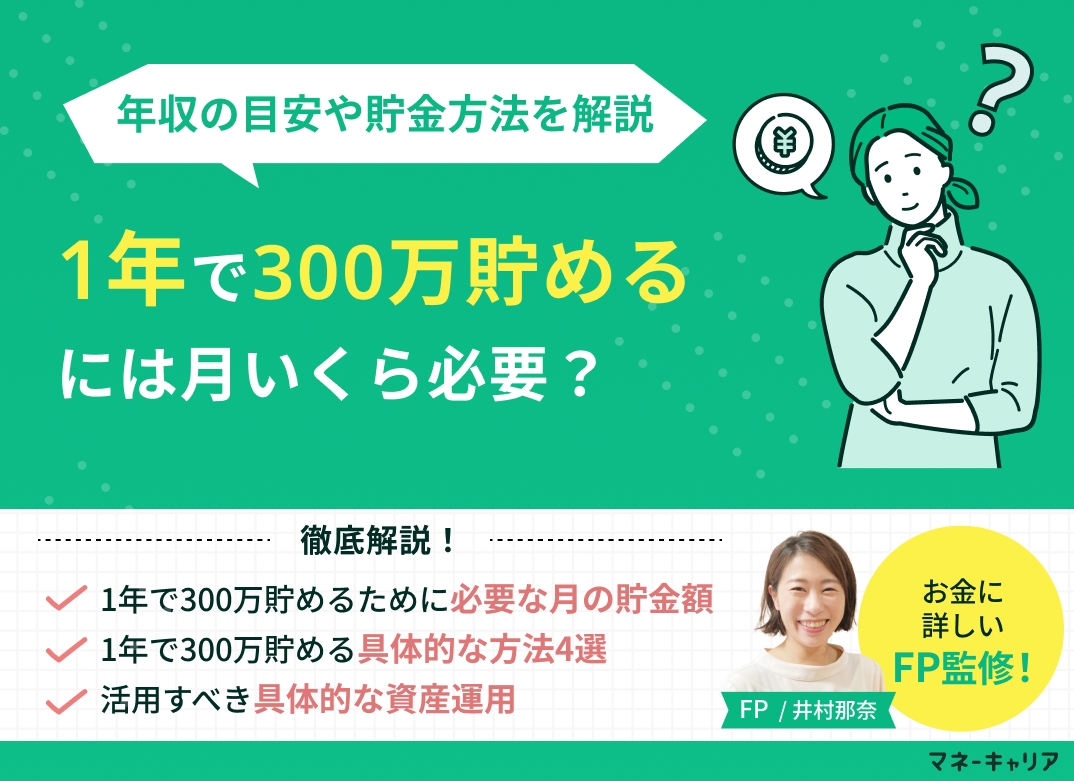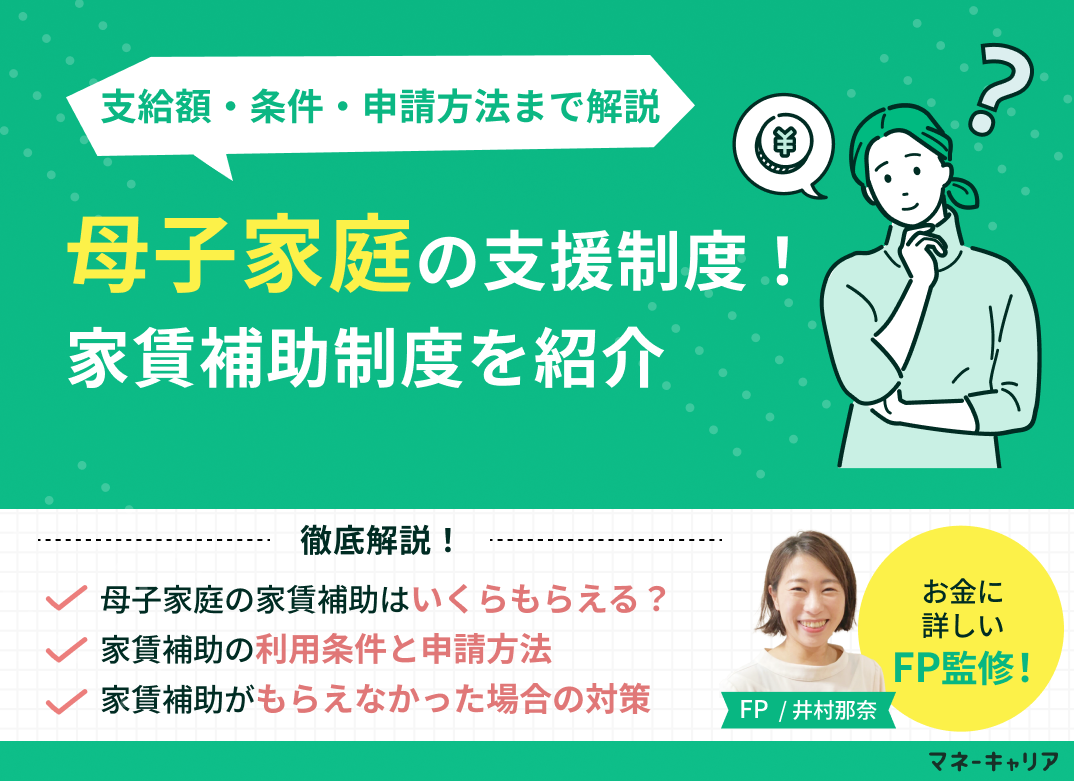
「母子家庭で家賃を払っていけるか不安……」
「家賃補助ってどんな制度があるの?」
そんな疑問や悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、母子家庭には自治体の家賃補助・公営住宅への優先入居・住宅扶助など複数の支援制度があります。
この記事では、母子家庭向けの家賃補助の種類や支給額の目安・申請条件や必要書類・補助が受けられなかった場合の対策も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
・「家賃補助を受けられる条件を知りたい」
・「補助がもらえなかったときの選択肢を知っておきたい」
そんな方は本記事を読むことで、安心して生活できる住宅支援の仕組みと活用方法が理解できます。
内容をまとめると
- 母子家庭向けの家賃補助には自治体制度・公営住宅・貸付制度・住宅扶助などがある
- 補助額や期間は制度ごとに異なる
- 所得制限や必要書類を満たすことが申請の条件
- 補助が受けられない場合は引越しや他制度の利用も選択肢
- マネーキャリアでは住宅費や家計全体の見直しを無料で相談できる

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 母子家庭の家賃補助にはどんなものがある?
- 地方自治体独自の家賃補助
- 公営住宅への優先入居
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金
- 生活保護の住宅扶助
- 母子家庭の家賃補助はいくらもらえる?金額と支給期間の目安
- 家賃補助の利用条件と申請方法
- 主な所得制限と受給条件
- 必要書類一覧と提出方法
- 他制度との併用可否
- 家賃補助がもらえなかった場合の対策
- 家賃の安いエリアへ引越す
- 公営住宅やURに申し込む
- 他の生活支援制度を利用
- 母子家庭の家賃補助に関するよくある質問
- 賃貸更新後も家賃補助は続く?
- 支給期間終了後はどうなる?
- 家賃補助以外に母子家庭が利用できる住宅関連支援は?
- 母子家庭で安心して暮らしたい方はお金のプロ「マネーキャリア」に相談
母子家庭の家賃補助にはどんなものがある?
母子家庭の家賃補助制度や、住居費用をカバーできるいくつかの支援制度があります。
代表的なものとしては次のとおりです。
- 地方自治体独自の家賃補助
- 公営住宅への優先入居
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金
- 生活保護の住宅扶助
複数の選択肢があり、それぞれ利用条件や助成額が異なるため、自分の状況に合う制度を把握しておくことが重要です。
具体的な制度の内容を確認していきましょう。
地方自治体独自の家賃補助
独自の家賃補助を設けている地方自治体があります。
たとえば東京都東久留米市では、ひとり親家庭で所定の条件を満たす場合、月々3,500円の家賃補助が受けられます。
公営住宅への優先入居
公営住宅への優先入居は、ひとり親家庭が家賃負担を軽減する手段のひとつです。
ひとり親世帯は抽選時に優遇される場合があり、一般の応募者より当選しやすい傾向があります。
市営住宅や都営住宅などは通常よりも低く家賃設定されているため、積極的に活用しましょう。
応募の際は、収入基準や募集時期を各自治体のホームページや窓口で確認してください。
母子父子寡婦福祉資金貸付金
母子父子寡婦福祉資金貸付金は、住居に関する資金を借りられる制度です。
「住宅資金」や「転宅資金」として、改築費や引っ越し費用をカバーできます。
生活保護の住宅扶助
母子家庭に限定された制度ではありませんが、生活保護の住宅扶助も利用可能です。
収入や資産が不足し生活できない場合に、家賃相当分を補助してもらえます。
母子家庭の家賃補助はいくらもらえる?金額と支給期間の目安
自治体独自の母子家庭への家賃補助は、各自治体ごとに貰える金額が異なります。
多くの場合、以下の例ように月額数千円から1万円程度の範囲で設定されていることがほとんどです。
- 東京都東久留米市:月3,500円
- 神奈川県厚木市:月1,000円~10,000円
- 神奈川県海老名市:月7,000円
家賃補助の利用条件と申請方法
家賃補助の利用条件と申請方法は、自治体によって細かく異なります。
確認しておくべき項目は以下のとおりです。
- 所得制限や受給条件
- 必要書類と提出方法
- 他制度との併用可否
それぞれの条件を把握しておかないと、せっかくの制度を活用できない可能性もあります。
自治体によって異なるものの、要点を確認していきましょう。
主な所得制限と受給条件
| 扶養人数 | 所得額 |
|---|---|
| 0人 | 2,080,000円未満 |
| 1人 | 2,460,000円未満 |
| 2人 | 2,840,000円未満 |
| 3人 | 3,220,000円未満 |
| 4人 | 3,600,000円未満 |
| 5人 | 3,980,000円未満 |
必要書類一覧と提出方法
- 母子家庭等家賃助成申請書
- 戸籍謄本(新規申請のみ・児童扶養手当の受給者は省略可)
- 申請者本人が借主として契約していることが分かる建物賃貸借契約書の写し
- 申請月分の家賃領収書等の写し(新規申請のみ)
- 個人番号利用に関する同意書(必要な方のみ)
- 所得証明書(必要な方のみ)
- 預金通帳など、申請者名義の口座番号等が分かるもの
他制度との併用可否
家賃補助がもらえなかった場合の対策
- 家賃の安いエリアへ引越す
- 公営住宅やURに申し込む
- 他の生活支援制度を利用
家賃の安いエリアへ引越す
公営住宅やURに申し込む
他の生活支援制度を利用
母子家庭の家賃補助に関するよくある質問
- 賃貸更新後も家賃補助は続く?
- 支給期間終了後はどうなる?
- 家賃補助以外に母子家庭が利用できる住宅関連支援は?