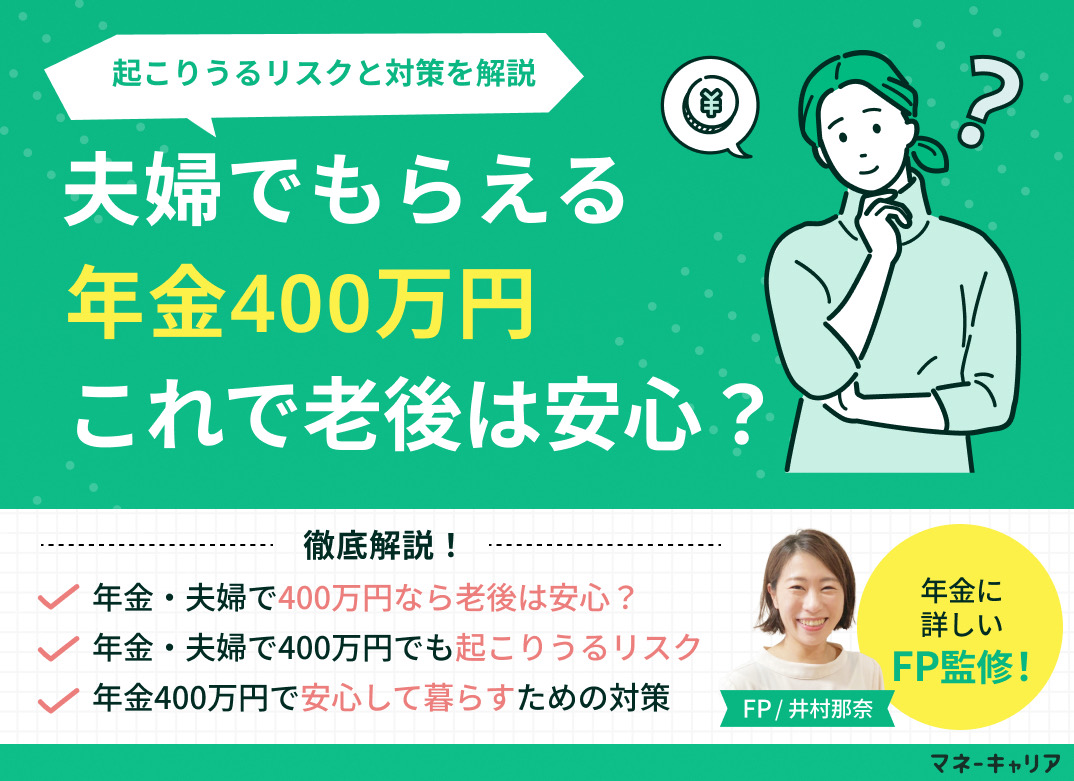

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
年金・夫婦で400万円なら老後は安心?
年金収入が夫婦で年間400万円あれば、老後の生活は安心だと感じる方も多いかもしれません。実際、これは全国平均と比べても高めの水準です。
しかし、手取り額や支出の実態を踏まえると、必ずしも「余裕がある」とは言い切れないケースもあります。
ここでは、年金400万円という収入がどの程度の生活レベルを支えるのかを、以下の3つの視点から解説します。
- 標準的な年金額と比較すると「かなり多い」
- 年金400万円の手取りはいくらになる?
- 年金400万円で老後の生活費は足りる?
年金額の見かけだけで判断せず、実際の生活に即した視点で安心できる老後を考えるヒントにしてください。
標準的な年金額と比較すると「かなり多い」
令和7年度の標準的な年金額は、夫婦2人分で月額232,784円と厚生労働省が公表しています。年間に換算すると約279万円となり、これが「平均的な年金生活」の目安とされます。
一方、夫婦で年金収入が400万円ある場合、標準的な水準を大きく上回っており、生活の安定度は高いといえます。住居費や医療費などの支出が抑えられていれば、趣味や旅行などにも予算を回せる可能性があります。
ただし、収入が多くても油断は禁物です。物価上昇や介護費用など、将来的な支出増加リスクには備えが必要です。
年金400万円の手取りはいくらになる?
年金収入が夫婦で400万円ある場合でも、実際の手取り額は控除後の金額です。特に65歳以上か未満かで「公的年金等控除」の額が異なり、手取りに差が生じます。以下は主な控除項目の一例です。
控除される主な項目(概算)
- 所得税(年金収入に応じて課税)
- 住民税(自治体により異なる)
- 国民健康保険料(自治体・年齢により変動)
- 介護保険料(原則65歳以上が対象)
公的年金等控除の例
- 65歳未満:年金収入130万円未満 → 控除額60万円
- 65歳以上:年金収入330万円未満 → 控除額110万円
これらを踏まえると、手取り額は以下のようになります
| 年齢区分 | 手取り年額(概算) | 月額換算 |
|---|---|---|
| 65歳未満 | 約330〜350万円 | 約27〜29万円 |
| 65歳以上 | 約340〜360万円 | 約28〜30万円 |
額面だけでなく、手取りベースでの生活設計が重要です。
年金400万円で老後の生活費は足りる?
夫婦で年金手取り月額が約29万円ある場合、基本的な生活費には十分対応可能です。
生命保険文化センターの調査によると、高齢無職世帯の平均的な消費支出は月約25.7万円。一方、「ゆとりある老後生活費」は月約37.9万円とされています。以下は収支の差額をまとめた表です。
| 生活費の種類 | 月額生活費(円) | 年金手取りとの差額(円) |
|---|---|---|
| 平均的な生活費 | 257,000 | +33,000 |
| ゆとりある生活費 | 379,000 | −89,000 |
基本的には「足りる水準」ですが、住居費や医療・介護費が高額になる場合や、ゆとりある生活を望む場合は不足する可能性があります。
年金や老後資金のお悩みは、無料FP相談でプロと一緒に解決しよう

年金や老後資金に不安を感じたら、専門家に相談するのが最も確実な方法です。マネーキャリアでは、FP(ファイナンシャルプランナー)資格を持つ専門家に、何度でも無料で相談できます。
保険や資産運用、家計の見直しなど幅広いテーマに対応しており、強引な勧誘もないため安心して利用可能です。
オンラインで予約・相談ができるため、忙しい方でも気軽に活用できます。夫婦で年金400万円の収入があっても、将来の支出に備えた対策は早めに検討しておくことが重要です。

年金・夫婦で400万円でも起こりうるリスク
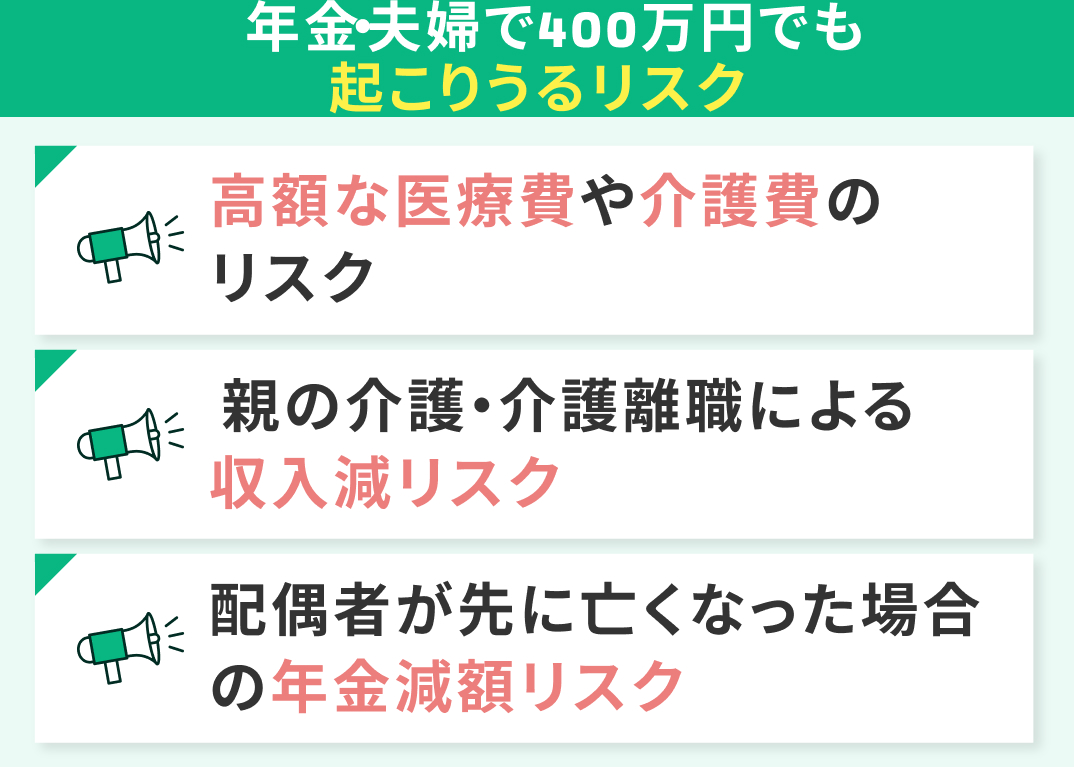
年金収入が夫婦で400万円あっても、老後の生活が常に安泰とは限りません。長寿化や社会保障制度の変化により、予想外の支出や収入減に直面する可能性もあります。
特に医療や介護、家族構成の変化などは、生活設計に大きな影響を与えるリスク要因です。
ここからは、年金400万円世帯でも注意しておきたい老後のリスクについて、以下の3つの視点から解説します。
- 高額な医療費や介護費のリスク
- 親の介護・介護離職による収入減リスク
- 配偶者が先に亡くなった場合の年金減額リスク
将来の不安を減らすために、どのような備えが必要かを一緒に考えていきましょう。
高額な医療費や介護費のリスク
年金収入が夫婦で400万円あっても、予期せぬ医療費や介護費が家計を圧迫する可能性は十分にあります。
特に高齢期には、慢性疾患や骨折、認知症などによる長期的な支出が発生しやすく、貯蓄を取り崩す要因となります。
また、平均寿命の延伸により「長生きリスク」も現実的な課題です。年金収入が安定していても、医療・介護費が年間数十万円〜百万円単位で発生するケースもあり、生活費とは別に備えが必要です。
収入が多い世帯ほど生活水準が高く、支出増加の傾向もあるため、油断は禁物です。
親の介護・介護離職による収入減リスク
年金収入が夫婦で400万円あっても、親の介護が始まると家計の前提が大きく崩れる可能性があります。
特に50代は資産形成のラストスパート期であり、離職による収入減は老後資金に深刻な影響を及ぼします。共働きでも、片方が介護離職すれば生活設計は一変します。
さらに、親の介護費を自分たちが負担するケースも多く、月数万円〜十数万円の支出が継続することもあることを理解しておきましょう。
親が元気なうちに、資産状況や加入保険の確認をしておくことが、将来のリスク回避につながります。
配偶者が先に亡くなった場合の年金減額リスク
夫婦で年金収入が400万円ある場合でも、配偶者が先に亡くなると受給額が大きく減少するリスクがあります。
特に、夫が厚生年金、妻が専業主婦という家庭では注意が必要です。夫が亡くなると、妻が受け取るのは「遺族厚生年金」となり、元の厚生年金額の約3/4が上限となります。加えて、妻自身の老齢基礎年金のみでは生活費を賄いきれない可能性も出てくるかもしれません。
収入が減る一方で、住居費や医療費などの固定支出は残るため、生活水準の見直しや資産の取り崩しが必要になるケースもあります。
年金400万円の夫婦が安心して暮らすための対策
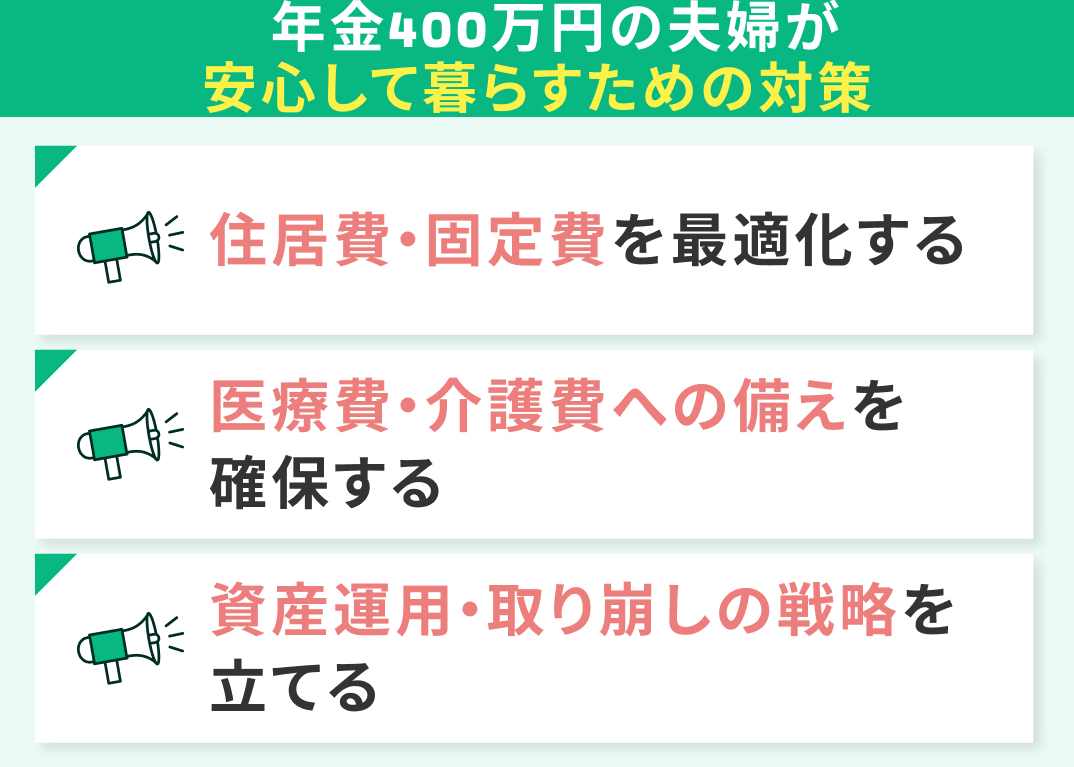
年金収入が夫婦で400万円あっても、将来にわたって安心して暮らすためには、計画的な備えが欠かせません。特に、住居費や医療費といった固定的な支出は、老後の家計に大きな影響を与える要素です。
また、資産の取り崩し方や運用の工夫によって、安心感はさらに高まります。
ここでは、年金400万円の夫婦が老後をより安定して過ごすために実践したい対策を、以下の3つの視点から解説します。
- 住居費・固定費を最適化する
- 医療費・介護費への備えを確保する
- 資産運用・取り崩しの戦略を立てる
将来の不安を減らし、安心して暮らすためのヒントとしてご活用ください。
住居費・固定費を最適化する
年金収入が夫婦で400万円ある場合でも、支出の見直しによって生活の安定度は大きく向上します。特に住居費や固定費は、老後の家計に継続的な影響を与えるため、早期の最適化が重要です。
以下は代表的な削減例です。
- 住宅ローンの完済:月5〜10万円の支出がゼロに
- 格安スマホへの乗り換え:月1万円→3,000円に削減
- 保険の見直し:不要な死亡保障を減らし、月5,000円以上の節約
- サブスクの整理:使っていない動画・音楽サービスを解約
- 電力・ガスのプラン見直し:年間1〜2万円の節約も可能
これらを組み合わせることで、年間で数十万円の支出削減が可能です。固定費の見直しは、老後の安心を支える「見えない収入」とも言えます。
医療費・介護費への備えを確保する
年金収入が夫婦で400万円あっても、医療費や介護費の急な負担には注意が必要です。公的制度として「高額療養費制度」があり、医療費の自己負担は月額上限が設けられています(例:年収370万〜770万円の世帯で約8万円+超過分の1%)。
また、介護保険制度では、所得に応じて1〜3割の自己負担が発生し、要介護度によっては月数万円〜10万円以上の支出になることもありこちらも注意が必要です。
これらの制度を理解したうえで、自己負担分に備えた貯蓄や、必要に応じた保険の見直しが不可欠です。
資産運用・取り崩しの戦略を立てる
年金収入が夫婦で400万円ある場合でも、インフレや長寿リスクに備えた資産運用と取り崩しの計画は不可欠です。
預貯金だけでは資産価値が目減りする可能性があるため、NISAやiDeCoなどの制度を活用した運用が有効です。老後の資産取り崩しでは、以下のような戦略が考えられます。
- 預貯金は生活費の短期資金として確保
- つみたてNISAは中期資金として、必要に応じて取り崩し
- iDeCoは年金の補完として、計画的に受け取り開始
資産を「使う順番」と「使う目的」に分けて管理することで、長寿リスクにも柔軟に対応できます。
【まとめ】年金・夫婦で400万円でも計画的なリスク対策を

これまで、年金収入が夫婦で400万円ある場合の生活水準や、起こりうるリスク、そしてその対策について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
標準的な年金額と比べて高水準である一方、医療・介護費、介護離職、配偶者の死亡による年金減額など、見過ごせないリスクも存在します。
また、固定費の見直しや資産運用・取り崩しの戦略を立てることで、より安定した老後生活が実現できます。
こうした不安や疑問は、専門家と一緒に整理することで、具体的な対策が見えてきます。マネーキャリアでは、FP資格を持つ専門家に無料で相談でき、保険・資産運用・老後資金など幅広いテーマに対応しています。
オンラインで気軽に相談できるので、老後の不安を感じたら、まずは一度プロに話してみることをおすすめします。






























