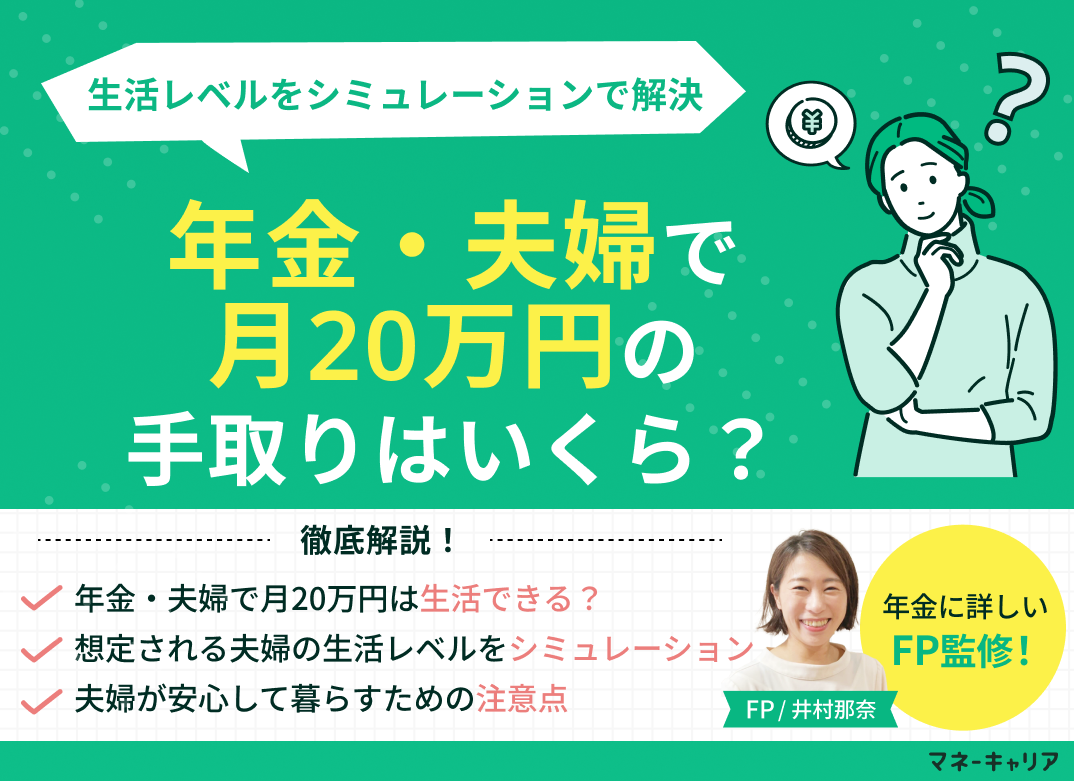

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
年金・夫婦で月20万円は生活できる?
厚生労働省の発表によると、令和7年度の夫婦2人分の標準的な年金額は232,784円(厚生年金加入の場合)※です。夫婦で20万円の年金は、標準額より32,784円低い水準となります。
実際の手取り額や生活費の実情を踏まえると、夫婦で20万円の年金で老後を送るには細かな計画が必要になるでしょう。
年金月20万円の手取りはいくら?
年金月20万円の場合、以下のようにシミュレーションすると約18万円になります。
・年金月20万円の場合
| 項目 | 内容 | 計算式 | 金額(年間) |
|---|---|---|---|
| 公的年金等控除 の適用 | 65歳以上・330万円以下 控除額110万円※1 | 2,400,000円(月額20万円×12か月) -1,100,000円 | 1,300,000円 (年金所得) |
| 基礎控除後の 課税所得 | 基礎控除48万円※2を差し引き | 1,300,000円-480,000円 | 820,000円 (課税所得) |
| 所得税の 負担額 | 税率5%・控除0円※3 | 820,000円×5% | 41,000円 |
| 住民税の 負担額 | 所得割10%+均等割5,000円※4 | 820,000円×10%+5,000円 | 87,000円 |
| 社会保険料 | 高齢者医療制度+介護保険料 | 86,306円※5+75,312円※6 | 161,618円 |
| 年間の 手取り額 | 収入から各種税金・保険料を差し引き | 2,400,000円(月額20万円×12か月) -(41,000円+87,000円+162,000円) | 2,110,382円 |
| 月額の 手取り目安 | 年間手取りを12か月で割る | 2,110,382円÷12か月 | 175,865円 |
※1参照:所得金額の計算方法|日本年金機構
※2参照:No.1199基礎控除
※3参照:No.2260所得税の税率|国税庁
※4参照:個人住民税|総務省
※5参照:後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について|厚生労働省
※6参照:令和6年度介護納付金の算定について(報告)|厚生労働省
上記の表が示すように、年金からは所得税・住民税などの税金に加え、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料といった社会保険料も天引きされるため、手取りは18万円となります。
老後の生活費は年金だけで足りる?
総務省の家計調査によると、高齢夫婦無職世帯の消費支出は月約25.7万円※1です。先ほどのシミュレーションで算出した額面20万円の年金手取り約18万円と比較すると、毎月約8万円、年間では約96万円の不足です。
さらに、生命保険文化センターの調査では、ゆとりある老後生活費は平均37.9万円※2とされています。この場合、月約20万円の赤字、年間約240万円が不足します。
| 生活レベル | 月額支出 | 手取り18万円との差額 | 年間不足額 |
|---|---|---|---|
| 基本的な生活 | 25.7万円 | ▲8万円 | ▲96万円 |
| ゆとりある生活 | 37.9万円 | ▲20万円 | ▲240万円 |
年金収入だけでは日常の生活費すら不足しやすく、ゆとりある暮らしを望む場合には大きな資金が求められます。
年金や老後資金のお悩みは、無料FP相談でプロと一緒に解決しよう

年金月20万円での生活設計には、支出管理や貯蓄計画など専門的な判断が求められます。
マネーキャリアは累計10万件を超える相談実績があり、FPが老後資金の不安を無料で解決に導きます。相談は何度でも無料で、納得いくまで繰り返し利用が可能です。
オンラインでの面談に対応しているため、自宅にいながら気軽に相談できます。予約もLINEで完結し、電話は不要なので手軽に始められます。

年金月20万円で想定される夫婦の生活レベルをシミュレーション
年金手取り20万円で暮らす場合、支出を抑えた倹約的な生活が前提となります。総務省の家計調査を参考に、実際の支出内訳をシミュレーションしてみましょう。
| 支出項目 | 月額 |
|---|---|
| 食費 | 6.0万円 |
| 住居費 | 1.3万円 |
| 光熱・水道費 | 1.7万円 |
| 通信・交通費 | 2.2万円 |
| 医療費 | 1.4万円 |
| 日用品・被服費 | 1.3万円 |
| 教養娯楽費 | 2.0万円 |
| 交際費 | 1.9万円 |
| その他 | 2.2万円 |
| 合計 | 20.0万円 |
※参照:65歳以上の夫婦のみの無職世帯(夫婦高齢者無職世帯)及び65歳以上の単身無職世帯(高齢単身無職世帯)の家計収支-2024年-|統計局ホームページ
※あくまで概算
シミュレーションでは手取り額とほぼ同額の支出となり、余裕はほとんどありません。食事は自炊中心で、外食は控えた節約が欠かせません。
娯楽は近所の散歩や図書館利用など、お金のかからない工夫が中心になるでしょう。
年金月20万円の夫婦が安心して暮らすための注意点
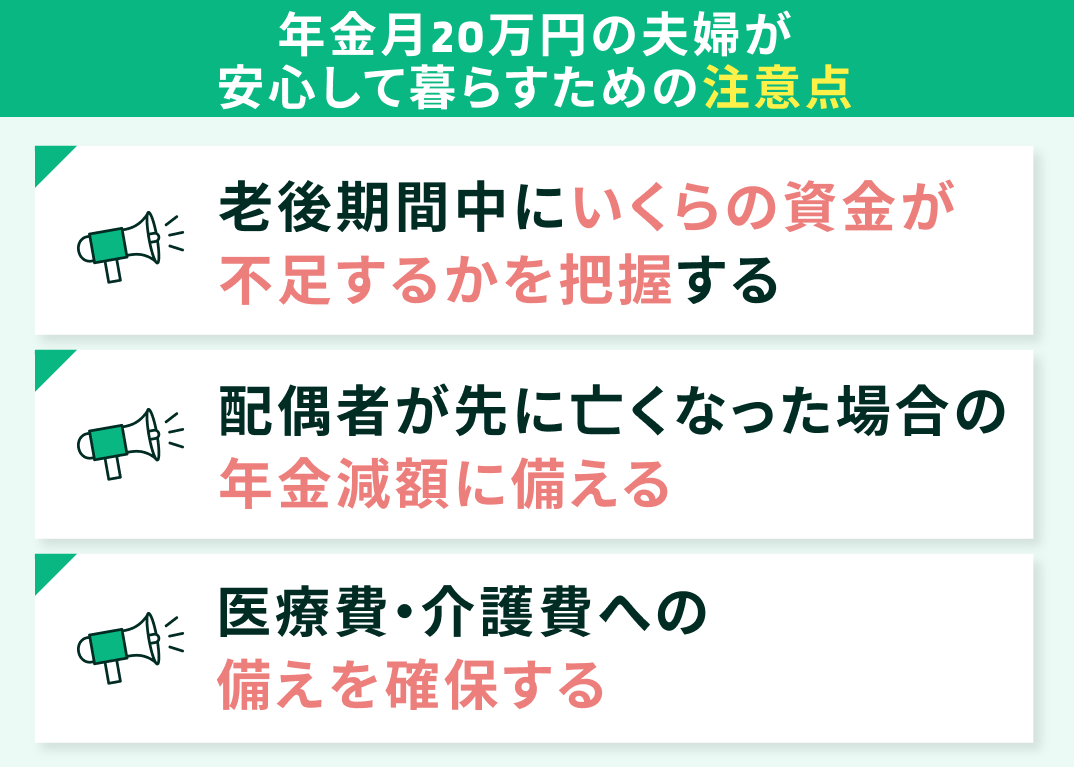
年金月20万円で暮らす場合、月々の収支管理だけでなく、将来起こりうるリスクにも備えましょう。老後に備えて、あらかじめ意識しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 老後期間中にいくらの資金が不足するかを把握する
- 配偶者が先に亡くなった場合の年金減額に備える
- 医療費・介護費への備えを確保する
これらのリスクを想定した資金計画を立てれば、突然の支出にも慌てず対応できます。
老後期間中にいくらの資金が不足するかを把握する
老後の資金計画を立てるには、まず不足額を老後期間全体でどの程度になるか明確にすることが重要です。
毎月の収支を把握し、年間・老後全体での不足額を算出すれば、必要な貯蓄額がわかります。必要な貯蓄を確保するために、以下のような対策を意識して実践しましょう。
- 毎月の収支を把握する
- 固定費を徹底的に削減する
- 不足分を貯蓄の計画的な切り崩しや副収入で補う
まず毎月の収入と支出を洗い出し、月々の不足額を確認します。
次に固定費を徹底的に見直し、削減できる項目を探しましょう。通信費や保険料、サブスクリプションサービスなど、見直しやすい支出から着手すると効果的です。
不足分は、貯蓄を計画的に取り崩したり、パート・アルバイトなどの副収入で補ったりする方法があります。
配偶者が先に亡くなった場合の年金減額に備える
配偶者が亡くなると年金受給額が減少するため、一人暮らしになったときの資金対策が必須です。とくに夫が厚生年金を受給し、妻が専業主婦だった家庭では注意が必要になります。
たとえば、老齢厚生年金を受給していた夫が亡くなった場合、妻には遺族厚生年金が支給されます。受け取れる年金は、遺族厚生年金(夫の厚生年金額の4分の3)※1と自分の老齢基礎年金の合計です。
以下は、夫婦が月額20万円の年金で生活している場合の内訳例です。
・夫婦の年金内訳※(夫存命時:合計20万円)
- 一人当たりの老齢基礎年金:69,308円※2
- 夫の老齢厚生年金:61,384円【200,000円-(69,308円×2人)】
・夫が亡くなった場合に妻が受給できる年金
- 妻の老齢基礎年金:69,308円
- 夫の遺族厚生年金:46,038円(=61,384円×3/4)※3
このように、夫が亡くなった場合、妻の年金収入は20万円から約11万5千円へと大幅に減少します。
医療費・介護費への備えを確保する
年齢を重ねると医療費や介護費の負担が増えるため、自己負担分に備えた貯蓄が欠かせません。高額療養費制度や介護保険制度を理解し、実際の負担額を把握しておく必要があります。
高額療養費制度では、医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に払い戻しを受けられます。70歳以上で年収約370万円未満の場合、外来の上限は月1万8,000円、入院を含めた上限は月5万7,600円※1です。
介護保険制度では、要介護認定を受けると介護サービスを1〜3割※2の自己負担で利用できます。ただし、在宅介護の場合でも月数万円、施設入所になると月10万円以上かかるケースもあります※3。
【まとめ】年金・夫婦で20万円の資金計画は早めにFPに相談しよう

年金月20万円(手取り約18万円)での夫婦生活は、支出を抑えた倹約が前提となります。高齢夫婦の平均的な生活費は月約25.7万円※であり、毎月約8万円の赤字が見込まれます。
配偶者が亡くなった場合の年金減額や、医療費・介護費の増加も考慮すれば、年金収入だけでは十分とはいえません。
マネーキャリアの無料FP相談では、累計10万件を超える実績をもとに、一人ひとりに合った老後資金計画を提案します。
何度でも無料で相談できるため、納得いくまで検討できます。年金への不安を抱える老後を専門家とともに、安心のある暮らしへと整えていきましょう。






























