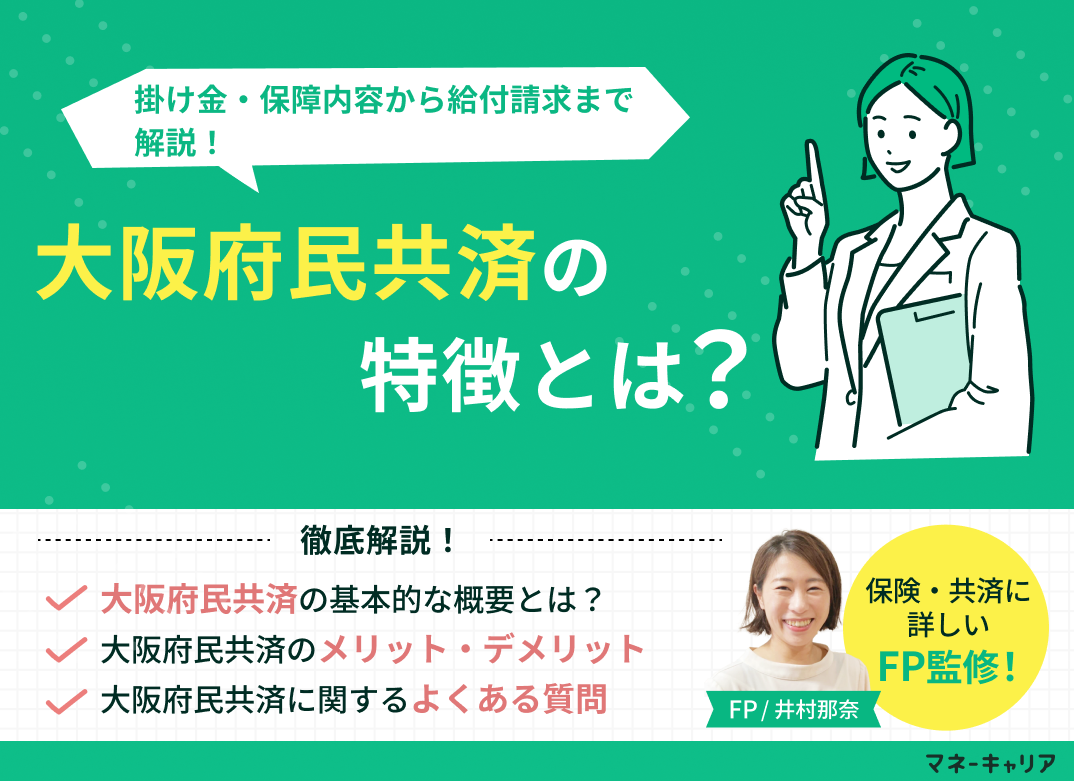この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 共済保険は入らない方が良いのかの判断基準とは
- 家族構成はどうか
- 他の収入源や貯蓄状況を考慮する
- 現在のライフステージ
- 公務員の共済保険とは?
- 公務員が共済保険に加入するメリット
- 割安な保険料
- 幅広い保障内容から選べる
- 家族も加入対象となる
- 公務員が共済保険に加入するデメリット
- 一人ひとりの状況に合わせた柔軟性が低い
- 一生涯保障ではない共済もある
- 掛け金が上がる可能性がある
- 公務員の共済保険に関わるよくある質問
- 公務員の退職後も共済保険は継続できる?
- 公務員の共済だけで老後資金は足りる?
- 民間保険と共済はどっちがお得?
- 公務員の共済全般に関わる悩みを解消できる方法とは?
- 公務員の共済保険の概要やメリット・デメリットまとめ
共済保険は入らない方が良いのかの判断基準とは
公務員が共済保険に入らないほうが良いかの判断基準には、大きく分けて以下の3つがあります。
- 家族構成はどうか
- 他の収入源や貯蓄状況を考慮する
- 現在のライフステージ
家族構成はどうか
公務員が共済保険に入らないほうが良いかの1つめの判断基準は、家族構成はどうかという点です。
公務員の共済保険(共済組合)は、以下の条件を満たすことで組合員と同様に短期給付などを受けることができます。
- 組合員の配偶者、子、父母などである
- 組合員の収入によって生計を維持している人が組合員の被扶養者として認定される
自身と同じ保障を受けさせたい扶養家族がいるなら、公務員の共済保険への加入を検討しましょう。
他の収入源や貯蓄状況を考慮する
2つめのポイントは、他の収入源や貯蓄状況を考慮することです。
公務員の共済保険は割安な掛け金で病気やケガ、出産、死亡、休業などさまざまなケースで給付金を受け取ることができます。
ただ、共済以外に保険金・給付金を得られる収入源があったり、十分な貯蓄があったりする場合には、共済保険に加入せずとも医療費や収入源をカバーできます。
共済保険に加入するか迷うときは、共済がなくても病気・ケガの手術・入院や収入源を貯蓄でカバーできるかを念頭に検討すると良いでしょう。
現在のライフステージ
3つめのポイントは、現在のライフステージです。
子どもが生まれたばかりだったり、成長期だったりする場合には万が一の際に手厚い保障が必要です。
一方、子どもが独立して自身も退職間際であれば、加入しなくても良い可能性もあります。
共済保険のみで十分なのか民間の保険を併用して加入すべきなのかは個人によって異なるため、プロに判断をしてもらうことをおすすめします。
公務員の共済保険とは?
公務員の共済保険は「共済組合」と呼ばれており、会社員の協会けんぽや健康保険組合に相当する公的医療保険です。
組合員である公務員が互いに助け合い、相互の生活の安定と福祉の向上が目的となっています。
共済組合には主に以下の2つの事業があり、それぞれ受けられる保障に違いがあります。
- 短期給付
- 長期給付
公務員が共済保険に加入するメリット
ここでは、公務員が共済保険に加入することのメリットを解説します。
主なメリットは以下の3つです。
- 割安な保険料
- 幅広い保障内容から選べる
- 家族も加入対象となる
割安な保険料
公務員が共済保険に加入する1つめのメリットは、保険料が割安であることです。
共済保険(共済組合)は団体保険であり、集団で加入することで団体割引が適用されます。
同じ内容の保障でも、民間の生命保険と比較して安く加入できます。
また、共済組合は組合員から集める掛け金だけでなく国や地方自治体からの負担金が財源に含まれていることも、保険料が割安な理由の1つです。
幅広い保障内容から選べる
2つめのメリットは、幅広い保障内容から選べる点です。
公務員の共済保険では「短期給付」と「長期給付」があり、それぞれ医療保障と死亡保障などをカバーしています。
共済組合に加入しておくだけで、病気・ケガ、死亡、後遺障害などさまざまなリスクをカバーすることが可能です。
1つの共済のみであらゆるリスクをカバーしたい公務員の方は、共済組合への加入を検討してみましょう。
家族も加入対象となる
3つめのメリットは、家族も共済の加入対象になることです。
公務員の共済保険(共済組合)は、組合員本人だけでなく、組合員に扶養されている家族も加入対象に含まれます。
被扶養者として認められるのは、組合員の収入で生計を維持していて、以下のいずれかに該当する人です。
- 組合員本人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹※同居・別居は問わない
- 上記以外の人で、3親等以内の親族※同居が条件
公務員が共済保険に加入するデメリット
ここからは、公務員が共済保険に加入するデメリットを解説します。
具体的なデメリットは以下の3つです。
- 一人ひとりの状況に合わせた柔軟性が低い
- 一生涯保障ではない共済もある
- 掛け金が上がる可能性がある
一人ひとりの状況に合わせた柔軟性が低い
公務員が共済保険に加入する1つめのデメリットは、一人ひとりの状況に合わせられる柔軟性が低いことです。
公務員の共済保険は公的保障であり、病気やケガをした場合の保障内容が決まっています。
民間の生命保険のように、家族構成や希望するライフプラン、健康状態などに応じて、保障内容を柔軟に変更するようなことはできません。
過程の状況に合わせて柔軟に保障を受けたい場合は、公務員の共済保険に加えて民間の生命保険への加入も検討してみましょう。
一生涯保障ではない共済もある
2つめのデメリットは、一生涯保障ではない共済があることです。
公務員の共済保険の一部は退職後も加入できるケースもありますが、基本的には退職と同時に脱退することになります。
民間の生命保険のように、生涯にわたる死亡保障や医療保障を得ることはできません。
終身の保障を得たい場合は、民間の生命保険などから終身タイプの保障を選択して加入する必要があります。
掛け金が上がる可能性がある
3つめのデメリットは、掛け金が上がる可能性があることです。
共済組合の掛け金は、一般的に以下の計算式で算出されます。
標準報酬月額×掛け金率=掛け金
公務員の共済保険に関わるよくある質問
ここでは、公務員の共済保険に関するよくある質問を解説します。
解説する質問内容は以下の3つです。
- 公務員の退職後も共済保険は継続できる?
- 公務員の共済だけで老後資金は足りる?
- 民間保険と共済はどっちがお得?
公務員の退職後も共済保険は継続できる?
公務員の共済保険は、退職したあとは脱退することになります。
脱退後は公的利用保険以外の保障がない状態であり、共済の代わりになる保険への加入を検討する必要があります。
ただ、公務員の共済保険には「任意継続組合員制度」があります。
この制度を利用すると退職後2年間、在職中と同様の短期給付を受けることができます。
公務員の共済だけで老後資金は足りる?
公務員の共済だけで老後資金が足りるかは、老後の生活費やライフプランによって異なります。
一例として老後に必要な最低限の生活費は、月額で平均23.2万円というデータがあります。
一方、ゆとりある老後生活費は平均37.9万円です。
公務員共済だけ足りるか判断するためには、老後の生活費にいくらかけたいのか、どのようなライフプランを送りたいかを明確にしましょう。
民間保険と共済はどっちがお得?
民間保険と共済のどっちがお得なのかは、それぞれのライフスタイルやご自身が保険商品に求めるものによっても異なります。
まず共済は民間保険と比べて掛け金が割安になっている傾向にあり、掛け金を安く抑えるなら共済の方がお得なことが多いです。
一方の民間保険は特約や特則が充実していて、ライフスタイルに応じてカスタマイズしやすいメリットがあります。
ご自身が必要とする保障のみを揃えたいなら、民間保険のほうがおすすめできます。
公務員の共済全般に関わる悩みを解消できる方法とは?
ここでは、共済全般に関わる悩みを解消できる方法を紹介します。
公務員の共済組合をはじめとした共済は、割安な掛け金で充実した保障を受けられるメリットがある一方、一生涯保障がなかったり、柔軟にカスタマイズできなかったりするデメリットもあります。
一方、民間の生命保険は共済よりも柔軟に特約を組み合わせられるため、家庭環境やライフステージに合わせてカスタマイズしやすいです。
共済・保険の加入先で迷っているなら、民間の生命保険にも共済にも精通した相談サービスを選ぶべきです。
共済の口コミ・評判を紹介してもらったり、民間保険への切り替えについて相談したりするなら、保険にも共済にも精通した「マネーキャリア」が最適です。
共済や保険の保障内容に詳しいFPが、共済組合のメリット・デメリットと比較しながら最適な生命保険を紹介してくれるのはもちろん、何度でも無料相談できるので、今日でも利用者数が急増しています。
 共済に関するすべての悩みにオンラインで解決できる
共済に関するすべての悩みにオンラインで解決できる
マネーキャリア:https://money-career.com/
<マネーキャリアのおすすめポイントとは?>
・お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、共済や民間の生命保険に知見の豊富な、ファイナンシャルプランナーのプロのみを厳選しています。
・もちろん、共済や民間の生命保険だけではなく、資産形成や総合的なライフプランの相談から最適な解決策を提案可能です。
・マネーキャリアは「丸紅グループである株式会社Wizleap」が運営しており、満足度98.6%、相談実績も100,000件以上を誇ります。
<マネーキャリアの利用料金>
マネーキャリアでは、プロのファイナンシャルプランナーに「無料で」「何度でも」相談できるので、相談開始〜完了まで一切料金は発生しません。
公務員の共済保険の概要やメリット・デメリットまとめ
ここまで、公務員が共済保険に入らないほうがいいのかの判断基準や、公務員の共済保険のメリット・デメリットを中心にお伝えしてきました。
記事のポイントをまとめると以下のとおりです。
- 公務員が共済保険に加入しないほうが良いかの判断基準は「家族構成」「他の収入源や貯蓄状況」「現在のライフステージ」がある
- 公務員の共済は短期給付と長期給付があり、それぞれ保障内容が異なる
- 公務員の共済保険は、掛け金の安さや家族が対象になるメリットがある
- 公務員の共済保険は、一生涯保障でない共済があることや、掛け金が上がる可能性がある点がデメリット
公務員の共済保険は割安な掛け金で家族まで含めて保障を受けられるため、公務員なら加入を検討したいものです。
ただし、人によっては共済保険に加入しないほうが良い人や、民間保険のほうが合っている人がいます。
共済と民間保険の比較や加入検討などで悩んでいる場合、一人で解決するには時間がかかり専門知識も必要です。
そこで、マネーキャリアのようにプロのFPへ「何度でも無料相談ができる」サービスを使うと、必要な保障を「過不足なく」将来に向けて準備ができます。
無料相談予約は30秒で完了するので、ぜひマネーキャリアを使って、共済を含む保障全般の悩みを解消しましょう。