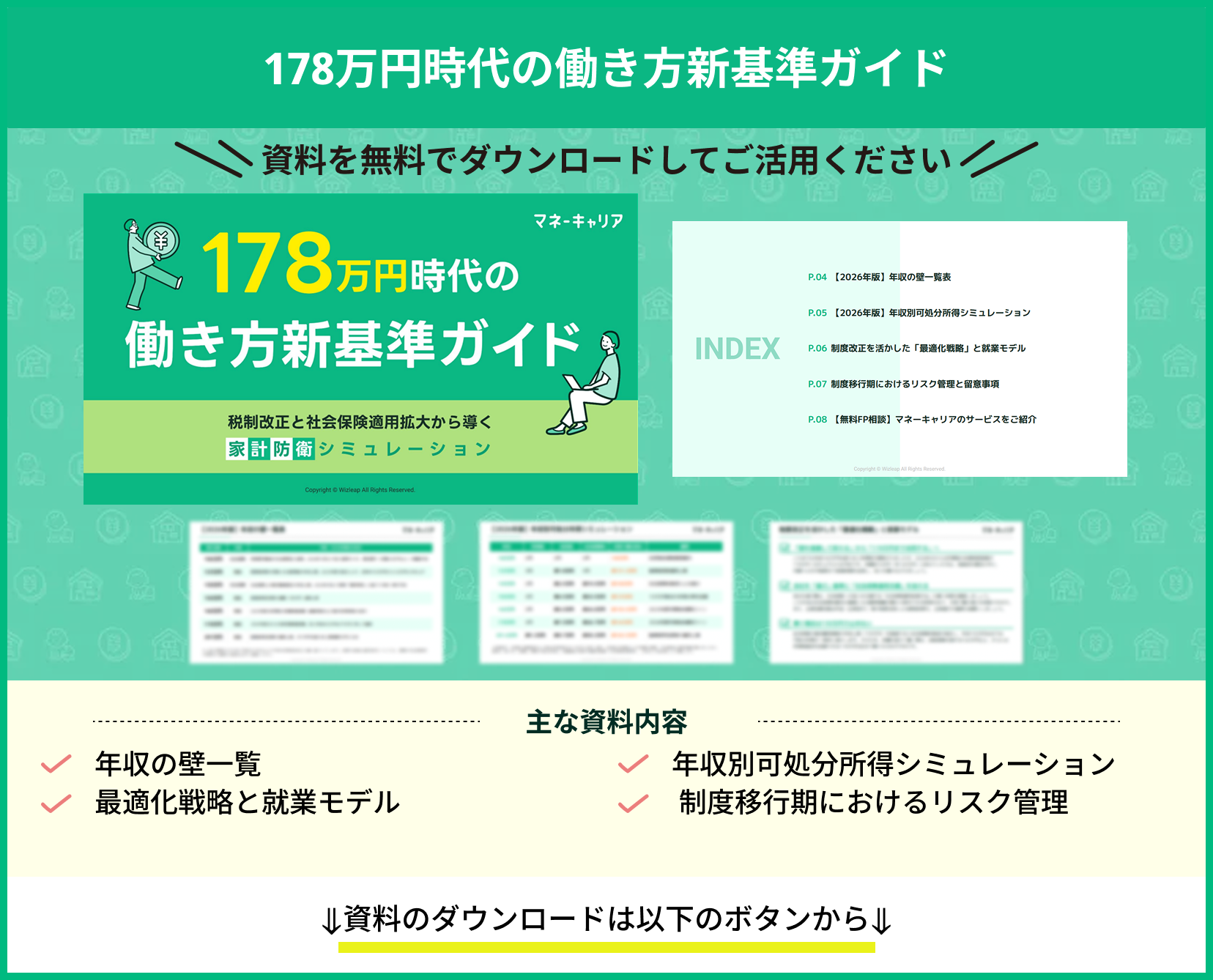パート収入は家計を支える大切な柱のひとつですが、年収が“123万円の壁”を超えると税金や世帯全体の手取り額に影響が出るため、注意が必要です。
とはいえ、税金や社会保険の仕組みは複雑で、「どこまで働くのがよいのか」・「手取りがどれくらい変わるのか」と、悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、123万円の壁の基礎知識から、所得税・住民税の負担額の目安、扶養や配偶者手当への影響まで、わかりやすく解説します。
・年収123万円を超えたときの税金や社会保険の影響を正しく知りたい
・経済的に損をする不安をなくしたい
上記のようなお悩みを持つ方は、本記事を参考にすると、安心して働き方を選ぶヒントが見つかり、家計の不安を減らすことができます。
結論として、パート収入が増えるタイミングでは、税金や保険の知識を整理し、将来的なメリットや負担のバランスを踏まえて働き方を判断することが大切です。
そこで、
マネーキャリアのように無料で何度でも、オンラインでお金の専門家(FP)に相談できるサービスを使い、後悔のない働き方を選ぶ人が増えています。

この記事の監修者
井村 那奈
フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
続きを見る
▼
閉じる
▲
パートにおける123万円の壁の基礎知識
パートにおける123万円の壁の基礎知識を、2つ解説します。
紹介する内容は以下のとおりです。
- 年収123万円は所得税の壁
- 年収123万円が課税ボーダーになる背景
仕組みを知ることで、収入と税金の関係が理解しやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
「収入を増やしたいけど、税金がどれだけかかるか不安」
「123万円と、扶養の関係はどうなってるの?」
そんな方は、マネーキャリアのオンライン無料相談窓口にご相談ください。
マネーキャリアでは、お金の専門家(FP)が、パート収入と税金の関係や扶養の条件ついて、わかりやすく無料でアドバイスします。
相談実績100,000件以上・相談満足度98.6%以上で、何度でも無料で相談できるので、ぜひお気軽にご相談ください。
年収123万円は所得税の壁
年収123万円は、
“所得税が課されるかどうか”を分ける基準です。
この金額を超えた場合、所得税がかかる可能性があります。
例えば、年収が123万より10万円多い133万円になると、超えた部分に5%が課税され、所得税はおよそ5,000円となります。
なお、年収が123万円以下の場合に非課税になるのは、あくまでも所得税です。
おおむね年収が103万円から110万円を超えると、住民税がかかる場合があるため、気を付けましょう。
住民税の計算方法や金額は、お住まいの地域や世帯の状況によって違いがあります。
心配な場合は、市区町村の窓口やホームページで確認しておくと安心です。
ちなみに、所得税とは、1年間の収入に応じて国に納める税金のことです。
対して住民税とは、前年の所得に基づいて市区町村などに納める地方税を指します。
年収123万円が課税ボーダーになる背景
年収123万円が“課税ボーダー”になる背景には、
控除額の改正があります。
令和7年度税制改正大綱により、2025年から基礎控除が48万円から58万円に引き上げられました。
さらに給与所得控除も、最低55万円から65万円に引き上げられています。
これらを合計すると、課税対象外となる金額が123万円になります。
基礎控除や給与所得控除の金額を引き上げた目的は、近年の物価高に対応することです。
これにより、所得税を課されない範囲で働きたいと考えているパートの年収上限が上がったことになります。

井村FP
123万円の課税ラインに加え、今後は178万円への引き上げを視野に入れた収支管理が欠かせません。
「結局、自分の場合はどの年収を目指すのが最も得なのか」という判断に迷う方は多いです。制度移行期に手取りを減らさないための新基準と、あなたに最適な働き方の目安を知りたい方は、下記のガイドを無料ダウンロードしてご活用ください。
\簡単20秒!メールアドレス登録で無料ダウンロード/
パートで123万円を超えた場合の影響
パートで123万円を超えた場合の影響を、3つ解説します。
紹介する内容は以下のとおりです。
- 本人に所得税・住民税が発生する
- 配偶者の税負担に変化が生じる
- 配偶者手当がもらえなくなる可能性がある
123万円は、超えたからといってすぐに大きな負担がのしかかるわけではありません。
しかし、それぞれの影響を知っておくことで、安心して収入計画が立てやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
本人に所得税・住民税が発生する
年収が123万円を超えると、
所得税と住民税が発生します。
所得税は123万円を超えた部分にのみ課税され、負担額は"超過分×5%"で計算されます。
例えば、年収133万円の場合は、約5,000円の所得税がかかります。
また、目安として110万円を超えると、住民税も課税されます。
年収123万円の場合は、年間で1万5,000円程度の負担です。
住民税には、全員が同じ金額を払う“均等割”と、収入に応じて払う“所得割”があります。
非課税限度額は自治体によって異なり、103万円〜110万円ほどが基準です。
このように123万円以上に収入を増やしても、所得税・住民税ともに、急に大きな負担がのしかかるわけではありません。
しかし、それぞれの税金の仕組みを知ることで、安心して働き方を選びやすくなるでしょう。
配偶者の税負担に変化が生じる
年収が123万円を超えると、配偶者が受けられる“配偶者控除”に変化が生じます。
本記事ではわかりやすくするため、配偶者を夫・本人を妻とする例で解説します。
“配偶者控除”は、妻の所得が48万円以下(給与収入ではおおむね123万円以下)の場合、夫に適用されて税金が安くなる制度です。
控除額は最大で38万円ですが、妻の所得が増えると、段階的に控除額が減っていきます。
そのため、妻の収入が増えると夫の税負担が高くなる可能性があります。
ただし、急に控除がゼロになるわけではなく、少しずつ減る仕組みになっているため、大きく気にする必要はないといえるでしょう。

井村FP
配偶者控除の段階的な変化を理解した後は、2026年からの「178万円」への枠拡大が「自分の世帯年収」にどう影響するかを確認しましょう。
年収が増えても手取りで損をしないための最適な就業モデルは、家族構成や働き方によって一人ひとり異なります。新基準における正確な収支目安と、あなたに合った働き方の選択肢を詳しく知りたい方は、下記のガイドを無料ダウンロードしてご活用ください。
\簡単20秒!メールアドレス登録で無料ダウンロード/
配偶者手当がもらえなくなる可能性がある
年収が123万円を超えると、
配偶者手当の支給対象外になることがあります。
配偶者手当とは、扶養している配偶者(妻)がいる場合に、夫に支給される"家族手当"の一種です。
扶養家族(妻)の収入が基準を超えると、手当が減額または廃止されるケースが多いです。
厚生労働省の調査では、生活手当(扶養手当・家族手当・育児支援手当など)の従業員1人あたりの平均支給額は、月額1万7,600円(※)とされています。
つまり、配偶者手当がなくなると、夫の収入が年間で21万1,200円の減になる可能性があり、家計に影響することもあるでしょう。
妻の収入を増やす際は、事前に夫の勤務先に、手当条件を確認しておくと安心です。
「配偶者手当や扶養など、用語が難しくて混乱する」
「配偶者手当がなくなったら、うちの家計はどう変わるのか心配」
そんな方は、マネーキャリアのオンライン無料相談窓口にご相談ください。
マネーキャリアでは、お金の専門家(FP)が、配偶者手当や扶養などの用語をわかりやすく説明し、妻の収入が増えたときの家計への影響についても、無料でアドバイスしています。
相談実績100,000件以上・相談満足度98.6%で、 何度でも無料で相談できるので、初めての方も安心してご相談ください。
パートでその他の年収の壁を超えた場合の影響
パートで、123万円以外の年収の壁を超えた場合の影響を、2つ解説します。
紹介する内容は以下のとおりです。
- 106万円は社会保険料の壁(勤務先が51人以上の場合)
- 130万の壁も社会保険料の壁(勤務先が50人以下の場合)
それぞれの基準を理解することで、手取りや保険料の変化を把握しやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
106万円は社会保険料の壁(勤務先が51人以上の場合)
パート先の従業員数が
51人以上の場合、年収が106万円を超えると、社会保険料の負担が新たに発生します。
具体的には、勤務先が51人以上の企業で、以下の要件を満たすと、妻自身が社会保険(厚生年金や健康保険)に加入する必要があります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である
- 月額賃金が8万8,000円以上である
- 2ヵ月を超える継続雇用の見込みがある
- 学生ではない
月額賃金8万8,000円は、年収で換算すると約106万円となり、これが"106万円の壁"と呼ばれる理由です。
106万円を超えると、年収のおよそ15%の社会保険料が給料から天引きされます。
例えば年収106万円なら、負担額はおおむね15万9,000円です。
123万円の壁を超えなければ、所得税の支払いは避けられます。
しかし、勤務先によっては、106万円を超えた時点で社会保険料の支払い義務が生じる点に注意が必要です。
ただし、この106万円の壁は今後、年金制度改革の関連法案が公布されてから、3年以内に撤廃される予定です。
そのため、将来的にはパートで気にするべきは、"週20時間以上の壁"のみになるといえます。
130万の壁も社会保険料の壁(勤務先が50人以下の場合)
パート先の従業員数が50人以下の場合、年収が130万円を超えると、夫の扶養から外れる可能性が高くなります。
扶養を外れると、妻は国民年金や国民健康保険に加入するか、加入要件を満たせば、勤務先で社会保険に加入する必要が出てきます。
国民健康保険と国民年金の負担は年間で約30万円にのぼる場合もあり、手取りが大きく減る恐れがある点に注意が必要です。
勤務先で社会保険に加入する場合も、年収全額に約15%の保険料がかかるしくみです。
ただし、一時的な収入増なら証明書を提出することで、2年間は扶養を維持できる特例があります(※)。
収入と保険料のバランスを考えながら、無理のない働き方を選ぶことが大切です。
「気にすべき条件が多くて混乱する」
「結局私の場合は、130万円を超えたら手取りがどれくらい減るの?」
そんな方は、マネーキャリアのオンライン無料相談窓口にご相談ください。
マネーキャリアでは、お金の専門家(FP)が、扶養の条件や130万円を超えたときの手取りの変化や家計の整理について、無料でアドバイスしています。
相談実績100,000件以上の確かな実力があるので、ぜひお気軽にご相談ください。
パートで123万円の壁に悩んだら専門家(FP)への相談がおすすめ
パート収入が増えるほど、「手取りは減らないか」「家計が赤字にならないか」と心配になる方も多いでしょう。
年収の壁への不安を減らすには、一度税金や社会保険の仕組みをしっかり整理することが大切です。
とはいえ、一人で複雑な制度を理解し、収入をシミュレーションするのは簡単ではありません。
マネーキャリアなら、お金の専門家(FP)が「年収をいくらに設定するか」「手取りがどのくらい変わるか」を一緒に整理し、具体的な金額でアドバイスします。
相談はオンラインで完結し、土日も対応・何度でも無料で利用できるので、ぜひお気軽にご相談ください。
パートの123万円の壁に関するよくある質問
パートの123万円の壁に関するよくある質問を、3つ解説します。
紹介する内容は以下のとおりです。
- パートで年収123万円を超えると所得税はいくらですか?
- パートで年収123万円を超えると住民税はいくらですか?
- パートの123万の壁と130万の壁の違いはなんですか?
これらの疑問を整理することで、税金や社会保険の仕組みが理解しやすくなるので、働き方を選ぶときの参考にしてください。
パートで年収123万円を超えると所得税はいくらですか?
年収123万円を超えた部分に、5%の所得税がかかります。
例えば、年収が133万円の場合は、123万円を引いたあとに残る"10万円"に課税されます。
この場合の所得税は、"10万円×5%"で約5,000円です。
生命保険料控除などの追加控除があれば、所得税の負担額はさらに小さくなるでしょう。
このように、123万円を超えたからといって急に大きな負担がのしかかるわけではありません。
こうした仕組みを知っておくと、収入を増やすときも安心して計画を立てやすくなるでしょう。
パートで年収123万円を超えると住民税はいくらですか?
年収123万円の場合は、年間でおおよそ1万5,000円程度の住民税がかかります。
住民税には、全員が同じ金額を払う“均等割”と、収入に応じてかかる“所得割”の2種類があります。
非課税限度額は自治体によって異なり、103万円から110万円ほどが基準です。
計算方法や金額は、地域や家族構成によって変わるため注意しましょう。
不安があるときは、市区町村の窓口やホームページで確認しておくと安心です。
パートの123万の壁と130万の壁の違いはなんですか?
123万円の壁は、所得税が発生する基準の収入ラインを指します。
一方で、130万円の壁は、社会保険の扶養から外れる収入基準です。
つまり、税金と保険で扱いが異なる点が大きな違いといえます。
123万円を超えると、所得税の負担が始まります。
130万円を超えると、勤務条件に応じて自分で社会保険に加入したり、国民健康保険・国民年金に切り替えたりする必要があります。
123万円の壁を理解して自分に合った働き方を選ぼう【まとめ】
123万円の壁は、正しく理解することで、自分に合った働き方を選べます。
具体的には、年収123万円を超えたときの税負担の変化、配偶者手当や扶養控除の影響、106万円や130万円の社会保険の壁を把握することが大切です。
とはいえ、一人で税金や社会保険の複雑な仕組みを理解し、収入を計画するのは簡単ではありません。
税負担や社会保険料の理解に不安を感じる方や、どの収入ラインを目指すべきか迷っている方は、専門家(FP)への相談をおすすめします。

井村FP
123万円前後での税負担や手取りの変化を把握し、自分にとって最も効率的な働き方の着地点を見つけましょう。
家族構成や現在の収入状況によって、最大化できる手取り額は一人ひとり異なります。2026年からの新基準を含めた「自分の場合の収支シミュレーション」を詳しく確認したい方は、下記のガイドを無料ダウンロードしてご活用ください。
\簡単20秒!メールアドレス登録で無料ダウンロード/