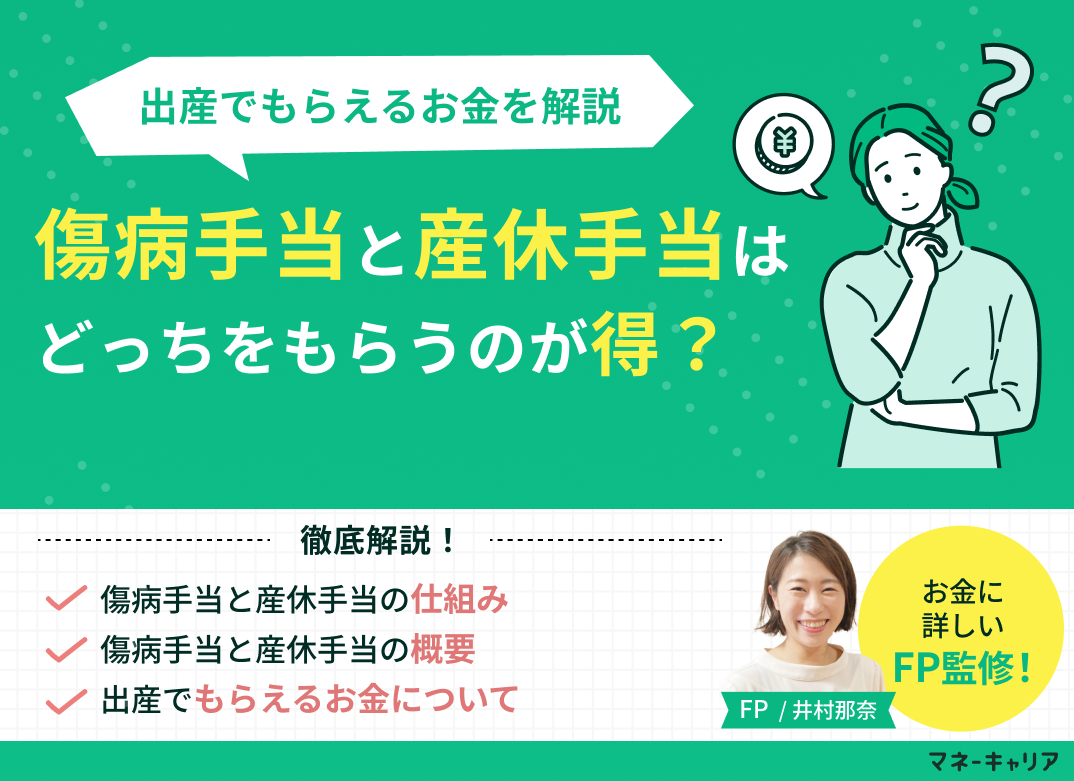
「妊娠中に体調を崩して休職したら、傷病手当ってもらえるの?」
「産休手当と傷病手当、結局どっちが得?」
そんな疑問や不安を抱えている方は多いでしょう。
結論からお伝えすると、傷病手当と産休手当(出産手当金)の支給時期が重なった場合、産休手当が優先されます。
この記事では、それぞれの制度の内容や申請方法、もらえる金額の違いを分かりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
・「自分がどの制度を利用できるか知りたい」
・「少しでも多くの給付を受けて出産費用の負担を減らしたい」
そんな方は、本記事を読むことで、制度の違いや損をしないための選択肢が明確になります。
内容をまとめると
- 傷病手当と産休手当は支給時期が重なった場合、産休手当が優先される
- それぞれの支給条件・金額・申請方法を詳しく解説
- 出産育児一時金・高額療養費・育児休業給付金など他制度も紹介
- 制度の組み合わせで給付金を最大限活用できる
- マネーキャリアでは自分に合った支援制度の無料相談ができる

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
傷病手当と産休手当はどっちが得?
傷病手当と産休手当は、基本的に選べるものではないため、どちらが得かという概念はありません。
というのも、この2つの制度は同時に併給することができず、自動的に調整される仕組みになっているからです。
原則としては出産手当金のほうが優先されますが、まれに傷病手当金のほうが金額が高いケースでは、その差額分を受け取れる場合があります。
傷病手当金とは?
傷病手当金とは、会社員などが加入している健康保険から支給される生活保障の制度です。
- もらえる条件
- 支給期間
- 支給される金額
- 申請方法
もらえる条件
傷病手当金をもらうには、以下のようないくつかの条件を満たしている必要があります。
- 病気やケガが業務外で発生している
- 労務不能となり仕事に就けない状態である
- 連続する3日間を含めて4日以上休業している
- 休業中に会社から給与の支払いがない
支給期間
傷病手当金の支給期間は、支給が開始された日(待期3日間の後の4日目)から最長で通算1年6ヶ月です。
ただし、連続ではなく断続的に支給された場合でも、合計が1年6ヶ月に達するまでが対象となります。
支給される金額
傷病手当金の支給額は、標準報酬月額(みなし給与額)を基に計算されます。
具体的には、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の「標準報酬月額」の平均額を基に、日額を算出します。
そのうえで、この日額に2/3をかけた金額が1日あたりの支給額になります。
申請方法
傷病手当金の申請は、まず勤務先へ相談しましょう。
病気やケガで仕事を休むことになったら、早めに人事や総務に連絡を入れ、必要な対応を確認してください。
その後、健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)のウェブサイトから、「健康保険 傷病手当金 支給申請書」をダウンロードします。
産休手当(出産手当金)とは?
産休手当とは、正式には「出産手当金」と呼ばれる給付制度です。
- もらえる条件
- 支給期間
- 支給される金額
- 申請方法
もらえる条件
- 会社員など健康保険の被保険者である
- 出産のために会社を休み、その期間に給与の支払いがない
- 妊娠4か月以降に出産している
支給期間
出産手当金の支給期間は、出産予定日以前の42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産後56日までが対象です。
この間に会社を休んでいて、かつ給与の支払いがない日数分が給付されます。
支給される金額
出産手当金の金額は、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬日額の2/3が1日あたりの支給額となります。
たとえば、日額が1万円の場合、約6,667円が1日分として支給される計算です。
申請方法
出産手当金の申請は、出産後に行うのが一般的です。
まずは、勤務先の人事や総務に連絡し、必要な書類の準備方法を確認しましょう。
申請には「健康保険 出産手当金支給申請書」が必要で、加入している健康保険組合や協会けんぽのウェブサイトから入手できます。
その他の出産でもらえるお金を確認しておこう
- 出産育児一時金
- 高額療養費制度
- 育児休業給付金
- 出生後休業支援給付
出産育児一時金
出産育児一時金は、赤ちゃん1人あたり原則50万円が支給される制度です。
健康保険に加入していれば原則受け取れるため、多くの家庭が利用できます。
高額療養費制度
高額療養費制度は、医療費が高額になったときに一定額を超えた分を払い戻してくれる制度です。
たとえば帝王切開など、医療行為を伴う出産では対象となることがあります。
育児休業給付金
育児休業給付金は、育休中に雇用保険から支給されるお金です。
雇用保険の被保険者なら、育児で仕事を休業している間、最大で子どもが1歳(最長2歳)になるまで給付金がもらえます。
出生後休業支援給付
出生後休業支援給付は、2025年4月から新たにスタートする制度です。
主に男性の育児参加を後押しするためのもので、「産後パパ育休(出生時育児休業)」を合計14日以上取得すると対象です。
傷病手当と産休手当に関するよくある質問
傷病手当と産休手当(出産手当金)は、どちらも収入が途絶える期間を支える大切な制度です。
しかし、制度が複雑なため以下のような疑問を持つ方も少なくありません。
- 会社を退職しても傷病手当・産休手当は支給される?
- 妊娠中に傷病手当がもらえるのはどんなとき?
- 制度が複雑で自分がもらえるお金がわかりにくい
それぞれの疑問に対して、わかりやすく丁寧に説明していきますので、ぜひ参考にしてください。
会社を退職しても傷病手当・産休手当は支給される?
退職後でも、条件を満たしていれば傷病手当や出産手当金は支給されます。
そのため、「会社を辞めたらもう受け取れない」と諦めてしまうのは早計です。
具体的には、退職日までに継続して1年以上健康保険の被保険者だった期間があり、退職時に傷病手当の支給対象になっていれば受給可能です。
妊娠中に傷病手当がもらえるのはどんなとき?
妊娠中でも、医師の診断により就労不能と判断された場合は傷病手当の対象となることがあります。
たとえば、重症妊娠悪阻(じゅうしょうにんしんおそ)や切迫流産、切迫早産などは代表的なケースです。
さらに、妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)や子宮頸管無力症など、長期の安静が必要な状態であれば対象となる可能性が高いでしょう。
制度が複雑で自分がもらえるお金がわかりにくい
「傷病手当や出産手当金など、どれが自分に該当するかわからない」と悩む方は非常に多いです。
制度には細かな条件や例外が多く、同じ状況でも受給できるかどうかは人によって異なるため、迷ってしまうのも無理はありません。
出産を機に将来のお金の不安を解消するなら「マネーキャリア」に相談
妊娠・出産に関して受け取れる傷病手当金と産休手当(出産手当金)の違いや条件、支給額や申請方法について解説しました。
これから出産を迎える方は、まずは自分がどの制度の対象になるかを確認し、申請漏れがないように準備を始めることが大切です。
とはいえ、「給付金をもらえても、将来のお金が不安」という方も多いのではないでしょうか。
そんな方は、「マネーキャリア」の無料相談を活用してみてください。
妊娠・出産でもらえるお金や、将来の家計管理、育児にかかる費用の準備など、何度でも無料で相談可能です。
妊娠・出産にまつわるお金の不安をなくしたい方は、一度「マネーキャリア」に相談してみてはいかがでしょうか。




























