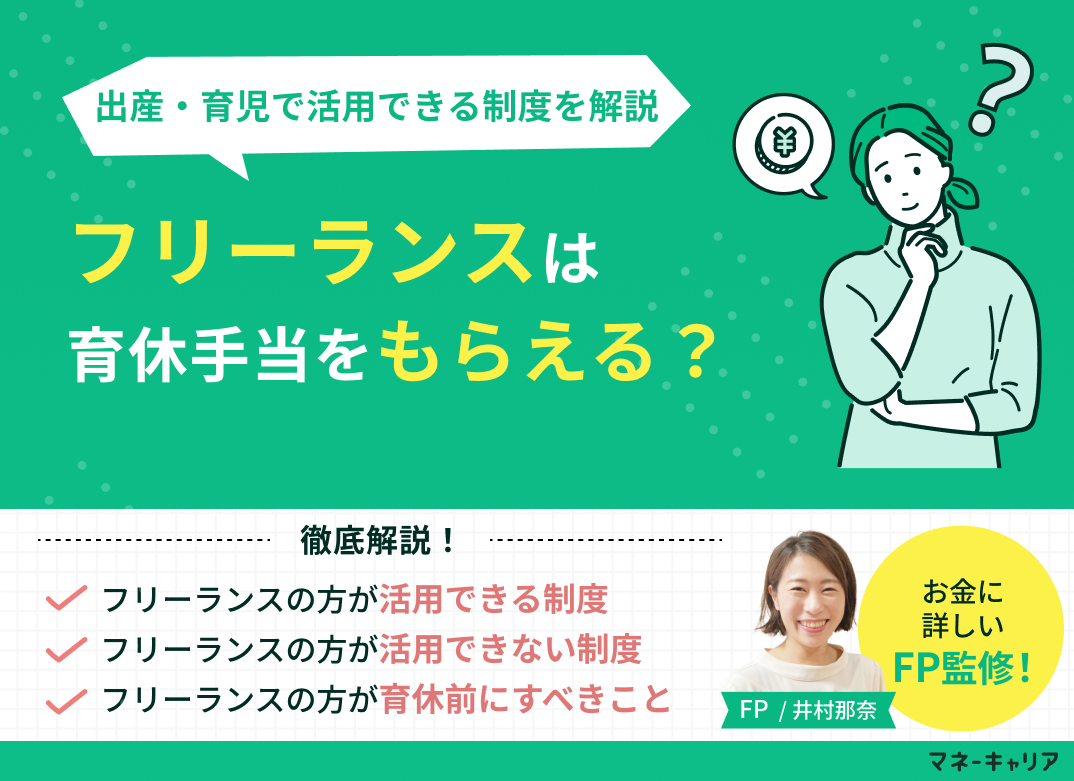
内容をまとめると
- フリーランスは育休手当の対象外なため、代わりに使える“出産・育児関連の支援制度”を知ることが大切です。
- 出産手当金や育児休業給付金は使えない一方で、出産育児一時金や児童手当など、活用できる制度もあります。
- 育休前には、クライアントとの調整や収入減への備え、パートナーとの話し合いが欠かせないポイントになります。
- 制度の理解や家計の整理を一人で進めるのがむずかしい方は、相談実績10万件以上・相談満足度98.6%以上”のマネーキャリアで無料相談を受けると安心です。

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- フリーランスは育休手当をもらえない!代わりに活用できる制度を解説
- 妊婦健診の費用助成
- 出産・子育て応援交付金
- 出産育児一時金
- 児童手当
- こども医療費助成
- 国民年金保険料の免除
- フリーランスが利用できない出産・育児の制度を解説
- 出産手当金
- 出生時育児休業給付金
- 育児休業給付金
- フリーランスで育児の手当に悩んだら専門家(FP)に無料相談がおすすめ
- フリーランスが育休前にしておくべきこと
- クライアントへの相談とスケジュール調整
- 産前産後の収入減への備え
- 産後の働き方を見据えたパートナーとの話し合い
- フリーランスの育休手当に関するよくある質問
- フリーランスの男性は育休をとれますか?
- フリーランスは産休をいつから取ればよいですか?
- フリーランスは制度の理解と準備で安心して育児と向き合える【まとめ】
フリーランスは育休手当をもらえない!代わりに活用できる制度を解説
フリーランスの方は、育休手当(育児休業給付金)をもらうことができません。
代わりに活用できる制度を、6つ解説します。
紹介する制度は以下のとおりです。
- 妊婦健診の費用助成
- 出産・子育て応援交付金
- 出産育児一時金
- 児童手当
- こども医療費助成
- 国民年金保険料の免除
使える制度を知っておくことで、育児期の経済的不安を減らすヒントになるので、ぜひ参考にしてください。
妊婦健診の費用助成
出産・子育て応援交付金
出産・子育て応援交付金は、妊婦や子育て家庭への経済支援と伴走型の相談支援を一体で受けられる制度です。
育休手当が使えないフリーランスにとっても、出産期の金銭的な負担を軽くする助けになります。
経済的支援としては、妊娠期・出産後に計10万円相当のギフトが支給されます。
支給方法は自治体によって異なり、商品券・現金給付などさまざまです。
また、支援を受けるには面談の実施が必須条件となっているため、申請前に制度の詳細をお住まいの自治体で確認しておくことが大切です。
出産育児一時金
出産育児一時金は、出産にかかる経済的負担を軽くするために支給される制度です。
健康保険(国民健康保険など)に加入しており、妊娠4ヵ月以上で出産した方であれば、フリーランスでも子ども1人につき50万円が支給されます。
原則として、健康保険組合から医療機関へ直接支払われる仕組みになっており、出産費用の自己負担を大きく軽減できます。
また、出産費用が50万円を下回った場合は、差額を申請して受け取ることも可能です。
制度をスムーズに活用するためにも、事前に加入している保険や医療機関の対応を確認しておくことが大切です。
児童手当
児童手当は、職業や働き方に関わらず、高校生年代までの子どもを育てているすべての家庭が対象となる基本的な支援制度です。
児童手当は、職業や働き方に関わらず、高校生年代までの子どもを育てているすべての家庭が対象となる基本的な支援制度です。
2024年12月以降の支給分からは、所得制限が撤廃され、子ども1人あたりの支給額は、0歳から高校生年代まで月額10,000円(第3子以降は月額30,000円)となります。
支給は偶数月(年6回)に、2ヵ月分ずつまとめて振り込まれます。
申請は出産や転入のタイミングでおこない、居住地の市区町村で手続きが必要です。
制度の詳細は、自治体の案内を確認しましょう。
こども医療費助成
こども医療費助成は、一定の年齢までの子どもが病院を受診した際に、自己負担となる医療費の一部または全額を自治体が助成してくれる仕組みです。
この制度は、子ども本人が公的医療保険に加入していれば利用できるため、フリーランス家庭でも活用できます。
例えば東京都では、乳幼児や義務教育就学児を対象とした医療費助成制度が整備されています。
なお、助成内容や年齢上限、自己負担の有無などは自治体ごとに異なります。
制度の詳細は、お住まいの自治体の窓口やホームページで確認しておくと安心です。
参照:医療助成|東京都福祉局
国民年金保険料の免除
フリーランスの方は、毎月納付している国民年金保険料について、出産前後に納付が免除される制度を利用できます。
この制度では、保険料の支払いが免除されても、その期間は納付したものとして扱われ、将来の年金額には影響しません。
対象となるのは、出産予定日または出産日の属する月の前月から4ヵ月間です。多胎妊娠の場合は最長6ヵ月間となります。
申請は出産予定日の6ヵ月前から可能で、手続きは居住地の役所や役場でおこないます。
将来の年金を減らさず、出産期の負担を軽くできる制度なので、早めに確認しておくと安心です。
フリーランスが利用できない出産・育児の制度を解説
フリーランスの方が利用できない出産・育児の制度を、3つ解説します。
紹介する制度は以下のとおりです。
- 出産手当金
- 出生時育児休業給付金
- 育児休業給付金(育休手当)
なぜこれらの制度が利用できないのかを知っておくことで、事前に備えるべき費用や、代わりに活用できる制度を検討しやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
出産手当金
出産手当金は、出産によって仕事を休んだ際に、加入している健康保険から支給される所得補償の制度です。
支給期間は、原則として出産予定日の42日前から出産後56日目までと定められています。
会社員や公務員などが対象で、国民健康保険に加入しているフリーランスは利用できません。
そのため、フリーランスの方は、産前産後の収入減に備えて、あらかじめ準備しておくことが大切です。
目安として、出産手当金と同等の補償額を想定する場合、例えば手取り月25万円の方なら、1日あたりの手当は約5,500円です。
つまり、出産前42日+出産後56日の計98日間で、約53万円の備えが目安になります。
出生時育児休業給付金
出生時育児休業給付金は、雇用保険に加入している人が、育休(いわゆる産後パパ育休)を取得した際に支給される手当です。
支給対象は、一定の賃金条件を満たし、育休を28日以内で取得した会社員や公務員などに限られます。
つまり、フリーランスの方は、この制度の対象外となります。
産後の生活費を補う手当が受けられないぶん、出産後の収入減に備えて、あらかじめ準備しておくことが大切です。
目安として、出生時育児休業給付金と同等の補償額を想定する場合、例えば月収30万円の方が28日間休むと、支給額は18万7,600円(=賃金日額1万円×休業期間28日×67%)になります。
子どもと安心して向き合うためにも、経済的な備えはできるだけ早めに始めておくと安心です。
育児休業給付金
フリーランスで育児の手当に悩んだら専門家(FP)に無料相談がおすすめ
フリーランスが育休前にしておくべきこと
フリーランスが育休前にしておくべきことを、3つ解説します。
紹介する内容は以下のとおりです。
- クライアントへの相談とスケジュール調整
- 産前産後の収入減への備え
- 産後の働き方を見据えたパートナーとの話し合い
事前に準備すべき内容を整理しておくことで、安心して育児に集中できる環境を整えやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
クライアントへの相談とスケジュール調整
フリーランスが育休をとるときは、クライアントへの相談とスケジュール調整が欠かせません。
具体的には、業務の縮小や休止・復帰の予定について、できるだけ早めに共有しておきましょう。
また、伝えるタイミングや言い方によっては、今後の案件継続に影響が出る可能性もあるため、慎重に進めたいところです。
話し合いを円滑に進めるために、相手への配慮を忘れず、入念に準備しておくと安心です。
産前産後の収入減への備え
産後の働き方を見据えたパートナーとの話し合い
フリーランスの育休手当に関するよくある質問
フリーランスの育休手当に関するよくある質問を、2つ解説します。
紹介する質問は以下のとおりです。
- フリーランスの男性は育休をとれますか?
- フリーランスは産休をいつから取ればよいですか?
よくある疑問をあらかじめ知っておくことで、自分に合った準備や働き方を考えやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
フリーランスの男性は育休をとれますか?
フリーランスは産休をいつから取ればよいですか?
フリーランスは制度の理解と準備で安心して育児と向き合える【まとめ】
フリーランスの方は、制度の理解と準備によって、安心して育児に向き合う環境を整えることができます。
具体的には、妊婦健診の助成や出産育児一時金などの活用、出産手当金や育児休業給付金が使えない点の理解、さらに貯蓄やクライアントとのスケジュール調整、パートナーとの話し合いなどがポイントになります。
とはいえ、一人で制度を整理し、自分に合った備え方を見つけるのは簡単ではありません。
育休中の生活やお金に不安がある方は、専門家(FP)への相談をおすすめします。




























