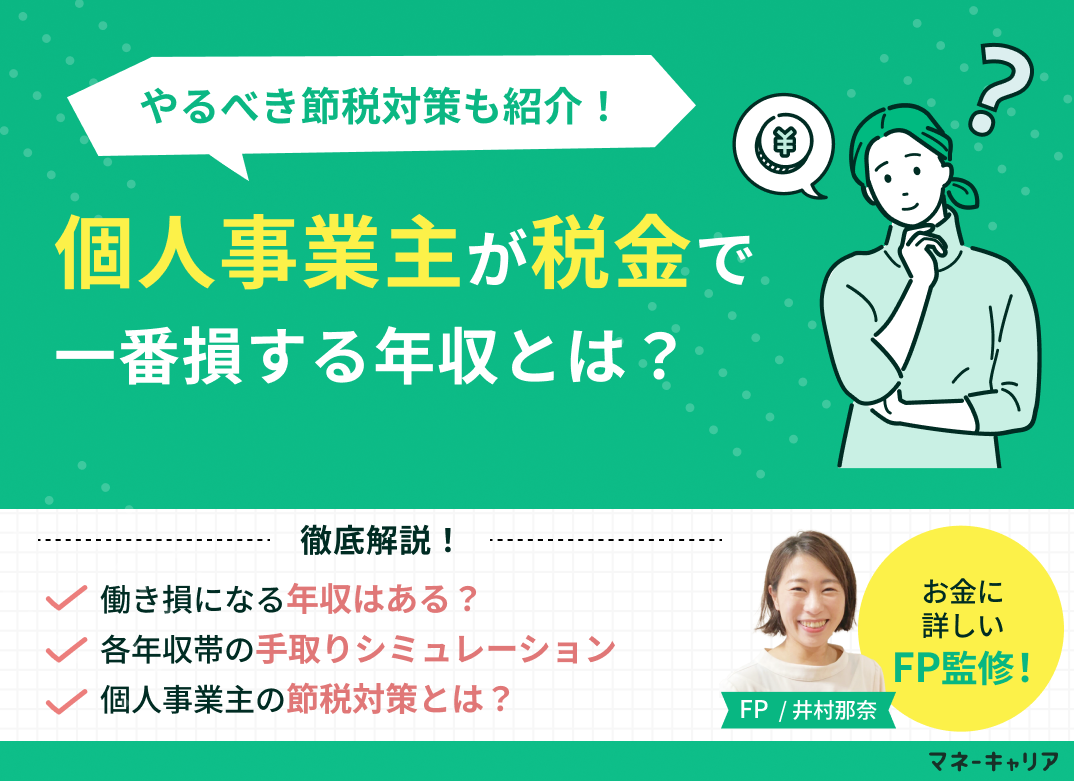
「個人事業主って、結局どれくらい稼げば一番お得なの?」
「年収が上がるほど税金で損する気がする……」
そんな不安や疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、個人事業主にとって税金面で一番得する年収は一概にいえませんが、所得効率を重視する場合は300万円〜600万円程度が目安とされています。
この記事では、年収ごとの手取り額の違いや働き損になる可能性のある年収帯・節税対策のポイントまで、個人事業主が知っておきたいお金の情報を詳しく解説します。
・「節税しながら効率よく収入を増やしたい」
・「損しない働き方を知りたい」
そんな方は、本記事を読むことで、年収ごとの損得の見極め方や税負担を軽くする方法がわかるはずです。
内容をまとめると
- 個人事業主にとって得する年収は300万〜600万円前後
- 年収1,000万円超で消費税や個人事業税の負担が増える
- 手取り額を年収帯ごとにシミュレーションで比較
- 経費・控除・青色申告などの節税対策も必須
- マネーキャリアなら税金や手取りに関する無料相談ができる

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 個人事業主が税金で一番得する年収は?
- 所得効率重視なら年収300万円~600万円くらい
- 手取りとのバランス重視なら年収600万円~1,000万円まで
- 働き損になる年収はある?
- 年収400~500万円程度で個人事業税が発生
- 年収(売上)1,000万円を超えると消費税が発生
- 各年収帯の手取りシミュレーション
- 年収400万円
- 年収600万円
- 年収800万円
- 年収1,000万円
- 個人事業主が節税するためにできる対策
- 経費を漏れなく計上する
- 青色申告を行う
- 事業専従者への給与支払いを活用する
- 各種控除を適切に使う
- 個人事業主が税金で一番得する年収に関するよくある質問
- 働き損になるなら売上を抑えたほうがいい?
- 経費をたくさん使えば税金は安くなる?
- iDeCoをやらないほうがいい人もいる?
- 税金面で不安がある個人事業主の方は「マネーキャリア」に相談
個人事業主が税金で一番得する年収は?
個人事業主の所得は、経費や家族構成によって「税金で得する年収」が変わります。
そのため、一概に「この年収が最も有利」とは断言できません。
ここでは、以下の2つの視点から「得しやすい年収の目安」を解説していきます。
- 所得効率を重視する場合の目安
- 手取り額とのバランスを優先した場合の年収帯
それぞれの考え方によってメリットは異なりますので、自分に合った判断基準を探るヒントにしてください。
所得効率重視なら年収300万円~600万円くらい
所得効率を重視するなら、年収300万円〜600万円程度がバランスのよい水準です。
この範囲であれば、課税所得195万円超〜330万円以下に該当するケースが多く、所得税率は10%に抑えられます。
なお、課税所得ごとの所得税率は以下のとおりです。
- 課税所得195万円超〜330万円以下:10%
- 課税所得330万円超〜695万円以下:20%
- 課税所得695万円超〜900万円以下:23%
- 課税所得900万円超〜1,800万円以下:33%
参照:国税庁 所得税の税率
さらに、控除の活用や青色申告特別控除を組み合わせれば、実質的な税負担をさらに軽減できるでしょう。
手取りとのバランス重視なら年収600万円~1,000万円まで
手取りとのバランスを意識するなら、年収600万円~1,000万円あたりがひとつの目安です。
この年収帯では、課税所得に対する税率が20~23%と上がるものの、収入の増加と控除の活用によって手取り額も伸びやすくなります。
ただし、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えると「課税事業者」となり、消費税を納める義務が発生する点には注意が必要です。
働き損になる年収はある?
個人事業主には、手取り額の伸びが鈍化する「働き損」と感じられる年収帯が存在します。
これは、所得が増えることで税負担も増加し、新たな社会保険料などの支払い義務が生じるためです。
以下では、働き損になりやすい2つの代表的なラインを紹介します。
- 年収400~500万円程度で個人事業税が発生
- 年収1,000万円を超えると消費税の納税義務が発生
それぞれの年収ラインで注意すべき点を見ていきましょう。
年収400~500万円程度で個人事業税が発生
年収400万円〜500万円前後で、個人事業税の課税対象となる可能性がでてきます。
具体的には、事業の所得(売上から経費を差し引いた金額)から各種控除を引いた課税所得が年間290万円を超えた場合に、個人事業税の納税義務が発生します。
個人事業税は、事業の種類によって税率が異なりますが、多くの場合5%程度が適用されます。
この税金は、地方自治体が個人事業主に対して課す地方税です。
年収(売上)1,000万円を超えると消費税が発生
年間売上が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者となります。
消費税は、売上にかかる税金を預かり金として国に納付する義務が生じるため、その分、手元に残る資金が実質的に減少します。
この制度により、事業者は売上の約10%を消費税として納める必要があり、利益率に大きな影響を与える可能性があります。
各年収帯の手取りシミュレーション
以下の年収帯の手取りを、実際にシミュレーションしていきます。
- 年収400万円
- 年収600万円
- 年収800万円
- 年収1,000万円
- 青色申告をしている(青色申告特別控除65万円を適用)
- 扶養家族なし
- 特別な控除(iDeCo・小規模企業共済・医療費控除など)は考慮しない
- 経費は年収の20%と仮定
- 国民健康保険料は東京23区の目安とする
- 復興特別所得税も考慮
年収400万円
個人事業主で年収400万円の場合、手取り額は約317万円が目安となります。
引かれる税金や社会保険料は以下のとおり。
- 所得税:7.5万円
- 住民税:15.7万円
- 個人事業税:1.5万円
- 国民年金保険料:20.4万円
- 国民健康保険料:38万円
- 合計:約 83.1万円
年収600万円
個人事業主で年収600万円の場合、手取り額は約465万円が目安です。
以下の金額が税金・社会保険料としてかかります。
- 所得税:19.8万円
- 住民税:30.2万円
- 個人事業税:9.5万円
- 国民年金保険料:20.4万円
- 国民健康保険料:55.0万円
- 合計:約 134.9万円
年収800万円
年収800万円の個人事業主の場合、手取り額は約590万円が目安となります。
税金・社会保険料は以下の金額がかかる見込み。
- 所得税:約 45.1万円
- 住民税:約 44.6万円
- 個人事業税:約 17.5万円
- 国民年金保険料:約 20.4万円
- 国民健康保険料:約 72.0万円
- 合計:約 209.6万円
年収1,000万円
年収1,000万円の個人事業主の場合、手取り額は約662万円が目安となります。
この年収帯では、消費税の納税義務が発生する点がこれまでの年収と大きく異なります。
ここでは、課税売上高から課税仕入高を差し引く本則課税方式を前提に算出しました。
- 所得税:71.2万円
- 住民税:57.3万円
- 個人事業税:25.5万円
- 国民年金保険料:20.4万円
- 国民健康保険料:104.0万円
- 消費税:60.0万円
- 合計:約 338.4万円
個人事業主が節税するためにできる対策
個人事業主が節税するためにはさまざまな対策方法があり、節税対策をしていないと、同じ売上でも納税額が大きくなる可能性があります。
以下の4つの方法を確認しておきましょう。
- 経費を漏れなく計上する
- 青色申告を行う
- 事業専従者への給与支払いを活用する
- 各種控除を適切に使う
それぞれの方法を詳しく解説していきます。
経費を漏れなく計上する
事業に要する支出を漏れなく経費として計上することは、税負担を適正化するために不可欠です。
事務所家賃、水道光熱費、通信費、消耗品費など、事業に必要なあらゆる費用が経費計上の対象となります。
これらの経費を正確に計上することで、無駄な税金の支払いを防ぐことができます。
青色申告を行う
青色申告には、最大65万円の特別控除や赤字の繰り越しなど、税制上の優遇措置が多数あります。
特に、青色申告特別控除を適用することで、課税所得を圧縮し、納税額を大幅に削減できる点が大きなメリットです。
これにより、実質的な手取り額を増やす効果が期待できます。
事業専従者への給与支払いを活用する
事業専従者への給与支払いは、節税に非常に有効な手段です。
家族に仕事を手伝ってもらい、その労働に対して適正な給与を支払えば、支払い給与を必要経費として計上できます。
ただし、「青色事業専従者給与」として適用を受けなければならず、届出や条件のクリアが必要です。
各種控除を適切に使う
各種控除を上手に活用することで、課税所得を大きく抑えられます。
代表的な控除は、医療費控除・住宅ローン控除・生命保険料控除・確定拠出型年金(iDeCo)などです。
これらの控除は、確定申告で適切に申請することで節税効果を得られます。
個人事業主が税金で一番得する年収に関するよくある質問
個人事業主で税金面に不安を感じている方の、よくある3つの質問を取り上げて解説します。
- 働き損になるなら売上を抑えたほうがいい?
- 経費をたくさん使えば税金は安くなる?
- iDeCoをやらないほうがいい人もいる?
順番に詳しく見ていきましょう。
働き損になるなら売上を抑えたほうがいい?
「働き損」を懸念して、意図的に売上を抑えるのは賢明ではありません。
売上が増えれば、将来的な設備投資や人材雇用といった事業拡大への投資が可能となり、収益の安定化や事業のさらなる成長につながります。
目先の税負担だけでなく、長期的な視点を持つことが重要です。
経費をたくさん使えば税金は安くなる?
適切に経費を計上することで、税負担を軽減できます。
経費は課税所得を減らす効果があるため、事業に関連する支出を漏れなく計上することが節税につながります。
ただし、プライベートな支出は経費に含めることはできません。あくまで事業活動に直接関連する費用のみが対象です。
iDeCoをやらないほうがいい人もいる?
iDeCoが向かない方も一定数存在します。
理由は、iDeCoは原則60歳まで引き出せないため、直近で大きな出費が予定されている場合は資金が拘束されるリスクがあるからです。
また、収入が不安定で掛金の拠出が継続できない人や、そもそも所得税・住民税をあまり払っていない人にとっては、節税メリットがほとんどありません。
税金面で不安がある個人事業主の方は「マネーキャリア」に相談
個人事業主が税金面で一番得をする年収の目安や、年収別の手取り額・税負担のバランス・節税のためにできる具体的な対策について解説しました。
これから確定申告や資金計画を立てる方は、まずは自分の年収帯と課税ラインを把握し、節税できるポイントを押さえることから始めてみましょう。
とはいえ、「どこまで経費にしていいの?」「iDeCoって本当に得なの?」など、自分に合った節税方法がわからず不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
そんなときは、「マネーキャリア」の無料相談を活用してみてください。
税金や手取りの最適化、iDeCo・NISAなどの活用法まで、個人事業主のライフスタイルに合わせたマネープランを何度でも無料で相談できます。
税金面で損をしたくない方や、今後の資金計画に不安がある方は、「マネーキャリア」に一度相談してみてはいかがでしょうか。




























