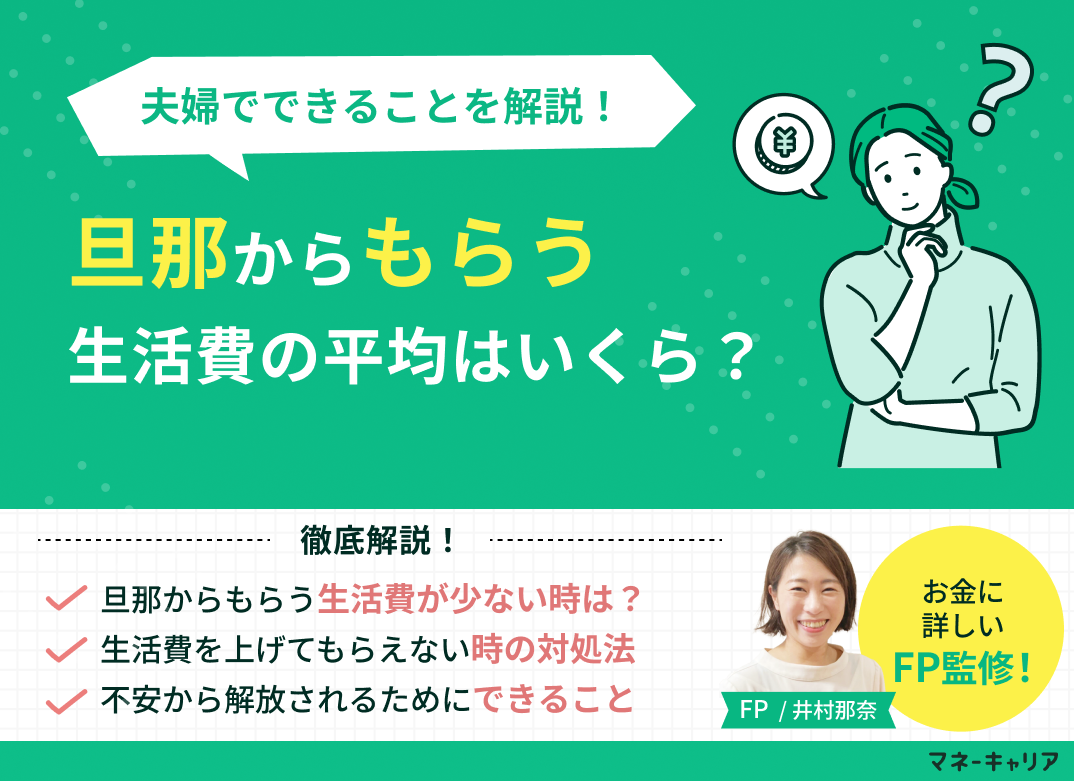
内容をまとめると
- 旦那さんからもらう生活費は家庭により大きく差がある
- 少ないと感じたら家計の見える化と共有が重要
- 話し合いで改善が難しい場合は節約・収入アップも選択肢
- 極端に少ない場合は経済的DVの可能性も視野に入れる
- マネーキャリアでは生活費や家計の悩みを無料で相談できる

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 旦那からもらう生活費の平均はいくら?
- 旦那からもらう生活費が少なくて困っている場合どうする?
- 生活費にいくらかかっているかを見える化する
- いくらでやりくりできるかの予算を立てる
- 生活費の内訳を夫婦で共有し生活費を増額してもらう
- それでも生活費を上げてもらえないときの対処法とは
- 家計を見直し節約術を取り入れる
- 妻が収入アップを目指す
- 生活費が極端に少ないなら経済DVの相談も視野に
- 将来への不安から解放されるために夫婦でできること
- 家計簿をつけて夫婦で共有する
- 理想のライフプランを話し合う
- ライフイベントに向けた貯蓄計画を立てる
- 旦那からもらう生活費の平均に関するよくある質問
- 旦那から渡される生活費が少なすぎる……我慢するべき?
- 他人がいくらもらっているかはあまり関係ない?
- 旦那が話し合いに積極的ではない場合は?
- 旦那からもらう生活費でお悩みの方は「マネーキャリア」に相談
旦那からもらう生活費の平均はいくら?
公的なデータでは、旦那さんから奥さんに渡す生活費の平均は見つかりませんでした。
そこで、2人以上世帯の生活費の平均から、旦那さんからもらう生活費の平均を考えます。
総務省の調査によると、2人以上世帯の生活費の平均は家賃を覗いて272,055円でした。
| 項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 食費 | 94,204 |
| 住居費
(家賃・住宅ローンを除く) | 18,270 |
| 水道光熱費 | 23,322 |
| 家具・家事用品 | 13,194 |
| 被服費 | 11,128 |
| 保険・医療費 | 14,878 |
| 交通・通信費 | 50,198 |
| 教育費 | 11,677 |
| 娯楽費 | 33,306 |
| その他 | 45,908 |
| 合計 | 272,055 |
旦那からもらう生活費が少なくて困っている場合どうする?
旦那からもらう生活費が少なくて困っている場合は、まず現状を冷静に整理しましょう。
具体的には、以下の3つのステップが効果的です。
- 生活費にいくらかかっているかを見える化する
- いくらでやりくりできるかの予算を立てる
- 生活費の内訳を夫婦で共有して増額を相談する
これらの流れに沿って行動することで、感情的な対立を避けつつ、生活の安定を目指せます。
それでは、順番に見ていきましょう。
生活費にいくらかかっているかを見える化する
生活費にいくらかかっているかを見える化しなければ、本当に必要な生活費を判断できません。
なぜなら、感覚的に「足りない」と訴えても、説得力を持たせるのが難しいからです。
家賃・食費・光熱費・日用品・子ども関連費などを項目ごとに分けて、実際にどれほど支出しているのかを表や家計簿アプリなどで明確にしましょう。
いくらでやりくりできるかの予算を立てる
生活費にいくらかかっているのか把握したら、やりくりする予算を立てましょう。
予算を決めておけば、予算の範囲内でやりくりしようという意識が芽生えます。
たとえば、食費は月10万円までと決めておけば、無駄な出費も防ぎやすくなるはずです。
生活費の内訳を夫婦で共有し生活費を増額してもらう
旦那に生活費の内訳を共有し、増額を求める際は、感情論ではなく事実に基づいた対話が重要です。
なぜなら、「なんとなく足りない」ではなく、数字と実例を挙げることで、相手の理解を得やすくなるからです。
たとえば、「食費が月8万円では足りず、毎月2万円赤字になる」と具体的に説明すれば、現実味を持って受け止めてもらえるでしょう。
それでも生活費を上げてもらえないときの対処法とは
それでも生活費を上げてもらえないときには、他の手段を講じる必要があります。
以下のような方法を検討してみましょう。
- 家計を見直し節約術を取り入れる
- 妻が収入アップを目指す
- 極端な場合は経済DVの相談も視野に入れる
相手が協力的でない場合でも、自分自身でできることを模索することで打開の糸口が見えてくるかもしれません。
それぞれの対処法について、詳しく解説していきます。
家計を見直し節約術を取り入れる
生活費を増やしてもらえない状況では、まず家計の見直しと節約術の導入が現実的な対策です。
無駄な出費がどこかに潜んでいる可能性があるため、支出項目をひとつひとつ洗い出してみましょう。
たとえば、スマホのプラン見直しやサブスクの解約、まとめ買いによる食費の削減など、小さな工夫で支出を抑えられるケースも少なくありません。
妻が収入アップを目指す
妻自身が収入アップを目指すことも、生活費問題の解決に有効です。
パートや在宅ワーク・スキルを活かした副業など、今の生活スタイルに合った働き方を検討してみましょう。
特に近年は、PC1台で始められる在宅ビジネスやクライアントワークなど、柔軟な働き方が増えています。
生活費が極端に少ないなら経済DVの相談も視野に
生活費が極端に少なく、生活に支障をきたす場合は、経済的支援の不足が深刻な問題となっている可能性があります。
経済的DV(ドメスティックバイオレンス)は、一方的に生活に必要な資金を渡さないことで相手を精神的に追い詰める行為です。
そのような状況が疑われる場合は、市町村の相談窓口や専門機関へ相談することを検討してください。
将来への不安から解放されるために夫婦でできること
旦那さんから必要な生活費はもらっているものの、このままでよいのか、将来への備えはできるのかと不安な方も多いでしょう。
そんなときは、以下のことに取り組んでみてください。
- 家計簿をつけて夫婦で共有する
- 理想のライフプランを話し合う
- ライフイベントに向けた貯蓄計画を立てる
それぞれの取り組みを、順を追って見ていきましょう。
家計簿をつけて夫婦で共有する
家計簿をつけて夫婦で共有することは、将来への不安を軽減する第一歩です。
なぜなら、収支を可視化することで「お金の流れ」が明確になり、無駄や不足の原因が見えやすくなるからです。
最近はアプリを使えば、レシートの撮影だけで簡単に記録でき、クラウドで夫婦のスマホと連携もできます。
理想のライフプランを話し合う
理想のライフプランを話し合うことは、日々の家計管理に意味を持たせるうえで欠かせません。
「何のためにお金を使い・貯めるのか」という目的が明確になるからです。
たとえば「35歳でマイホームを買いたい」「子どもは2人で大学まで支援したい」など、未来の設計図を夫婦で描くことによって、日々の支出の優先順位も自然と整理されていきます。
ライフイベントに向けた貯蓄計画を立てる
ライフイベントに向けた貯蓄計画を立てることで、将来的な出費に対する不安が減少します。
大きな支出は突然ではなく、事前に予測・準備できるものが多いからです。
たとえば、出産・進学・住宅購入・老後など、それぞれの時期にいくら必要になるのかを把握し、逆算して毎月の貯蓄目標を決めましょう。
旦那からもらう生活費の平均に関するよくある質問
旦那さんからもらう生活費に関する疑問は、多くの家庭で共通しています。
- 旦那から渡される生活費が少なすぎる……我慢するべき?
- 他人がいくらもらっているかはあまり関係ない?
- 旦那が話し合いに積極的ではない場合は?
それぞれのケースでの向き合い方について、回答を見ていきましょう。
旦那から渡される生活費が少なすぎる……我慢するべき?
旦那さんから渡される生活費が少なすぎる場合、我慢だけでは問題は解決しません。
たしかに「これくらいでやりくりしてほしい」という気持ちは旦那さんにもあるかもしれませんが、現実的に足りていないのなら早めに伝えるべきです。
他人がいくらもらっているかはあまり関係ない?
他人がいくら生活費をもらっているかは、参考にはなっても、自分たちにとっての「正解」とは限りません。
なぜなら、家計は収入・支出・価値観・家族構成などに大きく左右されるため、比較しても意味がない場合が多いからです。
旦那が話し合いに積極的ではない場合は?
旦那が生活費の話し合いに積極的でない場合は、アプローチの仕方を工夫することが必要です。
いきなり「生活費が足りない」と責めるような言い方では、相手も防衛的になってしまうかもしれません。
そこで、「将来に向けて家計を一緒に考えたい」「子どもの教育費を見通していきたい」といった前向きな話題から入るのが効果的です。




























