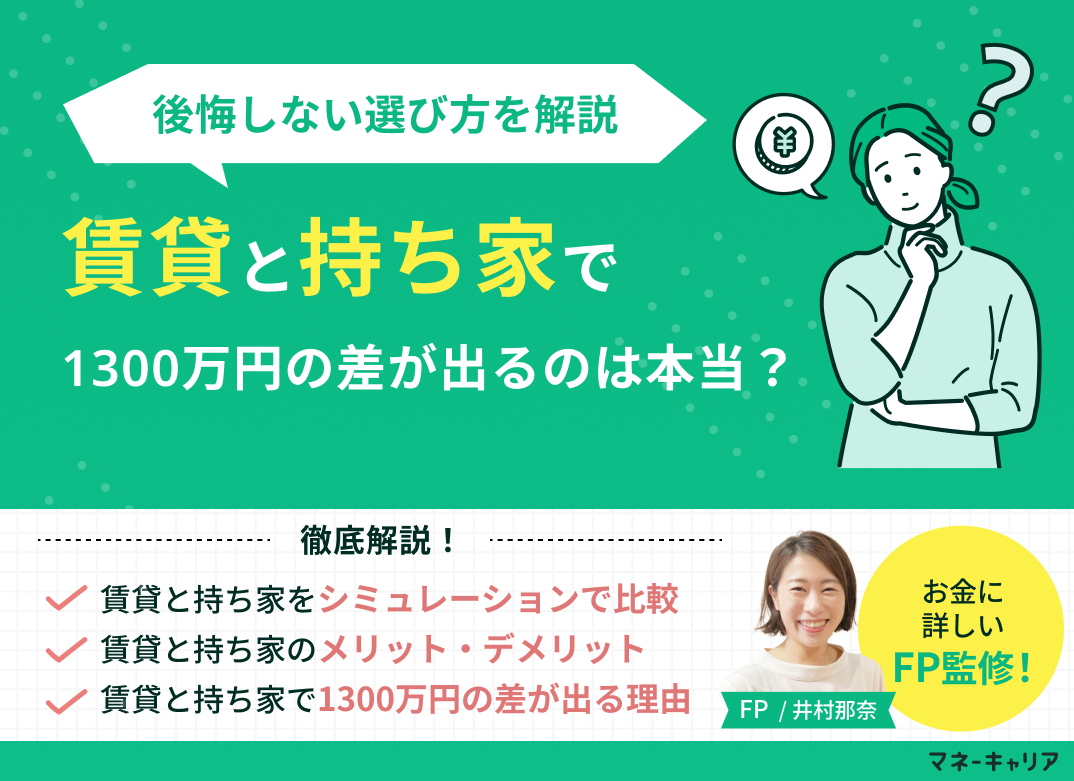
「賃貸のまま一生家賃を払い続けるのは損なの?」
「持ち家にしてもローンや修繕費が不安…」
そんな疑問を持つ方は多いでしょう。
結論からお伝えすると、賃貸と持ち家では条件によって1300万円近い差が出るケースがあり、自分のライフプランに合った選択が重要です。
この記事では、賃貸と持ち家のコスト差をシミュレーションで比較し、それぞれのメリット・デメリットを整理していますので、ぜひ参考にしてください。
・「今の家計で持ち家を買うべきか迷っている」
・「賃貸のまま老後を迎えるのが不安」
そんな方は、本記事を読むことで賃貸と持ち家の費用差やリスクを理解し、自分に合った住まいの選び方を見つけられます。
内容をまとめると
- 賃貸と持ち家では1300万円近い差が出るケースがある
- 賃貸は柔軟性がある一方、老後も家賃が必要
- 持ち家は資産になるが、維持費や売却リスクもある
- どちらが得かはライフプランによって変わる
- マネーキャリアでは住居費を含めたライフプランを無料で相談できる

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 賃貸と持ち家で1300万円の差が出る理由
- 賃貸と持ち家で1300万円の差は本当?シミュレーションで比較
- 賃貸のメリット・デメリット
- メリット1: 維持費や固定資産税の負担がない
- メリット2: ライフスタイルの変化に柔軟に対応できる
- デメリット1: 老後まで家賃が必要
- デメリット2: 資産にならない
- 持ち家のメリット・デメリット
- メリット1:住宅ローン完済後はコストが大幅に下がる
- メリット2:資産として手元に残る
- メリット3:間取りやデザインを自由にできる
- デメリット1:固定資産税や修繕費がかかる
- デメリット2:売却リスクや転居のしにくさ
- 賃貸と持ち家に関するよくある質問
- 賃貸派と持ち家派はどちらが多い?
- 賃貸と持ち家で1300万円の差は本当?
- 老後に賃貸は不安?家賃を払い続けられるか心配
- 賃貸と持ち家のどっちがいいか迷うなら「マネーキャリア」に相談
賃貸と持ち家で1300万円の差が出る理由
賃貸と持ち家の間で1300万円もの差が出るのは、生涯コストの構造が大きく異なるためです。
賃貸は一生涯にわたり家賃を支払い続ける必要があるのに対し、持ち家は住宅ローンを完済すればその後の住居費を大きく抑えられます。
賃貸と持ち家で1300万円の差は本当?シミュレーションで比較
本当に1,300万円近い差が出るのか、具体的な根拠を知りたい方も多いでしょう。
そこで、賃貸と持ち家の生涯コストをシミュレーションしました。
なお、シミュレーションは以下の一般的な条件下で試算しています。
- 年齢: 30歳からシミュレーションを開始し、85歳までの55年間で比較
- 年収: 500万円(年収は一定と仮定)
- 持ち家: 3,000万円のマンションを購入
- 賃貸: 毎月10万円の家賃の賃貸物件に居住
| 持ち家 | 賃貸 | |
|---|---|---|
| 初期費用 | 300万円 (物件価格の10%) | 50万円 (家賃5ヶ月分) |
| 住宅ローン | 3,000万円を35年ローン、金利1.5% | なし |
| 月々の返済/家賃 | 約9.2万円 (35年間) | 10万円 (生涯) |
| 修繕費・管理費 | 月2万円 (生涯) | なし |
| 固定資産税等 | 年10万円 (生涯) | なし |
| 更新料 | なし | 2年ごと家賃1ヶ月分 |
| 生涯引越し費用 | なし | 3回引越しで1回50万円 |
| 持ち家 | 賃貸 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 300万円 | 50万円 | 250万円(持ち家がプラス) |
| 住宅ローン返済 | 3,864万円 | なし | 3,864万円(持ち家がプラス) |
| 家賃 | なし | 6,600万円 | 6,600万円(賃貸がプラス) |
| 修繕費・管理費 | 1,320万円 | なし | 1,320万円(持ち家がプラス) |
| 固定資産税等 | 550万円 | なし | 550万円(持ち家がプラス) |
| 更新料 | なし | 150万円 | 150万円(賃貸がプラス) |
| 生涯引越し費用 | なし | 150万円 | 150万円(賃貸がプラス) |
| 生涯コスト合計 | 6,034万円 | 6,950万円 | 916万円(持ち家がお得) |
賃貸のメリット・デメリット
- メリット1: 維持費や固定資産税の負担がない
- メリット2: ライフスタイルの変化に柔軟に対応できる
- デメリット1: 老後まで家賃が必要
- デメリット2: 資産にならない
メリット1: 維持費や固定資産税の負担がない
メリット2: ライフスタイルの変化に柔軟に対応できる
デメリット1: 老後まで家賃が必要
デメリット2: 資産にならない
持ち家のメリット・デメリット
- メリット1:住宅ローン完済後はコストが大幅に下がる
- メリット2:資産として手元に残る
- メリット3:間取りやデザインを自由にできる
- デメリット1:固定資産税や修繕費がかかる
- デメリット2:売却リスクや転居のしにくさ
メリット1:住宅ローン完済後はコストが大幅に下がる
メリット2:資産として手元に残る
メリット3:間取りやデザインを自由にできる
デメリット1:固定資産税や修繕費がかかる
デメリット2:売却リスクや転居のしにくさ
賃貸と持ち家に関するよくある質問
最後に、賃貸と持ち家に関するよくある質問をご紹介します。
- 賃貸派と持ち家派はどちらが多い?
- 賃貸と持ち家で1300万円の差は本当?
- 老後に賃貸は不安?家賃を払い続けられるか心配
賃貸派と持ち家派はどちらが多い?
賃貸派と持ち家派はどちらが多いかというと、地域と年代で傾向が分かれます。
都心部や単身世帯が多いエリアでは賃貸の割合が高い一方、郊外や地方の家族世帯では持ち家が多くなりやすい傾向です。
賃貸と持ち家で1300万円の差は本当?
賃貸と持ち家で1300万円の差は、条件次第で起こり得ます。
理由は家賃・ローン金利・期間・維持費といった要素が長期間で積み重なるためです。
老後に賃貸は不安?家賃を払い続けられるか心配
老後に賃貸が不安かどうかは、年金や貯蓄の有無で左右されます。
なぜなら、老後も家賃を払い続ける負担は長期的に大きく、収入が減ると生活が圧迫され得るからです。
賃貸と持ち家のどっちがいいか迷うなら「マネーキャリア」に相談
賃貸と持ち家で1300万円もの差が生まれる理由やシミュレーション結果、さらにそれぞれのメリット・デメリットを整理しました。
これから住まいについて真剣に考えたい方は、まずは自分のライフプランを明確にして、住宅にかかる生涯コストをシミュレーションすることから始めてみましょう。
とはいえ、「将来の収入や生活スタイルを踏まえてどちらを選ぶべきかわからない」という方も多いはずです。
そんなときは、「マネーキャリア」の無料相談を活用してみてください。
住宅購入や賃貸の判断に必要な家計管理・住宅ローン・資産形成の相談を、何度でも無料で相談できます。
住まい選びで迷っている方は、一度「マネーキャリア」に相談して、ぜひ後悔のない住まいを選びをしてください。




























