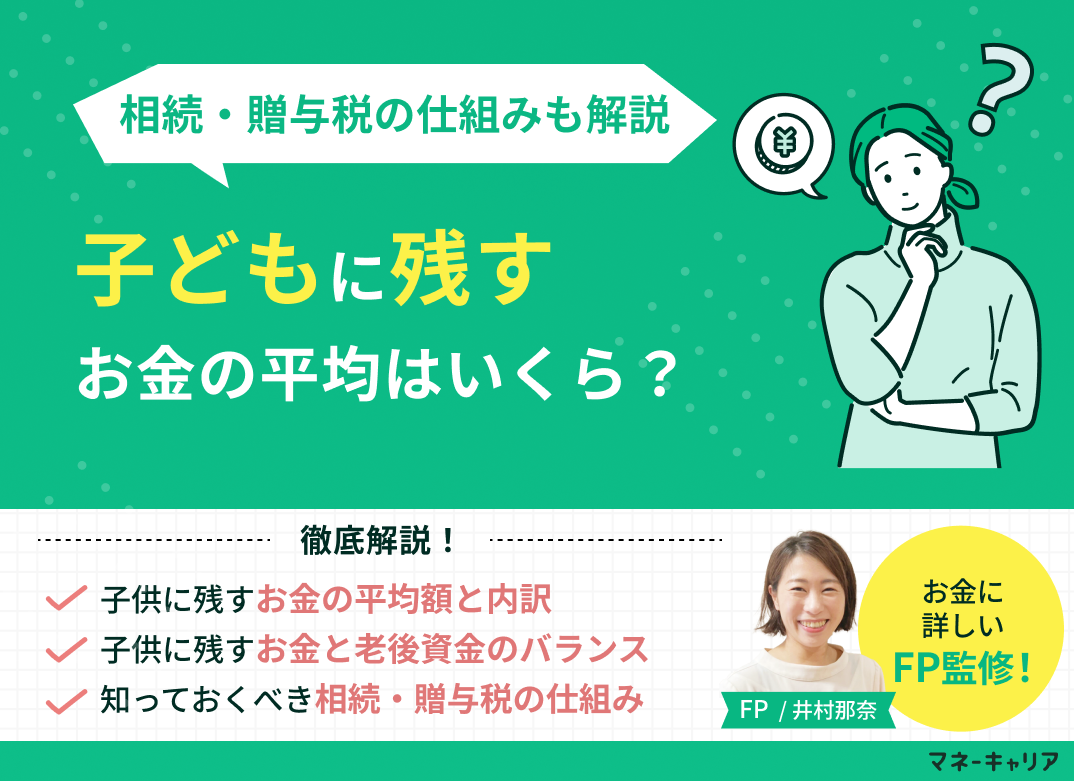
「自分が亡くなったあと、子供にどれくらいお金を残せばいい?」
「老後の生活費と子供に残すお金、どちらを優先すべき?」
そんな不安や疑問を抱えている方も多いでしょう。
結論からお伝えすると、子供に残すお金は平均額を参考にしつつ、まずは自分たちの老後資金を確保することが大切です。
この記事では、子供に残すお金の平均や相続財産の内訳、老後資金とのバランス、相続・贈与税の仕組みまでわかりやすく解説します。
・「子供にどのくらいお金を残せば安心?」
・「相続税や贈与税のことを知っておきたい」
そんな方は、本記事を読むことで子供に残すお金の適切な目安や、老後資金とのバランス、税金対策まで理解できます。
内容をまとめると
- 子供に残すお金の平均額や内訳がわかる
- 老後資金とのバランスの取り方が理解できる
- 相続税・贈与税の基本と対策を解説
- 資産運用・生命保険・不動産活用で準備を進められる
- マネーキャリアでは相続・老後資金の最適プランを無料相談できる

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 子供に残すお金の平均額と内訳は?
- 子供に残すお金の平均と中央値
- 相続財産の内訳
- 子供に残すお金と老後資金のバランス
- 夫婦で必要な老後資金の金額
- 子供にお金を残すうえでの注意点
- 子供にお金を残すなら知っておくべき相続・贈与税の仕組み
- 相続税がかからないケース
- 相続税の計算方法と税率
- 贈与税がかからないケース
- 贈与税の税率と注意点
- 子供や孫に残しておきたいお金
- 教育資金
- 結婚資金
- 住宅購入資金
- 老後資金
- 子供にお金を残すための準備方法
- 資産運用で効率よく増やす
- 生命保険で用意する
- 不動産を活用する
- 子供に残すお金に関するよくある質問
- 「子供にお金を残してはいけない」とはどういう意味?
- 相続対策はいつから始めるべき?
- 相続財産はどのように分けるのが一般的?
- 子供に残すお金の悩みがあるならお金のプロ「マネーキャリア」に相談
子供に残すお金の平均額と内訳は?
自分の子供にお金を残したいと考えている方は多いでしょう。
しかし、どんな資産でどれくらいの金額を残すべきなのか、イメージしにくいのではないでしょうか。
そこで、以下の内容を調査しました。
- 子供に残すお金の平均と中央値
- 相続財産の内訳
現実的な準備を進めるために、確認しておきましょう。
子供に残すお金の平均と中央値
MUFG資産形成研究所の調査によると、子供に残すお金の平均額は3,273万円、中央値は1,600万円です。
参考:MUFG資産形成研究所「退職前後世代が経験した資産承継に関する実態調査」(2020年)
なお、一部の富裕層が高額な遺産を残すことで平均額が押し上げられています。
より実態に近い、中央値を参考にしてください。
子どもへ相続した財産総額の分布は以下のとおりです。
- 1位:1円〜1000万円未満(29.3%)
- 2位:1000万円〜2000万円未満(20.2%)
- 3位:2000万円〜3000万円未満(11.4%)
- 4位:0円(9.1%)
- 5位:3000万円〜4000万円未満(6.3%)
相続財産の内訳
子供に残すお金と老後資金のバランス
「子供にお金を残したいけれど、自分たちの老後にはいくら必要なのか」と悩んでいませんか?
子供に残すお金と老後資金のバランスを意識することは、将来の安心を守るために欠かせません。
- 夫婦で必要な老後資金の金額
- 子供にお金を残すうえでの注意点
これらを押さえることで、自分たちの生活を守りつつ無理なく子供に資産を残せます。
それぞれ具体的に確認していきましょう。
夫婦で必要な老後資金の金額
結論として、夫婦2人で老後30年間を暮らすには数千万円単位の資金が必要です。
総務省の調査によると、高齢夫婦無職世帯の月々の収支が赤字となっているためです。
具体的には、65歳以上の夫婦無職世帯の実収入は252,818円、可処分所得は222,462円、消費支出は256,521円で月34,000円程度の不足が発生しています。
子供にお金を残すうえでの注意点
老後資金を削ってまで子供にお金を残すことは危険です。
自分たちの生活が不安定になれば、子供への負担が逆に増えてしまうでしょう。
老後に必要な資金を確保せずに多額の贈与を行うと、医療費や介護費用が足りなくなり、最終的に子供が補填するケースもあります。
子供にお金を残すなら知っておくべき相続・贈与税の仕組み
子供にお金を残すなら、相続税や贈与税の仕組みを理解することが重要です。
「どこまでが非課税で、どこから税金がかかるのか」を知ることで、余計な税負担を避けられます。
代表的なポイントは以下のとおりです。
- 相続税がかからないケース
- 相続税の計算方法と税率
- 贈与税がかからないケース
- 贈与税の税率と注意点
これらを知っておくと、手続きや節税の準備がスムーズです。
それぞれ順番に見ていきましょう。
相続税がかからないケース
相続税には基礎控除があり、一定額以下であれば課税されません。
具体的には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が基礎控除額です。
なお、法定相続人とは民法で定められた「遺産を相続する権利がある人」のこと。
主に亡くなった人の配偶者・子・父母・兄弟姉妹が法定相続人にあたります。
相続税の計算方法と税率
相続税は、遺産全体にかかる税金を計算し、それを各相続人が受け取った財産額に応じて均等に分ける仕組みです。
たとえば、課税価格が3,000万円で相続人が2人の場合、それぞれ1,500万円を基に税率をかけて算出します。
適用される税率は以下のとおりです。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ー |
| 1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億以上 | 55% | 7,200万円 |
参考:国税庁 相続税の税率
贈与税がかからないケース
贈与税にも非課税枠があります。
代表的なものは、年間110万円までの贈与が非課税になる「暦年贈与」です。
また、住宅取得資金贈与など、特定用途ではさらに非課税枠が拡大されます。
贈与税の税率と注意点
贈与税は、課税価格が増えるほど税率が上がる累進課税方式です。
一度にまとまった資金を贈与すると、税金が高くなるため気を付けましょう。
子供や孫に残しておきたいお金
子供や孫に残しておきたいお金は、以下のような費用があります。
- 教育資金
- 結婚資金
- 住宅購入資金
- 老後資金
どの資金から優先的に準備すべきか、あなた自身の家計に照らして考えてみてください。
それぞれの内容を順に解説していきましょう。
教育資金
教育資金は最もニーズが高く、まとまった支出が続く分野です。
たとえば、私立大学4年間で必要な学費は約400万円程度、下宿や通学費を含めると600万円を超える場合もあります。
結婚資金
結婚資金も贈与を活用できる代表例です。
国税庁が認める「結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度」を使えば、最大1,000万円まで非課税で贈与できます。
住宅購入資金
住宅購入資金は人生で最大級の支出です。
直近の税制改正では、省エネ住宅など条件を満たせば最大1,000万円まで贈与税が非課税になる特例があります。
老後資金
最後に、老後資金として不動産やまとまった資金を残すケースも多く見られます。
自宅や賃貸用不動産を相続財産として子供に引き継ぐ方法は、将来的な安定収入や住まいの確保に直結します。
ただし、自分たちの生活費を削ってまで資産を移すのは危険です。
子供にお金を残すための準備方法
子供にお金を残すための準備方法は、以下の3つの選択肢があります。
- 資産運用で効率よく増やす
- 生命保険で用意する
- 不動産を活用する
どの方法もメリットと注意点がありますが、早めに取り組むほど選択肢が広がります。
それぞれの準備方法について詳しく見ていきましょう。
資産運用で効率よく増やす
資産運用は長期的にお金を増やす有効な手段です。
たとえば、年利3%の投資信託に毎月5万円を20年間積み立てると、元本1,200万円が約1,637万円になります。
NISAやiDeCoなど税制優遇制度を使えば、さらに効率的に増やせるでしょう。
生命保険で用意する
生命保険は、万一のときに確実に資金を残せる方法です。
終身保険や定期保険を活用すれば、相続対策として非課税枠を活かしやすくなります。
法定相続人1人あたり、500万円までの死亡保険金は相続税の非課税枠に入る仕組みです。
不動産を活用する
不動産は資産価値を維持しやすく、相続時の分割もしやすい特徴があります。
住んでいる持ち家はもちろん子供に残せます。
賃貸用物件を持てば家賃収入を得ながら、将来的に子供へ資産の引き継ぎも可能です。
ただし、維持管理費や空室リスクがあるため、物件選びは慎重に行いましょう。
子供に残すお金に関するよくある質問
最後に、子供に残すお金に関するよくある質問をご紹介します。
- 「子供にお金を残してはいけない」とはどういう意味?
- 相続対策はいつから始めるべき?
- 相続財産はどのように分けるのが一般的?
どれも将来の安心に直結する内容です。
順番に詳しく見ていきましょう。
「子供にお金を残してはいけない」とはどういう意味?
ネット上で、「子供にお金を残してはいけない」という表現を見たことがある方もいるでしょう。
実際には、「生前贈与を活用して早めに資産を移すべき」という意味合いで使われることが多いです。
たとえば教育資金の一括贈与非課税制度を使えば、最大1,500万円まで贈与税がかからずに渡せます。
相続対策はいつから始めるべき?
相続対策は、できるだけ早く始めることがポイントです。
なぜなら、生前贈与の基礎控除(年間110万円まで非課税)を毎年活用でき、時間をかけるほど節税効果が高まるからです。
たとえば60歳から毎年110万円ずつ10年間贈与すれば、合計1,100万円を非課税で移せます。
相続財産はどのように分けるのが一般的?
相続財産は、原則として法律で定められた「法定相続分」に基づいて分けます。
たとえば配偶者と子供2人の場合、配偶者が2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつが目安です。
ただし、実際には相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で自由に決められます。
子供に残すお金の悩みがあるならお金のプロ「マネーキャリア」に相談
子供に残すお金の平均額や内訳、老後資金とのバランス、さらに相続・贈与税の基本知識や具体的な準備方法について紹介しました。
これから計画的に進めたい方は、まず「わが家は老後資金と子供に残すお金をどのように分けるか」という目標を明確にすることから始めてみてください。
とはいえ、資産運用・生命保険・不動産活用など、どの方法が自分の家庭に合うのか迷う方も多いでしょう。
そんなときは「マネーキャリア」の無料相談を活用してみてください。
相続や贈与対策、教育・住宅資金の準備など幅広いテーマについて、何度でも無料で相談できます。
自己流で悩むより、プロの意見を取り入れることで、より効率的にお金を残す準備ができるでしょう。
子供に残すお金や老後資金のバランスに悩んでいる方は、一度「マネーキャリア」に相談してみてはいかがでしょうか。




























