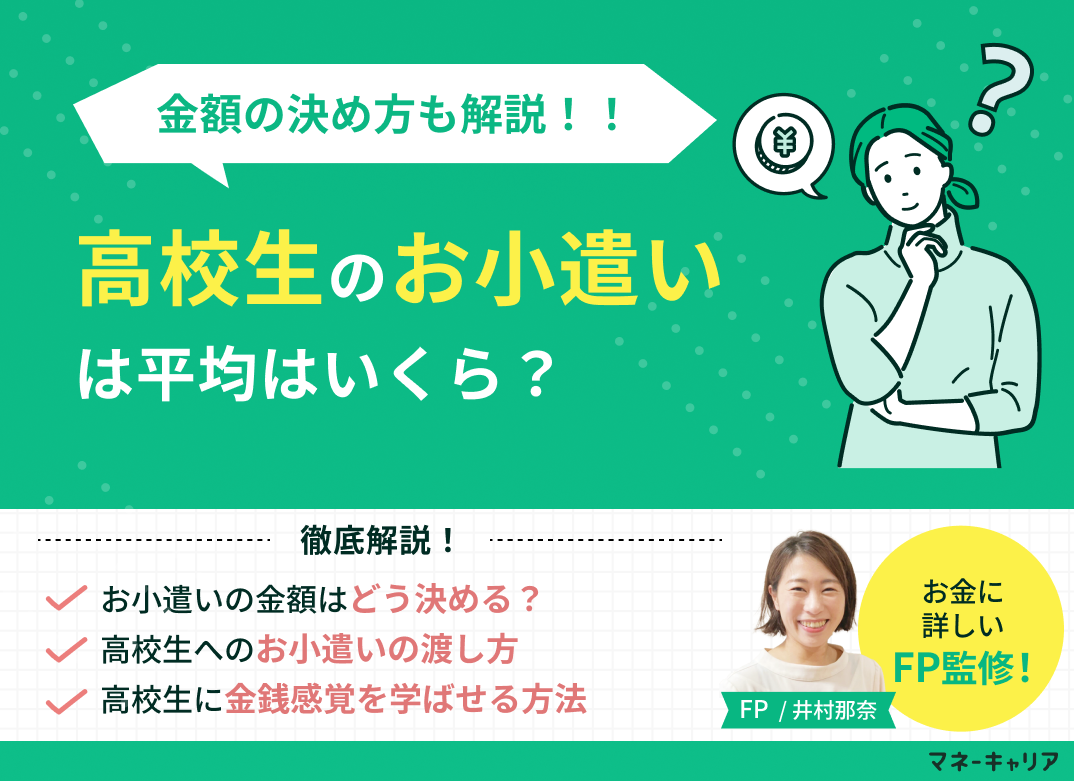
「高校生にお小遣いって、みんなどれくらい渡しているんだろう?」
「うちの子だけ少ないとかわいそうかな……」
そんな不安や疑問を抱えている保護者の方は多いでしょう。
結論からお伝えすると、高校生のお小遣いは全国平均を参考にしつつ、家庭の収入や生活スタイルに合わせて決めるのがベストです。
この記事では、高校生のお小遣いの平均額や学年別の目安・金額の決め方・渡し方の工夫までわかりやすく紹介します。
・「高校生にどれくらいお小遣いを渡せばいいか迷っている」
・「家庭の事情に合ったお小遣いの決め方を知りたい」
そんな方は、本記事を読むことで無理のないお小遣い設定の目安や、金銭感覚を身につけさせる方法まで学べます。
内容をまとめると
- 高校生のお小遣いの平均額や学年別目安がわかる
- 家計や学校生活の費用を踏まえた決め方を紹介
- 渡し方の工夫や金銭感覚を身につけさせる方法も解説
- マネーキャリアでは教育費や家計管理の無料相談ができる

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 高校生のお小遣いの平均はいくら?学年別の平均も紹介
- 高校生へのお小遣いの金額はどう決める?
- 家計とのバランスを考慮する
- 学校生活や交際費にかかる費用から逆算する
- 友達のお小遣い金額は参考程度にする
- 高校生へのお小遣いの渡し方
- 毎月一定額を渡す
- 必要なタイミングで渡す
- 1年分まとめて渡す
- 高校生に金銭感覚を学ばせるためには?
- お小遣い帳をつけさせる
- キャッシュレスでお金を渡す
- バイトを経験させる
- 高校生のお小遣いに関するよくある質問
- 高校生で毎月3,000円のお小遣いは少ない?
- バイトの有無でお小遣い金額は変えるべき?
- 親が出す費用はどこまで?
- 高校生のお小遣いに悩むならお金のプロ「マネーキャリア」に相談
高校生のお小遣いの平均はいくら?学年別の平均も紹介
高校生のお小遣いは、リクルートが提供する進路情報メディア「スタディサプリ進路」の調査(2025年)によると、平均額は約5,422円、中央値は5,000円とされています。
学年別の平均額は以下の通りです。
- 高校1年生:約5,512円
- 高校2年生:約4,893円
- 高校3年生:約5,727円
高校生へのお小遣いの金額はどう決める?
高校生に渡すべきお小遣いの金額は、家庭の収支や子どもの生活スタイルによって大きく変わります。
以下のポイントを基準に考えると、金額を決めやすくなるでしょう。
- 家計とのバランスを考慮する
- 学校生活や交際費にかかる費用から逆算する
無理のない範囲でお小遣いを設定するために、それぞれの考え方を順番に解説していきます。
家計とのバランスを考慮する
まずは家計全体の収支を見直し、そのなかから無理のない額を決めることが基本です。
例えば、月収が30万円の家庭ならお小遣いの目安を5,000円程度に設定し、貯蓄や教育費に充てる割合を確保する、といった調整が有効です。
また、特定の月だけ支出が増える場合(長期休暇・旅行など)も考慮してみてください。
学校生活や交際費にかかる費用から逆算する
子どもの学校生活にかかる実費をもとに逆算する方法もあります。
昼食代や交通費・友人との交際費など、月に必要な金額をリストアップするとよいでしょう。
合計額から「お小遣い」と「必要経費」を分けると、ムリのない金額が見えやすくなります。
友達のお小遣い金額は参考程度にする
友達のお小遣い額はあくまで参考程度にとどめ、家庭の事情に合わせて決めることが重要です。
たとえば、同じクラスの生徒が月8,000円もらっていても、自分の家庭が合わせる必要はありません。
世帯収入や教育費のかけ方、兄弟の人数などが違えば、お小遣いに回せる額も当然異なります。
高校生へのお小遣いの渡し方
高校生へのお小遣いは、金額だけでなく「渡し方」も家庭によってさまざまです。
- 毎月一定額を渡す
- 必要なタイミングで渡す
- 1年分まとめて渡す
どの方法にもメリットとデメリットがあるため、子どもの性格や生活スタイルに合わせて選んでみてください。
順番に解説していきましょう。
毎月一定額を渡す
もっとも一般的な方法が「毎月定額制」です。
たとえば、毎月5,000円を決まった日に渡し、交通費や昼食代は別途支給するなどルールを明確にします。
この方法は、子どもがお金を計画的に使う練習になりやすく、家計管理がしやすい点もメリットです。
必要なタイミングで渡す
「必要な時に必要な分だけ」という柔軟な方法もあります。
部活の合宿費や教材費など、月ごとに支出が変動する家庭に向いているでしょう。
この方法は、親子でその都度話し合う機会が増え、使途を確認しやすい利点があります。
1年分まとめて渡す
一括支給は、子どもの自己管理力を高めたいときに有効です。
たとえば、1年分6万円(5,000円×12か月)をまとめて渡し、部活や交際費なども含めて子ども自身にやりくりさせます。
高校生に金銭感覚を学ばせるためには?
お小遣いを通じて高校生に金銭感覚を学ばせることは、将来の自立に直結します。
そのためには、以下のような方法で「使う・貯める・増やす」の3つを自然に身につけさせることが大切です。
- お小遣い帳をつけさせる
- キャッシュレスでお金を渡す
- バイトを経験させる
これらを活用することで、子どものお金への意識が大きく変わります。
詳しく見ていきましょう。
お小遣い帳をつけさせる
最初のステップはお小遣い帳を使った「見える化」です。
お小遣い帳をつけることで、どこにいくら使ったかが一目で分かり、使いすぎ防止になります。
支出ごとに記録し、月末に振り返る習慣をつけさせましょう。
キャッシュレスでお金を渡す
最近はキャッシュレス決済を使う高校生も増えています。
プリペイドカードやチャージ式交通系ICカードに毎月5,000円をチャージして渡す方法も便利です。
利用履歴が残るため、親子でお金の流れを確認しやすい利点があります。
バイトを経験させる
高校生になったら、アルバイトを通じて「自分で稼ぐ感覚」を身につけさせるのも効果的です。
週3回のコンビニ勤務で月3万円を稼げば、お小遣いとあわせて金銭感覚が大きく変わります。
実際に労働対価を得ることで、無駄遣いが減り、将来のキャリア意識も芽生えやすくなります。
高校生のお小遣いに関するよくある質問
高校生のお小遣いに関して、多くの保護者が感じている疑問や迷いをご紹介します。
- 高校生で毎月3,000円のお小遣いは少ない?
- バイトの有無でお小遣い金額は変えるべき?
- 親が出す費用はどこまで?
このような疑問を整理しておくと、親子の間でトラブルが減り、納得感のあるルールづくりができます。
順番に解説していきましょう。
高校生で毎月3,000円のお小遣いは少ない?
高校生で毎月3,000円という金額は、全国平均から見るとやや少なめです。
リクルートの調査では、高校生全体の平均額は約5,400円、中央値は5,000円という結果が出ています。
バイトの有無でお小遣い金額は変えるべき?
バイトをしている高校生の場合、お小遣いの額を調整する家庭は多いです。
例えば、月に3万円のバイト代があるなら、親からのお小遣いをゼロにするか、補助的に少しだけ渡すなど方法はさまざまでしょう。
重要なのは「親のお金+バイト代」でどのくらい自由に使えるかを確認し、生活に支障がない範囲で設定することです。
親が出す費用はどこまで?
親がどこまで費用を負担するかは、家庭によってさまざまです。
一般的には、通学定期代・昼食代・教材費などの必要経費は親が負担し、交際費や趣味・嗜好品はお小遣いから支払わせるケースが多いでしょう。
「洋服代はシーズンごとに上限1万円まで」「スマホ代は親が負担するがゲーム課金は本人負担」など、細かく線引きをすると混乱が減ります。




























