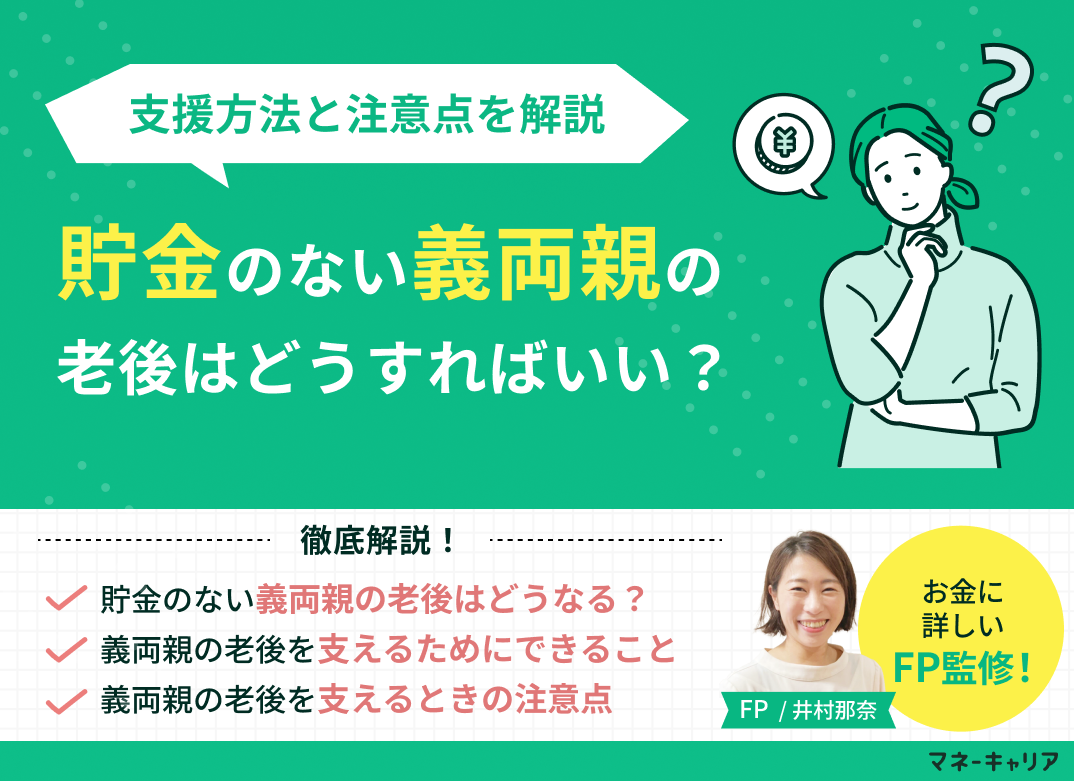
内容をまとめると
- 貯金のない義両親の老後を支える際は無理をしないことが大切
- 専門家のアドバイスを参考にして家計の見直しを一緒に進めるのも有効
- FPに相談すれば家計改善や老後資金の不安を軽減できる
- マネーキャリアは相談実績10万件以上で経験豊富なFPに相談できる
- 家計管理や老後資金の相談にはマネーキャリアがおすすめ

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 貯金のない義両親の老後はどうなる?
- 高齢者の医療・介護費用の実態
- 年金受給額の平均
- 高齢者の家計の収支状況
- 高齢者の貯金・金融資産の平均額
- 貯金のない義両親の老後資金が不足した場合のリスク
- 医療費や介護費の支払いが困難になる
- 日常生活で病気やケガのリスクが高まる
- 希望通りの老後生活を送れない可能性がある
- 貯金のない義両親の老後を支えるためにできること
- 家計に余裕がある場合は資金の援助を検討する
- 義両親の生活費の見直しをサポートする
- 同居や近居で住居費などの負担を減らす
- 国や自治体の支援制度・福祉サービスを活用する
- 貯金のない義両親の老後を支えるときの注意点
- 自分たちの生活を圧迫しない範囲で支援する
- 義両親との金銭トラブルを避けるためにルールを決める
- 家族で話し合い支援方法を決める
- 支援の内容や金額は定期的に見直す
- 必要に応じて専門家(FPなど)に相談する
- 貯金のない義両親の老後について家族で話し合おう【まとめ】
貯金のない義両親の老後はどうなる?
貯金のない義両親が老後を迎えると、医療費や介護費用、生活費の不足など、さまざまなリスクが生じます。
そのままでは生活が安定せず、突発的な出費にも対応しづらくなる可能性があります。
そのため、子世帯としては、老後のマネープランを一緒に考えたり、家計管理のアドバイスを行ったりしてサポートすることが大切です。
ただし、適切な支援をするためには、老後にかかる費用や高齢者の生活費、医療・介護費の実態など、一定の知識を押さえておく必要があります。
これらを理解しておくことで、義両親が安心して生活できる環境をつくることが可能です。
高齢者の医療・介護費用の実態
年金受給額の平均
厚生労働省の調査では、年金の平均受給額は月額14万7,360円(国民年金を含む)です。
そのため、義両親の納付状況によっては、この平均に近い金額を受け取れる可能性があります。
ただし、自営業などで国民年金のみの場合、満額でも月額6万9,308円(令和7年4月分〜)にとどまります。
義両親が貯金がなく老後の生活に不安がある場合は、受け取れる年金額を確認し、その上で家計の見直しや管理方法を一緒に考えていくことが大切です。
高齢者の家計の収支状況
総務省統計局の調査によると、65歳以上の高齢者世帯の家計収支は次のようになっています。
【夫婦のみの無職世帯】
・実収入:25万2,818円
・支出:28万6,877円
・収支差額:▲3万4,059円
※支出には「消費支出」と「非消費支出」の両方が含まれます。
このデータからもわかるように、多くの高齢者世帯は毎月赤字の家計となっており、その不足分を貯金などから補いながら生活しているのが現状です。
高齢者の貯金・金融資産の平均額
参考として、年代ごとの平均貯金額や金融資産の状況も見ておきましょう。
金融広報中央委員会の調査によると、年代別の平均額は以下のとおりです。
| 年代 | 貯金額 | 金融資産保有額(貯金を含む) |
|---|---|---|
| 20代 | 105万円 | 249万円 |
| 30代 | 286万円 | 601万円 |
| 40代 | 361万円 | 889万円 |
| 50代 | 472万円 | 1,147万円 |
| 60代 | 885万円 | 2,026万円 |
| 70代 | 774万円 | 1,757万円 |
| 全体平均 | 563万円 | 1,307万円 |
※金融資産を保有していない世帯を含む
上記のとおり、多くの世帯は老後などに備えて一定の貯金や金融資産を持っています。
しかし、貯金がない場合は日々の家計管理をしっかり行い、黒字を意識して生活することが大切です。
また、義両親に貯金がなくても、株式や投資信託、保険などの金融資産を持っている可能性があります。
資産の有無を確認しておくことで、今後の資金計画をより具体的に立てやすくなります。
貯金のない義両親の老後資金が不足した場合のリスク
貯金のない義両親の老後資金が不足した場合、どのようなリスクがあるかを把握しておくことは大切です。
主なリスクとしては以下の3点が挙げられます。
- 医療費や介護費の支払いが困難になる
- 日常生活で病気やケガのリスクが高まる
- 希望通りの老後生活を送れない可能性がある
医療費や介護費の支払いが困難になる
貯金のない義両親が老後を迎えると、医療費や介護費の支払いが難しくなるリスクがあるため注意が必要です。
高齢になると病気や体調不良の可能性が高まり、医療費や介護費は家計への大きな負担となります。
さらに、介護が必要になると平均で月額約9万円がかかるとされ、貯金がなければ支払いは厳しい状況です。
医療費や介護費の支払いが難しくなると、必要な医療や介護を十分に受けられず、安定した生活を維持できなくなる恐れがあります。
日常生活で病気やケガのリスクが高まる
貯金のない義両親は、老後資金が不足すると日常生活で病気やケガのリスクが高まるため、注意が必要です。
例えば、経済的な理由で真夏にエアコンを控えることで熱中症の危険が高まります。
また、住まいをバリアフリー化できない場合、転倒によるケガや足腰への負担が増えることもあります。
さらに、風邪や体調不良の際に病院受診を控えてしまい、病気のリスクが高まることも少なくありません。
希望通りの老後生活を送れない可能性がある
貯金がない義両親の場合、老後に希望する暮らしややりたいことを実現するのが難しくなる可能性があります。
旅行や趣味といった楽しみを我慢する必要があり、日々の生活も最低限の支出に抑えなければならなくなることがあります。
現役時代に「老後に楽しみたいから今は我慢しよう」と思っていたことも、貯金がないことでほとんど叶えられずに落胆やストレスの原因になるでしょう。
近年は物価も上昇しており、新しいことを始める際にはまとまった費用がかかることも多いため、貯金がないことで老後の楽しみを十分に満喫できないリスクが高まります。
貯金のない義両親の老後を支えるためにできること
貯金のない義両親の老後を支えるためにできることには、次のような方法があります。
- 家計に余裕がある場合は資金の援助を検討する
- 義両親の生活費の見直しをサポートする
- 義両親の今後の資金計画を一緒に立てる
- 同居や近居で住居費などの負担を減らす
- 国や自治体の支援制度・福祉サービスを活用する
家計に余裕がある場合は資金の援助を検討する
貯金のない義両親の老後を支える方法の一つとして、資金援助があります。
家計に余裕がある場合は、必要に応じて資金を援助することで、義両親の生活費の不足を補い負担を軽減できます。
例えば、援助された資金は、医療費や介護費、電気代や食費などに充てることが可能です。
義両親は安心して生活でき、無理な節約や我慢による健康リスクを抑えることができます。
援助の方法や金額は家庭ごとに異なるため、無理のない範囲で計画的に行うことが大切です。
義両親の生活費の見直しをサポートする
生活費の見直しをサポートすることも、貯金のない義両親の老後を支える方法の一つです。
食費や光熱費、通信費、保険料、住居費などの支出を一緒に確認して見直すことで、家計の負担を軽減できます。
例えば、保険や携帯電話の契約プランを適切なものに変更するだけで、月に1万円以上の削減につながる場合があります。
また、住宅ローンを低金利に借り換えて、月々の返済負担を減らすことも可能です。
子世帯が生活費の見直しをサポートすることで、義両親の家計に余裕が生まれる可能性があります。
同居や近居で住居費などの負担を減らす
義両親の老後の生活を支える方法として、同居や近居も選択肢の一つです。
例えば、義両親の家で子世帯が一緒に暮らし生活費を分担することで、住居費や光熱費の負担を抑えられる可能性があります。
近居を選んだ場合でも、定期的に一緒に食事をすることで食費の節約につながります。
また、病気や介護が必要になったときにも、物理的に距離が近いことでサポートがしやすくなり、緊急時の対応もスムーズです。
孫と過ごす時間が増えることで、義両親の心の健康にも良い影響を与えることが期待できます。
国や自治体の支援制度・福祉サービスを活用する
義両親が貯金がない上に生活に困っている場合は、国や自治体の支援制度や福祉サービスを活用するのも選択肢の一つです。
例えば、生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者、障害者などを対象に生活費や住宅費の貸し付けを行っています。
一時的な生活再建のための貸し付けや、自宅を担保にした貸し付けなど、さまざまな形態が用意されています。
このような制度を活用することで、生活費の負担を大きく軽減することが可能です。
利用を検討する際は、制度の内容や条件、手続き方法を事前にしっかり確認しておきましょう。
貯金のない義両親の老後を支えるときの注意点
貯金のない義両親の老後を支援する際には、以下のポイントに注意して進めることが大切です。
- 自分たちの生活を圧迫しない範囲で支援する
- 義両親との金銭トラブルを避けるためにルールを決める
- 家族で話し合い支援方法を決める
- 支援の内容や金額は定期的に見直す
- 必要に応じて専門家(FPなど)に相談する
自分たちの生活を圧迫しない範囲で支援する
貯金のない義両親を支援する際は、自分たちの家計や生活を圧迫しない範囲で行うことが大事です。
無理に多額の資金援助をすると、生活費や教育費、マイホーム資金、老後資金などに影響が出て、家計の安定が損なわれる可能性があります。
支援を行う際は、現実的にどの範囲まで援助できるかを把握して、無理のない金額や方法を設定することが大切です。
また、必ずしも金銭的支援だけがサポートではなく、生活費の見直しや家計改善のアドバイスを行うだけでも義両親にとって大きな支えになるでしょう。
義両親との金銭トラブルを避けるためにルールを決める
義両親への支援を行う際は、金銭トラブルを避けるために、事前に明確なルールを決めておくことが大切です。
サポートの内容や金額、頻度などを話し合い、家族全員が納得した形にしておかないと「もっともらえると思っていた」「この金額は少ない」といった誤解や不満が生じてトラブルの原因になります。
また、家族の状況や義両親の生活環境の変化に応じて、定期的にルールを見直すことも大切です。
ルールがあることで、金銭トラブルのリスクを軽減し、義両親との関係を良好に保ちながら支援を続けられます。
家族で話し合い支援方法を決める
義両親への支援方法を決める際は、自分たちだけで一方的に判断せず、義両親も交えて話し合うことが大事です。
子世帯の都合や考えだけで支援内容を決めると、義両親のニーズに合わず、せっかくのサポートが負担や不満につながる可能性があります。
例えば、生活費の援助が助けになると思っても、義両親は望んでいない場合がありますし、逆にプライドが傷つき関係性が悪化することもありえます。
そのため、どの範囲まで援助するか、どのような形でサポートするかを話し合い、義両親の意向を尊重して決めることが大切です。
支援の内容や金額は定期的に見直す
義両親の老後を支える際には、最初に決めた支援内容や金額をそのまま続けるのではなく、定期的に見直すことが大切です。
生活状況や健康状態、医療や介護の必要性は時間の経過とともに変化します。
また、支える側である子世帯の家計やライフステージも変わっていくためです。
そのため、定期的に「今のサポートは適切か」「無理をしていないか」を確認して、必要に応じて調整することが大切です。
必要に応じて専門家(FPなど)に相談する
貯金のない義両親の老後を支える際、FPなどの専門家に相談するのもおすすめです。
FPは家計の状況を分析し、無理のない支出の見直しや貯金計画、老後資金のプランについてアドバイスをしてくれます。
そのアドバイスをもとに、義両親に家計改善の方法を伝えることができます。
オンラインに対応している窓口であれば、自宅から気軽に利用可能です。
金銭的な支援だけでなく、家計の管理や改善をサポートすることも、義両親の安心した老後を支える大切な方法です。
貯金のない義両親の老後について家族で話し合おう【まとめ】
貯金のない状態で老後を迎えると、生活費だけでなく医療費や介護費の支払いが難しくなり、思わぬリスクを抱えることになります。
義両親の老後を支える際には一方的に決めるのではなく、しっかり話し合い、お互いが納得できる方法を選ぶことが大切です。
また、生活費の支援は無理のない範囲にとどめ、自分たちの家計を圧迫しないことも重要です。
FPのアドバイスを受け、家計の見直しや資金計画をサポートするのも有効な手段となります。
義両親の老後に不安を感じる方は、専門家からアドバイスをもらうなど、まずはできることから始めてみましょう。




























