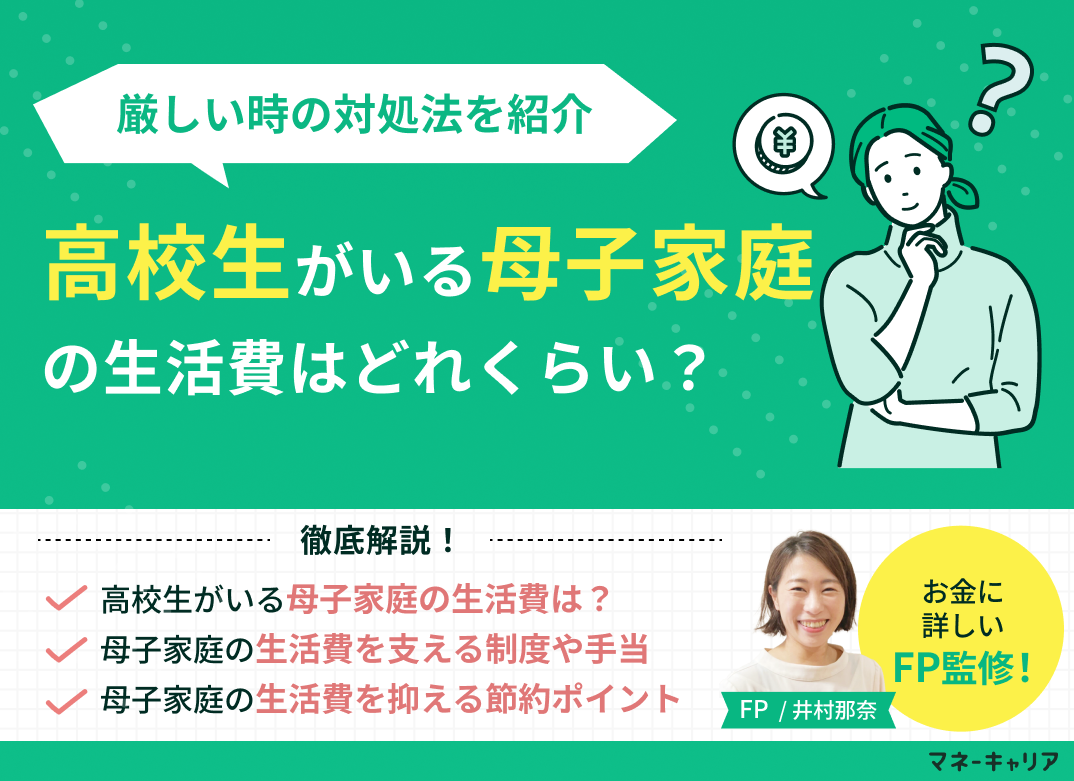
内容をまとめると
- 生活費が厳しいと感じたら支出を見直したり収入を増やすことが必要
- 生活費に加えて進学費用や老後資金の準備も早めに始めることが大切
- FPに相談することで家計改善や将来資金の不安を解消できる
- マネーキャリアは相談実績10万件以上で経験豊富なFPに相談可能
- 家計管理や将来資金の相談にはマネーキャリアがおすすめ

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 高校生がいる母子家庭の生活費は?
- 生活費の内訳と平均額
- 平均年収
- 就業状況・働き方
- 平均貯金額
- 高校生がいる母子家庭の生活費を支える制度や手当
- 児童扶養手当
- 特別児童扶養手当
- 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
- 高校生がいる母子家庭の生活費を抑える節約ポイント
- 通信費や保険料などの固定費を見直す
- 交際費や日用品などの変動費を抑える
- 高校生がいる母子家庭の生活費が厳しいときの対処法
- 副業・アルバイトで収入を増やす
- 公的支援制度を活用して生活費を補う
- FPなどの専門家に相談してアドバイスをもらう
- 高校生がいる母子家庭で生活費以外に準備すべき将来資金
- 子どもの進学費用(大学など)
- 万が一に備える生活防衛資金
- 自身の老後資金
- 高校生がいる母子家庭の生活費に関するよくある質問
- 生活費が足りないときはどうすればいいですか?
- 家計が厳しいときはどこに相談したらいいですか?
- 高校生がいる母子家庭で生活費が厳しいときは早めの対策を【まとめ】
高校生がいる母子家庭の生活費は?
高校生を育てる母子家庭で、生活費がどのくらいかかるのかを把握しておくことは大切です。
一般的な平均額を知ることで、家計の目安を立てたり、節約の参考にできます。
ここでは以下のポイントについて解説します。
- 生活費の内訳と平均額
- 平均年収
- 就業状況・働き方
- 平均貯金額
生活費の内訳と平均額
総務省統計局の調査によれば、高校生のいる母子家庭の1ヶ月の生活費は平均23万5,648円となっています。
主な内訳は、次のとおりです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 食料 | 5万5,095円 |
| 電気代 | 7,606円 |
| ガス代 | 3,986円 |
| 上下水道料 | 3,800円 |
| 家具・家事用品 | 5,762円 |
| 被服及び履物 | 8,648円 |
| 保健医療 | 6,388円 |
| 授業料等 | 8,352円 |
| 交際費 | 4,149円 |
※男親または女親と未婚の子供の世帯 長子が高校生、専門学校生、短大・高専生の場合
生活費は地域やライフスタイルで差がありますが、平均額を知ることで計画や節約の参考になります。
平均より多くかかっている項目があれば、重点的に節約を検討してみましょう。
平均年収
厚生労働省の調査によれば、母子家庭の平均年収は次のとおりです。
| 収入状況 | 平均年収 |
|---|---|
| 平均年間収入 (母自身の収入) | 272万円 |
| 平均年間就労収入 (母自身の就労収入) | 236万円 |
| 平均年間収入 (世帯全員の収入) | 373万円 |
平均収入272万円を月収に換算すると、約22.6万円となります。
また、学歴別に見た母親の平均年間就労収入は次のようになっています。
・中学校:130万円
・高校:191万円
・高等専門学校:258万円
・短大:259万円
・大学・大学院:383万円
・専修学校・各種学校:254万円
・その他:171万円
職種や勤務先、個人の努力などにもよりますが、データからは学歴が高いほど収入も上がる傾向が確認できます。
就業状況・働き方
厚生労働省の調査によると、母子家庭の就業状況は以下のとおりです。
| 就業状況 | 割合 |
|---|---|
| 正規の職員・従業員 | 48.8% |
| 自営業 | 5.0% |
| パート・アルバイト | 38.8% |
正社員が約半数を占め、パート・アルバイトは約4割となっています。
参考までに、父子家庭の就業状況は次のとおりです。
・正規の職員・従業員:69.9%
・自営業:14.8%
・パート・アルバイト:4.9%
父子家庭では正社員の割合が約7割と高く、パート・アルバイトは1割未満にとどまります。
平均貯金額
厚生労働省の調査によれば、母子家庭の貯金状況は次のとおりです。
| 貯金額 | 割合 |
|---|---|
| 50万円未満 | 39.8% |
| 50万〜100万円未満 | 9.6% |
| 100万〜200万円未満 | 11.5% |
| 200万〜300万円未満 | 5.8% |
| 300万〜400万円未満 | 5.0% |
| 400万〜500万円未満 | 1.6% |
| 500万〜700万円未満 | 4.8% |
| 700万〜1,000万円未満 | 2.5% |
| 1,000万円以上 | 5.8% |
| 不明 | 13.7% |
このデータから、母子家庭の多くは貯金が少なく、特に50万円未満の世帯が約4割を占めていることがわかります。
将来の教育費や急な出費に備える余裕が十分でない場合もあるため、家計の見直しや収入増の対策をとり、貯金を増やしていくことが大切です。
高校生がいる母子家庭の生活費を支える制度や手当
高校生がいる母子家庭の生活費を支える制度や手当には、次のようなものがあります。
- 児童扶養手当
- 特別児童扶養手当
- 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
児童扶養手当
児童扶養手当は、母子家庭や父子家庭を経済的に支え、子どもの健やかな成長を後押しするために設けられた制度です。
支給対象は、18歳に達した年度末までの子どもを養育している親で、子どもに障害がある場合は20歳未満まで対象となります。
支給額は、子どもの人数や所得額によって変動する仕組みです。
| 子どもの人数 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 1人目 | 4万6,690円 | 4万6,690円〜1万1,010円 |
| 加算額(2人目以降1人につき) | 1万1,030円 | 1万1,020円〜5,520円 |
※令和7年4月〜
手当は年6回に分けて、2ヶ月分ごとに支給されます。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、障害のある20歳未満の子どもを支援し、福祉の向上を目的とした制度です。
支給額は障害の程度によって異なります。
| 障害の程度 | 支給額 |
|---|---|
| 1級 | 5万6,800円 |
| 2級 | 3万7,830円 |
※令和7年4月〜
支給は年3回(4月・8月・12月)で、各回に4ヶ月分がまとめて支給されます。
ただし、前年の所得が一定額を超える場合は手当を受けられません。
例えば、子ども1人の場合の所得上限は497万6,000円(収入換算で約686万2,000円)です。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
収入が減ったり失業したりして国民年金保険料を納めるのが難しい場合は、申請により保険料の免除を受けることができます。
免除額は「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4種類で、生活費の負担を軽減できます。
免除を受けると将来の年金額は減りますが、10年以内であれば追納も可能です。
高校生がいる母子家庭の生活費を抑える節約ポイント
高校生がいる母子家庭の生活費を抑える節約ポイントには、次のようなものがあります。
- 通信費や保険料などの固定費を見直す
- 交際費や日用品などの変動費を抑える
通信費や保険料などの固定費を見直す
高校生がいる母子家庭で生活費を抑えるには、固定費の見直しが効果的です。
通信費や保険料などの固定費は毎月必ず発生する支出であり、見直し次第で大きな節約につながります。
例えば、スマホやインターネット回線・Wi-Fiの料金プランを変更したり、不要なオプションを解約したりするだけでも月々の負担を軽減可能です。
また、生命保険や医療保険も保障内容を確認して、重複や過剰な保障があれば変更することで無駄を減らせます。
固定費を適切に見直し・管理することは、長期的な家計の安定にもつながります。
交際費や日用品などの変動費を抑える
交際費や日用品、食費などの変動費は、家計の中でも調整しやすい支出です。
食費はまとめ買いや特売、クーポンの活用で節約でき、日用品は必要な分だけ購入することがポイントです。
また、交際費もクーポンを使うなど、友人との付き合い方を工夫することで負担を減らせます。
変動費を見直すことで、生活費のやりくりが楽になり、貯金や将来資金の準備も進めやすくなります。
高校生がいる母子家庭の生活費が厳しいときの対処法
高校生のいる母子家庭で生活費が厳しい場合、次のような対処法があります。
- 副業・アルバイトで収入を増やす
- 公的支援制度を活用して生活費を補う
- FPなどの専門家に相談してアドバイスをもらう
副業・アルバイトで収入を増やす
高校生がいる母子家庭で生活費が厳しいときは、節約だけでなく、副業やアルバイトで収入を増やすことも対策の一つです。
母親自身は、在宅でできるデータ入力やライティング、内職、短時間勤務のパートなどを選べば、子育てや家事と両立しやすく、安定した収入の補填につながります。
また、高校生の子どもがアルバイトを始めることも一つの選択肢です。
学業に支障がない範囲で働くことで、家計の助けになるだけでなく、社会経験や金銭感覚を学ぶ良い機会にもなります。
副業やアルバイトは、無理のない範囲で取り組むことが継続のポイントです。
公的支援制度を活用して生活費を補う
公的支援制度を活用することも、高校生がいる母子家庭の生活費が厳しいときの対処法の一つです。
例えば、国民健康保険料の減額や年金保険料の免除制度を活用すれば、毎月の支出を一時的に軽減できます。
さらに、失業や収入減で生活が厳しいときには、生活福祉資金貸付制度を利用して、生活再建に必要な資金を借りることも可能です。
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度では、生活費や住宅費、就職準備資金など、さまざまな目的で資金を借りることができます。
生活費が厳しいときは、このような公的支援制度の利用も検討してみるとよいでしょう。
FPなどの専門家に相談してアドバイスをもらう
高校生がいる母子家庭で生活費が厳しいときの対処法が、FPなどの専門家に相談することです。
FPは家計の収支状況をもとに、無理のない節約方法や支出の見直し、将来に必要な資金の計画などをアドバイスしてくれます。
また、税金対策や保険の見直しについても相談可能です。
対面だけでなくオンラインでの相談にも対応しているサービスが多く、忙しい方でも自宅から手軽に利用できます。
専門家のアドバイスを受けることで、家計改善の方向性が明確になり、安心して生活費のやりくりが行えるようになります。
高校生がいる母子家庭で生活費以外に準備すべき将来資金
高校生がいる母子家庭で生活費以外に準備すべき将来資金には、次のようなものがあります。
- 子どもの進学費用(大学など)
- 万が一に備える生活防衛資金
- 自身の老後資金
子どもの進学費用(大学など)
高校生がいる母子家庭では、大学や短大、専門学校などの進学費用の準備も重要です。
進学には入学金や授業料だけでなく、教科書代、通学費などが必要になります。
特に私立大学や理系学部を選択する場合、4年間で1,000万円近い費用がかかることも珍しくありません。
奨学金や教育ローンを利用する家庭も多いですが、返済の負担を考えると、できるだけ資金を準備しておくことが安心につながります。
児童手当を教育資金に充てたり、NISAを活用して積立投資を行うのも有効です。
計画的に資金を準備しておくことで子どもの進路選択の幅が広がり、安心して学業に専念できる環境をつくることができます。
万が一に備える生活防衛資金
高校生がいる母子家庭では、日常の生活費に加え、万が一に備えた生活防衛資金を準備しておくことが大切です。
生活防衛資金とは、収入の減少や病気、失業など予期せぬ事態に対応するためのお金のことで、目安として生活費の3〜6ヶ月分を確保しておくと安心です。
この資金があれば、仕事ができず収入が減ったとしても、一定期間はこれまで通りの生活を維持できます。
子どもの学業や生活に影響が及ぶのを防ぐこともでき、精神的な余裕にもつながります。
万が一に備え、平時から計画的に準備しておくことが大切です。
自身の老後資金
高校生がいる母子家庭では、子どもの教育費や生活費の確保に目が向きがちですが、自身の老後資金についても計画的に準備しておくことが大事です。
公的年金だけでは十分な生活を維持できない可能性があります。
総務省統計局の調査によれば、65歳以上の家計収支の平均は次のとおりです。
・夫婦のみの無職世帯:月3万4,058円の赤字
・単身無職世帯:月2万7,817円の赤字
このような現実を踏まえ、早めに貯金や投資を始め、老後資金を計画的に備えておくことが将来の安心につながります。
高校生がいる母子家庭の生活費に関するよくある質問
高校生がいる母子家庭の生活費に関するよくある質問は、次のとおりです。
- 生活費が足りないときはどうすればいいですか?
- 家計が厳しいときはどこに相談したらいいですか?
生活費が足りないときはどうすればいいですか?
生活費が足りないときは、まず支出の見直しを行い、固定費や変動費を削減できないか確認しましょう。
特に通信費や保険料、光熱費などは契約内容を見直すだけで負担を軽減できる場合があります。
それでも改善が難しい場合は、副業やアルバイトなどで収入を増やすことも大切です。
自分だけで解決策を見つけるのが難しいときは、FPなどの専門家に相談してアドバイスを受けることもおすすめです。
家計が厳しいときはどこに相談したらいいですか?
家計が厳しく、生活費のやりくりに不安がある場合は、FPへの相談がおすすめです。
FPは家計の収支状況を分析し、支出の見直しポイントや無理のない貯金計画、将来必要な資金の準備方法などをアドバイスしてくれます。
マネーキャリアは、10万件以上の相談実績を持つFPサービスです。
Googleの口コミでは5点中4.8点を獲得しており、利用者からは高い評価を得ています。
また、事前にFPの得意分野や口コミをチェックして、自分に合った担当者を選ぶこともできます。
高校生がいる母子家庭で生活費が厳しいときは早めの対策を【まとめ】
高校生がいる母子家庭で生活費が厳しいと感じる場合は、早めに支出の見直しや節税、収入アップの取り組みを行うことが大切です。
また、公的支援制度を活用して一時的に生活費を補うのも対処法の一つです。
さらに、目先の生活費だけでなく、子どもの進学資金や自身の老後資金、生活防衛資金など将来に備えた資金も準備しておく必要があります。
お金の不安を減らし、家計の改善や資金準備を計画的に行うために、FPなど専門家のアドバイスを受けながら進めることをおすすめします。




























