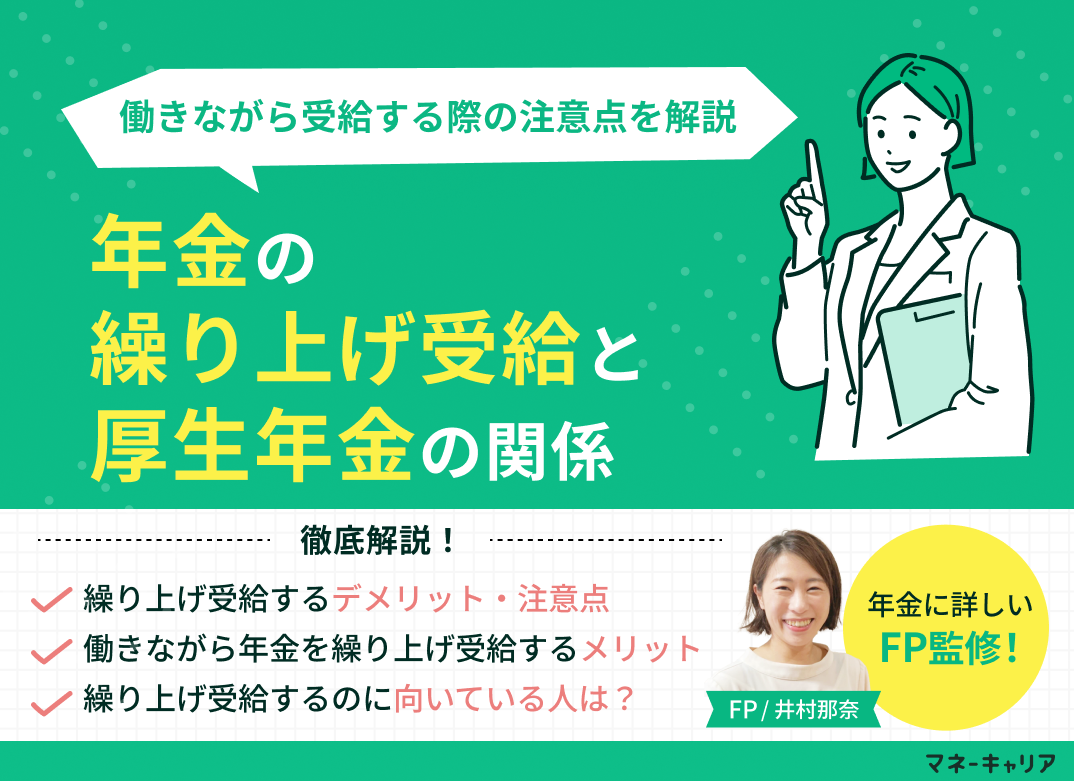この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 専業主婦の年金を増やすには?5つの方法を解説
- ① 任意加入制度を活用する
- ② つみたてNISAやiDeCoを活用する
- ③ 貯蓄型保険に加入する
- ④ パート勤務で厚生年金に加入する
- ⑤ 繰り下げ受給で増額を狙う
- 専業主婦の年金のお悩みは無料FP相談で解決しよう
- 専業主婦が年金を増やすときの注意点
- 夫婦全体での老後資金計画を立てる
- 固定費の削減で「使えるお金」を増やす
- 健康・寿命リスクを踏まえて判断する
- 専業主婦の年金についてよくある質問
- 専業主婦の年金はいくらもらえるの?
- 夫が先に亡くなった場合、年金はどうなる?
- 専業主婦の年金も税金や社会保険料が引かれる?
- NISAで儲けると扶養から外れるの?
- 【まとめ】専業主婦の年金を増やすには早めの行動が有利|迷ったらFPに相談を
専業主婦の年金を増やすには?5つの方法を解説
専業主婦の年金を増やすには、5つの方法が有効です。なぜなら、老齢基礎年金だけでは、生活にゆとりが出にくいからです。
ただし、制度ごとに条件や費用、リスクがあるため、次の5つを目的別に検討しましょう。
- 任意加入制度を活用する
- つみたてNISAやiDeCoを活用する
- 貯蓄型保険に加入する
- パート勤務で厚生年金に加入する
- 繰り下げ受給で増額を狙う
① 任意加入制度を活用する
任意加入制度※1とは、60歳以降も国民年金に任意で加入し、保険料を納めることで将来の年金額を増やせる仕組みです。
たとえば、60歳から65歳まで5年間加入すれば、65歳以降に受け取る老齢基礎年金を上積みできます。さらに、受給資格期間(10年)を満たしていない場合は、70歳まで延長加入して資格の確保もできます。
任意加入できる人の条件は次のとおりです(すべてを満たす必要があります)。
- 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ受給をしていない方
- 20歳から60歳までの納付済期間が480月未満の方
- 厚生年金や共済年金に加入していない方
② つみたてNISAやiDeCoを活用する
公的年金を補う方法として、積立投資を選ぶ人が増えています。当編集部の調査では「iDeCoや新NISAで積立投資を始めている」と答えた人が36.3%に上り、老後資金の不安解消策として多い結果でした。
税制優遇を受けながら資産を積み立てることは、将来の備えとして有効です。
| 項目 | 新NISA(つみたて投資枠)※1 | iDeCo(個人型確定拠出年金)※2 |
|---|---|---|
| 内容 | ・2024年から開始 ・運用益や配当が非課税 ・投資期間の制限なく 長期で積立ができる | ・掛金全額が所得控除の対象 ・運用益も非課税 ・60歳以降の受給時には 退職所得控除などの優遇 |
※1参照:NISAを知る|金融庁
※2参照:iDeCoの概要|厚生労働省
③ 貯蓄型保険に加入する
老後資金づくりの方法として、貯蓄型保険に加入する選択肢があります。貯蓄型保険とは、主に保障と貯蓄の両機能を備え、解約時や満期時に解約返戻金や満期保険金を受け取れる仕組みです。
<主な貯蓄型保険>
- 養老保険
- 終身保険
- 個人年金保険
計画的に老後資金を積み立てられる点が、共通のメリットです。貯蓄が苦手でも強制的に資金を準備でき、個人年金保険料控除や生命保険料控除により税負担の軽減も期待できます。
一方で、デメリットや注意点もあります。途中解約では、支払総額を下回る元本割れが起こりやすい点です。貯蓄型保険は契約時の利率でのみ増えるため、インフレ下では実質価値が目減りするリスクもあります。
④ パート勤務で厚生年金に加入する
専業主婦が老後の年金を増やす有効な方法の一つに、パート勤務を通して厚生年金に加入する選択肢があります。
国民年金のみの場合、老齢基礎年金の受給額は満額でも年約83万円程度にとどまりますが※1、厚生年金を上乗せできれば受給額を増やせます。
厚生年金の被保険者となる条件を満たすと、厚生年金および健康保険に加入します。加入すると給与から保険料が天引きされるため手取りは減少しますが、将来的には老齢厚生年金が受け取れるようになります。
さらに、厚生年金の保険料は労使折半であり、会社が自分の負担分と同額を負担してくれるため、効率的に老後資金を準備できる点が大きなメリットです。
⑤ 繰り下げ受給で増額を狙う
専業主婦が受け取る老齢基礎年金は、満額を受け取っても老後生活に十分とはいえません。不足を補う方法のひとつが「繰り下げ受給」です。受給開始を65歳から遅らせると年金額が増える仕組みで、1か月繰り下げるごとに0.7%ずつ加算されます※。
下記の表には、65歳と70歳で受給した場合の違いを一例としてまとめました。
| 比較項目 | 65歳受給 | 70歳受給 |
|---|---|---|
| 年金年額 | 約78万円 | 約111万円 (増額率は42%※) |
| 年金月額 | 6.5万円 | 9.2万円 |
| 80歳の受給額 | 1,170万円 | 1,110万円 |
| 82歳の受給額 | 1,326万円 | 1,332万円 |
基礎年金のみの場合、70歳で受給した方が月2~3万円多く受け取れます。65歳からの受給額を上回るには、82歳以降まで長生きする前提が必要なため、自身の健康状態や寿命への見通しが重要な判断材料です。
一方でデメリットもあります。繰り下げ中の5年間は年金を受け取れないため、生活費を預貯金や資産運用で補う必要があります。さらに、増額分を受け取る前に本人が亡くなった場合、結果的に損になるリスクもあるのです。
専業主婦の年金のお悩みは無料FP相談で解決しよう

老後の生活資金に、不安を抱える人は少なくありません。生命保険文化センターの調査によれば「公的年金だけでは生活が不十分」と考える人は約8割にのぼります※。
専業主婦の場合「年金だけで暮らせるのか」「将来どれくらい受け取れるのか」といった悩みを抱えがちです。こうした不安は、FPに相談することで具体的な解決策が見えてきます。
FPは夫婦の年金額や家計状況、ライフプランを踏まえて最適な方法を提案してくれる存在です。公的年金だけに頼らず早めに備えることで、将来の資金不足を解消しやすくなります。悩みを一人で抱え込まず、第三者であるFPに相談してみましょう。

専業主婦が年金を増やすときの注意点
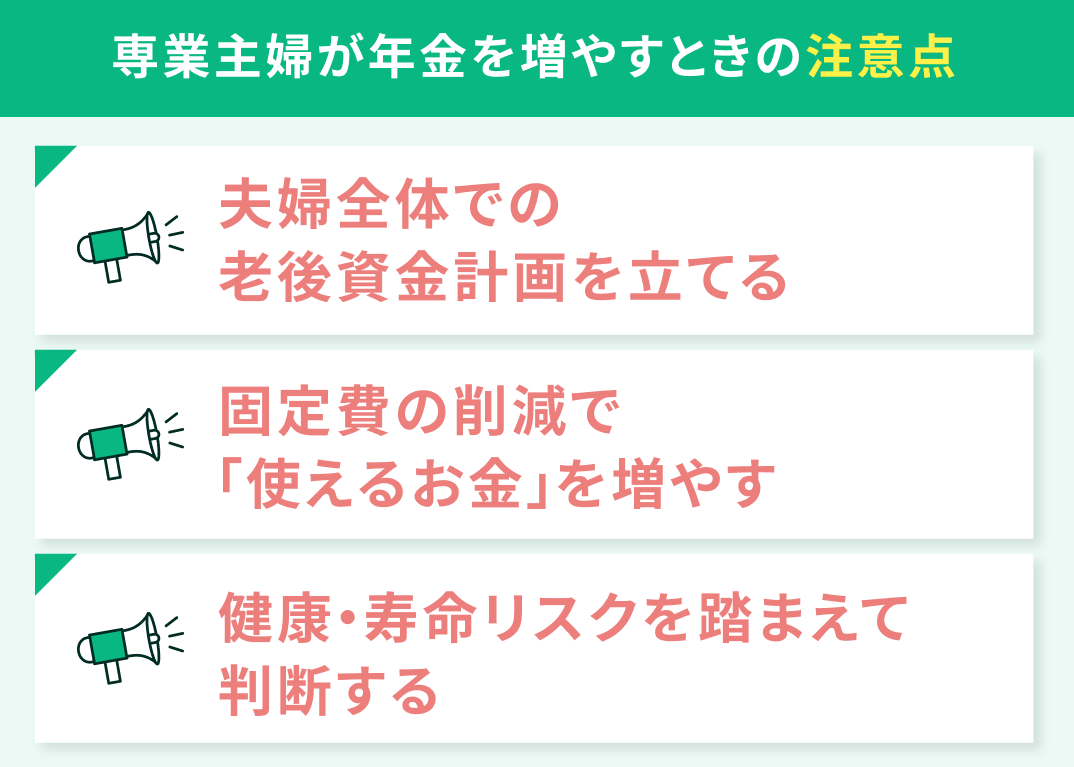
- 夫婦全体での老後資金計画を立てる
- 固定費の削減で「使えるお金」を増やす
- 健康・寿命リスクを踏まえて判断する
夫婦全体での老後資金計画を立てる
老後の資金計画は、夫婦それぞれではなく世帯単位で設計しましょう。公的年金や退職金、貯蓄、遺族年金の見込み額まで洗い出し、夫婦のライフプランに合わせた必要資金を算出しましょう。
昨今の物価高などにより、年金収入だけでは生活が厳しくなる可能性が高いため、計画的な準備が大切です。
<準備のポイント>
- 夫婦それぞれの年金・退職金・貯蓄を合算し、世帯の収入全体を確認する
- どちらが繰下げ受給を選ぶか、どのくらい働くかを一緒に考える
- 「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で年金見込額を確認し、必要資金との差を明確にする
夫婦で将来の考えが合わないときは、第三者であるFPに相談すると整理しやすくなります。
固定費の削減で「使えるお金」を増やす
老後資金を準備するには、収入を増やすだけでなく支出を減らすことも効果的です。特に毎月発生する固定費を見直せば、一度の取り組みで長期間にわたり節約効果が続くため、家計改善への影響は大きくなります。
<主な固定費>
- 居住費
- 水道光熱費
- 通信費
- 保険料
- 車の維持費
固定費は、変動費より削減しやすい費用です。大手キャリアから格安SIMに乗り換えたり、不要なサブスクリプションを解約したりすれば、毎月数千円単位の節約につながります。
居住費は、固定費の中でも負担割合が大きい項目です。賃貸なら家賃交渉や割安物件への転居、持ち家なら住宅ローンの借り換えなどが軽減できる方法として挙げられます。
健康・寿命リスクを踏まえて判断する
老後資金の設計においては、自身や配偶者の健康状態や寿命の見通しを前提に判断することも大切です。年金を65歳から受け取るか、繰上げ・繰下げ選ぶかは、金額の比較ではなく「長生きに備えるか」「元気なうちに受け取るか」という価値観の選択でもあります。
日本人の平均寿命は男性で約81年、女性で約87年とされていますが※1、実際の寿命は個人差が大きく、家族の健康歴や生活習慣も影響します。繰下げ受給を選ぶと1ヶ月ごとに0.7%増額され、70歳からの受給なら最大42%の上乗せが可能です※2。
ただし、65〜69歳の間に年金を受け取れないため、総受取額で得になるかは寿命に左右されます。
専業主婦の年金についてよくある質問
- 専業主婦の年金はいくらもらえるの?
- 夫が先に亡くなった場合、年金はどうなる?
- 専業主婦の年金も税金や社会保険料が引かれる?
- NISAで儲けると扶養から外れるの?
専業主婦の年金はいくらもらえるの?
老齢基礎年金の満額は40年間の加入で受給でき、2025年度では年額約83万1,700円(月額6万9,308円)です※1。
年金額は毎年度の物価や賃金の変動に応じて見直されるため、将来的にも変動する可能性があります。ただし、満額を受け取るには40年分の保険料納付が必要で※2、未加入や未納期間がある場合はその分だけ減額されるのです。
実際には、すべての人が満額を受け取れるわけではありません。結婚や出産により未納期間が生じたり、国民年金保険料を全額納めていなかったりする期間があると、受給額が減ります。
夫が先に亡くなった場合、年金はどうなる?
夫が厚生年金に入っていた場合、妻は「遺族厚生年金」を受け取れます。遺族厚生年金の金額は、夫の老齢厚生年金のうち報酬比例部分の4分の3です。
たとえば、夫が月16万円の年金を受け取り、そのうち報酬比例部分が12万円なら、妻の遺族厚生年金は9万円程度になります。
妻の老齢基礎年金は遺族厚生年金と併せて受け取れますが、妻にも老齢厚生年金の受給権がある場合は、重なる部分が調整されます。つまり、妻の老齢厚生年金分にあたる金額が、遺族厚生年金から差し引かれる仕組みです。
そのため、夫婦で生前に受け取っていた合計よりも、妻が一人で受け取る年金は少なくなるのが一般的です。
専業主婦の年金も税金や社会保険料が引かれる?
専業主婦が受け取る年金について所得税が課されるケースは少なく、非課税となる場合がほとんどです。なぜなら、基礎控除として一律58万円※1と、年齢に応じて「公的年金等控除」が適用されるからです。
<受給時の年齢による控除額の比較>
| 年齢 | 65歳未満 | 65歳以上 |
|---|---|---|
| 公的年金等控除 | 60万円 | 110万円 |
| 合計 (基礎控除含む) | 118万円 | 168万円 |
専業主婦が受け取る老齢基礎年金は年額83万円前後であるため、ほとんどの場合は課税所得が発生せず、所得税が源泉徴収されることもありません。
住民税についても、基礎控除や公的年金等控除により、多くの人は非課税となります。
NISAで儲けると扶養から外れるの?
NISAで得た利益が理由で専業主婦が税制上の扶養から外れることは、2025年現在の制度では基本的にありません。NISA口座で得られる配当や売却益はすべて非課税扱いで、確定申告の必要もなく、税法上の「所得」に含まれないからです。そのため、配偶者控除や配偶者特別控除などには影響しません。
社会保険上の扶養基準は「年収130万円未満」であることが一般的で、主に給与や年金といった継続的な収入で判断されます。ただし、健康保険の扶養を判定する際は、税金のように「所得」ではなく、収入の見込み額で判断します。
加入している健康保険組合や協会けんぽによって基準が異なるため、運用益が大きくなる場合は事前に確認しておくことが大切です。
【まとめ】専業主婦の年金を増やすには早めの行動が有利|迷ったらFPに相談を

専業主婦が将来受け取れる公的年金額は決して多くなく、満額の老齢基礎年金でも2025年度で月約6万9,308円にとどまります※。夫婦でゆとりある老後生活を送るにはそれ以上の金額が必要になるため、公的年金だけでは不足が避けられません。
iDeCoや新NISAの活用、繰下げ受給などを組み合わせることで、将来の受給額を増やす対策が可能です。
マネーキャリアは、老後資金や年金に関するあらゆる悩みを相談できる無料のサービスです。専属のFPが担当制で一貫して対応し、保険や資産運用も含めた総合的な視点でアドバイスを受けられるのが強みのひとつです。まずはマネーキャリアで専門家に相談し、将来の安心につなげましょう。