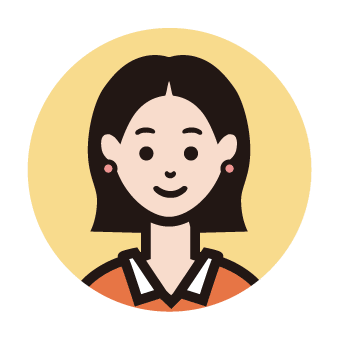内容をまとめると
- 双子を出産した際、育児休業給付金や出産手当金などは原則1人分の支給なのに対し、出産育児一時金や児童手当は2人分受け取ることができる。
- 公的支援制度やベビーシッター補助など地域や国のサポートを上手に活用しつつ、保育園は双子でも優遇されない実情を踏まえて、早めの家計・育児計画を立てることが重要。
- 家計・育児計画を立てるのに不安がある方は、無料で何度でもFP(ファイナンシャルプランナー)に相談できる「マネーキャリア」を利用し、客観的かつオーダーメイドなアドバイスを受けるのがおすすめ。

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 双子出産前に知っておきたい育休制度の全体像
- 産前産後休暇と育児休業の違い
- 出産育児一時金・育児休業給付金・出産手当金の違い
- 双子で2倍もらえる手当・もらえない手当の整理
- 出産育児一時金は2人分がもらえる
- 育児休業給付金は1人分と同額がもらえる
- 出産手当金は1人分と同額が原則
- 児童手当は2人分がもらえる
- 双子育児で使える公的支援制度と保育園の実情
- 自治体の双子家庭への支援
- 国のベビーシッター補助制度
- 注意:保育園は基本的に優遇されない
- 双子の育休中にやっておくべき出費対策
- 今後の家計をシミュレーションする
- 急な出費に備える
- 双子の育休手当に関するよくある質問
- 夫も育休を取るべきですか?おすすめの分担方法は?
- 双子を産んだ場合、毎月の手当はいくら支給されますか?
- 双子の子育てについて金銭的不安がある方におすすめのサービス
- 双子の育休手当は2倍もらえる?損しないためのポイントまとめ
双子出産前に知っておきたい育休制度の全体像
双子出産前に知っておきたい育休制度の全体像を2つ解説します。
紹介する内容は以下のとおりです。
- 産前産後休暇と育児休業の違い
- 出産育児一時金・育児休業給付金・出産手当金の違い
各制度の特徴を知ることで、出産前後の働き方や家計の準備に余裕が持てるので、ぜひ参考にしてください。
産前産後休暇と育児休業の違い
産前産後休暇と育児休業の違いを知ることで、双子出産前後の働き方の計画が立てやすくなります。
産前産後休暇は、出産する本人が取得できる休暇で、労働基準法第65条に定められています。
双子を妊娠した場合、産前は出産予定日の14週間前から、産後は出産翌日から8週間まで取得可能です(※1)。
ただし、産後6週間を過ぎたあとは医師の許可を得て職場復帰することもできます(※1)。
一方、育児休業は子どもの養育のために一定期間仕事を休める制度です。
双子であっても取得期間は変わらず、原則1年、保育所に入れない場合などの特例が認められれば最長2年まで延長できます(※2)。
※1 参照:労働基準法第65条|e-GOV法令検索
※2 参照:育児・介護休業法第5条|e-GOV法令検索
出産育児一時金・育児休業給付金・出産手当金の違い
出産育児一時金・育児休業給付金・出産手当金の違いを知ることで、双子出産前後の家計を整えやすくなります。
それぞれのもらえる時期・金額・申請先が異なるため、事前に理解しておくと手続きの見通しが立てやすくなるからです。
出産育児一時金は、健康保険から原則50万円(※1)が支給され、医療機関を通じた“直接支払制度”の利用が一般的です。
育児休業給付金は、育休開始から6ヵ月間は賃金の67%、その後は50%が支給され、会社を通じてハローワークに申請します(※2)。
出産手当金は、双子など多胎妊娠では産前98日から産後56日まで、給与の2/3相当額が健康保険から支給されます(※3)。
次の章では、これらの制度が“双子の場合いくらもらえるのか”という視点で解説するので、ぜひあわせてチェックしてください。
※1 参照:出産育児一時金の支給額・支払方法について|厚生労働省
※2 参照:育児休業等給付の内容と支給申請手続|厚生労働省
※3 参照:出産手当金について|全国健康保険協会
双子で2倍もらえる手当・もらえない手当の整理
双子で2倍もらえる手当・もらえない手当を整理して解説します。
紹介する制度は以下のとおりです。
- 出産育児一時金は2人分がもらえる
- 育児休業給付金は1人分と同額がもらえる
- 出産手当金は1人分と同額が原則
- 児童手当は2人分がもらえる
それぞれの支給ルールを知ることで、期待と実際のギャップを減らし、計画的に育児資金を準備しやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
出産育児一時金は2人分がもらえる
出産育児一時金は、1人あたり50万円(※)が支給されるため、双子の場合は合計100万円が受け取れます。
対象となるのは、産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合です。
また、双子の出産は管理入院や帝王切開になるケースが多く、医師の指示があれば医療保険の適用も可能です。
医療費の自己負担は3割となるため、高額な出産費用でも実質的な支出は抑えられるケースがあります。
さらに、医療機関への直接支払制度を使えば、退院時にまとまった費用を立て替えずに済みます。
直接支払制度とは、出産育児一時金が医療機関に直接支給される仕組みです。
育児休業給付金は1人分と同額がもらえる
育児休業給付金は、子どもが双子でも金額は1人分と同額です。
支給額は、先述のとおり育休開始から6ヵ月間は賃金の67%、その後は50%(※)です。
この仕組みは、出産育児一時金のように、子ども1人あたりに支給される手当とは考え方が異なります。
育児休業給付金は、育児に専念できるように親の所得減を補う目的で設計されているからです。
そのため「双子だから2倍もらえるはず」と期待すると、実際の支給額とのギャップに戸惑うかもしれません。
支給条件や仕組みを正しく理解しておくことが、育休中の家計管理をスムーズに進める第一歩になります。
出産手当金は1人分と同額が原則
出産手当金は、子どもが双子でも金額は1人分と同額です。
この手当は、出産のために仕事を休み、給与が支給されない期間に、健康保険から支給されます。
支給額は、先述のとおり直近の給与の2/3相当額が目安(※)です。
ただし、勤務先の健康保険組合によっては、出産手当金に独自の上乗せ制度(付加給付)を設けている場合があります。
こうした制度の有無や内容は健康保険組合によって異なるため、詳細は勤務先または加入している健康保険組合に確認しておくと安心です。
児童手当は2人分がもらえる
児童手当は、2人分支給されます。
子ども1人あたりに支給される制度のため、双子の場合は自動的に支給額も2倍になります。
例えば、3歳未満なら1人月額1万5000円(※)が支給され、双子なら合計で月3万円となります。
申請は、養育者本人が住民票のある市区町村に"認定請求書"を提出する必要があります。
児童手当は申請月の翌月分から支給されるため、申請が遅れると1ヵ月分を受け取れない可能性もあります。
スムーズに受け取るためにも、出産前から準備を進めておくと安心です。
双子育児で使える公的支援制度と保育園の実情
双子育児で使える公的支援制度と保育園の実情を3つ解説します。
紹介する内容は以下のとおりです。
- 自治体の双子家庭への支援
- 国のベビーシッター補助制度
- 注意:保育園は基本的に優遇されない
各制度の特徴を知ることで、育児の負担を少しでも軽くするヒントが見つかりやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
自治体の双子家庭への支援
自治体の双子家庭への支援は、地域ごとに内容が異なるため、住んでいる場所の制度をあらかじめ確認しておくことが大切です。
事前に知っておけば、育児の手が足りない場面でも頼れる選択肢を確保しやすくなるからです。
例えば、東京都荒川区ではツインズサポート事業により、家事や育児を助けるヘルパーを派遣しています。
また、埼玉県では“3キュー子育てチケット”として、多子世帯向けに子育て関連サービスで使えるクーポンを配布しています。
こうした地域独自の支援を上手に活用することで、夫婦で協力しながら無理のない双子育児に取り組みやすくなります。
国のベビーシッター補助制度
国のベビーシッター補助制度は、正式には"企業主導型ベビーシッター利用者支援事業"という名称です。
勤務先の企業がこの制度に登録している場合、提携するベビーシッター利用が、子ども1人につき1回あたり最大4,400円(2,200円×2枚)割引になります。
双子など多胎児家庭は助成限度額9,000円(※)となり、より手厚い支援が受けられます。
対象となるのは、この制度に登録している企業に勤める保護者です。
勤務先から交付を受けることで、この割引券を利用できます。
会社が制度に参加しているかどうかは、人事部や総務部に確認しておくと安心です。
注意:保育園は基本的に優遇されない
保育園は、基本的に双子だからといって入園優先などの特別な優遇があるわけではありません。
というのも、入園選考のルールは自治体ごとに異なり、全国共通の加点基準などがあるわけではないからです。
そのため、双子でも必ず同じ園に入れるとは限らず、別々の園に分かれるケースも実際にあります。
また、双子の受け入れ経験が少ない園では、同時授乳や体調不良時の引き取りなどに保育士が対応しきれない場面も考えられます。
あらかじめ希望園の情報を集め、必要に応じて見学や相談をしておくことで、保育園選びの不安を軽減しやすくなります。
双子の育休中にやっておくべき出費対策
双子の育休中にやっておくべき出費対策を2つ解説します。
紹介する方法は以下のとおりです。
- 今後の家計をシミュレーションする
- 急な出費に備える
先を見越した準備をしておくことで、今後の家計の不安を減らしやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
今後の家計をシミュレーションする
今後の家計をシミュレーションしておくことで、出費対策が進めやすくなります。
収入が減る時期に、どのくらい使ってよいかの目安があると、支出にメリハリをつけやすくなるからです。
まずは、毎月の固定費・変動費・育児関連費をざっくりでも書き出してみましょう。
そのうえで、育休後の働き方や保育料の見通しを踏まえて、1年間のお金の流れをおおまかに組み立ててみるのが効果的です。
先を見通しておくことで、"今の時期だけ必要な出費"にも納得感をもって使いやすくなります。
急な出費に備える
急な出費に備えることで、出費対策を強化しやすくなります
育休中は収入が限られるため、突然の医療費や家電の故障が起こると家計に大きな打撃となるからです。
例えば“緊急用の生活口座”を分けておくだけでも、予想外の支出に落ち着いて対応できる安心材料になります。
金額の目安は、生活費の1ヵ月分を、できる範囲で確保しておくのがおすすめです。
普段使いの口座とは別に、ネット銀行や普通預金口座に分けておくと、誤って使ってしまうリスクも減らせます。
備えがあるという意識そのものが、育休中の不安を軽くしてくれる効果もあります。
双子の育休手当に関するよくある質問
双子の育休手当に関するよくある質問を、2つ解説します。
紹介する質問は以下のとおりです。
- 夫も育休を取るべきですか?おすすめの分担方法は?
- 双子を産んだ場合、毎月の手当はいくら支給されますか?
よくある疑問を押さえておくことで、悩んだときのヒントになるはずなので、ぜひ参考にしてください。
夫も育休を取るべきですか?おすすめの分担方法は?
夫も育休を取ることで、双子育児を無理なく分担できる体制が整いやすくなります。
というのも、双子育児では夜泣きや授乳・抱っこなどが重なる場面が多く、物理的に1人では回らないことも多いためです。
分担方法としては、先輩パパ・ママからは、交代制よりも“並走型”の分担がスムーズだったという声もあります。
例えば、片方が授乳中に、もう片方が寝かしつけや哺乳瓶の準備を担うなど、同時並行で役割をこなす形です。
家庭ごとにやり方はさまざまですが、ふたりで一緒に育児に向き合う時間が、今後の子育てや家族の絆にもつながっていくでしょう。
双子を産んだ場合、毎月の手当はいくら支給されますか?
双子を産んだ場合の毎月の手当は、児童手当と育児休業給付金の2つが基本です。
児童手当は子ども単位で支給されるため、3歳未満なら月額1万5,000円×2人=月3万円が支給されます。
一方で、育児休業給付金は親に対して支給される制度のため、双子であっても育休を取る親が1人なら、受け取れるのは1人分のみです。
金額の目安は、育休開始から6ヵ月間は賃金の67%、その後は50%となっています。
このように、手当ごとに“誰が対象か”や“支給の仕組み”が異なる点を理解しておくと、家計の見通しを立てるうえで役立ちます。
双子の子育てについて金銭的不安がある方におすすめのサービス
双子の育児は、日々の生活費から教育資金まで、支出が1人育児の約2倍にふくらむこともあります。
さらに育休中の収入減が重なることで、「この先の生活が心配」と不安を感じる方も少なくありません。
特に、突然の医療費や予期せぬ出費に備える貯蓄と、将来の教育費に備える資産形成の両立は、多くの家庭にとって悩みの種です。
とはいえ、すべてを自分たちだけで調べて計画を立てるのは大変です。制度ごとの違いや申請のタイミング、家計設計の見直しには、一定の知識と時間が求められます。
そんなときに心強いのが、お金の専門家であるFP(ファイナンシャルプランナー)への無料相談サービスです。
中でも「マネーキャリア」では、FPに何度でも無料で相談できるため、児童手当や出産手当金の申請タイミングに加え、教育費や生活費の見通しをふまえた現実的な資金計画まで、家計の不安を納得いくまで解消できますよ。

▼マネーキャリアの概要
- お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、年収や節税について知見の豊富な、ファイナンシャルプランナーのプロのみを厳選。
- 資産形成や総合的なライフプランの相談から最適な解決策を提案可能。
- マネーキャリアは「丸紅グループである株式会社Wizleap」が運営しており、満足度98.6%、相談実績も100,000件以上を誇る。

双子の育休手当は2倍もらえる?損しないためのポイントまとめ
双子を出産した場合でも、育休手当や出産手当金は「2人分もらえる」わけではない点に注意が必要です。
これらは親の収入減を補う制度のため、支給額は基本的に1人分と同等です。
一方で、「出産育児一時金」や「児童手当」は子ども1人あたり支給されるため、双子なら自動的に2人分を受け取れます。
制度ごとに支給対象や条件、申請先が異なるため、正確な理解と早めの準備が損を防ぐカギとなります。
こうした制度の整理や手当の受け取り計画に失敗して損をしないためにも、FPが何度でも無料で手続きや計画立てをサポートしてくれる「マネーキャリア」のようなサービスを利用する方が増えています。