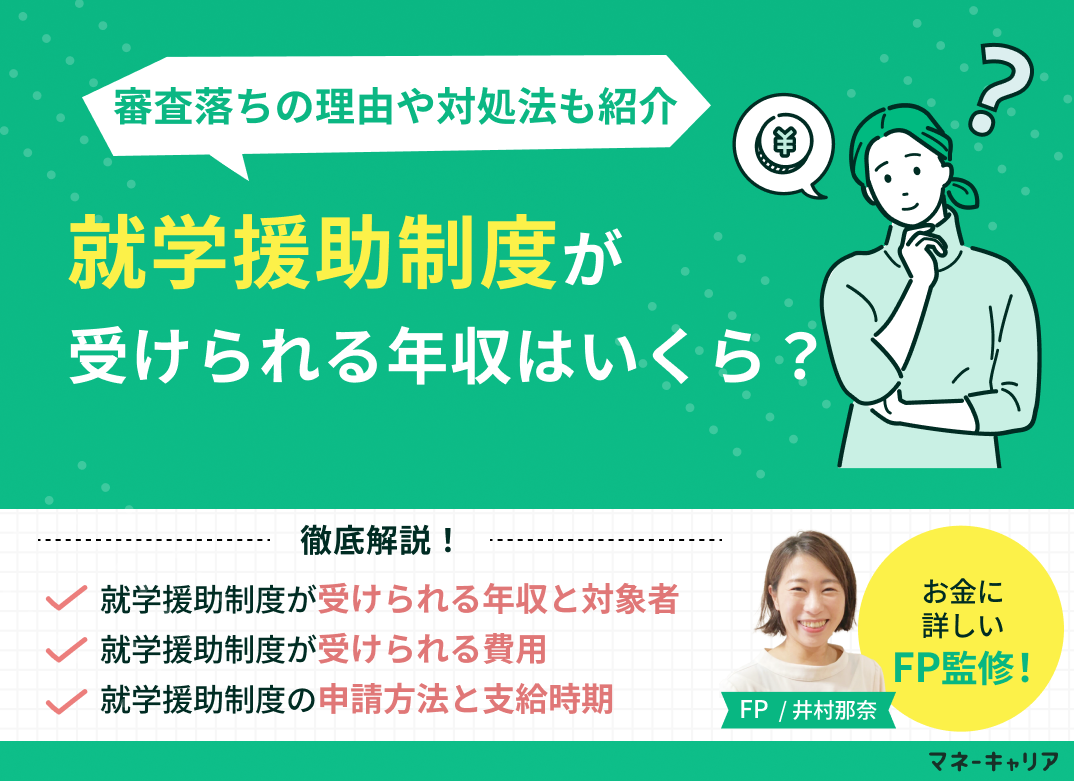
「うちの年収で、就学援助って受けられるのかな?」
「生活は厳しいけど、申請しても落ちたらどうしよう…」
そんな不安や疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。
この記事では、就学援助制度の対象となる年収や条件・受けられる支援の内容・申請方法・審査に落ちた場合の対処法まで詳しく解説します。
・「子どもの学用品や給食費が家計を圧迫している」
・「教育費の不安を少しでも軽くしたい」
そんな方は、本記事を読むことで就学援助制度の仕組みがわかり、今すぐできる対策が見つかるかもしれません。
内容をまとめると
- 就学援助制度の対象者は世帯年収や生活状況により決まる
- 給食費や学用品費などが支給される支援制度
- 申請には収入証明や必要書類の準備が必要
- 審査に落ちても不服申し立てや他制度の検討が可能
- マネーキャリアでは教育費や家計に関する無料相談ができる

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
続きを見る
閉じる
この記事の目次
- 就学援助制度が受けられる年収と対象者
- 就学援助制度が受けられる費用
- 就学援助制度の申請方法と支給時期
- 就学援助制度の審査に落ちる原因
- 収入の基準を超えている
- 所得の申告に不備がある
- 書類に不備がある
- 資産があると判断されている
- 就学援助制度が受けられなかったときの対処法
- 審査結果に不服の申し立てを行う
- ほかの支援制度を探す
- 家計を見直す
- 就学援助制度が受けられる年収に関するよくある質問
- 世帯の人数によって年収基準は変わる?
- 昨年の年収が基準以下でも、今年の年収が上がったら対象外?
- 失業保険や児童手当なども年収に含まれる?
- 子どもの教育費に不安がある方はお金のプロ「マネーキャリア」に相談
続きを見る
就学援助制度が受けられる年収と対象者
結論、就学支援制度が受けられる世帯年収は、おおよそ350万円~450万円以下がひとつの基準です。(参考:文部科学省)
ただし、自治体によって基準が異なるため、あくまで目安と捉えてください。
たとえば、中野区では3人世帯で年収約350万円・4人世帯で約431万円が基準である一方、札幌市では4人世帯で収入343万~369万円が基準です。
さらに、支給対象は以下の項目に当てはまる方です。
- 各市区町村に住民票があり、小・中学校に在籍している児童・生徒の保護者
- 生活保護を受けている世帯(教育扶助)
- 生活保護は受けていないが、経済的に困窮しており、各市区町村が定める所得基準以下である世帯
就学援助制度が受けられる費用
就学援助制度が受けられる費用は、日常的にかかる学校関連の出費が幅広く含まれます。
たとえば、学用品費・通学用品費給食費に加えて、修学旅行や校外活動費なども支援の対象です。
特に新入学時には「新入学児童生徒学用品費等」として、まとまった援助が受けられることもあります。
就学援助制度の申請方法と支給時期
スムーズに支援を受けるために、就学援助制度の申請方法と支給時期を正しく把握しておきましょう。
申請には、自治体または学校から申請書を入手し、世帯の所得を証明する書類や住民票などの必要書類を提出する場合があります。
申請先は学校または市区町村の教育委員会が基本で、オンラインでのダウンロードが可能な自治体も増えています。
就学援助制度の審査に落ちる原因
就学援助制度の申請が通らない背景には、以下のような理由があります。
- 収入の基準を超えている
- 所得の申告に不備がある
- 書類に不備がある
まずは審査基準を知り、自分の状況に当てはまるかどうかを確認していきましょう。
収入の基準を超えている
就学援助制度を利用するには、世帯の年収が一定の基準を下回っていることが条件です。
地域によって異なりますが、生活保護基準の1.1〜1.3倍を目安に審査されるのが一般的です。
基準をわずかに上回るだけでも、審査の結果、対象外となる場合があります。
所得の申告に不備がある
所得申告にミスや未提出の書類があると、審査の過程で正確な判定ができず、審査に落ちることがあります。
たとえば、確定申告をしていない、住民税の申告を怠っているなどが典型例です。
書類に不備がある
申請書類に記入漏れや添付書類の不足があると、審査に進めません。
住民票の続柄や世帯主の記載漏れ・印鑑の押し忘れ・必要な証明書の提出忘れなどがよくある不備です。
資産があると判断されている
就学援助制度では、年収だけでなく資産状況も審査対象になります。
たとえば、預貯金が多かったり、不動産を所有していたりすると、「援助が必要な世帯」とは見なされにくいでしょう。
就学援助制度が受けられなかったときの対処法
審査に落ちたとしても、子どもの教育に必要な支援を諦める必要はありません。
以下の方法を試してみましょう。
- 審査結果に不服の申し立てを行う
- ほかの支援制度を探す
- 家計を見直す
それぞれの方法を詳しく解説していきます。
審査結果に不服の申し立てを行う
就学援助の審査結果に納得がいかない場合は、不服申立てが可能です。
具体的には、自治体の教育委員会に対して理由書を提出し、再審査を求めるという流れです。
申立てには期限があるため、結果通知を受け取ったら早めに行動しましょう。
ほかの支援制度を探す
就学援助が受けられなくても、自治体やNPO・学校独自の支援制度が用意されていることがあります。
制服や給食費の補助・学用品の支援・修学旅行の費用を助成する制度などを活用しましょう。
また、児童扶養手当や母子父子寡婦福祉資金貸付金など、家庭全体の支援につながる制度も利用できます。
家計を見直す
制度に頼るだけでなく、家計のなかで無理のない範囲でやりくりできるか見直すことも欠かせません。
まずは毎月の支出を書き出し、固定費や変動費のバランスをチェックしましょう。
特にスマホ代やサブスク、保険料の見直しは効果が出やすいポイントです。
就学援助制度が受けられる年収に関するよくある質問
就学援助制度に申し込む際の、特によくある3つの疑問にお答えします。
- 世帯の人数によって年収基準は変わる?
- 昨年の年収が基準以下でも、今年の年収が上がったら対象外?
- 失業保険や児童手当なども年収に含まれる?
それぞれの回答を見ていきましょう。
世帯の人数によって年収基準は変わる?
世帯人数によって、年収の基準は異なります。
たとえば、子どもが1人の場合と3人いる場合とでは、生活にかかる費用が大きく変わるため、自治体は世帯人数を考慮して年収基準を調整しています。
昨年の年収が基準以下でも、今年の年収が上がったら対象外?
基本的には「昨年の所得」が基準ですが、状況によって柔軟に対応されることもあります。
たとえば、今年になってから就職や転職で収入が増えた場合、その情報を提出するよう求められるケースがあるでしょう。
失業保険や児童手当なども年収に含まれる?
児童手当や失業保険などの一時的な給付金は、基準の年収に含まれないケースもあります。
「収入」と「所得」が別に扱われる自治体もあるからです。
子どもの教育費に不安がある方はお金のプロ「マネーキャリア」に相談
就学援助制度の対象となる年収の目安や支給内容・申請方法・審査に落ちる原因や対処法を解説しました。
制度の利用には年収や世帯構成による条件があるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。
これから支援制度の活用を検討したい方は、まずは自分の世帯の収入状況や条件を整理することから始めてみましょう。
とはいえ、「制度の対象になるのかわからない」「落ちたらどうすればいいの?」と不安に感じている方も少なくないはずです。
そんなときは、「マネーキャリア」の無料相談を活用してみてください。
就学援助制度だけでなく、教育費の準備や他の支援制度の活用法・家計の見直しなどについて、何度でも無料で相談可能です。
スマホから簡単に申し込めて、女性FPも多数在籍しているため、相談しやすい環境が整っています。
専門家のサポートを受けることで、将来に向けて安心できるアドバイスをもらいましょう。




























