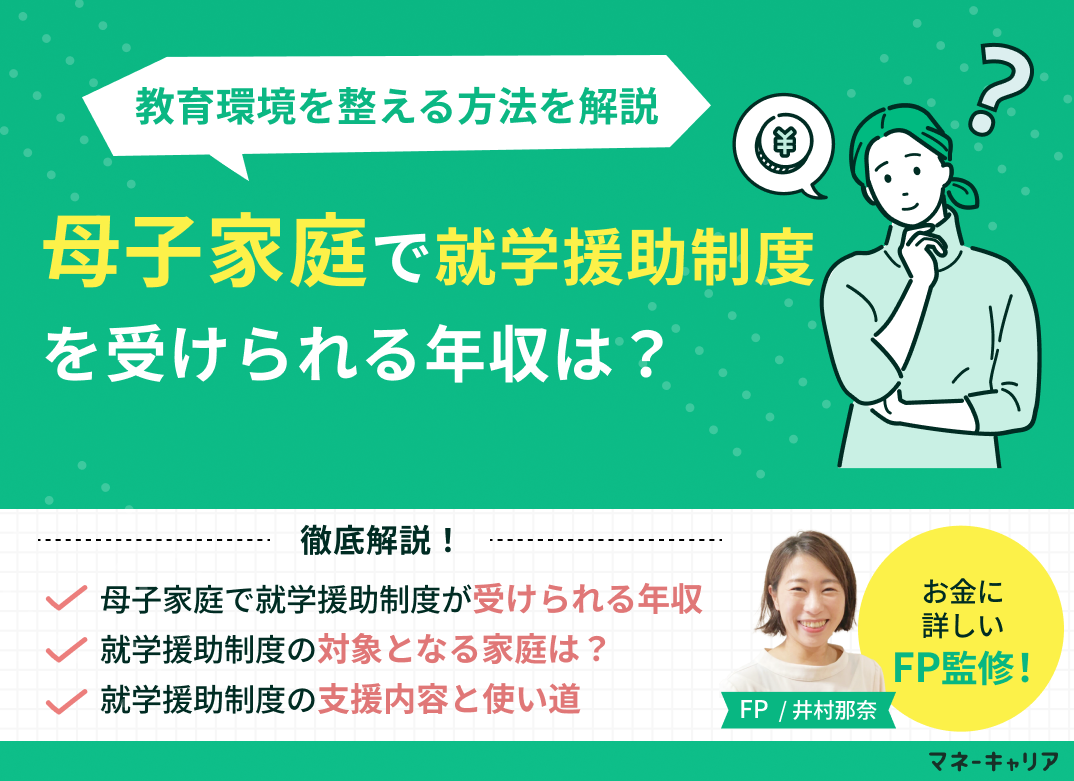
内容をまとめると
- 母子家庭でも就学援助は年収に応じて利用可能
- 学用品費や給食費などの支援が受けられる
- 就学援助以外にも複数の支援制度を併用可能
- 教育費の不安は計画・支援・相談で軽減できる
- マネーキャリアでは教育費や家計相談を無料で受けられる

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 母子家庭で就学援助制度が受けられる年収の目安
- 就学援助制度の対象となる家庭は?
- 就学援助制度で受けられる支援内容と使い道
- 就学援助制度の申請方法と必要書類
- 母子家庭が使える就学援助以外の支援制度一覧
- 児童扶養手当
- ひとり親家庭等医療費助成制度
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金
- 住宅に関する支援
- 国民健康保険料の軽減・減免
- ひとり親控除
- 児童育成手当
- 母子家庭でも子どもの教育環境を整えるための4つの工夫
- 家計を把握し子どもの教育プランを立てる
- 収入を安定させ増やすための行動をする
- 計画的に貯める仕組みを作る
- お金の専門家に相談する
- 母子家庭で就学援助制度を受けられる年収のよくある質問
- 養育費は年収に含まれるの?
- 同居の家族の収入も審査対象になる?
- 児童扶養手当をもらっていれば就学援助も受けられる?
- 母子家庭で子どもの教育費にお悩みなら「マネーキャリア」に相談
母子家庭で就学援助制度が受けられる年収の目安
- 母と子ども1人:年収200万円~280万円以下
- 母と子ども2人:年収250万円~350万円以下
- 母と子ども3人:年収300万円~400万円以下
就学援助制度の対象となる家庭は?
- 生活保護を受けている世帯
- 生活保護の停止・廃止が当年度または前年度にあった世帯
- 児童扶養手当を受給しているひとり親世帯(※児童手当や育成手当は対象外)
- 所得が市区町村の定める基準を下回る世帯
就学援助制度で受けられる支援内容と使い道
- 学用品費:教科書以外のノートや筆記用具の購入費
- 体育実技用具費:体操服や体育用シューズの費用
- 新入学児童生徒学用品費等:入学時にかかる特別費用
- 通学用品費・通学費:ランドセルや定期券などの通学手段に関する費用
- 修学旅行費・校外活動費:学校主催の課外活動にかかる費用
- 医療費:学校内でのけがや病気に対する医療費の自己負担分
- 学校給食費:給食の費用(全額または一部)
- クラブ活動費・生徒会費・PTA会費・卒業アルバム代:学校生活に付随する費用
- オンライン学習通信費:一部自治体ではWi-Fiや端末利用料なども対象
就学援助制度の申請方法と必要書類
- 申請書の入手方法:教育委員会または学校から入手。市区町村によってはWebからのダウンロードも可能
- 必要書類:世帯全員分の所得証明(源泉徴収票、確定申告書控えなど)・住民票やマイナンバーに関する書類など
- 申請書の提出先:子どもが通う学校または市区町村の教育委員会
- 支給時期:自治体によって異なるものの、年度初めや学期ごとに振込されることが多い
母子家庭が使える就学援助以外の支援制度一覧
就学援助制度の審査に通らなかった場合でも、母子家庭にはさまざまな支援制度が用意されています。
以下で代表的な制度を紹介します。
- 児童扶養手当
- ひとり親家庭等医療費助成制度
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金
- 住宅に関する支援
- 国民健康保険料の軽減・減免
- ひとり親控除
- 児童育成手当
児童扶養手当
ひとり親家庭等医療費助成制度
母子父子寡婦福祉資金貸付金
住宅に関する支援
国民健康保険料の軽減・減免
ひとり親控除
児童育成手当
母子家庭でも子どもの教育環境を整えるための4つの工夫
母子家庭でも子どもの教育環境を整えるためには、日々の工夫と準備が欠かせません。
限られた収入のなかでも、将来の進学や学びの選択肢を広げることは十分可能です。
そこでここでは、以下の4つの視点から、教育環境を充実させるための具体策をご紹介します。
- 家計を把握し子どもの教育プランを立てる
- 収入を安定させ増やすための行動をする
- 計画的に貯める仕組みを作る
- お金の専門家に相談する
順番に詳しく解説していきますので、ご自身の状況に照らし合わせて活用してください。
家計を把握し子どもの教育プランを立てる
家計を正確に把握し、子どもの教育プランを立てることが教育費に対する不安を減らす第一歩です。
なぜなら、収支が見えていない状態では、必要な貯蓄目標や支出の優先順位が判断しにくくなるからです。
たとえば「大学まで進学させたい」といった将来の教育方針に応じて、どのタイミングでいくら必要かを具体的に試算しておくことで、焦りのない準備ができます。
収入を安定させ増やすための行動をする
収入を安定させ、将来的に増やすための行動を起こすことは、母子家庭にとって非常に重要です。
というのも、教育資金の準備には長期的かつ持続的な収入が必要だからです。
たとえば、資格取得や転職・副業の開始など、スキルアップを図ることで将来の収入源を広げられるでしょう。
計画的に貯める仕組みを作る
教育資金を確保するためには、計画的に貯める仕組みを作りましょう。
思い立ったときだけの貯金では、安定して必要額を積み上げるのは難しいからです。
具体的には、児童手当に手をつけずに貯める、毎月の給与から自動積立をするなど、強制的にお金が貯まる流れを整えておく方法があります。
お金の専門家に相談する
お金の専門家に相談することで、教育費に関する不安を解消しやすくなります。
自分だけでは見落としがちな支援制度や、最適な貯め方を客観的に教えてもらえるからです。
母子家庭で就学援助制度を受けられる年収のよくある質問
就学援助制度の年収基準に関する、よくある疑問について整理しました。
- 養育費は年収に含まれるの?
- 同居の家族の収入も審査対象になる?
- 児童扶養手当をもらっていれば就学援助も受けられる?
就学援助制度の審査で不利にならないためにも、一つずつ回答を確認していきましょう。
養育費は年収に含まれるの?
養育費の取り扱いは、就学援助制度の収入基準に含まれるかどうか、自治体によって判断が分かれることがあります。詳細は、お住まいの自治体の窓口にご確認ください。
自治体によっては、養育費も「定期的な収入」として審査の対象になります。
ただし、実際の判断は自治体によって異なり、申告が必要な場合と、非課税で扱われる場合があります。
同居の家族の収入も審査対象になる?
同居している家族の収入も、原則として就学援助の審査対象になります。
「世帯全体の経済状況」を基に援助の必要性が判断されるためです。
たとえば、祖父母や兄弟と同居しており、その家族に一定の収入がある場合は、申請者自身が低所得でも支援対象外となる可能性があります。
児童扶養手当をもらっていれば就学援助も受けられる?
児童扶養手当を受給していても、必ずしも就学援助制度が受けられるとは限りません。
両者は別々の制度であり、それぞれに独立した審査基準があるからです。
児童扶養手当の対象でも、住んでいる自治体の収入基準を超えている場合は、就学援助が受けられないことがあります。
母子家庭で子どもの教育費にお悩みなら「マネーキャリア」に相談
母子家庭で利用できる就学援助制度の年収基準や支援内容・申請方法に加えて、その他の支援制度や教育費を確保するための工夫も紹介しました。
子どもの教育環境を整えるには、まずは家計を把握し、どの支援が受けられるかを確認することが大切です。
とはいえ、「自分の収入で本当に支援が受けられるのか不安」「どの制度をどう活用すればいいのかわからない」と悩む方も多いでしょう。
そんなときは、「マネーキャリア」の無料相談を活用してみてください。
教育費の準備や支援制度の活用法・家計の見直しなど、お金の不安をプロと一緒に整理できます。
「教育費が心配」「どこから手をつけたらいいかわからない」という方は、一度マネーキャリアに相談してみましょう。




























