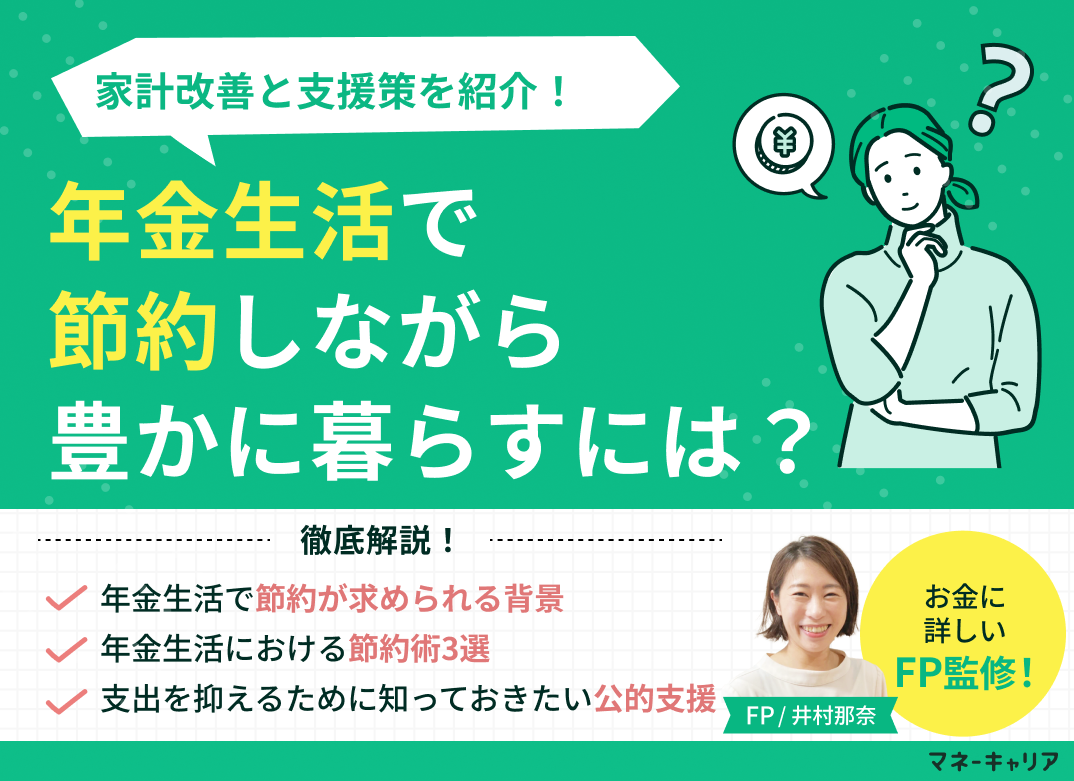
▼この記事を読んでわかること
「少しでも節約して安心して老後を過ごしたい」
そんな思いを抱えている方は少なくありません。年金生活では、無理な節約ではなく、ムダを減らしつつ、生活の質を落とさない工夫が大切です。
本記事では、年金生活を無理なく豊かにするための節約術や家計の見直しポイント、さらに公的な支援制度の活用方法まで、分かりやすくご紹介します。
本記事を読むことで年金生活の無理のない節約術が分かり、今後安心して暮らすためのヒントになります。
内容をまとめると
- 年金生活で節約が求められる背景には、支出増加と年金支給額の減少、単身高齢世帯の増加と家計の実情などがあります。
- 年金生活における節約術では、支出の見える化をしたり、固定費の見直しで毎月の支出を軽減するがおすすめです。
- ただし、家計の無駄を一人で判断するのは難しいため、プロに相談することで客観的な目線からアドバイスをもらえます。
- 特に、マネーキャリアのような無料相談窓口なら年金生活に合わせた支出の見直しや、今後のライフプランに応じた節約方法を中立的な立場で提案してもらえます。

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
続きを見る
閉じる
この記事の目次
- 年金生活で節約が求められる背景
- 年金生活における節約術3選
- 支出の見える化でムダを防ぐ
- 固定費の見直しで毎月の支出を軽減
- ストレスの少ない節約習慣を取り入れる
- 年金生活での食費・日用品費の節約アイデア
- 買い物ルールを決めてムダを防ぐ
- 節約に役立つ調理・保存テクニックを活用
- 支出を抑えるために知っておきたい公的支援
- 医療費の節約につながる制度
- 税負担を軽くする控除制度
- 住まい関連の支援と割引制度
- 年金生活の節約でよくある質問
- 節約しすぎずバランスよく生活するには?
- 国民年金だけで生きていける?
- 年金生活で夫婦2人で生活するにはいくら必要?
- 年金生活での節約に関する悩みを解決するには?
- 年金生活での節約に関する悩みまとめ
続きを見る
年金生活で節約が求められる背景
年金だけでは生活が厳しいと感じる高齢者が増えている背景には、物価上昇による支出の増加と、年金支給額の実質的な減少があります。
たとえば、光熱費や食料品など生活必需品の価格が上がっている一方で、年金の増加はわずかにとどまり、可処分所得が減っているのが実情です。
総務省統計局の「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要」によると、65歳以上の単身無職世帯の毎月の実収入は約13万1,116円, そのうち社会保障給付(主に年金)は約12万1,629円にとどまります。
一方で、毎月の支出は約16万1,933円にのぼり、約2万8,000円の赤字となっています。
このように、年金だけでは毎月の生活費がまかなえない高齢単身世帯が少なくないという現実が最新統計でも明らかになっています。
夫婦世帯であれば分担できる支出も、一人暮らしではすべて自己負担になるため、家計が圧迫されやすくなります。
また、長寿化が進む今の時代では、老後資金をより長く持たせる工夫も不可欠です。
医療費や介護費用といった将来の支出に備えるためにも、今のうちから支出を見直し、無駄を省く努力が必要とされているのです。
こうした社会背景をふまえると、年金生活でも節約しながら豊かに暮らすための知恵と工夫が、ますます重要になってきています。
年金生活における節約術3選
年金だけで生活する中では、毎月の限られた収入でやりくりしていく必要があります。
無理な我慢を重ねるのではなく、ストレスを減らしながら節約できる工夫を取り入れていくことが大切です。
ここでは、年金生活における代表的な節約術を3つご紹介します。
- 支出の見える化でムダを防ぐ
- 固定費の見直しで毎月の支出を軽減
- ストレスの少ない節約習慣を取り入れる
支出の見える化でムダを防ぐ
限られた年金での生活を成り立たせるためには、まず現状の支出を「見える化」することが欠かせません。
多くの人が、何にどれだけ使っているのかを正確に把握できていないまま、なんとなくお金が減っていると感じているものです。
日々の出費を家計簿やアプリで記録することで、どこにムダが潜んでいるのかを明らかにできます。
たとえば、毎日のコンビニ通いや使っていないサブスクサービスの料金など、少額でも積み重なれば家計を圧迫します。
見える化することで、優先順位の低い支出を自然とカットしやすくなり、効率的な節約につながります。s
まずは「何に、いくら使っているか」を大まかに把握することから始めてみるべきです。
固定費の見直しで毎月の支出を軽減
年金生活において、支出を節約する上で最も効果が大きいのが「固定費の見直し」です。
固定費とは、毎月必ず発生する家賃・光熱費・通信費・保険料などの支出のことです。
変動費と違って一度設定すれば継続的に節約効果が見込めるため、早めに見直しておきたい項目です。
たとえばスマホは、大手キャリアから格安SIMに乗り換えるだけで、月額数千円の節約につながることもあります。
保険についても、年齢や家族構成の変化に合わない内容のまま継続しているケースが多く、保障内容を整理すれば適切な保険料に抑えられる可能性があります。
また、ケーブルテレビや定期購読のように使っていないサービスがあれば、これを機に一度棚卸ししてみましょう。
ストレスの少ない節約習慣を取り入れる
節約は一時的なものでなく、長く続けてこそ意味があります。
しかし、無理な節約は生活の質を下げ、かえってストレスを生む原因にもなりかねません。
年金生活では、続けやすく負担の少ない「ストレスフリーな節約習慣」を意識することが大切です。
たとえば、毎日の買い物をスーパーの特売日やポイント還元日などに合わせたり、まとめ買いをして余計な外出や無駄遣いを減らしたりするのも効果的です。
さらに、調理の手間や光熱費を抑えるために「作り置き」を活用すれば、忙しさや疲労感の軽減にもつながります。
自分に合った無理のない習慣を取り入れ、生活を快適に保ちながら賢く節約していきましょう。
年金生活での食費・日用品費の節約アイデア
年金収入での生活では、食費や日用品費のような「毎日かかる支出」をいかに抑えるかが大切です。
しかし、ただ我慢する節約ではストレスが溜まり、継続しづらいのも現実です。
そこで今回は、無理をせずに続けられる「ルール化」や「工夫」で、支出を上手にコントロールする方法を紹介します。
特に高齢期には体調や健康にも配慮が必要なため、「安ければいい」という発想ではなく、質を保ちながらも無駄を減らす視点を重視しています。
- 買い物ルールを決めてムダを防ぐ
- 節約に役立つ調理・保存テクニックを活用
買い物ルールを決めてムダを防ぐ
節約の第一歩は、「なんとなく買う」をやめることです。
年金生活では、収入が一定な分、支出のコントロールが家計の安定に直結します。そこで効果的なのが、自分なりの「買い物ルール」を設けることです。
また、買い物リストをあらかじめ作っておくのも有効です。
ポイントは「使い切る日を想定した量」にすることです。
冷蔵庫に何が残っているかをスマホで撮影しておく、前回買った商品の賞味期限をメモしておくなど、買いすぎ・重複購入の防止にもなります。
加えて、日用品については「定期便」や「共同購入」を活用するのもおすすめです。
Amazonや生協の定期購入サービスを使えば割引が効く場合が多く、買い忘れや都度の交通費も抑えられます。
さらに友人や近所の方とまとめて買ってシェアする「共同購入」は、割引価格で手に入れつつ交流のきっかけにもなります。
「節約=我慢」ではなく、「ルール=自分を守るツール」として活用することで、ストレスなく継続できる節約につながります。
節約に役立つ調理・保存テクニックを活用
調理や保存の工夫を取り入れることで、食材のムダを減らし、結果的に食費の節約につながります。
しかも、やり方によっては時間の節約や栄養バランスの向上にもつながるため、年金生活の生活満足度も高まります。
まずおすすめしたいのが、「食材を捨てない保存術」です。
たとえば、大根やにんじんの皮はきんぴらや味噌汁の具材に再利用できますし、野菜のヘタもコンソメスープにすれば栄養も無駄なく摂取できます。
野菜を冷凍保存する場合も、カットしてから生のまま保存するよりも、一度湯通ししてから冷凍した方が味の劣化を防げます。また、「冷凍・冷蔵保存の使い分け」も節約には重要です。
冷蔵庫の中で忘れられがちな食品(豆腐や納豆、練り物など)は「冷蔵期限管理リスト」を冷蔵庫の扉に貼っておくと、買いすぎや食材ロスを防げます。
最後にもうひとつ、見落としがちなのが「省エネ調理」です。
例えば、保温調理鍋を活用すれば、煮込み料理もガス代を抑えながら調理可能ですし、電子レンジを活用した下ごしらえも時短と光熱費節約の両面でおすすめです。
支出を抑えるために知っておきたい公的支援
年金生活では、限られた収入で日々の生活を成り立たせなければなりません。
とはいえ、我慢ばかりの節約では気持ちが続きにくく、生活の質も下がりがちです。
そんなときに頼りになるのが「公的サポート制度」です。
ここでは、知っておくと家計の支出を大きく抑えられる制度を3つの分野に分けて解説します。
- 医療費の節約につながる制度
- 税負担を軽くする控除制度
- 住まい関連の支援と割引制度
医療費の節約につながる制度
高齢になるほど、医療費の負担は家計にとって深刻な問題となります。実際、年金生活の中でも医療費は大きな支出割合を占める項目のひとつです。
そこで活用したいのが、「高額療養費制度」と「医療費控除」です。まず、高額療養費制度とは、1ヶ月あたりの医療費が一定額を超えた場合、その超過分が払い戻される制度です。
たとえば70歳以上の方で年金生活をしている人(住民税非課税世帯など)は、自己負担上限が月8,000円程度になるケースもあります。
窓口での支払いが厳しい場合は、「限度額適用認定証」を事前に取得しておくことで、支払いを上限内に抑えることも可能です。
また、医療費控除は年間の医療費が10万円(または総所得の5%)を超えた場合に、確定申告をすることで所得控除を受けられます。
通院時の交通費や市販薬代も条件を満たせば対象になるため、領収書の保管を習慣づけておくべきです。
さらに、自治体によっては高齢者向けに「インフルエンザ予防接種」「がん検診」などの費用補助を実施している場合もあります。
節約しながら健康を守るためにも、お住まいの自治体の福祉課などに問い合わせてみるとよいでしょう。
参照:厚生労働省
税負担を軽くする控除制度
年金生活でも、住民税や所得税などの負担は避けられません。
しかし、「知らないことで損をしている」人が多いのも税金の分野です。そのため、節約につながる代表的な控除制度を押さえておきくべきです。
まず、「公的年金等控除」は、年金を受け取っている人全員に適用される基本控除です。
例えば、65歳以上の人で年金収入が年400万円以下であれば、課税所得がゼロになるケースも少なくありません。
所得税や住民税の申告が不要な人もいますが、「還付申告」を行うことで納めすぎた税金が戻ってくる場合もあります。
さらに、「障害者控除」や「寡婦・寡夫控除」「扶養控除」なども適用条件を満たせば利用可能です。
たとえば、配偶者と死別して一定の条件を満たした場合には、住民税が非課税になるケースもあるため、自身が該当するかを毎年確認する習慣をつけておくことをおすすめします。
また、ふるさと納税も、うまく活用すれば実質2,000円の負担で食料品や日用品を受け取れるお得な制度です。
年金受給者でも課税所得があれば対象になるので、簡単な「控除上限額シミュレーション」などで自分の限度額を確認してみるとよいでしょう。
参照:国税庁
住まい関連の支援と割引制度
「持ち家でも賃貸でも、住まいに関する出費は大きい」というのは、年金生活者共通の悩みです。
しかし、住宅関連の支援制度を知っておくことで、出費を大きく減らすことが可能になります。
まず、賃貸住まいの方に注目していただきたいのが「住宅確保給付金」や「高齢者向け優良賃貸住宅制度(高優賃)」です。
これは、収入が一定以下の高齢者に対して、家賃の一部を助成する仕組みです。
自治体によって条件や上限額は異なりますが、1万円〜3万円程度の家賃補助を受けられる例もあります。
一方で持ち家の方も、「固定資産税の減免」や「バリアフリー改修に伴う税控除」が利用できる場合があります。
特に、手すりの設置や段差解消といったバリアフリーリフォームは、補助金の対象になる可能性もあるため、自治体の住宅支援窓口で確認するべきです。
また、「電気・ガスの社会的配慮割引」も見逃せません。
東京電力や関西電力などの一部電力会社では、生活保護受給者や住民税非課税世帯、高齢者世帯に対して毎月の基本料金が割引される制度があります。
条件を満たしていれば、申請するだけで年間数千円の節約が見込めます。
住まいに関する支出は年金生活の中でも大きな割合を占めるからこそ、使える支援は最大限活用して、無理なく快適な生活を目指しましょう。
参照:厚生労働省
年金生活の節約でよくある質問
年金生活に入ると、「この先、本当にやっていけるのか」「節約はどこまで必要なのか」といった不安を抱える方も多くいます。
特に、国民年金だけの方や夫婦二人での生活を考えている方は、現実的な支出や生活水準とのバランスに悩むケースが少なくありません。
ここでは、年金生活にまつわる「よくある節約の疑問」について、わかりやすく解説していきます。
- 節約しすぎずバランスよく生活するには?
- 国民年金だけで生きていける?
- 年金生活で夫婦2人で生活するにはいくら必要?
節約しすぎずバランスよく生活するには?
多くの方が、年金生活において節約は必要不可欠ですが、過度な我慢はかえって心身に負担をかけてしまいます。
大切なのは「節約するところ・しないところ」のメリハリをつけることです。
たとえば、光熱費や通信費のように見直しやすい固定費は、節約効果が持続しやすい分野です。
一方で、健康や人との交流に関わる支出は、ある程度の予算を確保しておくことが、豊かな年金生活につながります。
健康食品や運動、趣味の会費、交際費などをすべて削ってしまうと、生活の満足度が著しく下がり、孤立や健康悪化のリスクも高まります。
節約は手段であり目的ではありません。
必要以上に締め付けるのではなく、「安心して暮らせるペース」を意識することで、年金生活でも無理なく前向きに暮らすことができます。
国民年金だけで生きていける?
「国民年金しかもらえない場合、本当に生活できるのか?」というのは、多くの人が抱える切実な疑問です。
2025年度の国民年金(老齢基礎年金)の満額支給額は年約83万円(月額約6.93万円)であり、これだけで生活を成り立たせるのは現実的にはかなり厳しい状況です。
実際のところ、単身世帯の高齢者の平均生活費は月13万円前後とされており、年金だけでは毎月数万円の赤字になります。生活保護や各種補助制度を併用している人も少なくありません。
しかし、対策がまったくないわけではありません。たとえば、国民年金加入時に「付加年金」や「国民年金基金」に加入していれば、上乗せの年金を受け取ることができます。
また、60歳以降も年金の繰下げ受給を選ぶことで、受給額を最大42%増やすことも可能です。
加えて、生活費そのものを下げる工夫も有効です。
地方移住や公営住宅の活用、固定費の見直し、食費の節約などを実践することで、支出を年金水準に合わせていくことも不可能ではありません。
「国民年金だけ=詰み」ではなく、制度の理解と生活設計次第で、現実的な老後生活は可能です。まずは自分の年金見込み額を確認し、補填すべき部分と対策を早めに考えておきましょう。
年金生活で夫婦2人で生活するにはいくら必要?
年金生活に入る夫婦が最も気になるのが、「2人で暮らしていくにはいくら必要か?」という問題です。
総務省の家計調査(2024年最新)によると、高齢夫婦無職世帯の平均支出は月約24万円です。
対して、夫婦2人分の年金収入(厚生年金+国民年金)は平均月20万円程度のため、毎月4〜5万円ほどの赤字になるケースが多いとされています。
これを補うには、退職金や貯金などの老後資産の取り崩し、もしくは収支を下げる生活の工夫が必要です。
たとえば、車を手放す、外食を減らす、保険の見直しをするなど、固定費や変動費を調整することで、年間数十万円単位の節約が可能です。
また、65歳以降も少しだけ働く「プチ就労」や、在宅でできる副業を取り入れる人も増えています。月2〜3万円でも収入が増えれば、生活のゆとりが大きく変わります。
近年では、シルバー人材センターやクラウドワークスなどを活用して、自分のペースで働く高齢者も多く見られます。
夫婦2人での年金生活は、決して贅沢はできないかもしれませんが、工夫と制度の活用で無理なく安心して暮らすことは十分可能です。
まずは家計の現状を把握し、数年単位のシミュレーションをしておくことをおすすめします。
年金生活での節約に関する悩みを解決するには?
ここでは、年金生活における節約や家計管理の不安を解決する方法をご紹介します。


「年金だけで生活していけるのか不安」「これ以上どこを節約すればいいのか分からない」と悩む方は少なくありません。
ですが、将来の医療費や物価上昇といったリスクも見据え、今のうちに専門家と一緒に家計を見直すことが安心への第一歩です。
そんなときに頼りになるのが、お金のプロに無料で相談できる「マネーキャリア」です。
マネーキャリアでは、中立的な立場のファイナンシャルプランナーが、家計や年金の状況に合わせたオーダーメイドの節約・貯蓄プランを提案してくれます
もちろん相談は完全無料で、無理な勧誘も一切なしで安心です。マネーキャリアに相談することで、将来の不安を安心に変えることが期待できます。

▼マネーキャリアの概要
- お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、年収や節税について知見の豊富な、ファイナンシャルプランナーのプロのみを厳選。
- 資産形成や総合的なライフプランの相談から最適な解決策を提案可能。
- マネーキャリアは「丸紅グループである株式会社Wizleap」が運営しており、満足度98.6%、相談実績も100,000件以上を誇る。

年金生活での節約に関する悩みまとめ
年金生活では、限られた収入の中で「どこをどう節約すればよいか」「支援制度をどう活用すればいいか」など、多くの悩みを抱える方が少なくありません。
今回の記事では、買い物や調理の工夫、公的サポート制度、税金や住まいの支援策まで、さまざまな節約のアイデアをご紹介しました。
しかし、節約には「その人に合ったやり方」が必要です。年金額・家族構成・住まい・資産状況によって、優先すべき対策は大きく異なります。
だからこそ、老後資金や生活費の不安を感じている方は、専門家と一緒に家計を見直すことがおすすめです。
特におすすめのマネーキャリアでは、年金や老後の暮らしに強いファイナンシャルプランナー(FP)に何度でも無料で相談できます。
中立的な立場から、あなたに合った節約法・支援制度・資金準備の方法を丁寧にアドバイスしてくれますよ。
マネーキャリアを使って、将来の年金生活でのお金の不安を解消し、無理のない節約方法を始めましょう。




























