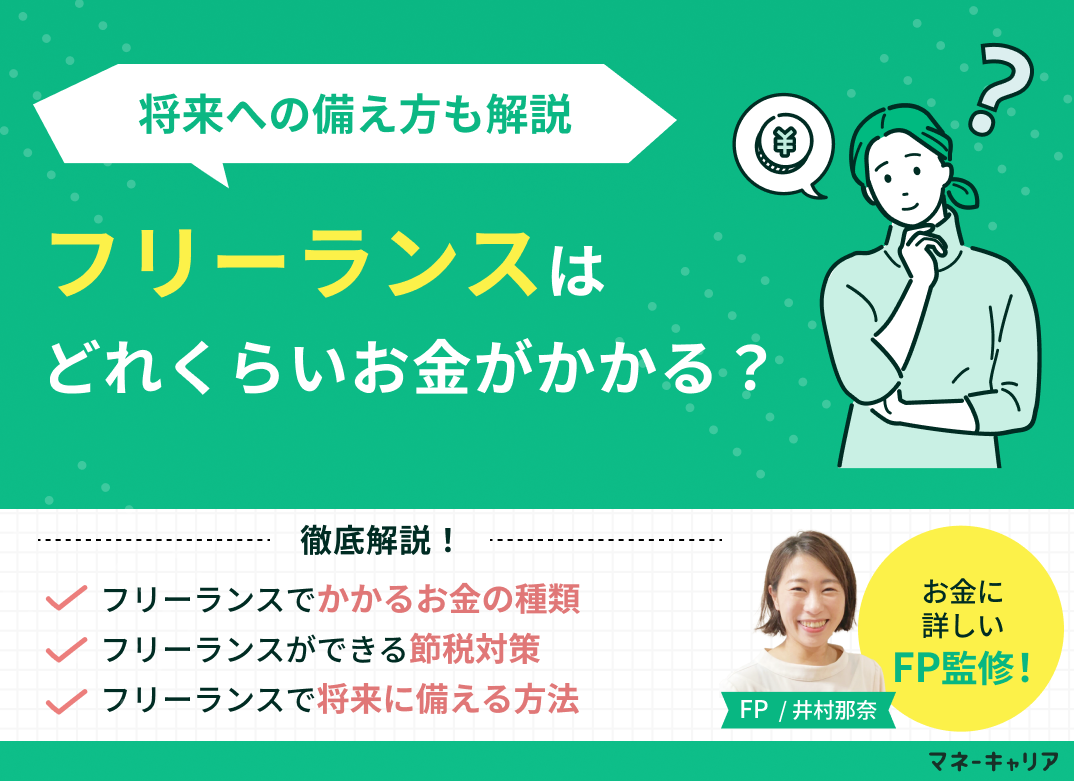
「フリーランスになると税金や保険ってどうなるの?」
「収入が安定しないのに、どれくらいお金がかかるのか不安……」
そんな疑問や不安を抱えている方は多いでしょう。
結論からお伝えすると、フリーランスでもお金の流れを理解し、節税や将来への備えを早めに整えれば、安定した働き方が実現できます。
この記事では、フリーランスにかかる税金・社会保険の種類、節税対策、将来の資産形成まで、基本から実践までをまとめて解説します。
・「独立したばかりでお金のことがわからない」
・「税金や保険を整理して将来の不安を減らしたい」
そんな方は、本記事を読むことでフリーランスのお金の全体像や負担を減らす具体策を得られるので、ぜひ参考にしてください。
内容をまとめると
- フリーランスにかかる税金・社会保険の全体像がわかる
- 節税・将来の資産形成など具体的な対策を紹介
- iDeCoやNISA、国民年金基金など長期的な備え方が学べる
- 収入が不安定でもお金の見える化と管理方法が理解できる
- マネーキャリアでは事業や家計に合った節税・貯蓄プランの無料相談ができる

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
フリーランスでかかるお金の種類は?
フリーランスでかかるお金の種類は会社員と大きく異なるため、「思ったより手元に残らないのでは?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
フリーランスでかかるお金は以下のとおりです。
- 国民健康保険・国民年金保険
- 所得税・復興特別所得税
- 住民税
- 消費税
- 個人事業税
これらの負担を把握し、計画的に資金を確保することが安定経営の第一歩です。
順番に詳しく見ていきましょう。
国民健康保険・国民年金保険
フリーランスになると会社員の社会保険から外れ、国民健康保険・国民年金に加入します。
家族構成や住んでいる市町村によって異なりますが、たとえば年収300万円の場合、国民健康保険料は年間30万円前後です。
また、国民年金は一律で月額17,510円(2025年度)かかります。
所得税・復興特別所得税
所得税と復興特別所得税は、所得額に応じて段階的に課税されます。
課税所得が300万円の場合、所得税率は超過累進税率が適用され、税額は202,500円。
さらに復興特別所得税2.1%が加算されるため、合計で206,752円が課税されます。
住民税
住民税は前年の所得に対して翌年課税され、原則一律10%(所得割+均等割)です。
たとえば年収300万円の場合、住んでいる地域や年齢などによって異なりますが、年間30万円前後がひとつの目安です。
会社員は給与天引きですが、フリーランスは自分で納付書により支払う必要があります。
消費税
消費税は原則として、課税売上が1,000万円を超えると納税義務が生じます。
ただし、2023年10月からインボイス制度が始まり、免税事業者でも取引先から登録を求められるケースが増えました。
たとえば年商900万円でも、インボイス発行のために課税事業者になる選択をする方もいます。
個人事業税
個人事業税は、一定の業種において年間の所得が290万円を超えると課税されます。
例として、デザイン業やライター業などは対象業種に含まれ、税率は3〜5%です。
開業したばかりで所得が少ない場合は非課税になることもありますが、事業が軌道に乗ると負担が増えるでしょう。
フリーランスができる節税対策
「フリーランスの税金が高い」と感じていても、手続きや知識不足で損をしている方も多いのではないでしょうか。
そこで、フリーランスができる税金対策をご紹介します。
- 青色申告をする
- 経費を漏れなく計上する
- 所得控除を申告する
これらを実践することで、課税所得を減らし、手元に残るお金を増やせます。
順番に見ていきましょう。
青色申告をする
青色申告は、最大65万円(または55万円)の控除が受けられる制度です。
年収500万円・経費100万円の場合、青色申告をするだけで数万円の節税につながります。
さらに、家族への給与を経費にできる「青色事業専従者給与」などの特典もあります。
経費を漏れなく計上する
経費を正しく計上することは、フリーランスの節税の基本です。
打ち合わせの交通費、クラウドサービス利用料、資料購入費などはすべて経費になります。
税務調査にも安心して対応できるよう、経費を領収書や明細で管理しておきましょう。
所得控除を申告する
所得控除を漏れなく申告することで、課税所得を減らせます。
「小規模企業共済」「iDeCo(個人型確定拠出年金)」などを活用すれば、年間数十万円の所得控除が可能です。
扶養控除や医療費控除など、生活状況に応じた控除も見逃せません。
フリーランスで将来に備えるおすすめの方法
フリーランスは会社員に比べて収入が安定せず、将来への備えに不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
しかし、フリーランスでも以下のような方法で無理なく将来に備えられます。
- iDeCo・NISAで資産運用
- 国民年金基金
- 付加年金
これらの制度を活用することで、税制優遇を受けつつ老後資金を効率的に増やせます。
順番に確認していきましょう。
iDeCo・NISAで資産運用
iDeCo(個人型確定拠出年金)は掛金が全額所得控除になり、運用益も非課税になる制度です。
仮に、年利3%で運用できたとすると、元本720万円は1,161万円以上になる計算です。
新NISAなら年間360万円まで投資でき、売却益・配当が非課税になるため、事業収入が不安定な方にも使いやすいでしょう。
国民年金基金
国民年金基金は、自営業者やフリーランスが国民年金に上乗せして加入できる公的な年金制度です。
掛金は全額所得控除になり、将来受け取る年金額を増やせます。
たとえば月額2万円の掛金で、将来は終身年金として受給可能です。
付加年金
付加年金は、国民年金に月400円を上乗せして支払うことで、将来年金が増える制度です。
20年間払い続けると9万6,000円の負担で、受給開始後は毎年約4,800円の年金が上乗せされます。
2年で上乗せした分が回収できるため、長期的に見ればメリットが大きいと言えるでしょう。
フリーランスのお金に関するよくある質問
フリーランスのお金に関する、よくある質問をご紹介します。
- フリーランスの売上や経費はどのように管理するの?
- 所得税はいくらからかかる?
- 会社員よりも節税できる?
これらを知っておくと、手元に残るお金を増やし、安心して事業に集中できます。
順番に見ていきましょう。
フリーランスの売上や経費はどのように管理するの?
売上や経費は、クラウド会計ソフトを活用してリアルタイムで記録するのが効率的です。
freeeやマネーフォワードクラウドなどの会計ソフトなら、銀行口座やクレジットカードと連携でき、自動仕訳で手間が減ります。
また、レシートや領収書をスマホで撮影するだけで経費登録ができるので、帳簿づけが苦手な人にもおすすめです。
所得税は所得がいくらからかかる?
所得税は、基礎控除や各種控除を差し引いた課税所得に対してかかります。
たとえば基礎控除48万円、青色申告特別控除65万円を差し引くと、課税所得が113万円以下なら所得税がかかりません。
会社員よりも節税できる?
フリーランスは、経費計上や青色申告控除、各種所得控除を活用することで、会社員よりも節税の幅が広がります。
たとえば家賃の一部を事務所として経費計上できたり、通信費や書籍代を経費にしたりも可能です。
一方で社会保険料の事業主負担がないため、トータルでは負担が増えるケースもあります。




























