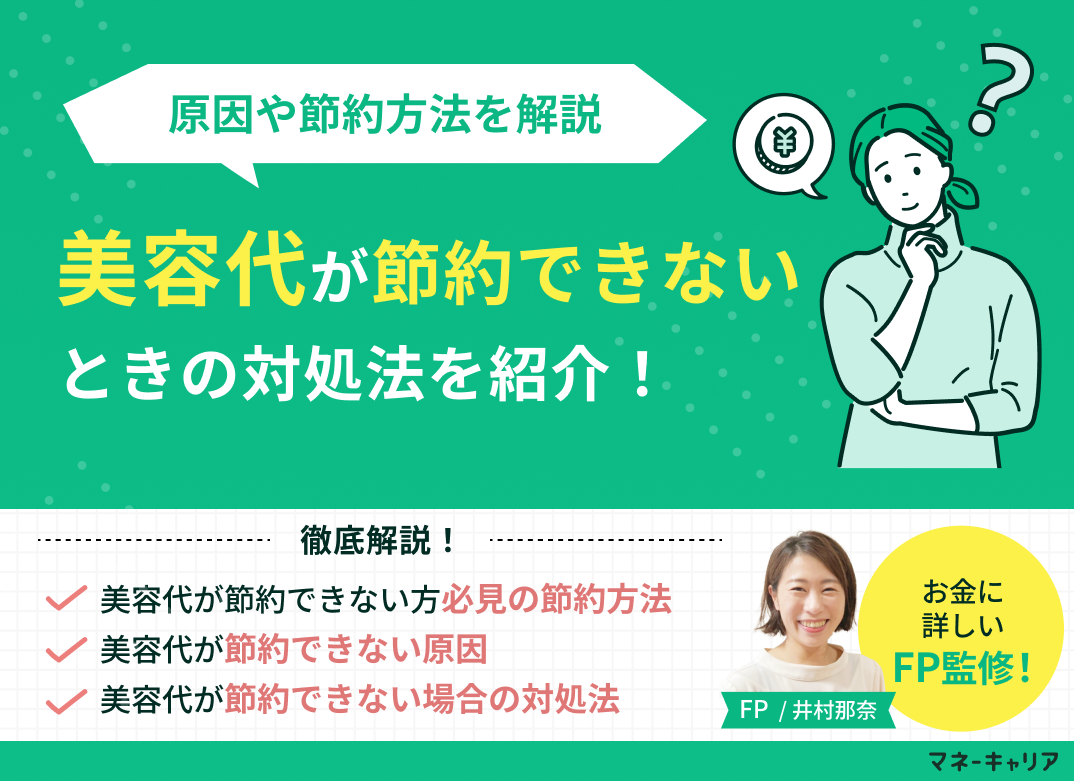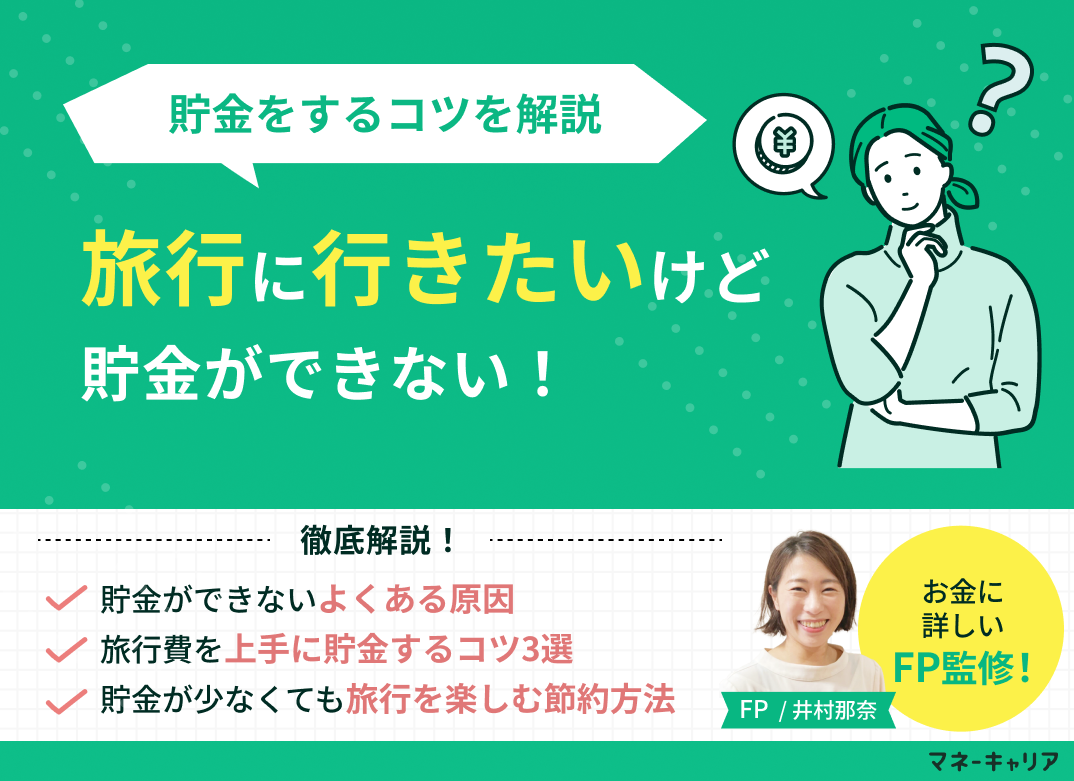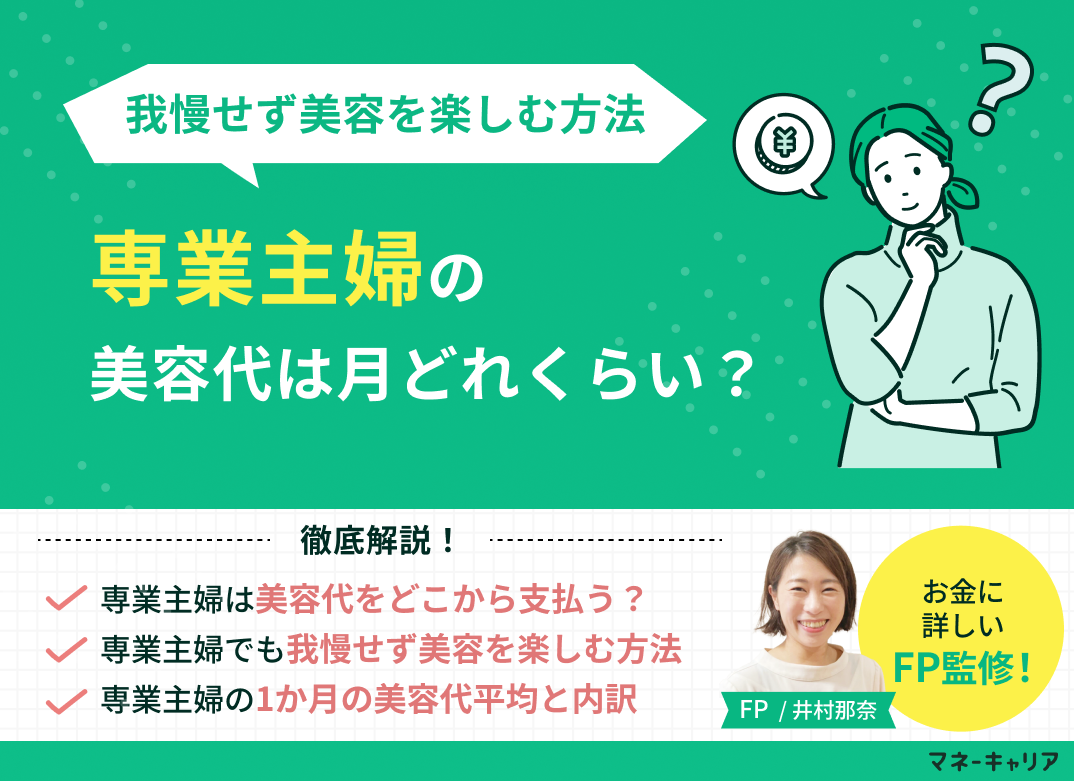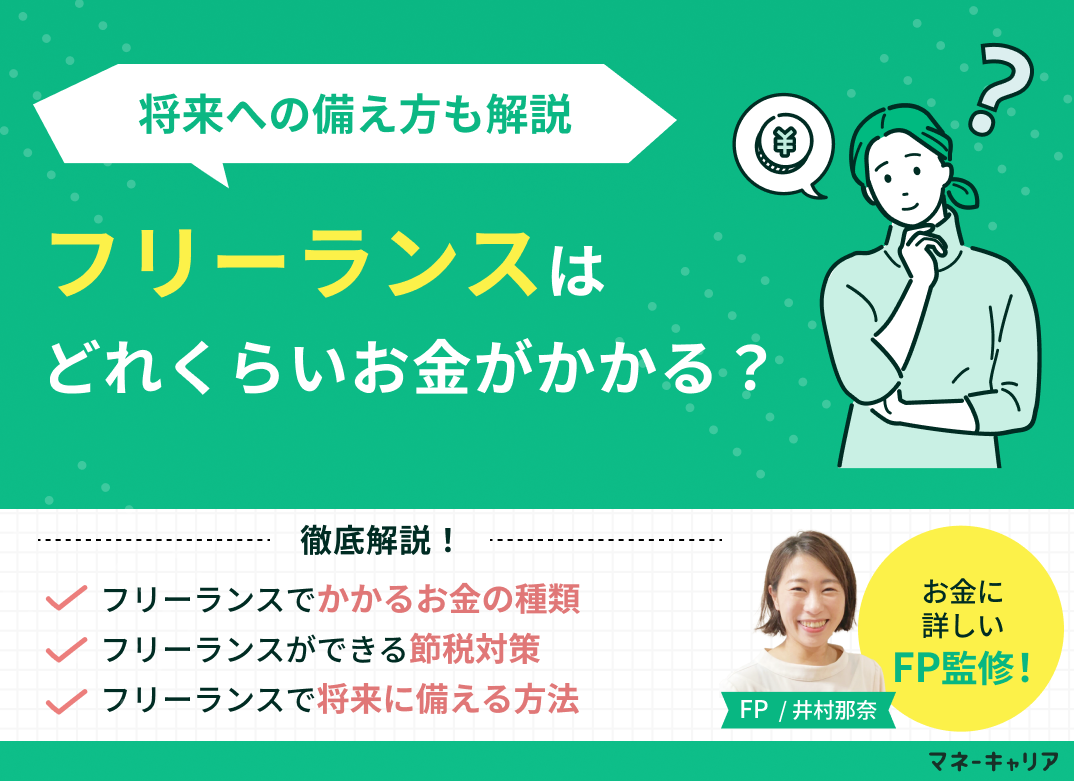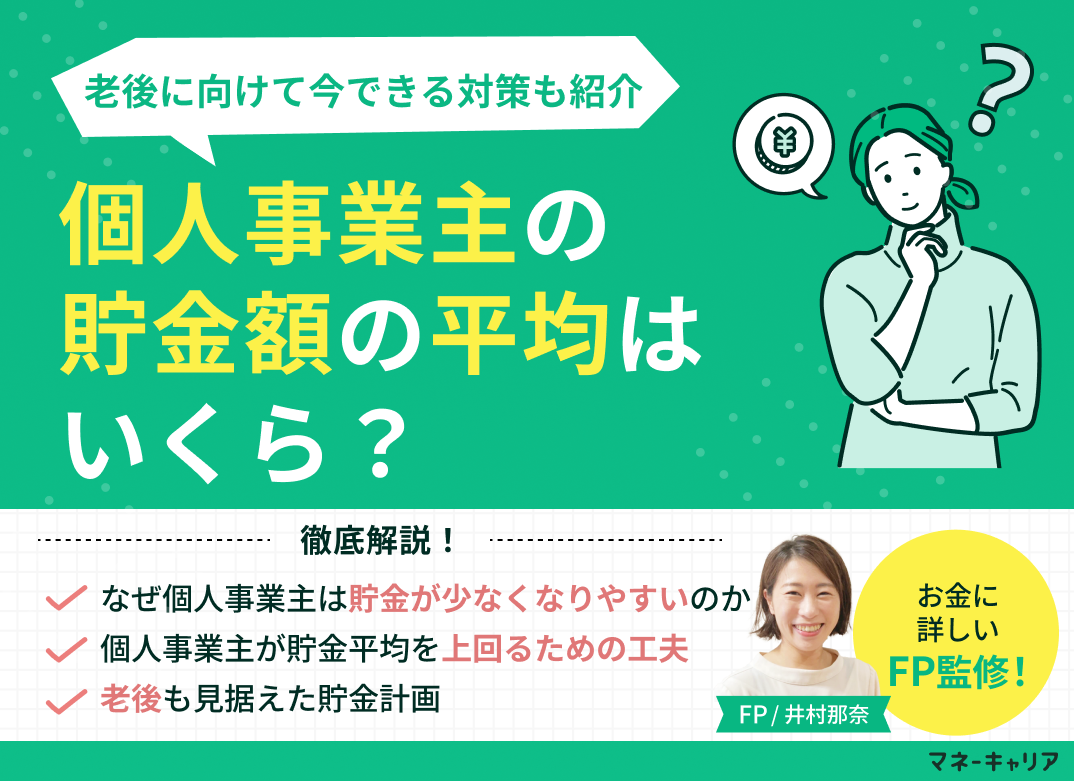
内容をまとめると
- 個人事業主全体の貯金額は統計データがなく、明確な平均値を示すのは難しいのが現実です。ただし、会社員と違って安定収入が得られるわけではないため差が大きい傾向にあります。
- 個人事業主は、事業でお金が必要になることも多く収入の安定性が低い働き方。そのため、貯金が少なくなってしまいがちです。
- 現在個人事業主で働いている方は、まず利益や事業にかかる経費、生活費のバランスを考えるのがおすすめです。自分で判断できない場合は、プロに相談する方法もあります。
- 特に「マネーキャリア」のような無料相談窓口なら、経験豊富なFPが対応してくれるのが魅力。第三者の立場から今できる貯金方法を教えてもらえます。

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 個人事業主全体の平均貯金額は?
- なぜ個人事業主は貯金が少なくなりやすいのか
- 収入の安定性が低い働き方だから
- 税金や経費で現金が残りにくいから
- 将来への貯金を後回しにしがちだから
- 事業にお金を回しがちだから
- 個人事業主が貯金平均を上回るための工夫
- 収支を可視化するツールを活用する
- 事業口座と生活口座を分けて管理する
- 先取り貯金と固定費を見直す
- 個人事業主必見|老後も見据えた貯金計画
- 必要な貯金額の目安を決める
- 教育費や住宅費との優先順位をつける
- 長期で備える資金計画を立てる
- ライフプラン表の作成をする
- 個人事業主に活用してほしい制度と仕組み
- 新NISAやiDeCo
- 小規模企業共済
- 国民年金基金
- 個人事業主の貯金平均に関するよくある質問
- 貯金がゼロでも間に合いますか?
- 年齢別に見る理想の貯金額とは?
- 教育費や住宅ローンと事業を両立するためには?
- 個人事業主の貯金で平均額が不安な時に使うべき方法とは?
- 個人事業主の貯金額平均まとめ
個人事業主全体の平均貯金額は?
個人事業主(フリーランス)の平均貯蓄額は約431万円で、正社員の359万円と比べてやや高い水準にあります(ライフネット生命保険株式会社調べ)。
一見すると貯金ができているように見えるフリーランスですが、実態はかなりばらつきがあるのが現状です。
たとえば、上記の調査では約10人に1人は「貯蓄1,000万円以上」と回答しており、高収入層では着実に資産を築けている人もいます。
その一方で、「貯蓄0円」という回答も約5人に1人の割合で存在しており、貯蓄格差が大きいのが特徴的です。
こうしたデータからも、自分に合った貯蓄戦略やリスク対策を早めに検討することが重要だといえるでしょう。
ただし、個人事業主だけを対象にした国の調査結果はなく、現在の正確なデータが分からない点に注意が必要です。
近年の物価高、インボイス制度の導入など、フリーランス・個人事業主の働き方は変わりつつあります。
「想像以上に税金がかかる」「支払いが多い」と悩み個人事業主も多くいるのが現実です。
なぜ個人事業主は貯金が少なくなりやすいのか
- 収入の安定性が低い働き方だから
- 税金や経費で現金が残りにくいから
- 将来への貯金を後回しにしがちだから
- 事業にお金を回しがちだから
収入の安定性が低い働き方だから
税金や経費で現金が残りにくいから
将来への貯金を後回しにしがちだから
事業にお金を回しがちだから
個人事業主が貯金平均を上回るための工夫
- 収支を可視化するツールを活用する
- 事業口座と生活口座を分けて管理する
- 先取り貯金と固定費を見直す
収支を可視化するツールを活用する
事業口座と生活口座を分けて管理する
先取り貯金と固定費を見直す
個人事業主必見|老後も見据えた貯金計画
- 必要な貯金額の目安を決める
- 教育費や住宅費との優先順位をつける
- 長期で備える資金計画を立てる
- ライフプラン表の作成をする
必要な貯金額の目安を決める
まず大切なのは、「老後にいくら必要なのか」というゴールを把握することです。目安としては、老後生活費の不足分×想定年数で算出する方法が一般的です。
たとえば、毎月の不足額が10万円、老後が30年間とすると、単純計算で3,600万円の準備が必要となります。
この金額はあくまで一例ですが、現在の生活費や家族構成、公的年金の見込み額をもとに、自分に合った金額を割り出すことが重要です。
公的年金は「ねんきんネット」で確認可能なので、早めにチェックしておくと安心です。
教育費や住宅費との優先順位をつける
子どもの教育費や住宅購入など、人生の支出イベントは老後資金とバッティングしがちです。すべてにお金をかけるのではなく、優先順位をつけて計画的に貯金することが欠かせません。
たとえば、教育費は子どもの年齢でおおよそのピークが予測できるため、学資保険のほか新NISAの制度を活用して計画的に準備するのが現実的です。
一方で住宅費は、無理のないローン設計や繰り上げ返済によって、老後のキャッシュフローに余裕を持たせる工夫が可能です。
限られた資金の中で、どのタイミングでどこに資金を集中させるか、ライフステージ全体を見渡しながらバランスを取ることが、個人事業主にとっては特に重要です。
長期で備える資金計画を立てる
老後資金は一朝一夕に準備できるものではないため、時間を味方にした長期的な資金計画が必要です。
たとえば、新NISAやiDeCoなどの制度を活用することで、税制メリットを得ながら少額から老後資金を準備できます。
個人事業主の場合、売上の変動に合わせて無理なく積み立てられる方法を選ぶことがポイントです。
月ごとの収支に応じて「最低金額+余裕がある月は増額」という柔軟な積立設定もおすすめです。
また、年に一度は運用状況や生活の変化に合わせて見直すことで、計画が形骸化するのを防ぐことができます。
ライフプラン表の作成をする
老後資金を「なんとなく」で貯めていると、目標とのズレが生じやすくなります。
そこでおすすめなのが、自分のライフイベントと収支を年単位で可視化した「ライフプラン表」の作成です。
ライフプラン表を作ることで、「○年後に教育費がピークを迎える」「ここで住宅ローンの支払いが終わる」など、将来の資金の出入りが一目で把握できます。
これにより、老後に向けた貯金の優先順位や時期を論理的に組み立てることが可能になります。
将来の見通しが立てば、今やるべき貯金額や運用方針も自然と可視化できるのが魅力です。
個人事業主に活用してほしい制度と仕組み
個人事業主が将来に向けて貯金を増やすには、ただ貯めるだけでなく、「制度や仕組み」を上手に活用することが重要です。
会社員と比べて社会保障制度の恩恵が少ない個人事業主にとって、老後の資金づくりは自分の努力次第になります。
そのため、節税しながら老後資金を準備できる制度を最大限に活用することが、安定した将来設計への第一歩になります。
ここでは、特におすすめしたい3つの制度について詳しく解説していきます。
- 新NISAやiDeCo
- 小規模企業共済
- 国民年金基金
新NISAやiDeCo
2024年から始まった「新しいNISA(通称:新NISA)」や「iDeCo(個人型確定拠出年金)」は、老後資金づくりにおける代表的な制度です。
どちらも少額から始められ、資産形成を効率的に行うことができます。
新NISAは、非課税で投資できる枠が大幅に拡大し、制度も恒久化されたため、個人事業主の資産形成に非常に有効です。
「つみたて投資枠」で年間120万円、「成長投資枠」で年間240万円、合計で最大年間360万円まで投資できます。
生涯にわたる非課税保有限度額は1,800万円で、運用益はずっと非課税となります。
iDeCoと違っていつでも引き出せるため、老後資金だけでなく、事業資金や教育資金など、さまざまな目的に対応できる自由度の高さが魅力です。
一方、iDeCoは原則60歳まで引き出せない分、掛金が全額所得控除の対象となり、節税効果が非常に高いのが特長です。
個人事業主の場合、iDeCoの拠出限度額が月額68,000円と会社員より高めに設定されているため、より多くの資産を所得控除の対象としながら積み立てることができます。
収入の波に合わせて拠出額を調整することもできるため、柔軟な資産形成が可能です。
「まずは少額から」「生活に無理のない範囲で」といった使い方もできるので、制度を知っておくだけでも大きなアドバンテージになります。
小規模企業共済
小規模企業共済は、個人事業主や中小企業の経営者が「退職金」を自分で積み立てるための制度です。
毎月1,000円〜70,000円の範囲で掛金を設定でき、掛金は全額所得控除の対象になります。
つまり、積み立てながら節税にもつながるという、非常にメリットの大きい制度です。 共済金は、事業を廃業した際や引退時に退職金として受け取ることができます。
また、受取方法は「一括」「分割」「一括+分割併用」から選ぶことができ、老後の生活スタイルに応じた柔軟な設計が可能です。
任意で解約する場合、掛金の納付月数が240か月(20年)未満だと元本割れしますが、事業の廃業や役員の退任といった共済事由で請求する場合は、より短い期間でも元本を上回る可能性があります。
また、積立期間中でも共済金を担保にして低金利の貸付を受けることもできるため、万が一の資金繰りにも役立ちます。
手続きも比較的シンプルで、最寄りの商工会議所や金融機関から加入できます。
国民年金基金
国民年金基金は、国民年金に上乗せして「第二の年金」を作るための制度です。個人事業主のように厚生年金に加入していない人にとって、老後の受取額を増やす手段として非常に有効です。
加入者は、あらかじめ決められた「口数」に応じて保険料を支払い、将来は年金として定額を受け取ることができます。
終身年金型と確定年金型(◯年間のみ受け取り)を選べるため、自分のライフプランに合わせた設計が可能です。
掛金は全額が所得控除の対象となるため、節税効果も抜群な点も魅力です。iDeCoと合わせて利用することも可能で、老後資金の柱を複数持っておくことで、リスク分散にもなります。
ただし、加入後に原則として途中解約ができないため、長期的に支払いを続けられるかどうかの見極めが必要です。
また、年齢や性別によって受け取れる年金額が異なるため、事前にシミュレーションを行っておくと安心です。
「公的年金だけでは不安」「老後に備えて毎月一定額を確保したい」と考える個人事業主には、ぜひ検討してほしい制度のひとつです。
個人事業主の貯金平均に関するよくある質問
個人事業主として働いていると、「他の人はどれくらい貯金しているんだろう?」「このままで大丈夫なのかな?」と不安になることもあるかもしれません。
収入の波がある働き方だからこそ、目標設定やペース配分に迷う方は多いものです。
ここでは、個人事業主からよく寄せられる「貯金に関する疑問」にお答えします。
- 貯金がゼロでも間に合いますか?
- 年齢別に見る理想の貯金額とは?
- 教育費や住宅ローンと事業を両立するためには?
貯金がゼロでも間に合いますか?
結論から言うと、貯金がゼロの状態でも「今からの行動次第」で充分間に合います。大切なのは、現状を正しく把握し、これからの収支やライフイベントを可視化したうえで、明確な目標と計画を立てることです。
まずは生活費とは別に、少額でも「事業用貯金」「将来用の貯金」を分けて積み立て始めるのが効果的です。
例えば、新NISAや小規模企業共済などの制度を利用することで、効率的に資産形成を進めることが可能です。
また、収入に波がある個人事業主にとっては、「貯める月」と「維持する月」を分けて考えるのも一つの工夫です。
大切なのは金額よりも「貯める習慣」を早期に持つことです。スタートが遅れても、行動すれば未来は変えられます。
年齢別に見る理想の貯金額とは?
年齢によってライフイベントや支出が大きく変わるため、それに応じた貯金の「目安」を把握しておくことは重要です。
以下はあくまで一例ですが、参考値として知っておくと将来設計に役立ちます。
- 30代:独立から数年以内の人も多いため、生活防衛資金として「半年分の生活費+事業運転資金」が理想。 貯金額で言えば100万〜300万円程度を目安に。
- 40代:子育てや住宅ローン、事業投資のピーク期。目安としては300万〜800万円の貯金を確保しておきたい時期です。
- 50代以降:老後資金の準備が本格化する時期。1,000万円〜2,000万円以上を目指し、年金や退職金の代わりとなる資産形成を進めていくことが大切です。
ただし、事業規模や家庭環境によって最適な金額は異なります。「自分にとっての理想の金額」を考えるためには、ライフプラン表を作成してみるのもおすすめです。
教育費や住宅ローンと事業を両立するためには?
教育費・住宅費・事業資金はどれも重要な支出項目ですが、すべてに均等にお金をかけようとするとキャッシュフローが圧迫されてしまいます。
優先順位を明確にし、「一気にすべて整える」のではなく、時期をずらして戦略的に対応していくことが鍵です。
例えば、教育費はピークが予測しやすいため、新NISAや学資保険などで計画的に準備することが可能です。
住宅ローンに関しては、無理な返済プランを避け、繰り上げ返済や借り換えなどで総支払額を抑える工夫も必要です。
一方で、事業資金は急な支出や投資が発生することも多いため、生活費とは別に「事業用の予備資金口座」を作っておくと安心です。
中長期で考えれば、事業の安定が教育や住宅にもプラスに働くため、必要に応じて外部資金や補助制度の活用も検討していきましょう。
個人事業主の貯金で平均額が不安な時に使うべき方法とは?
ここでは、個人事業主が「貯金の平均額」に不安を感じたときに活用すべき具体的な方法をご紹介します。
「自分の貯金額って少ないのかな」「将来が不安だけど、何から見直せばいいかわからない」と悩む方も多くいます。
しかし、将来のリスクやライフイベントを踏まえた資金計画を立てるには、保険や資産運用のプロと一緒に考えるのが安心です。
そんなときに頼りになるのが、お金の専門家に無料で相談できるマネーキャリアというサービスです。
マネーキャリアなら、特定の商品を勧められることなく、中立的な立場からあなたの家庭状況に合わせたアドバイスが受けられます。
さらに、オンライン対応で全国どこからでも無料相談できるのも大きな魅力です。

▼マネーキャリアの概要
- お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、年収や節税について知見の豊富な、ファイナンシャルプランナーのプロのみを厳選。
- 資産形成や総合的なライフプランの相談から最適な解決策を提案可能。
- マネーキャリアは「丸紅グループである株式会社Wizleap」が運営しており、満足度98.6%、相談実績も100,000件以上を誇る。

個人事業主の貯金額平均まとめ
個人事業主は収入が不安定なぶん、貯金のしにくさに悩む方が多い働き方です。
実際、貯金ゼロというケースも珍しくありませんが、老後や教育費など、将来に向けた備えは早めに取り組んでおくことが大切です。
本記事では、個人事業主が貯金を増やすための考え方や制度(iDeCo・小規模企業共済・国民年金基金など)、理想の貯金額、ライフステージごとの優先順位など、幅広く解説してきました。
とはいえ、家族構成や収入状況、事業フェーズによって「自分にとって最適な貯金戦略」は大きく異なります。
だからこそ、プロのアドバイスを受けて一緒に整理してみるのがおすすめです。
その際、マネーキャリアでは、個人事業主ならではの悩みに寄り添い、家計・保険・貯蓄・資産形成まで無料でサポートが可能です。中立な立場から、あなたのライフプランにぴったりのアドバイスを受けられます。