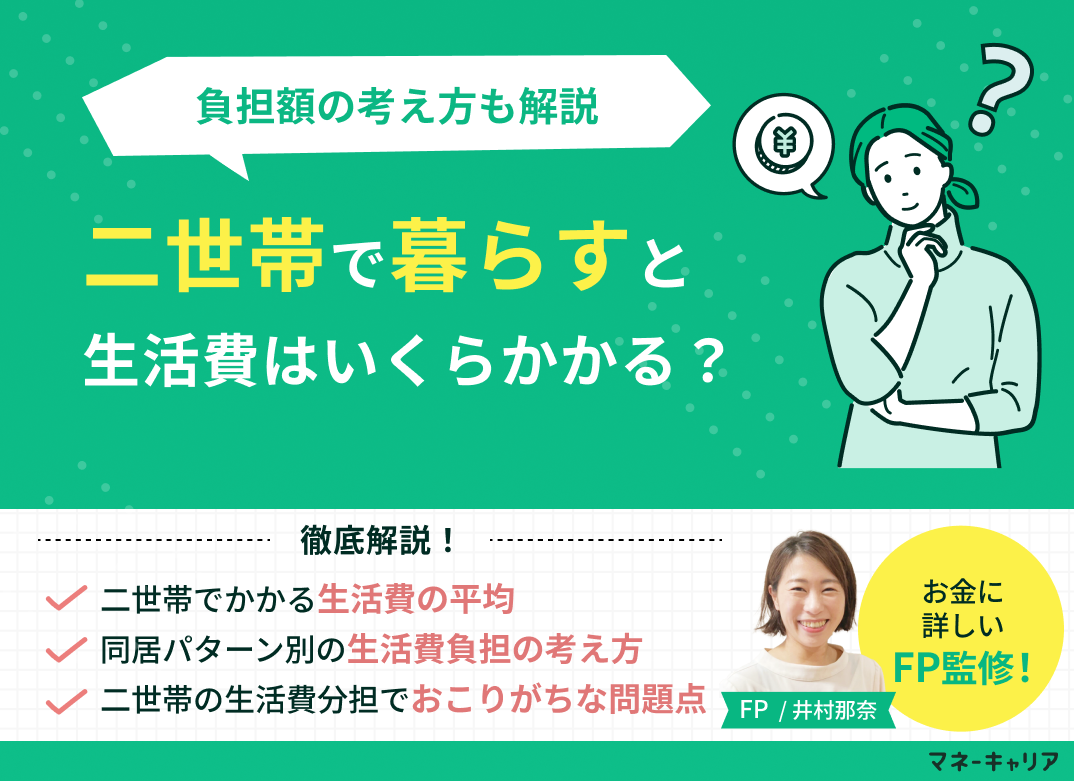
内容をまとめると
- 二世帯の生活費は、世帯人数や支出項目別のデータを把握することで、平均額や相場観を明確にできる。
- 同居パターンごとの費用負担方法を理解することで、不公平感を避けながら現実的な分担ルールを設計できる。
- 生活費分担で起こりやすいトラブルと予防策を知ることで、関係悪化を防ぎ、長期的に円満な同居を続けられる。
- 二世帯同居の家計管理に不安がある方は、相談実績10万件超・満足度98.6%超のマネーキャリアを活用することで、家計の整理と円満な生活費分担を両立できる。

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 二世帯でかかる生活費の平均を解説
- 世帯人数別の消費支出額(全体像)
- おもな費目別の支出額
- 二世帯の同居パターン別に見る生活費負担の考え方
- 親世帯の家に子ども世帯が同居するケース
- 子ども世帯の家に親世帯が同居するケース
- 二世帯の生活費分担でおこりがちな問題点
- 水道光熱費・食費などの負担割合があいまいになりやすい
- 共有部分の使用量や負担感に不公平を感じる
- 支払い忘れや遅延により一方に不満が生じる
- 想定外の出費がどちらか一方に偏る
- 二世帯で生活費を分担する方法4ステップ
- 1.共有部分と独立部分を明確化する
- 2.毎月発生する共有支出を洗い出す
- 3.年単位で発生する共有支出も洗い出す
- 4.すべての支出を踏まえて負担割合を関係者全員で話し合って決める
- 二世帯の生活費は平均いくら?関連するよくある質問
- 二世帯住宅はやめた方がいいですか?
- 生活費を親に渡す場合はいくらがいいですか?
- 二世帯の生活費平均と円満な分担のコツ【まとめ】
二世帯でかかる生活費の平均を解説
二世帯でかかる生活費の平均を、統計データをもとに、2つの視点から解説します。
紹介する内容は以下のとおりです。
- 世帯人数別の消費支出額(全体像)
- おもな費目別の支出額
全体像と費目別の両方を押さえることで、自分の家庭に近い条件に照らし合わせながら、より現実的な生活費の見積もりや分担計画を立てやすくなります。
なお、提示するデータは全国平均の参考値ですが、初期段階でおおまかな費用感をつかむ判断材料として、ぜひ参考にしてください。
世帯人数別の消費支出額(全体像)
総務省の家計調査(2024年)によると、世帯人員別の1ヵ月の消費支出は、以下のとおりです。
| 世帯人数 | モデルケース | 消費支出額 |
|---|---|---|
| 4人 | 親1人+ 子ども夫婦+ 子ども1人 | 345,000円 |
| 5人 | 親2人+ 子ども夫婦+ 子ども1人 | 361,000円 |
| 6人以上 | 親2人+ 子ども夫婦+ 子ども2人以上 | 357,000円 |
※参照:第3-1表 世帯人員別1世帯当たり1か月間の収入と支出(2024年)|総務省
世帯人数が増えると支出は高くなる傾向がありますが、6人以上になるとやや減少しています。
これは、食費や光熱費が増える一方で、家具・家事用品など一部の支出は一定額を超えて増えにくいためと考えられます。
また、電気・ガス・水道などの光熱費には基本料金部分があるため、世帯全体で共有することで1人あたりの負担が割安になる効果もあります。
こうした傾向を理解しておくことで、二世帯同居の予算を立てる際に、世帯構成に合わせた現実的な費用見積もりが可能になります。
おもな費目別の支出額
食料や光熱水道費は、世帯人数が増えるほど支出が大きくなる傾向があります。
一方で、家具・家事用品は一定人数を超えると減少することもあります。
これは、冷蔵庫や洗濯機などの大型家電や調理器具が共有でき、買い替え頻度が下がるためと考えられます。
世帯人数別の支出額は、次のとおりです。
| 世帯人数 | 食料 | 光熱・水道 | 家具・家事用品 |
|---|---|---|---|
| 4人 | 96,023円 | 23,520円 | 12,979円 |
| 5人 | 104,580円 | 25,874円 | 14,386円 |
| 6人以上 | 113,808円 | 29,667円 | 12,646円 |
※参照:第3-1表 世帯人員別1世帯当たり1か月間の収入と支出(2024年)|総務省
食費は、1人増えるごとにおおむね8,500円〜9,000円の増加が見られます。
光熱水道費も人数に比例して上昇し、6人以上では4人世帯より6,000円程度高くなります。
家具・家事用品は5人世帯までは増えますが、6人以上になると減少しています。
こうした費目別データを把握しておくことで、二世帯同居の予算や費用分担を話し合う際に、根拠のある数値をもとに具体的な負担割合を決めやすくなります。
二世帯の同居パターン別に見る生活費負担の考え方
二世帯の同居パターン別に見る生活費負担の考え方を、2つのケースから解説します。
紹介するケースは以下のとおりです。
- 親世帯の家に子ども世帯が同居するケース
- 子ども世帯の家に親世帯が同居するケース
それぞれの特徴や負担の仕方を知ることで、同居前の話し合いがスムーズになりやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
親世帯の家に子ども世帯が同居するケース
親世帯の家に子ども世帯が同居する場合は、家賃負担がない分、子世帯が生活費の多くを負担するケースがよく見られます。
これは、家賃がかからないことで生まれた余裕を、生活費に充てられる場合が多いためです。
ただし、親が住宅ローンを返済中であれば、子ども世帯が一部を負担するかを事前に取り決めておくことが望ましいです。
また、光熱費や食費などは人数増加で膨らみやすく、不公平感や誤解の原因にもなりかねません。
負担範囲や割合は、同居前に明確に話し合っておきましょう。
子ども世帯の家に親世帯が同居するケース
子ども世帯の家に親世帯が同居する場合は、親が生活費の一部を負担するケースがよく見られます。
そのため、家賃や住宅ローンを子世帯が支払っている場合は、親世帯に一部を負担してもらうかどうかを事前に話し合っておくことで、不公平感や将来のトラブルを防ぎやすくなります。
ただし、親の年金額や貯蓄が少ない場合は、住居費ではなく食費や光熱費など日常的な費用のみを一部負担してもらう方法もあります。
また、介護が必要になったり、親の収入の減少が見込まれたりする場合には、子世帯が生活費の大部分を負担することも想定しておくと安心です。
二世帯の生活費分担でおこりがちな問題点
二世帯の生活費分担でおこりがちな問題点を、4つ解説します。
紹介する問題点は以下のとおりです。
- 水道光熱費・食費などの負担割合があいまいになりやすい
- 共有部分の使用量や負担感に不公平を感じる
- 支払い忘れや遅延により一方に不満が生じる
- 想定外の出費がどちらか一方に偏る
こうした問題点は、同居前に把握しておくことで、具体的な対策や分担ルールを話し合いやすくなり、無用なトラブルを防ぐことにつながるので、ぜひ参考にしてください。
水道光熱費・食費などの負担割合があいまいになりやすい
水道光熱費や食費などの負担割合があいまいになりやすいのが、二世帯の生活費分担でおこりがちな問題点です。
理由は、同じ家に住んでいても親世帯と子世帯で使用量や消費スタイルが異なり、さらにメーターやレシートで正確に分けられない場合が多いからです。
加えて、季節や行事によって支出が大きく変動することもあり、毎月の金額が一定にならないことも影響します。
このため、同居前に“誰がどこまで負担するか”を項目ごとに取り決めておくことが望ましいです。
共有部分の使用量や負担感に不公平を感じる
共有部分の使用量や負担感に不公平を感じやすいのが、二世帯の生活費分担でおこりがちな問題点です。
これは、キッチンや浴室など共用部分の使用頻度が世帯ごとに異なり、その差が光熱水道費やガス代に直接影響するためです。
例えば、調理回数が多い世帯ではガス代や電気代が高くなり、朝晩2回の入浴をする世帯では、水道代や光熱費が増えます。
こうした費用が積み重なることで、支出の偏りや心理的な不公平感が生まれやすくなります。
そこで、あらかじめ使用ルールや費用分担の基準を話し合っておくことで、不満や誤解を防ぎつつ、納得感のある分担がしやすくなります。
支払い忘れや遅延により一方に不満が生じる
どちらかの世帯が生活費をまとめて立て替える場合、もう一方の支払い忘れや遅延は、不満や不信感を招きやすくなります。
これは、親も子も「家族だから」と気が緩み、支払いが不明瞭になりやすいために起こりがちな問題点です。
この状態が続くと、信頼関係の悪化や言い争いなど、同居生活全体に悪影響を及ぼすおそれがあります。
例えば、数万円以上の立て替えが何ヵ月も清算されず、片方の負担感が高まるケースです。
そこで、毎月何日にいくら支払うかを事前に決め、全員で共有しておくことで、不公平感やトラブルを未然に防ぎやすくなります。
想定外の出費がどちらか一方に偏る
想定外の高額な出費は、負担割合が不明確になりやすく、一方に偏ることで不満や経済的な負担感を大きくします。
なぜなら、給湯器の故障や屋根の修理・大型家電の買い替えなど、高額かつ突発的な支出は、事前に分担ルールを決めていない場合が多いからです。
その結果、支払いが特定の世帯に集中すると、「なぜ自分だけがいつも支払うのか」という感情が生まれ、関係悪化のきっかけにもなりえます。
そのため、修繕費や大型家電購入など高額支出の分担ルールも同居前に話し合っておくことで、不公平感や金銭トラブルを防ぎやすくなります。
二世帯で生活費を分担する方法4ステップ
二世帯で生活費を分担する方法を、4つのステップに分けて解説します。
紹介する方法は以下のとおりです。
- 1.共有部分と独立部分を明確化する
- 2.毎月発生する共有支出を洗い出す
- 3.年単位で発生する共有支出も洗い出す
- 4.すべての支出を踏まえて負担割合を関係者全員で話し合って決める
事前に手順を把握しておくことで、感覚や思い込みではなく、具体的な金額や項目に基づいた話し合いができます。
これにより、不公平感や思わぬトラブルを減らし、同居生活を長く続けやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
1.共有部分と独立部分を明確化する
生活費を公平に分けるためには、まず"どこが共有で、どこが独立しているのか"をはっきりさせることが重要です。
なぜなら、共有部分の費用は全員に関係するため、境界があいまいだと、負担している世帯の不満が生まれすくなるからです。
例えば、完全同居型では電気・水道・ガスなどの光熱費や、食事を一緒にする場合の食費がすべて共有費用になります。
一方で、キッチンや浴室が別の"部分共有型"や、各設備がすべて独立している"完全分離型"では、独立部分の費用は世帯ごとに計算できますが、玄関・廊下・庭などの共有スペースにかかる費用は話し合いが必要です。
同居前に"どこが共有で、どこが独立か"を図面やリストで確認しておくことで、負担ルールを決めやすくなり、後々のトラブル防止にもつながります。
2.毎月発生する共有支出を洗い出す
毎月発生する共有支出を洗い出すことは、公平な負担割合を決めるための重要ステップです。
なぜなら、頻繁に発生する金額の全体像が見えないままでは、どちらの世帯に負担が偏っているのか判断できず、不公平感が生まれやすくなるからです。
例えば、光熱費や食費、インターネット通信費、日用品費など、二世帯で共有している支出項目をすべてリスト化します。
このとき、請求書や明細で“実際の金額”を確認するのが基本です。
金額と項目が明確になれば、「光熱費は折半」「食費は利用割合で分ける」など、具体的かつ納得感のある分担ルールを話し合いやすくなります。
3.年単位で発生する共有支出も洗い出す
年単位で発生する共有支出も事前に洗い出しておくことは、公平な負担割合を決めるために欠かせません。
なぜなら、固定資産税や火災保険料、大型設備の点検・修理費などは、支払い頻度が低く日常の家計に反映されにくい一方で金額が大きく、負担が偏りやすくなるからです。
こうした年間支出は“月割り計算”にしておくと、計画的に積み立てられ、支払い時の負担を抑えられます。
事前に準備しておけば、突発的な出費による不公平感や金銭トラブルを防ぎ、二世帯間の家計管理を安定させやすくなります。
4.すべての支出を踏まえて負担割合を関係者全員で話し合って決める
最後に、すべての支出を踏まえて、負担割合を関係者全員で話し合って決めることが重要です。
なぜなら、全員で合意しておくことで納得感が高まり、一方的な決定による不満や反発を防げるからです。
分担方法は、均等割りにするのか、項目別にするのかを明確にし、計算担当者も決めておきましょう。
また、いつから誰が支払いを始めるのかを、事前に共有しておくことも欠かせません。
なお、決定事項は口頭だけでなく文書化しましょう。
さらに、定期的に状況を共有して必要に応じて見直すことで、長期的にも公平な分担を維持しやすくなります。
二世帯の生活費は平均いくら?関連するよくある質問
二世帯の生活費に関する悩みで、特によくある質問を、2つ解説します。
紹介する質問は以下のとおりです。
- 二世帯住宅はやめた方がいいですか?
- 生活費を親に渡す場合はいくらがいいですか?
よくある疑問の答えや考え方を知っておくことで、感情や思い込みだけで判断するのを避けられるので、ぜひ参考にしてください。
二世帯住宅はやめた方がいいですか?
二世帯住宅は、必ずしもやめた方がいいとは限りません。
理由は、経済面や生活面で大きなメリットを得られる場合が多いからです。
例えば、家賃や光熱費を抑えられたり、子育てや介護のサポートを受けられたりすることがあげられます。
ただし、費用や家事の負担が一方に偏ったり、プライバシーの確保が難しい場合は、ストレスや不満が生じやすくなります。
そのため、同居前に、費用分担・生活ルール・将来の変化などについて具体的に話し合っておくことで、メリットを活かしつつトラブルを防ぎやすくなります。
生活費を親に渡す場合はいくらがいいですか?
親に渡す生活費の額は、親の収入や支出の状況に応じて決めるのが適切です。
親の収入だけでは賄えない生活費の不足分を補う形にすれば、親の生活を安定させつつ、子世帯の家計にも余裕を残せるため、双方の負担感を減らせます。
同居の場合は、一般的に月2〜5万円程度を渡すケースが多く見られます。
ただし金額は、家計全体の収支や同居の形態(完全同居・部分共有・完全分離)によって柔軟に調整しましょう。
二世帯の生活費平均と円満な分担のコツ【まとめ】
二世帯の生活費平均と分担の決め方を把握することは、円満な同居生活を送るための重要なポイントです。
具体的には、世帯人数別・費目別の支出額を把握し、同居パターンごとの負担の考え方や、起こりやすい問題への対策を取り入れることで、不公平感を防ぎやすくなります。
さらに、生活費を分担する4つのステップを実践すれば、家計トラブルの予防にもつながります。
とはいえ、全国平均額を参考にして最適な負担割合を計算し、全員が納得できる形に整えるのは簡単ではありません。
自分の世帯に合った生活費の適正額や、分担の決め方に不安を感じる方は、専門家(FP)への相談をおすすめします。




























