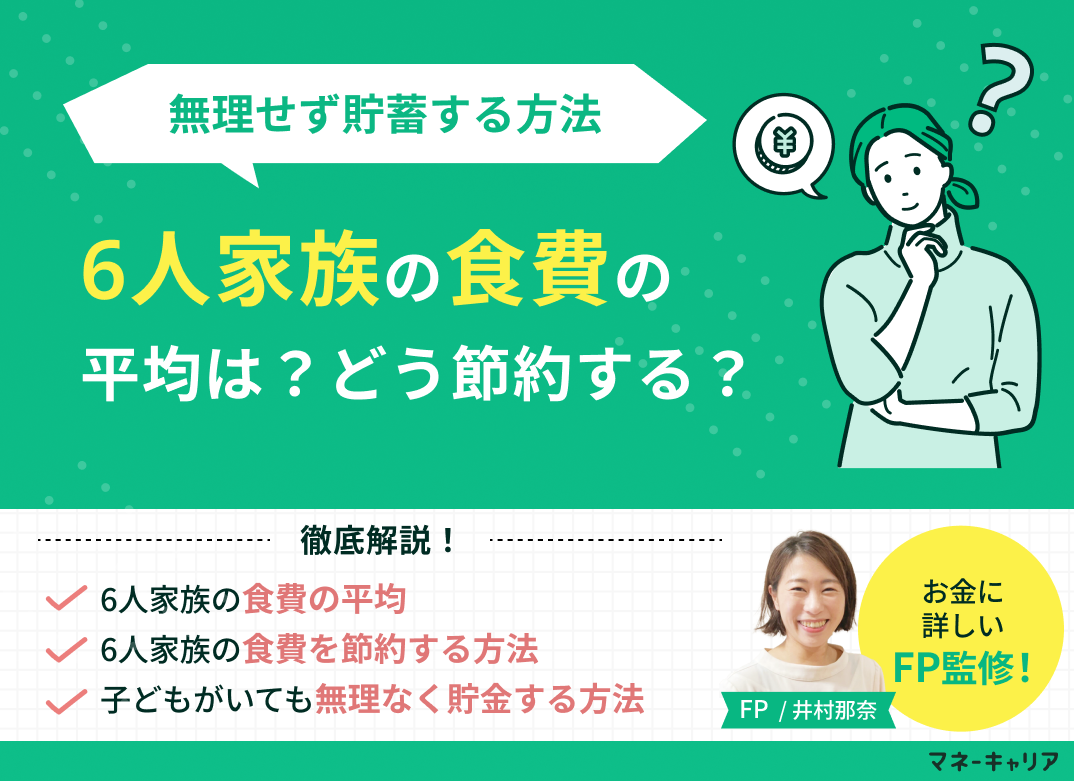
「子どもが食べ盛りで、毎月の食費がどんどん増えていく……」
「6人家族の平均食費ってどれくらい?もっと上手に節約できないかな?」
そんな疑問や不安を抱えている方は多いでしょう。
結論からお伝えすると、6人家族でも工夫次第で食費を抑えながら栄養バランスを保ち、教育費や貯金に回せます。
この記事では、6人家族の平均食費や節約テクニック、教育費や貯金を確保する方法までを解説します。
・「食費が増え続けて家計が苦しい」
・「6人家族ならではのコツを知りたい」
そんな方は、本記事を読むことで無理のない節約で食費を下げつつ、将来のために貯金を増やすヒントを得られるはずです。
内容をまとめると
- 6人家族の平均食費と節約ポイントがわかる
- まとめ買い・作り置き・自炊などコスパの高いテクニックを紹介
- 固定費の見直しや先取り貯金で教育費・貯金を確保できる
- 将来のための効率的な貯め方も解説
- マネーキャリアでは6人家族の家計に合った節約・貯蓄プランの無料相談ができる

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 6人家族の食費の平均はどれくらい?
- 6人家族の食費を節約するためのテクニック
- まとめ買いで食材を安く買う
- 冷凍保存や作り置きで食材を無駄にしない
- お米の量を多めにする
- 定番メニューを固定する
- できる限り自炊する
- 子どもがいても無理なく貯金する方法
- 固定費を見直す
- 外食費やレジャー費を抑える
- 先取り貯金を自動化する
- 食費を節約しすぎず教育費を確保する手段
- 定期預金を利用する
- NISAで効率よく増やす
- 学資保険で貯める
- 6人家族の食費節約に関するよくある質問
- 食費を節約しすぎるのはよくない?
- 食費は毎月いくらまでが理想?
- 子どもが成長しても食費を抑えるコツは?
- 6人家族の家計でお悩みならお金のプロ「マネーキャリア」に相談
6人家族の食費の平均はどれくらい?
6人家族の食費が高く悩んでいる方のなかには、食費平均がいくらなのか気になっている方も多いのではないでしょうか。
総務省の家計調査によると、6人以上世帯の食費の平均は118,265円であるとわかっています。
6人家族の食費を節約するためのテクニック
6人家族の食費を節約するには、ただ我慢するのではなく、節約方法を見直せば無理なくコストを下げられます。
どこから始めれば良いか迷う方は、次の方法を参考にしてみてください。
- まとめ買いで食材を安く買う
- 冷凍保存や作り置きで食材を無駄にしない
- お米の量を多めにする
- 定番メニューを固定する
- できる限り自炊する
これらを組み合わせれば、1か月に1〜2万円の節約も夢ではありません。
順番に見ていきましょう。
まとめ買いで食材を安く買う
まとめ買いは、大量購入によりコストパフォーマンスよく食材が手に入ることが最大のメリットです。
業務用のスーパーでは、鶏むね肉2kgを1,000円台で購入でき、1食あたりのコストを約半分に抑えられます。
週1回のまとめ買いにシフトするだけで、無駄な買い足しやコンビニ利用を減らせるでしょう。
冷凍保存や作り置きで食材を無駄にしない
冷凍保存や作り置きを活用すれば、食材のロスを最小限に抑えられます。
野菜はカットして冷凍する、肉は下味冷凍にしておくなど、週末にまとめて準備すると平日の調理時間も短縮が可能です。
お米の量を多めにする
お米を主食にすると、コストを抑えつつ満腹感を得られます。
パンや麺類よりも栄養バランス・腹持ちが良く、アレンジも効くため、食費管理がしやすくなるでしょう。
定番メニューを固定する
定番メニューを固定すると、買う食材や調味料が絞られ、結果的にコストダウンになります。
たとえば、月曜はカレー、火曜は炒め物など、曜日ごとのメニューを決めると献立作りの時間も減ります。
できる限り自炊する
自炊は外食や中食に比べてコストを約半分に抑えられることが多いです。
たとえば1人500円の外食を週3回利用するだけで、6人家族では月3万6,000円の支出になります。
一方、自炊なら同じメニューを1人300円以下で作れることも多く、年間で数十万円の差になるでしょう。
子どもがいても無理なく貯金する方法
毎月の食費が高くても、子どものために無理なく貯金したいと考えている保護者の方は多いでしょう。
食費を削らずに貯金するために、以下の方法を試してみてください。
- 固定費を見直す
- 外食費やレジャー費を抑える
- 先取り貯金を自動化する
こうした方法を組み合わせることで、無理のない貯金が現実的になります。
順番に見ていきましょう。
固定費を見直す
まずは毎月の固定費を削減しましょう。
スマホ代を家族6人分、格安SIMに変更すると年間で12万円以上浮くケースもあります。
保険の見直しや安い電力会社へ切り替えなども節約に有効です。
外食費やレジャー費を抑える
外食やレジャーを完全にやめる必要はありませんが、工夫次第で節約できます。
たとえば月4回の外食を月2回に減らし、残りは家で手作りピザやタコ焼きにすれば子どもも楽しめるでしょう。
レジャーも自治体の無料イベントや公園利用に切り替えると、年間で数万円の節約効果が可能です。
先取り貯金を自動化する
貯金を習慣化するには先取りが鉄則です。
給料日に自動で別口座へ3万円ずつ移す設定をしておくと、使い込み防止になります。
ネット銀行なら毎月の自動振替や目的別口座機能が無料で使えるところも多いです。
食費を節約しすぎず教育費を確保する手段
食費を極端に削るのではなく、教育費を優先的に確保することが将来への安心につながります。
教育費の備え方は、以下のような方法があります。
- 定期預金を利用する
- NISAで効率よく増やす
- 学資保険で貯める
これらを組み合わせることで、食費を確保しつつ教育資金をしっかり積み立て可能です。
順番に見ていきましょう。
定期預金を利用する
教育費の基盤づくりに定期預金は有効です。
定期預金は普通預金より金利が高いので、確実にお金を増やすのに適しています。
元本が保証されており、中途解約しない限り預けたお金が減ることはありません。
NISAで効率よく増やす
より効率的に教育費を増やしたいなら、NISAが選択肢に入ります。
NISAで月2万円を20年間積み立てた場合、仮に年利4%で運用できたとすると、約730万円まで増える計算になります。
非課税制度を活用することで利益への課税を抑えられ、複利効果が得やすいのがメリットです。
学資保険で貯める
学資保険は計画的に教育費を積み立てたい家庭に向いています。
10年払いで200万円積み立てるプランなら、18歳時に学費一時金として受け取れる設計です。
保護者に万一のことがあった場合でも、保険料の支払いが免除されるなど保障性も兼ね備えています。
6人家族の食費節約に関するよくある質問
最後に、6人家族の食費節約に関するよくある質問をご紹介します。
- 食費を節約しすぎるのはよくない?
- 食費は毎月いくらまでが理想?
- 子どもが成長しても食費を抑えるコツは?
回答を見ていきましょう。
食費を節約しすぎるのはよくない?
食費を極端に削ることは健康リスクを高め、結果として医療費がかさむことも考えられます。
特に小中高生の子どもがいる家庭では、タンパク質や野菜不足になりやすいといえます。
食費を削りすぎた場合、必要な栄養が取れず成長に影響が出ることもあります。
食費は毎月いくらまでが理想?
家計の黄金比に当てはめると、食費は手取りの15%前後が理想といわれます。
月収35万円なら約52,500円、月収40万円なら約60,000円、月収50万円なら約75,000円が目安です。
子どもが成長しても食費を抑えるコツは?
子どもが大きくなると食費は自然に増えますが、仕組みを整えれば上手に管理できます。
例えば週1回のまとめ買いと作り置きで無駄買いを防ぐことで、月5,000〜1万円の節約が可能です。
また、キャッシュレス決済で「食費専用カード」を作り、月の上限を決める方法も効果的です。




























