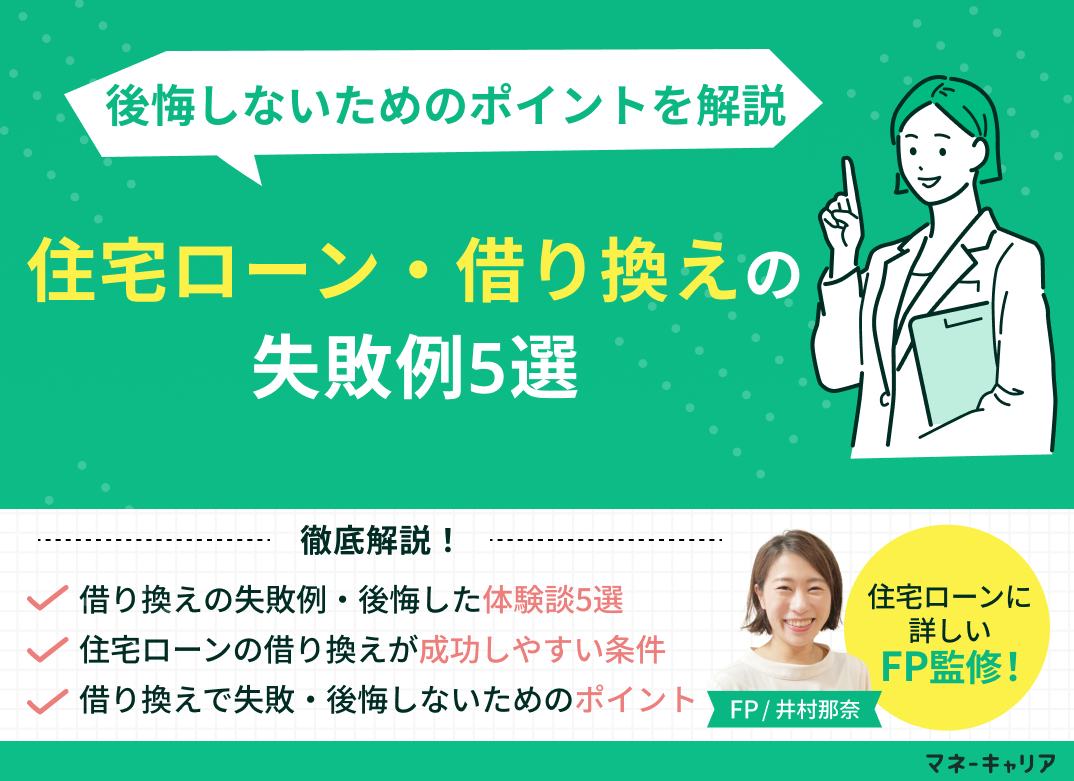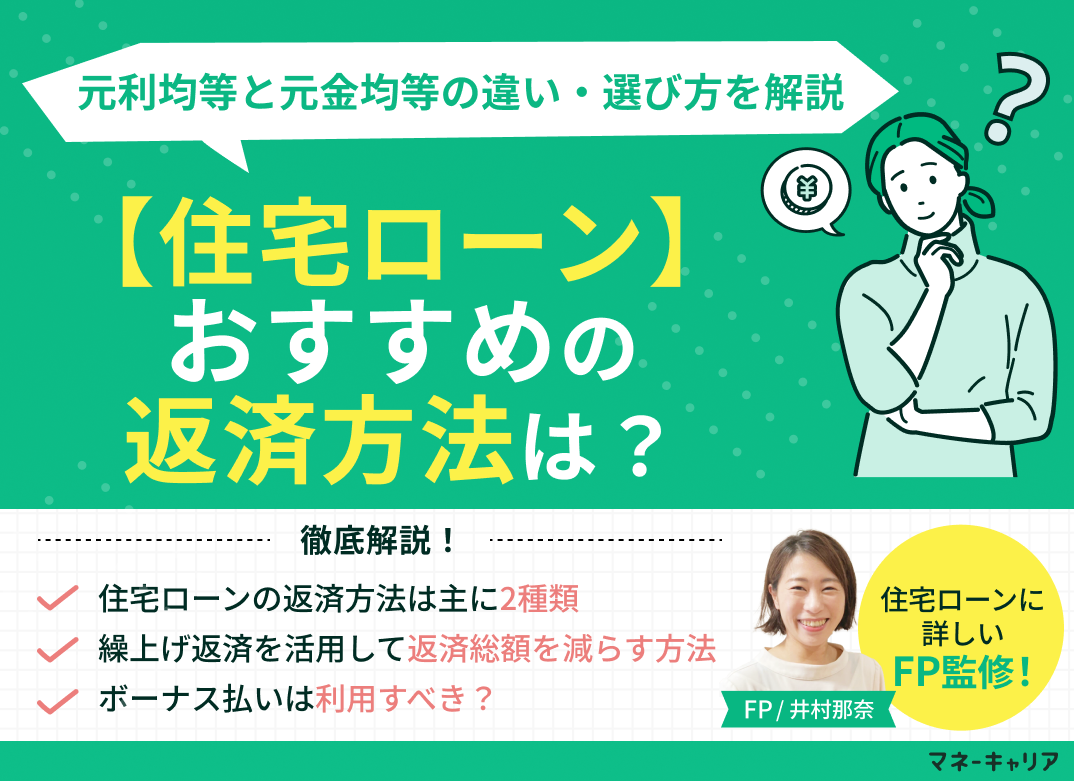内容をまとめると
- 住宅ローンと家賃の支払い額が同じの場合、長期的に比較すると総居住費に大きな差はないケースが多い
- 住宅ローンと賃貸契約の大きな違いは、住宅ローンは完済すれば自分の資産になる点と住宅ローン控除が受けられる点
- 賃貸物件のメリットは気軽に住む場所を変えられる点と修繕費が必要ない点
- 住宅ローンか賃貸物件かで比較をするなら、利用者の相談満足度が98.6%のマネーキャリアでの無料相談で納得いくまで相談するのがおすすめ

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 住宅ローンと家賃はどっちがお得?
- 住宅ローンと家賃の支払いを35年間で比較した総居住費の違い
- 今の家賃で借り入れ可能額はいくらになる?
- 住宅ローンを組んでマイホームを購入するメリット・デメリット
- 住宅ローンを組むメリット1:完済後は資産になる
- 住宅ローンを組むメリット2:住宅ローン控除が活用できる
- 住宅ローンを組むメリット3:団体信用生命保険(団信)に加入できる
- 住宅ローンを組むデメリット1:金利上昇で総返済額が予想よりも上がるリスクがある
- 住宅ローンを組むデメリット2:突然の収入源などで滞納リスクが発生する
- 住宅ローンを組むデメリット3:簡単に引っ越せない
- 家賃を払う賃貸契約のメリット・デメリット
- 賃貸契約のメリット1:気軽に住む場所を変えられる
- 賃貸契約のメリット2:修繕費などが必要ない
- 賃貸契約のメリット3:固定資産税などの税金を払わなくていい
- 賃貸契約のデメリット1:老後も家賃を払い続けなければならない
- 賃貸契約のデメリット2:高齢になると借りること自体が難しくなる場合もある
- 賃貸契約のデメリット3:間取りや設備を自分で決められない
- 家賃を払う賃貸物件に住み続ける場合に考えられるリスクは?
- 老後に考えられるコスト
- 高齢になって賃貸物件を借りるときに気を付けること
- 住宅ローンと賃貸に関してよくある質問
- 住宅ローンの支払いが「家賃より安い」は本当?
- 住宅ローンを借りたまま賃貸物件にだせる?
- 住宅ローンか賃貸がいいか疑問を解消する方法とは?
- 住宅ローンと家賃の支払いどっちがお得かを無料で相談:マネーキャリア
- まとめ:住宅ローンと家賃の特徴と違いを知って納得のいく物件を探そう
住宅ローンと家賃はどっちがお得?
マイホームを購入して住宅ローンを組むか、賃貸契約をして家賃を払うか、どちらがお得になるか気になる人は多いです。
ここでは住宅ローンと家賃の支払いの違いについて詳しく解説していきます。
- 住宅ローンと家賃の支払いを35年間で比較した総居住費の違い
- 今の家賃で借り入れ可能額はいくらになる?
住宅ローンと家賃の支払いを35年間で比較した総居住費の違い
住宅ローンと家賃の支払いを35年間続けた場合での総居住費の違いを比較していきます。
住宅ローンを組む場合、購入価格が3,500万円・返済金利が1.5%で計算し、賃貸契約では毎月10万円の家賃とします。
| 住宅ローン返済 | 家賃支払い | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 35年の毎月支払額 | 107,165円 | 100,000円 | 7,165円 |
| 35年の年間支払額 | 1,285,980円 | 1,200,000円 | 85,980円 |
| 35年間の総支払額 | 45,009,300円 | 42,000,000円 | 3,009,300円 |
| 月平均の支払額 | 107,165円 | 100,000円 | 7,165円 |
今の家賃で借り入れ可能額はいくらになる?
現在賃貸契約をしている人、あるいは毎月の家賃と住宅ローンの返済額が同じの場合の借入可能額について説明していきます。
家賃9万円を住宅ローン返済に充てるとした場合に、借入期間が30年・固定金利1.5%・元利均等の条件で計算します。
| 家賃= 住宅ローンの返済額 | 借り入れ可能額 (全期間固定) |
|---|---|
| 6万円 | 約1,750万円 |
| 7万円 | 約2,050万円 |
| 8万円 | 約2,300万円 |
| 9万円 | 約2,630万円 |
| 10万円 | 約2,900万円 |
| 11万円 | 約3,100万円 |
| 12万円 | 約3,500万円 |
現在、賃貸物件にお住まいの人は毎月支払っている家賃で経済的に困っていないのであれば、同じ価格の返済額で借り入れできる額を検討するのもおすすめです。
また、金利タイプや返済期間など個々の事情によっても借入可能額は変化するので、目安としての材料で見ておくと比較しやすいです。
参考:nomu.com
住宅ローンを組んでマイホームを購入するメリット・デメリット
マイホームを購入して住宅ローンを組むか賃貸にするかで迷っている人は、メリットとデメリット両方を知って、自分にあった方を選ぶのがおすすめです。
住宅ローンを組むメリットは次のとおりです。
- 住宅ローンを組むメリット①完済後は資産になる
- 住宅ローンを組むメリット②住宅ローン控除が活用できる
- 住宅ローンを組むメリット③団体信用生命保険(団信)に加入できる
- 住宅ローンを組むデメリット①金利上昇で総返済額が予想よりも上がるリスクがある
- 住宅ローンを組むデメリット②突然の収入源などで滞納リスクが発生する
- 住宅ローンを組むデメリット③簡単に引っ越せない
住宅ローンを組むメリット1:完済後は資産になる
住宅ローンを完済すると、購入した物件は大きな資産として自分のものになるのが大きなメリットです。
たとえば、月々10万円のローンを30年かけて支払い続けた3,000万円の住宅は自分の資産として残りますが、賃貸契約で家賃を毎月10万円払っていても、資産にはなりません。
そのため、将来的に子どもや孫へと相続させたり売却して現金化したりといった選択肢が広がる点もメリットとして挙げられます。
さらに、完済した住宅を賃貸として貸し出せば毎月の定期的な収入源にもなるので、新しい資産形成を考えている人にもおすすめです。
住宅ローンを組むメリット2:住宅ローン控除が活用できる
住宅ローンを組んでマイホームを購入すると、所得税と住民税が一定額控除される住宅ローン控除を利用できます。
たとえば、2023年の住宅ローン控除では、借入額の0.7%が10~13年間にわたって税金から差し引かれます。
仮に年収800万円で3,000万円のローンを組んだ場合、年間14万円の控除を受けられる計算になります。
住宅ローン控除が活用できれば、住宅ローンの総返済額も減らせるので賃貸にはないメリットが受けられます。
そのため、現金があってもあえて住宅ローンを組む人もいるほどです。
住宅ローンを組むメリット3:団体信用生命保険(団信)に加入できる
住宅ローンを組むと、万が一の場合に備えて団体信用生命保険(団信)に加入することができます。
たとえば、住宅ローンの返済中に借入人が死亡や重度障害状態になった場合、残りのローン残高が保険金で返済される仕組みになっています。
この保証のおかげで、残された家族が住宅ローンの返済に追われることなく、住み慣れた家に住み続けることができます。
また、団信の中には従来の保証内容だけでなく、がんや三大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)にも対応した団信も増えています。
ただし、団信の保険料は金融機関によって異なっていて、住宅ローンの金利に上乗せされる形で支払うことになります。
加入時の年齢や健康状態によっては加入できない場合もあるため、事前に条件を確認することが重要です。
住宅ローンを組むデメリット1:金利上昇で総返済額が予想よりも上がるリスクがある
住宅ローンを組む際に重要な考慮ポイントとして、金利の変動によって総返済額が想像以上に上がってしまうリスクです。
とくに変動金利型のローンを選択した場合、金利が上昇すると総返済額が増加す仕組みがあります。
たとえば、3,000万円を35年で借り入れた場合、金利が1%から2%に上昇すると、月々の返済額は約15,000円増加し、総返済額では約620万円もの差が生じる可能性があります。
一般的に、固定金利よりも変動金利のほうが金利設定が低いので、金利が上昇しなければ固定金利で契約したときよりもお得にはなります。
ただし金利市場は専門家でも長期予測が難しいので、変動金利を選ぶ場合はリスクも知っておく必要があります。
住宅ローンを組むデメリット2:突然の収入源などで滞納リスクが発生する
住宅ローンを組む際には、収入の変動が起きた場合のリスクも考慮する必要があります。
たとえば失業や病気による休職・会社の業績悪化による給与カット、さらに育児や介護による収入減少など、さまざまな要因で返済が困難になるケースがあります。
滞納まではいかないにしても、生活費が圧迫されるなどライフスタイルにも影響が出るので注意が必要です。
なお賃貸物件に住んでいる場合は、現在よりも安い家賃のところに引っ越す方法も取れるので、毎月の支払いを軽くする方法が選びやすいです。
長い期間を考えて、無理なく返済できる経済状況を維持できるかが、住宅ローンを組む場合に求められます。
住宅ローンを組むデメリット3:簡単に引っ越せない
住宅ローンでマイホームを購入すると、簡単には引越しができなくなるデメリットがあります。
そのため、転職や転勤の可能性が高い人にとってはマイホームの購入を思い切ることが難しいです。
また子どもが増える・親と同居するなど、家族構成の変化や周囲の環境変化にすぐに対応するのも難しくなります。
もしマイホームを売却して新しい土地や住居に引っ越す場合でも、ローンの残債や売却時の手数料・税金などの諸費用や手間など、時間と労力も必要です。
仮にマイホームを売却できても、売却益で住居ローンを完済できないと、新しい住居の費用に加えてローンの返済まで残ります。
住宅ローンを組む場合は、長期的な目線で返済計画を立てる必要があります。
家賃を払う賃貸契約のメリット・デメリット
賃貸契約をして毎月家賃を払う場合のメリットは次のとおりです。
- 賃貸契約のメリット1:気軽に住む場所を変えられる
- 賃貸契約のメリット2:修繕費などが必要ない
- 賃貸契約のメリット3:固定資産税などの税金を払わなくていい
- 賃貸契約のデメリット1:老後も家賃を払い続けなければならない
- 賃貸契約のデメリット2:高齢になると借りること自体が難しくなる場合もある
- 賃貸契約のデメリット3:間取りや設備を自分で決められない
賃貸契約のメリット1:気軽に住む場所を変えられる
賃貸契約のメリットのひとつは、住む場所を気軽に変えられることです。
なぜなら、賃貸契約は一般的に一定の期間が終了すれば、更新するか引っ越すかの選択が自由にできるからです。
たとえば、仕事の異動で勤務地が遠くなったり、結婚や子育てなどで家族構成にあった間取りの部屋に移り住むことも難しくありません。
持ち家の場合は、住宅ローンの残債が残っているとなかなか引っ越しに踏み切れないですが、賃貸の場合なら退去を決めてからすぐに行動に移せます。
長期間同じ場所に住むことを希望しない人や、転勤が多い人・転職も考慮したい人には賃貸物件の方があっています。
賃貸契約のメリット2:修繕費などが必要ない
賃貸物件では、居住者が修繕費を支払う必要がないのが持ち家とは大きく違うメリットです。
なぜなら、建物の経年劣化による修繕や設備の故障に関する費用は、基本的に大家さんや管理会社などが負担するからです。
たとえば、エアコンの故障や水回りのトラブル・壁紙の修繕などは大家さんや管理会社が費用を負担し業者に依頼してくれます。
そのため、持ち家の場合のように常に万が一に備えて修繕費を用意しなくても済むのが大きいです。
また、業者の手配なども居住者がする必要はないので、業者を探すといった手間も必要ありません。
賃貸契約のメリット3:固定資産税などの税金を払わなくていい
賃貸契約のメリットとして固定資産税などの税金を負担しなくて済むことが挙げられます。
賃貸住宅に住んでいる場合、住宅に関する税金は物件の所有者が支払うため、居住者は経済的な負担が軽減されます。
また、固定資産税の他にも都市計画税の負担も必要ないので、家賃と火災保険料・敷金・礼金くらいしか気にしなくていいのがポイントです。
しかも敷金・礼金は賃貸契約時に支払うだけで終わる出費なので、継続的に支払う必要があるのは毎月の家賃と、賃貸契約の更新料と保険料くらいです。
賃貸契約のデメリット1:老後も家賃を払い続けなければならない
賃貸契約のデメリットのひとつは、老後も家賃を払い続けなければならない点です。
持ち家であれば、住宅ローン返済が終われば居住費に関わるのは固定資産税などしかないですが、賃貸は住み続ける間常に毎月の家賃がかかります。
一般的に、退職をすると現役時代よりも収入が減るため、家賃の支払いで生活費や医療費の支払いに困るリスクもあります。
たとえば、月額8万円の家賃を支払っている場合、年間で96万円もの支出が必要です。
老後の平均的な年金受給額が月額20万円程度だとすると、家賃だけで半分近くも占めてしまうことになります。
さらに将来的に家賃の値上げリスクも考慮する必要があるため、長期的な人生設計が難しくなる可能性を考慮しておくことが大切です。
賃貸契約のデメリット2:高齢になると借りること自体が難しくなる場合もある
高齢になると賃貸物件を借りること自体が難しくなる場合がある点がデメリットです。
一般的に不動産会社や大家さんは、事故や病気の発生・家賃滞納・身寄りがない場合の保証問題などを懸念して、部屋を貸してくれないケースもあります。
さらに高齢の方の場合は連帯保証人を見つけるのが難しいことも多く、保証会社でも年齢を理由に保証を断られるケースもあります。
また入居できたとしても、緊急連絡先や身元引受人の確保が必要となったり、前払い家賃や敷金の上乗せを求められたりする場合もあるので注意が必要です。
将来的に住まいの確保については、できるだけ早めに対策を検討することをおすすめします。
賃貸契約のデメリット3:間取りや設備を自分で決められない
賃貸物件では、住まいの間取りや設備について、自分の希望通りのカスタマイズは基本的にできません。
賃貸物件はあらかじめ決まったデザインや設備が備わっており、自由に変更することができない場合がほとんどです。
たとえば、壁の色を変えたりキッチンやお風呂・トイレのリフォームなどは勝手にできません。
また賃貸物件の場合、退去時には原状回復が必要になるので、自己負担で改装しても撤去しなければならないので、さらにコストがかかります。
自分好みの間取りや設備を希望する人にとっては、賃貸物件は自由度が低いと感じる可能性があります。
家賃を払う賃貸物件に住み続ける場合に考えられるリスクは?
毎月家賃を払って賃貸物件に住み続ける場合に起こりうるリスクは次のとおりです。
- 老後に考えられるコスト
- 高齢になって賃貸物件を借りるときに気を付けること
老後に考えられるコスト
賃貸物件に住み続け間は、常に毎月の家賃支払いが続きます。
老後は年金を受給して生活する人が多いので、一般的には現役時代よりも収入が少なくなります。そのため、現役時代と比較して家賃の負担が大きくなる可能性があります。
また賃貸物件に住み続ける場合、退職後の年金収入だけで家賃を支払えるかを確認する必要があります。
さらに、加齢に伴いバリアフリーなどの住環境の改善が必要になった場合には、住み替えのための引っ越し費用や、新しい物件の敷金・礼金なども必要になります。
加えて、家賃も不動産市場の物価変動や契約更新時の値上げが考えられるため、長期的な視点での計画が重要です。
高齢になって賃貸物件を借りるときに気を付けること
高齢者の賃貸契約では、年齢による入居制限や保証人の問題など、若い世代には考える必要がなかった課題があります。
たとえば、家賃保証会社の審査が通りにくくなったり、連帯保証人の確保が難しくなったりする点です。
さらに、バリアフリーや医療機関へのアクセスなど、生活環境面での条件もまた、若い世代の時に重視する必要がなかった面も検討する必要が出てきます。
できるだけ早いうちから、賃貸物件のメリットとデメリットを比較して、自分にとって最適な方法を検討することが大切です。
住宅ローンと賃貸に関してよくある質問
住宅ローンと賃貸契約に関してよくある質問と回答を紹介します。
- 住宅ローンの支払いが「家賃より安い」は本当?
- 住宅ローンを借りたまま賃貸物件にだせる?
住宅ローンの支払いが「家賃より安い」は本当?
結論からいうと、住宅ローンの月々の支払額が家賃より安いように見えても、実際の総負担額を考えると、それほど大きな差はありません。
住宅ローンは長期間の返済を前提としており、金利によっては月々の支払い額が家賃と大差ないことがあるのです。
たとえば都市部のマンションを購入した場合、ローンによる支払い額と賃貸の家賃がほぼ同額になることも珍しくありません。
さらに、住宅ローンを組んでマイホームを購入すると、ローンを完済すればいずれ資産となる点が賃貸物件と大きく異なる点です。
将来性や資産性など考えて、最終的には賃貸契約の方が総居住費が高くなる可能性も考慮して比較することが大切です。
住宅ローンを借りたまま賃貸物件にだせる?
住宅ローンを借りたまま物件を賃貸に出すことは可能ですが、いくつかの条件があります。
住宅ローンは通常、自己居住用として借り入れるので、賃貸物件として貸し出すなら借入先の金融機関に相談をして承諾を得るのが必要です。
転勤や進学などの事情で引っ越す場合、月々の家賃収入が住宅ローンの返済額を上回ることが説明できれば、比較的通りやすいです。
さらに家賃収入が住宅ローンの返済以外にも賃貸管理費や修繕費などの費用にも充てられれば、経済面での負担も少なく済みます。
ただし、確定申告や管理費用を含め収支計画を立てないと、家賃収入だけでは足りない事態になるので注意が必要です。
住宅ローンか賃貸がいいか疑問を解消する方法とは?
住宅ローンを組んでマイホームを購入するか、賃貸物件を契約して毎月家賃を支払うか自分に合っているを決めるのは難しいです。
それは個々人の経済状況や家族構成・人生設計によってもベストな答えが異なるからです。
そのため、何を重視して比較すればいいかわからない・何から始めればいいか見つけられない人もいます。
そこで、住宅ローンの検討方法や家計の見直しなどをトータルに相談できるマネーキャリアの利用がおすすめです。
自分には住宅ローンを組むべきか、賃貸の方があっているのかの相談ができます。
専門性と満足度のどちらも兼ね備えたファイナンシャルプランナーが無料で何度でも相談に乗ってくれます。
住宅ローンと家賃の支払いどっちがお得かを無料で相談:マネーキャリア

住宅ローンに関する全ての悩みにオンラインで解決できる
マネーキャリア:https://money-career.com/
<マネーキャリアのおすすめポイントとは?>
・お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、住宅ローンに知見の豊富な、ファイナンシャルプランナーのプロのみを厳選しています。
・もちろん、住宅ローンだけではなく、資産形成や総合的なライフプランの相談から最適な解決策を提案可能です。
・マネーキャリアは「丸紅グループである株式会社Wizleap」が運営しており、満足度98.6%、相談実績も100,000件以上を誇ります。
<マネーキャリアの利用料金>
マネーキャリアでは、プロのファイナンシャルプランナーに「無料で」「何度でも」相談できるので、相談開始〜完了まで一切料金は発生しません。

まとめ:住宅ローンと家賃の特徴と違いを知って納得のいく物件を探そう
今回は住宅ローンと賃貸のメリット・デメリットからわかる特徴について詳しく解説しました。
住宅ローンの返済と家賃の支払いは、条件にもよりますが大きな差が出ない場合もあります。
そのため、自分のライフスタイルや収入・好み・家族構成によって最適な方法は異なります。
しかし、比較・検討すべきことが多く複雑になりやすいので、自力で比較するのは難しい・時間がかかるという人も多いです。
そんな人には、住宅ローンと賃貸の比較をはじめ、長期的な資産計画や家計の見直しなどを相談できるマネーキャリアの利用をおすすめします。
マネーキャリアは、LINEを使えばたったの30秒で完了し、相談料無料・回数制限なしなので、納得いくまで相談できます。