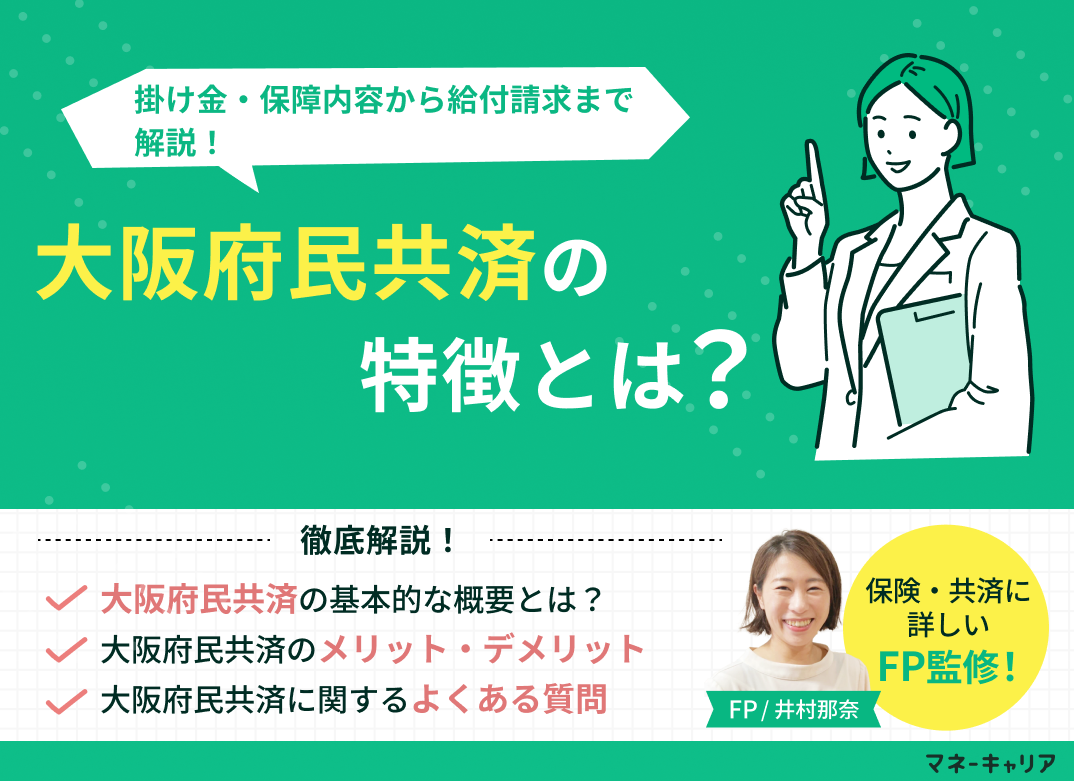私学共済事業団によって運営される私学共済の積立貯金は高金利で安全性が高いと言われる一方で、手続きの煩雑さや年2回しか申込みができないなどの制約があることも事実です。
内容をまとめると
- 私学共済積立貯金は手続きが煩雑で学校経由が必須、申込期間が年2回のみと限定的、オンラインサービスも制限されているというデメリットがある
- また、銀行預金のようなペイオフ制度の対象外であるというリスク面も理解しておく必要がある
- デメリットはあるものの、銀行預金より高い利率と元本保証、月1,000円から始められる少額投資という魅力的なメリットがあるが、同時に保障内容についても考えう必要がある。
- そのため、将来の保障や今の自分にかかる保障や私学共済のデメリットに懸念がある場合、マネーキャリアのような「専門家に無料で何度でも共済や保険について相談できるサービス」を使う人も増えている

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 私学共済の積立貯金とは?
- 私学共済の積立貯金の仕組み
- 対象者と加入条件
- 積立方法と金額設定
- 私学共済積立貯金の4つのデメリット
- デメリット1:手続きが煩雑で学校経由が必須
- デメリット2:申込期間が年2回と限定的
- デメリット3:オンラインで運用実績が確認ができない
- デメリット4:ペイオフ制度の対象外という点
- 私学共済積立貯金の4つのメリット
- メリット1:銀行預金と比較して高い利率
- メリット2:安全性の高さと元本保証
- メリット3:1,000円から始められる少額投資
- メリット4:柔軟な払い戻し制度
- 私学共済積立貯金の具体的な利用方法
- 申込手続きの流れ
- 積立額の変更・中断・復活方法
- 払い戻し・解約の手順
- 私学共済積立貯金はこんな人におすすめ
- 安全志向の初心者投資家
- 将来のライフイベントにかかるお金を準備中の方
- 自動積立で貯蓄習慣を身につけたい方
- 私学共済の積立貯金に関するよくある質問とは
- Q1:積立貯金を始めるタイミングはいつがベスト?
- Q2:退職時の手続きはどうすればいい?
- Q3:積立額の上限はある?
- Q4:私学共済の積立貯金の安全性は本当に高い?
- Q5:積立貯金と財形貯蓄はどう違う?
- 将来の保障全般の悩みを簡単に解消する方法とは?
- 私学共済積立貯金のメリット・デメリットまとめ
私学共済の積立貯金とは?
私学共済の積立貯金の仕組み
対象者と加入条件
積立方法と金額設定
私学共済の積立貯金は、毎月の給与から自動的に天引きされる方式で積み立てられます。
具体的には、1,000円から1,000円単位で金額を設定でき、上限は月額10万円までとなっています。
したがって、自分の経済状況に合わせて柔軟に積立額を決められるのが大きな特徴です。
私学共済積立貯金の4つのデメリット
以下では、私学共済積立貯金の5つの主要なデメリットについて詳しく解説します。
私学共済の積立貯金には多くのメリットがある一方で、いくつかの注意すべきデメリットも存在します。
特に手続きの煩雑さや利率の問題は、加入前に知っておくべき重要なポイントです。
デメリット1:手続きが煩雑で学校経由が必須
私学共済の積立貯金は、すべての手続きが学校経由で申し込む必要があります。
このような仕組みになっている理由は、私学共済制度が学校単位で管理されているためです。
例えば、新規申込みや払い戻しの際には、必ず所属機関の事務担当者に申請書を提出し、承認を得なければなりません。
そのため、急いでお金が必要な場合でも即日対応が難しいと言えます。
デメリット2:申込期間が年2回と限定的
私学共済積立貯金の新規申込みや積立額の変更は、年に2回(4月と10月)しかできません。
例えば、急に資金計画が変わって積立額を増やしたいと思っても、申込期間外では対応できません。
つまり、高頻度で資金管理を望む方にとっては、この時期的制約が不便に感じられるでしょう。
デメリット3:オンラインで運用実績が確認ができない
私学共済積立貯金では、オンラインでの残高確認や取引ができないという不便さがあります。
残高を確認するには通知を待つか、学校の事務局を通じて問い合わせる必要があります。
したがって、日常的に資産状況を把握したい方にとっては大きな不便を感じるポイントとなっています。
デメリット4:ペイオフ制度の対象外という点
私学共済積立貯金は、銀行預金で適用されるペイオフ制度の対象外となっています。
これは、私学共済積立貯金が預金保険機構ではなく、私学共済事業団によって運営されているためです。
例えば、万が一の事態が発生した場合、銀行預金のような公的保護制度の対象とはならない可能性があるので、リスク分散の観点からは、全ての資産をこの制度に預けることには慎重になるべきと言えます。
私学共済積立貯金の4つのメリット
以下では、私学共済積立貯金の4つの主要なメリットについて詳しく解説します。
これらのメリットを活用することで、効率的な資産形成が可能になります。特に銀行預金と比較した際に、多くの教職員が積極的に利用する理由となっています。
メリット1:銀行預金と比較して高い利率
私学共済積立貯金は、一般的な銀行の定期預金と比較して高い利率となっています。
例えば、現在の利率は約0.35%程度で、大手銀行と比較すると0.1%ほど高いです。
また、長期間積み立てることで、複利効果による資産増加が期待できます。
メリット2:安全性の高さと元本保証
私学共済積立貯金は、元本が100%保証されている金融商品です。
たとえば、株式投資などのリスク資産と異なり、元本割れの心配がなく安心して資金を預けられます。
つまり、リスクを取りたくない教職員にとって、最適な資産運用先の一つと言えます。
メリット3:1,000円から始められる少額投資
私学共済積立貯金は、月々1,000円という少額から始められる敷居の低さが魅力です。
そのため、初任給で生活が不安定な若手教員でも無理なく始められ、徐々に金額を増やしていくことができます。
このように、貯蓄初心者にとっても取り組みやすい資産形成の第一歩となります。
メリット4:柔軟な払い戻し制度
私学共済積立貯金は、必要に応じて柔軟に払い戻しを受けられる制度設計になっています。
この柔軟性がある理由は、加入者のライフイベントに対応できるよう配慮されているからです。
例えば、一部払い戻しの場合は手数料がかからず、必要な分だけ引き出すことが可能です。
つまり、急な出費が必要になった場合でも、全額解約せずに対応できる点がメリットです。
私学共済積立貯金の具体的な利用方法
ここでは、私学共済積立貯金の具体的な手続き方法について解説します。
私学共済積立貯金を最大限に活用するためには、具体的な利用方法を理解することが重要です。
申込みから払い戻しまでの一連の流れを把握しておくことで、スムーズに制度を利用できます。
申込手続きの流れ
私学共済積立貯金の申込みは、所定の申込書を学校の事務局に提出することから始まります。
このような手続きが必要な理由は、給与からの天引きを行うために雇用先の承認が必要だからです。
例えば、4月または10月の申込期間中に、希望する積立金額を記入した申込書を提出します。そして、申込みが承認されると翌月から自動的に給与から積立が開始されるという流れです。
※参照:積立貯金のご案内|私学共済事業団
積立額の変更・中断・復活方法
私学共済積立貯金の積立額は、ライフステージに合わせて変更することができます。
たとえば、昇給時には増額申請を、家族が増えて支出が増えた場合には減額申請を行うことができます。
また、一時的に積立を中断し、経済的余裕ができたときに復活させることも可能です。
払い戻し・解約の手順
私学共済積立貯金の払い戻しや解約は、専用の請求書を学校の事務局に提出して行います。
一部払い戻しの場合は「積立貯金払戻請求書」を、全額解約の場合は「積立貯金解約請求書」を提出します。
そして、審査後に指定の銀行口座に払い戻し金が振り込まれるという流れになります。
私学共済積立貯金はこんな人におすすめ
ここでは、特に私学共済積立貯金が向いている人のタイプを紹介します。
私学共済積立貯金は、すべての教職員に適しているわけではなく、それぞれの金融目標や性格によって、最適な活用方法は異なります。
安全志向の初心者投資家
私学共済積立貯金は、投資初心者や安全志向の強い方に特におすすめです。
このタイプの方に適している理由は、元本保証されていて投資リスクがほとんどないからです。
例えば、株式投資の値動きに不安を感じる方や、資産運用の第一歩を踏み出したい方にとって心理的ハードルが低いといえます。
つまり、リスクを考慮しながらも、銀行預金よりは効率的に資産を増やしたい方に最適な制度といえます。
将来のライフイベントにかかるお金を準備中の方
私学共済積立貯金は、数年以内に具体的なライフイベントを控えている方に適しています。
安全に資金を貯めながらも、必要時に柔軟に引き出せる仕組みなので、引き出したいときに引き出せる点は大きな強みです。
例えば、結婚資金や住宅の頭金、子どもの教育費など、数年後に大きな出費が予定されている場合などに安心です。
とくに、目標金額と期間が明確な方にとって、計画的な資金準備の手段として活用できます。
自動積立で貯蓄習慣を身につけたい方
私学共済積立貯金は、貯蓄習慣を確立したいと考えている方にもおすすめです。
私学共済は給与からの天引きになるので、意識せずとも自動的に貯蓄が進みます。
「貯金しようと思っても月末には使ってしまう」という方でも、強制的に貯蓄にお金が回るので、「貯める前に使う」のではなく「使う前に貯める」という習慣を身につけたい方にも向いています。
私学共済の積立貯金に関するよくある質問とは
私学共済積立貯金について、下記で多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめています。
これらの質問は実際に教職員から比較的多く寄せられるものなので、ぜひ参考にしましょう。
Q1:積立貯金を始めるタイミングはいつがベスト?
私学共済の積立貯金は、できるだけ早く始めることが最も効果的です。
早期開始がおすすめな理由は、複利効果により長期間積み立てるほど資産が効率的に増えるからです。
例えば、20代で始めた場合と40代で始めた場合では、同じ積立額でも最終的な資産額に大きな差が生じます。
したがって、私立学校に就職したらすぐに申込期間(4月か10月)に合わせて申し込むのがベストタイミングです。
Q2:退職時の手続きはどうすればいい?
私学共済積立貯金は、退職時に自動的に解約されるわけではなく、手続きが必要です。
この手続きが必要な理由は、退職後も継続して積立を希望するケースもあるからです。
仮に、退職時に全額解約を希望する場合は「積立貯金解約請求書」を、継続を希望する場合は「積立貯金継続申出書」を提出します。
つまり、退職前に必ず学校の事務局に相談し、自分の希望に合った手続きを行うことが重要です。
Q3:積立額の上限はある?
私学共済積立貯金には、月額10万円という積立上限が設定されています。
例えば、月々10万円を積み立てた場合、年間では120万円となり、多くの教職員にとって十分な貯蓄額となります。
そのため、より多額の資産運用を希望する場合は、他の金融商品と併用することを検討すべきです。
Q4:私学共済の積立貯金の安全性は本当に高い?
私学共済積立貯金は一般的な金融商品と比較すると、元本割れのリスクが少ないといえます。
たとえば、通常の金融機関が提供する金融商品と比べて、金融機関の破綻リスクや、為替変動のリスクを心配する必要はほとんどなく、安心して資金を預けられる制度と言えます。
Q5:積立貯金と財形貯蓄はどう違う?
両者の違いが生じる理由は、運営主体と対象者が異なります。
財形貯蓄は一般企業の従業員向けで金融機関が運営するのに対し、私学共済積立貯金は私立学校教職員向けで私学共済事業団が運営します。
私学共済積立貯金の方が利率が高く、私立学校教職員にとってはより有利な制度と言えるでしょう。
将来の保障全般の悩みを簡単に解消する方法とは?
私学共済積立貯金は資産形成の一手段ですが、将来の保障を考える上では私学共済だけでは不足するケースがあります。
実際に、老後資金や万一の備えなど不安を抱える教職員の方も多い一方、こうした悩みを一人で解決するのは難しく、インターネット上にも情報があまりありません。
そのため、ファイナンシャルプランナーなど、教職員の状況を理解した専門家に相談することで、より効果的な資産形成と保障の両立ができるようになるのです。
そこで、マネーキャリアのように「プロのFPに納得いくまで何度でも無料で相談できるサービス」を使うと、将来の保障はもちろん、家計やお金周りの不安もまとめて解消できます。

共済に関するすべての悩みにオンラインで解決できる
マネーキャリア:https://money-career.com/
<マネーキャリアのおすすめポイントとは?>
・お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、共済や民間の生命保険に知見の豊富な、ファイナンシャルプランナーのプロのみを厳選しています。
・もちろん、共済や民間の生命保険だけではなく、資産形成や総合的なライフプランの相談から最適な解決策を提案可能です。
・マネーキャリアは「丸紅グループである株式会社Wizleap」が運営しており、満足度98.6%、相談実績も100,000件以上を誇ります。
<マネーキャリアの利用料金>
マネーキャリアでは、プロのファイナンシャルプランナーに「無料で」「何度でも」相談できるので、相談開始〜完了まで一切料金は発生しません。
私学共済積立貯金のメリット・デメリットまとめ
私学共済積立貯金は、上手に活用することで私立学校教職員の資産形成を強力にサポートする制度です。
メリットとデメリットを理解し、自分の状況に合わせた活用法を見つけることが重要ですが、長期的な視点で積立を続けることが大切です。
一方、私学共済のみで将来の万が一に備えるには、保障が不足していたり、資産形成において効率的でなかったりするケースもあります。
そこで、マネーキャリアのようにプロのFPに何度でも無料相談できるサービスを活用して、「保障と資産形成」を両立する教職員の方も増えています。
無料相談予約は30秒で完了するので、ぜひマネーキャリアを使い、将来の保障やお金に関わる不安を解消しましょう。