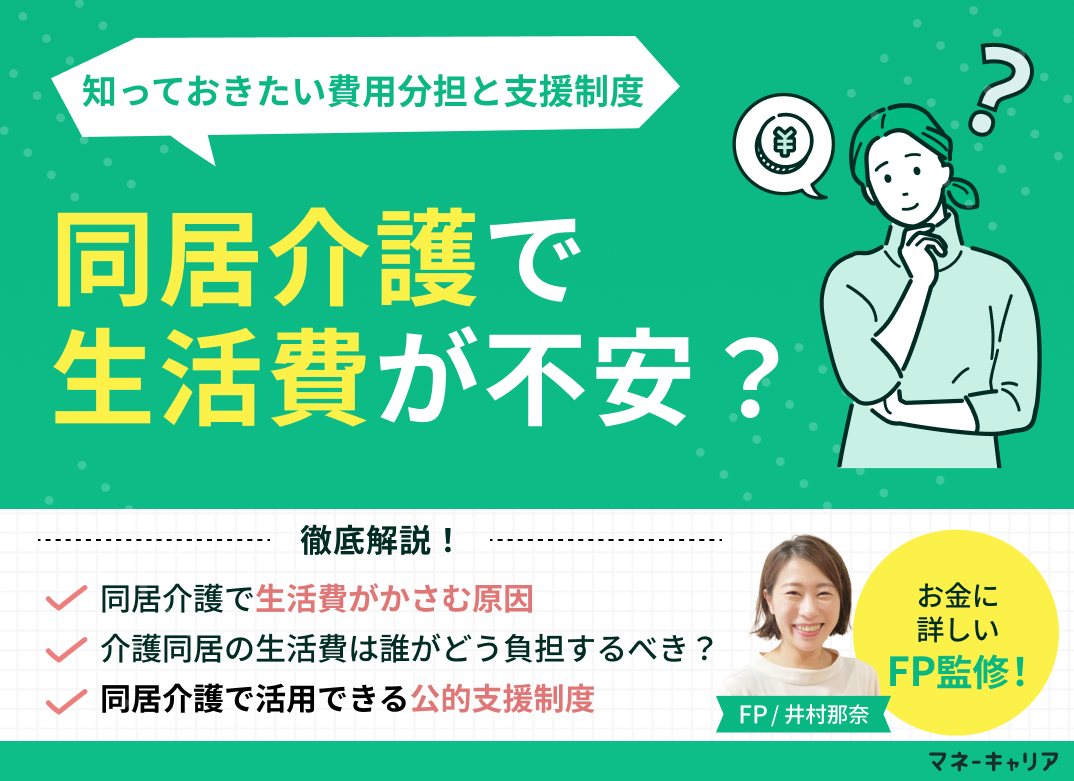
内容をまとめると
- 同居介護で生活費がかさむ原因には、家計の負担割合が不明確になっていることや公共料金や通信費の無駄が多いこと、介護サービスの利用調整ができていないなどの原因が考えられます。
- 介護同居の生活費は、親と子で生活費を分けるか、親の年金や貯金を使用していくケースが一般的です。
- 介護同居の生活費で揉めないためには、プロを交えて話をしたり、あらかじめ必要な金額を可視化しておくことが重要です。
- そんな時、マネーキャリアなら家計の見直しや介護にかかる費用の分担方法、将来を見据えたライフプランの整理まで、中立的な立場の専門家が無料でサポートしてくれます。

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 同居介護で生活費がかさむ原因
- 家計の負担割合が不明確になっている
- 公共料金や通信費の無駄が多い
- 介護サービスの利用調整ができていない
- 介護同居の生活費は誰がどう負担するべき?
- 親と子で生活費を分けるケース
- 親の年金や貯金を使用していくケース
- 介護同居の生活費で揉めないために必要なこと
- 同居介護で活用できる公的支援制度
- 介護保険制度
- 医療費助成・高額療養費制度
- 住宅改修や福祉用具貸与の支援制度
- 介護費と生活費に活用できる税制優遇
- 扶養控除や障害者控除
- 医療費控除
- 介護同居の生活費に関するよくある質問
- 親の年金だけで生活はできる?
- 兄弟が費用負担をしてくれない場合はどうしたらいい?
- 生活保護の対象になるケースとは?
- 介護同居の生活費に悩んだ際に使うべき方法とは?
- 介護同居の生活費についてまとめ
同居介護で生活費がかさむ原因
親との同居で介護をする生活が始まると、「思っていたより生活費が増えた」と感じる方は少なくありません。
介護そのものの負担だけでなく、日常生活にかかる支出もじわじわと家計にのしかかってくるため、無意識のうちに家計が圧迫されているケースもあります。
ここでは、同居介護で生活費がかさむ主な原因について解説します。支出が増える理由を正しく理解することで、無駄の見直しや負担の分担につなげやすくなります。
- 家計の負担割合が不明確になっている
- 公共料金や通信費の無駄が多い
- 介護サービスの利用調整ができていない
家計の負担割合が不明確になっている
同居介護における生活費負担の大きなトラブル原因のひとつが、「誰が何を負担するのか」が曖昧になっていることです。
とくに、光熱費・食費・日用品費などの「共有支出」は、家族の人数や使用頻度が増えることで増加しやすく、明確なルールがないまま誰か一人がまとめて支払っていると、不満の原因になります。
「親の年金からどこまで出すか」「子世帯の生活費とどう分けるか」といった費用分担の基準がないと、気づけば一方的な負担になってしまうこともあります。
さらに、兄弟姉妹との関係性や相続問題にも発展しかねません。生活費がかさんできたと感じたら、まずは支出の内訳を「見える化」し、話し合いで役割分担を整理することが大切です。
可能であれば、第三者(ファイナンシャルプランナーなど)を交えて中立的に整理すると、感情的な対立を避けることができます。
公共料金や通信費の無駄が多い
同居によって家族の人数が増えると、食費はもちろん、水道光熱費や通信費などの固定費が自然と増加します。
特に介護が必要な高齢者の場合は、冷暖房をつける時間が長くなったり、テレビや照明を常時使用していたりと、電気代がかさみやすい傾向があります。
また、通信費についても、親世代と子世代で契約がバラバラのまま放置されているケースが多く、不要な契約や重複しているサービスに気づかず支払っていることも少なくありません。
「親と同居してから支出が増えた」と感じた場合は、まず固定費を一つずつ点検してみることをおすすめします。
支出の増加は、日々の習慣が生み出していることも多いため、一度暮らし全体を俯瞰して見直してみることをおすすめします。
介護サービスの利用調整ができていない
介護が必要な状態になっても、「できるだけ家族で支えたい」と考える人は多くいます。
しかし、その思いが強すぎると、必要以上に自宅介護に頼ってしまい、家族の時間や労力、結果的にお金も消耗するという事態に陥ることがあります。
たとえば、デイサービスや訪問介護などの介護保険サービスをうまく使えば、費用を抑えながら介護の負担を軽減できますが、「使い方がよくわからない」「もったいない気がして遠慮している」といった理由で活用できていないケースも少なくありません。
また、要介護認定の申請が遅れてしまったり、ケアマネジャーとの連携が不十分で、自費サービスに頼ってしまっていることも、生活費の増加につながります。
公的サービスを上手に組み合わせて介護の効率化を図ることは、金銭面・精神面の両方でメリットがあります。
地域包括支援センターやケアマネジャーに相談しながら、「介護の仕組み」を見直すことも、生活費の最適化につながる大事な視点です。
介護同居の生活費は誰がどう負担するべき?
親との同居介護が始まると、気になるのが「生活費を誰が、どのように負担するか」という問題です。
介護にかかるお金だけでなく、食費や光熱費、日用品などの日常的な支出も増えるため、事前に話し合いができていないと、「なんとなく負担している」「自分だけが支払っている」といった不満が生じやすくなります。
ここでは、同居介護における生活費の負担方法としてよく見られる2つのケースを紹介します。
- 親と子で生活費を分けるケース
- 親の年金や貯金を使用していくケース
親と子で生活費を分けるケース
最もトラブルが少ないのが、「生活費を親と子で明確に分担する」という方法です。
たとえば、食費や水道光熱費などの共有費は折半にする、またはそれぞれが決まった金額を出し合って共通財布で管理するといったやり方が一般的です。
親がまだある程度の収入や年金を得ている場合、金銭的にも分担がしやすく、お互いの負担感が減るというメリットがあります。
たとえ金額のバランスに差があっても、「どこを誰が支払うか」という線引きが明確であることで、感情的なトラブルが起きにくくなります。
ただし、家計を完全に分けるのではなく、「日用品は子世帯」「光熱費は親」など、家庭ごとに負担内容を柔軟に決めることも大切です。
家計簿アプリや簡単な一覧表などで定期的に支出を見える化することが、円滑な同居介護を続けるうえで大きな助けになります。
親の年金や貯金を使用していくケース
親が要介護の状態にある場合、本人の年金や貯金を活用して生活費や介護費をまかなうというケースも多く見られます。
とくに、子世帯に経済的な余裕がない場合は、親の年金収入をベースに生活を組み立てていくことが現実的な選択となります。
この方法のメリットは、子世帯の金銭的な負担を抑えられることにありますが、一方で注意が必要なのが「お金の使い道を家族内で共有しておくこと」です。
親の財産を管理する立場になると、他の兄弟姉妹とのトラブルが生じることもあるため、使途や金額はしっかり記録しておくことが大切です。
また、親の資産状況によっては「あと何年持つか」をシミュレーションしておく必要もあります。
介護期間が長期化すれば、年金や預貯金だけでは足りなくなる可能性もあるため、早めにプロのアドバイスを受けておくこともおすすめです。
今後、医療や介護にかかる費用が増えることを見越して、支援制度や介護保険の活用も同時に検討しながら、家族で協力して持続可能な生活設計を行いましょう。
介護同居の生活費で揉めないために必要なこと
介護をきっかけに親との同居が始まると、避けて通れないのが「生活費の分担」をめぐる問題です。
特に、親の年金や貯金をどこまで使うのか、子世帯がどれだけ負担するのかなど、金銭的な役割分担を曖昧にしたまま生活をスタートさせると、のちのち深刻な揉め事に発展する可能性があります。
生活費で揉めないために最も大切なのは、「お金の話を遠慮せず、具体的に言葉にすること」です。
たとえば、食費・光熱費・介護雑費などを洗い出し、親の年金や子世帯の収入からどれくらい支出するのかを一覧表などにして共有します。
紙でも家計アプリでも構いませんが、数字を見える化することで、お互いの負担感や認識のズレを防げます。
また、兄弟姉妹がいる場合は、「誰がどの役割を担っているのか」「支援が必要ならどう分担するのか」なども明確にしておくことが大切です。
実際に介護を担っている人と、遠方に住む家族との温度差がトラブルの火種になるケースは少なくありません。
話し合いの場では、「誰が悪い」というスタンスではなく、「どうすれば皆が無理なく続けられるか」を軸にすることが重要です。
感情的な議論を避けるためにも、ファイナンシャルプランナーや地域包括支援センターといった第三者を交えたミーティングを活用すると、冷静かつ建設的な対話がしやすくなります。
介護は一時的な出来事ではなく、数年単位で続くライフイベントです。
だからこそ、家族全体で話し合い、納得できるルールを早期に整えることが、生活費トラブルを回避するカギとなります。
同居介護で活用できる公的支援制度
同居での介護が始まると、生活費だけでなく医療費や設備費など、思った以上に出費がかさみます。
国や自治体が用意している制度をうまく活用すれば、介護や医療にかかる費用の大部分をカバーできることもあります。
ここでは、同居介護を続けるうえで知っておきたい代表的な支援制度を紹介します。
- 介護保険制度
- 医療費助成・高額療養費制度
- 住宅改修や福祉用具貸与の支援制度
介護保険制度
要介護(または要支援)認定を受けた高齢者が利用できるのが介護保険制度です。
制度を利用することで、訪問介護・デイサービス・ショートステイ・福祉用具のレンタルなど、さまざまな介護サービスを原則1割〜3割の自己負担で受けられます(所得によって異なります)。
同居での介護の場合、「できるだけ家でみたい」という想いがあっても、家族だけで介護を続けるのは身体的・精神的にも限界があるものです。
介護保険サービスを取り入れることで、家族の負担を軽減しながら、必要なケアを受けることができます。
利用には、自治体での要介護認定の申請と、ケアマネジャーによるケアプランの作成が必要です。
早めに地域包括支援センターなどに相談し、スムーズに制度利用を開始できるよう準備しておきましょう。
参照:厚生労働省
医療費助成・高額療養費制度
高齢の親が慢性疾患や入退院を繰り返すと、介護と並行して医療費の負担も家計に重くのしかかります。そんなときに活用したいのが、高額療養費制度です。
この制度は、月々の医療費が一定額を超えた場合に、自己負担限度額を超えた分が払い戻される仕組みです。
収入に応じて上限額は異なりますが、突然の入院などで大きな支出があったときにも、後から戻ってくる安心感があります。
また、住んでいる自治体によっては、高齢者や障害者に対する医療費助成制度が設けられている場合もあります。
住民税非課税世帯や低所得世帯を対象に、医療費の助成や補助が受けられることもあるため、事前に市区町村の窓口で確認しておくべきです。
介護と医療の出費は密接に関わってくるため、「医療費の補助制度」も併せてチェックすることが家計管理の鍵となります。
参照:厚生労働省
住宅改修や福祉用具貸与の支援制度
同居介護では、親の移動や入浴、排泄の介助が必要になる場面も多く、自宅のバリアフリー化や介護用設備の導入が必要です。
その際に利用できるのが、介護保険制度内の住宅改修費の支給や福祉用具貸与(レンタル)制度です。
住宅改修については、手すりの設置や段差解消、床材の変更などにかかる費用を上限20万円まで(自己負担1〜3割)補助してくれる制度があります。
介護保険の認定を受けたうえで、事前にケアマネジャーを通じて申請・施工を行うことが必要です。
また、福祉用具貸与では、ベッド・車いす・歩行器・ポータブルトイレなどが月額数百円〜数千円でレンタル可能です。購入せずに済むため、経済的負担を大きく軽減できます。
介護環境を整えることで、介護する側・される側の両方にとって安全で快適な暮らしが実現します。
必要に応じて、地域のケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談しながら進めると安心です。
参照:厚生労働省
介護費と生活費に活用できる税制優遇
親との同居介護にかかる費用は、生活費・医療費・介護費など多岐にわたり、家計への負担も大きくなります。
そんな中で見落としがちなのが、税制面での優遇制度です。
実は、適切に申告することで税金の負担を減らし、家計にゆとりをもたらすことが可能です。
ここでは、介護と生活に関わる代表的な税制優遇について解説します。
- 扶養控除や障害者控除
- 医療費控除
扶養控除や障害者控除
親と同居していて、主に自分が生活費や介護費を負担している場合は、「扶養控除」や「障害者控除」を受けられる可能性があります。
まず、扶養控除は、所得税や住民税の負担を軽くできる制度で、条件を満たす親を「控除対象扶養親族」として申告することで適用されます。
特に70歳以上の親を扶養している場合は、控除額は最大で58万円(同居老親の場合)になることもあります。
さらに、要介護認定や身体障害者手帳を所持している親については、「障害者控除」や「特別障害者控除」の対象になる場合もあります。
これにより、さらに27万円〜40万円の所得控除を受けられることが可能です。
これらの控除は、年末調整や確定申告での申告が必要です。
「親を扶養に入れていなかった」「障害者手帳があるのに控除を使っていない」など、知らないうちに損していたという人も少なくありません。ぜひ早めに確認しておきましょう。
参照:国税庁
医療費控除
介護と同時にかかってくるのが医療費の負担、特に同居する親の通院・治療・医薬品の購入費がかさむと、出費が家計を圧迫してしまいます。
そんな時に使えるのが、医療費控除という制度です。
医療費控除は、1年間に支払った自己負担の医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合に、確定申告で所得控除を受けられる制度です。
親の医療費でも、家計を同一にしていれば「家族の分もまとめて申告」することが可能です。
対象となるのは、診療費や入院費のほか、通院のための交通費(公共交通機関のみ)、薬代、訪問看護や一部の介護サービスなども含まれます。
意外と見落とされがちですが、介護保険サービスの自己負担分(1〜3割)も医療費控除の対象となるケースがあります。
日々のレシートを保管し、年末に集計するだけでも節税につながるため、こまめに記録しておくと安心です。
参照:国税庁
介護同居の生活費に関するよくある質問
親との同居介護が始まると、日々の生活費や介護費用が想像以上にかさみ、「このままでやっていけるのだろうか」と不安を感じる方は少なくありません。
特に、年金収入や兄弟間での費用分担、さらには生活保護の対象になるかどうかなど、身近でありながらも判断が難しいテーマが多くあります。
そこでここでは、介護同居に関して寄せられることの多い代表的な質問を取り上げ、それぞれの状況に応じた考え方や対処法を紹介します。
生活費の不安を軽減するためにも、正しい情報をもとに準備と対策を進めていくべきです。
- 親の年金だけで生活はできる?
- 兄弟が費用負担をしてくれない場合はどうしたらいい?
- 生活保護の対象になるケースとは?
親の年金だけで生活はできる?
親の年金だけで同居生活をまかなえるかどうかは、親の年金額と家族構成、そして必要な支出の内容によって大きく異なります。
一般的に高齢者一人あたりの年金受給額は月10万円〜15万円ほどとされており、これだけで生活費・医療費・介護費をまかなうのは難しいケースが多いのが現実です。
同居介護では、食費や光熱費などの生活費が家族全体で増えるうえ、介護にともなう出費(通院、福祉用具、在宅サービスなど)も積み重なります。
親の年金だけに頼ってしまうと、子世帯の家計を圧迫しかねません。
そのため、年金をベースにしつつ、不足分は誰がどのように補うのか、あらかじめルールを決めておくことが大切です。
また、税制優遇や介護保険サービスの活用、公的支援制度なども視野に入れて、必要な支出を抑える工夫をすることも現実的な対策です。
兄弟が費用負担をしてくれない場合はどうしたらいい?
介護に関わる費用や労力が一部の家族に偏ることはよくあります。
特に、実際に同居して介護を担っている側が生活費や介護費をほぼ全額負担しており、離れて暮らす兄弟姉妹が協力的でないというケースも少なくありません。
こうした状況で一番大切なのは、「感情ではなく数字で話す」ことです。
たとえば、月にかかっている食費、医療費、介護関連の出費などを具体的にリスト化し、それを共有することで、現実的な負担の大きさを可視化できます。
それでも費用分担が難しい場合は、実費分を「将来の相続時に清算する」ことや、「労力と費用の役割を分ける」といった取り決めを検討することも可能です。
また、家庭内での話し合いが難しい場合は、第三者であるケアマネジャーや地域包括支援センター、ファイナンシャルプランナーなどを交えて相談すると、冷静な対話がしやすくなります。
家族間の負担が偏りすぎると、介護の継続が困難になるため、早めに話し合いの場を持つことが重要です。
生活保護の対象になるケースとは?
親との同居介護を続ける中で、「もう家計が限界」と感じたとき、最終的な選択肢として頭をよぎるのが生活保護かもしれません。
生活保護は、最低限度の生活を維持することが難しい人に対して、国が生活費や医療費を補助する制度です。
ただし、生活保護の受給には一定の条件があり、資産や収入の有無、扶養義務者(子どもなど)の支援状況などが審査対象となります。
親自身に十分な年金や貯金がなければ、生活保護の申請は可能ですが、同居している子世帯の収入や資産も調査されるため、すぐに受給が認められるとは限りません。
とはいえ、生活保護を申請すること自体に制限はないため、「もう支出が限界」「どこにも頼れない」という場合には、一度地域の福祉事務所に相談するのが良いでしょう。
制度を使うことは恥ずかしいことではなく、生活を立て直すための一時的な支援として有効です。
また、生活保護に至る前に、他の公的支援(高額療養費制度、医療費助成、介護保険サービスなど)を活用できる場合もあるため、できるだけ早めに情報収集と対策を始めることをおすすめします。
参照:厚生労働省
介護同居の生活費に悩んだ際に使うべき方法とは?
ここでは、介護同居で家計が苦しくなったときに取るべき現実的な対処法をご紹介します。
「親の年金だけで足りない…」「支出ばかり増えて、生活費をどう見直せばいいかわからない」と悩む方は少なくありません。
ですが、将来的な介護の長期化や自身の老後資金への影響を考えると、今のうちに家計全体を見直し、必要な制度や控除を活用していくことが大切です。
そんな時は、お金の専門家と一緒に状況を整理できる「マネーキャリア」の活用がおすすめです。
マネーキャリアなら、相談はすべて無料です。中立的な立場で、介護・生活費・老後資金など、一人ひとりの家庭事情に合わせた具体的な改善策を提案してくれます。
担当FPの経歴や口コミも事前に確認できるため、安心して相談を始められます。スマホ一つで予約が完了するため、気軽に相談してみるべきです。

▼マネーキャリアの概要
- お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、年収や節税について知見の豊富な、ファイナンシャルプランナーのプロのみを厳選。
- 資産形成や総合的なライフプランの相談から最適な解決策を提案可能。
- マネーキャリアは「丸紅グループである株式会社Wizleap」が運営しており、満足度98.6%、相談実績も100,000件以上を誇る。

介護同居の生活費についてまとめ
介護をきっかけに親との同居が始まると、生活費・医療費・介護費用などの支出が一気に増加し、家計に不安を感じる方が少なくありません。
この記事では、費用がかさむ原因や支出の分担方法、使える税制優遇や公的支援制度について詳しく解説してきました。
同居介護は、感情面だけでなく経済面での負担も大きいため、あらかじめ必要な支出を見える化し、家族内での話し合いや制度の活用が欠かせません。
特に扶養控除や医療費控除など、使える制度を把握しておくだけでも、手元に残るお金に大きな違いが生まれます。
とはいえ、家計の見直しや支援制度の判断は家庭ごとに事情が異なるため、「うちの場合はどうしたらいいの?」という悩みには専門家の力を借りるのが安心です。
そんなとき頼りになるのが、「マネーキャリア」の無料相談サービスです。
介護や生活費の見直しに限らず、老後資金、保険、相続、税金など幅広いお金の相談に対応できる専門家が在籍しています。
中立的な立場で、一人ひとりの状況に合った提案をしてくれるため、初めての方でも安心です。




























