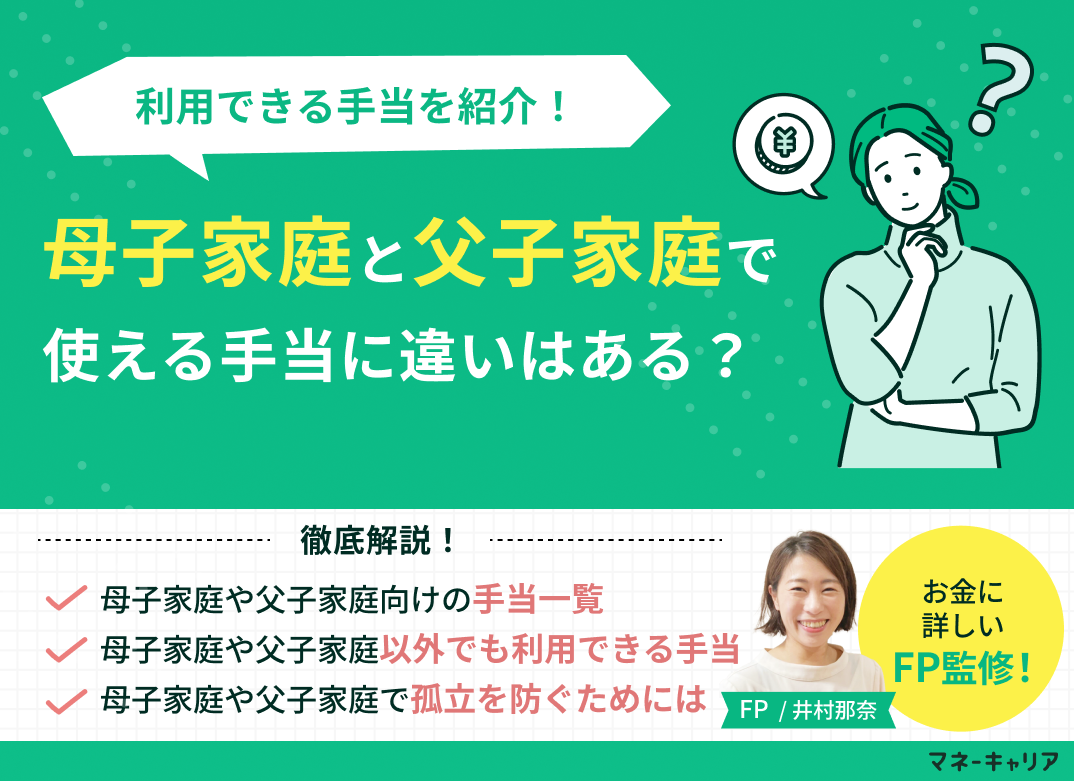
「母子家庭と父子家庭で受けられる手当って違うの?」
「全部知っておかないと損しそうで不安……」
そんな疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、基本的な手当は母子家庭も父子家庭も共通しています。
この記事では、母子家庭・父子家庭で受けられる手当の一覧や、それぞれの特徴・手当の申請方法や注意点を解説しますので、ぜひ参考にしてください。
・「どんな手当を受けられるのか整理したい」
・「申請漏れやもらい忘れを防ぎたい」
そんな方は、本記事を読むことで手当の全体像を把握し、家計の負担を軽くする具体的な方法がわかります。
内容をまとめると
- 母子家庭と父子家庭では受けられる手当は共通
- 児童扶養手当・医療費助成・住宅手当など複数の支援を受けられる
- 申請方法や地域差に注意が必要
- 孤立を防ぐには家事・育児支援や相談先を活用
- マネーキャリアでは手当や家計改善を無料で相談できる

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 母子家庭と父子家庭で受けられる手当に違いはある?
- 母子家庭や父子家庭向けの手当一覧
- 児童扶養手当
- ひとり親家庭等医療費助成制度
- 高等職業訓練促進給付金
- 住宅手当
- 保育料の軽減
- 母子家庭や父子家庭以外でも利用できる手当
- 児童手当
- 医療費制度
- 生活保護
- 特別児童扶養手当・障害児福祉手当
- 遺族年金
- 母子家庭や父子家庭で孤立を防ぐためには
- 家事・育児支援を積極的に活用
- 両親やきょうだいなど家族にも頼る
- 情報収集できる相談先を見つける
- 母子家庭と父子家庭の手当の違いに関する質問
- 手当の申請方法や注意点は?
- できる限り多く手当をもらうには?
- 地域によって支給額は異なる?
- 母子家庭や父子家庭で金銭的不安があるなら「マネーキャリア」に相談
母子家庭と父子家庭で受けられる手当に違いはある?
母子家庭と父子家庭で受けられる手当に違いはありません。
以前は母子家庭を優先する制度が存在していましたが、社会情勢の変化により格差は解消されました。
特に2010年8月1日に施行された「児童扶養手当法の一部を改正する法律」によって、児童手当が父子家庭も対象となった点は大きな進展です。
母子家庭や父子家庭向けの手当一覧
母子家庭や父子家庭向けの手当は多岐にわたります。
主な制度は以下のとおりです。
- 児童扶養手当
- ひとり親家庭等医療費助成制度
- 高等職業訓練促進給付金
- 住宅手当
- 保育料の軽減
それぞれの内容を見ていきましょう。
児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活を支えるために支給される制度です。
所得制限があり、子どもの人数や請求者の所得に応じて金額が加算されます。
たとえば、大阪市が給付している児童扶養手当の月額は以下のとおりです。
| 対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 1人目 | 46,690円 | 46,680円~11,010円 |
| 2人目以降 | 11,030円 | 11,020円~5,520円 |
参照:大阪市 児童扶養手当
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親と子どもの医療費の自己負担を軽減する制度です。
医療費の補助範囲は自治体ごとに異なりますが、通院や入院にかかる費用を抑えられます。
高等職業訓練促進給付金
高等職業訓練促進給付金は、資格取得を目指すひとり親を支援する制度です。
看護師や介護福祉士など、長期の専門教育が必要な職種への再就職を後押しします。
住宅手当
住宅手当は、賃貸住宅に住むひとり親家庭の家賃負担を軽減するための支援です。
支給額や上限は自治体により異なり、所得基準や家賃額の条件を満たす必要があります。
保育料の軽減
保育料の軽減制度は、子育てと仕事を両立させるひとり親家庭を支援するものです。
自治体の基準に基づき、保育料が一部または全額免除される場合があります。
母子家庭や父子家庭以外でも利用できる手当
母子家庭や父子家庭以外でも利用できる手当は複数あります。
主な制度は以下のとおりです。
- 児童手当
- 医療費制度
- 生活保護
- 特別児童扶養手当・障害児福祉手当
- 遺族年金
状況に応じて利用できる制度を組み合わせることで、家計の負担を軽減できます。
それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
児童手当
児童手当は、子どもの成長に伴う養育費を支援する制度です。
0歳から18歳までが対象で、支給される月額は3歳未満なら一律1万5千円・3歳以上は1万円(所得上限超過で一律5千円)です。
医療費制度
医療費制度は、子どもの医療費や通院費を軽減する仕組みです。
多くの自治体では「子ども医療費助成」として、自己負担が無料または数百円程度に抑えられます。
たとえば東京都では、所得制限なしで高校生年代までの医療費を助成しています。
生活保護
生活保護は、最低限の生活を保障する国の制度です。
収入や資産が基準を下回る場合に、生活費や住宅費・医療費などが支給されます。
特別児童扶養手当・障害児福祉手当
特別児童扶養手当・障害児福祉手当は、障害のある子どもを育てる家庭への支援です。
障害の程度や等級によって月額支給額が異なり、最大で5万円以上受け取れるケースもあります。
例として、特別児童扶養手当(1級)は月額5万5千円程度です。
遺族年金
遺族年金は、家族の生計を支えていた方が亡くなったときに支給される年金です。
受給額は亡くなった方の年金加入状況や報酬額によって異なりますが、子どもの人数に応じて加算されます。
母子家庭や父子家庭で孤立を防ぐためには
母子家庭や父子家庭で経済的にも精神的にも安定を目指すには、孤立を防ぐことが重要です。
以下の方法で、他者から協力を得られます。
- 家事・育児支援を積極的に活用
- 両親やきょうだいなど家族にも頼る
- 情報収集できる相談先を見つける
ひとりで抱え込むよりも、複数の支援を組み合わせたほうが安心感が生まれます。
それぞれの方法を具体的に見ていきましょう。
家事・育児支援を積極的に活用
家事・育児支援を積極的に活用することで、孤立感や負担を軽減できます。
たとえば、ファミリーサポートセンターでは、地域の人が子どもの預かりや送迎を手伝ってくれる仕組みがあります。
自治体によっては家事援助サービスの補助が出る場合もあるので、金銭的な負担を抑えながら利用可能です。
両親やきょうだいなど家族にも頼る
両親やきょうだいなど家族にも頼れる場合、協力を求めることも必要です。
定期的に連絡を取り合い、困りごとを共有するだけでも心理的な負担が軽くなります。
たとえば、週末だけ実家に子どもを預けて自分の時間を作ると、リフレッシュできるでしょう。
情報収集できる相談先を見つける
情報収集できる相談先を持つことも孤立を防ぐポイントです。
自治体の子育て支援課・福祉課・ひとり親家庭等自立支援センター・社会福祉協議会などを活用してみてください。
これらの機関では経済的支援だけでなく、仕事探しや生活改善のアドバイスも受けられます。
母子家庭と父子家庭の手当の違いに関する質問
最後に、母子家庭と父子家庭の手当の違いに関する質問をご紹介します。
- 手当の申請方法や注意点は?
- できる限り多く手当をもらうには?
- 地域によって支給額は異なる?
これらを知ることで、受給漏れを防ぎ家計を安定させやすくなります。
それぞれの疑問について詳しく見ていきましょう。
手当の申請方法や注意点は?
手当の申請方法は自治体によって異なるため、正しく理解しておきましょう。
たとえば、児童扶養手当では住民票や所得証明書など複数の書類が必要です。
できる限り多く手当をもらうには?
できる限り多く手当をもらうには、対象となる制度を幅広く調べることが欠かせません。
児童扶養手当や医療費助成だけでなく、住宅手当や学習支援金など自治体ごとの独自制度もあります。
地域によって支給額は異なる?
地域によって支給額は異なる場合があります。
基本的な国の制度は全国共通ですが、自治体独自の加算や補助が設定されていることがあるからです。
母子家庭や父子家庭で金銭的不安があるなら「マネーキャリア」に相談
母子家庭・父子家庭で受けられる手当の違いや種類・申請方法、また孤立を防ぐためのサポート活用法について紹介しました。
これから支援を受けながら安定した生活を目指す方は、まずは受給できる手当を整理し、申請準備を始めることから取り組んでみてください。
とはいえ、「どの手当が自分に適用されるのかわからない」「家計のやりくりも同時に見直したい」と悩む方も多いでしょう。
そんなときは、「マネーキャリア」の無料相談がおすすめです。
手当の活用方法や家計管理・将来の教育費や生活費の準備まで、お金のプロ(FP)に幅広く相談できます。
金銭的不安を少しでも減らしたい方は、一度「マネーキャリア」に相談してみてはいかがでしょうか。




























