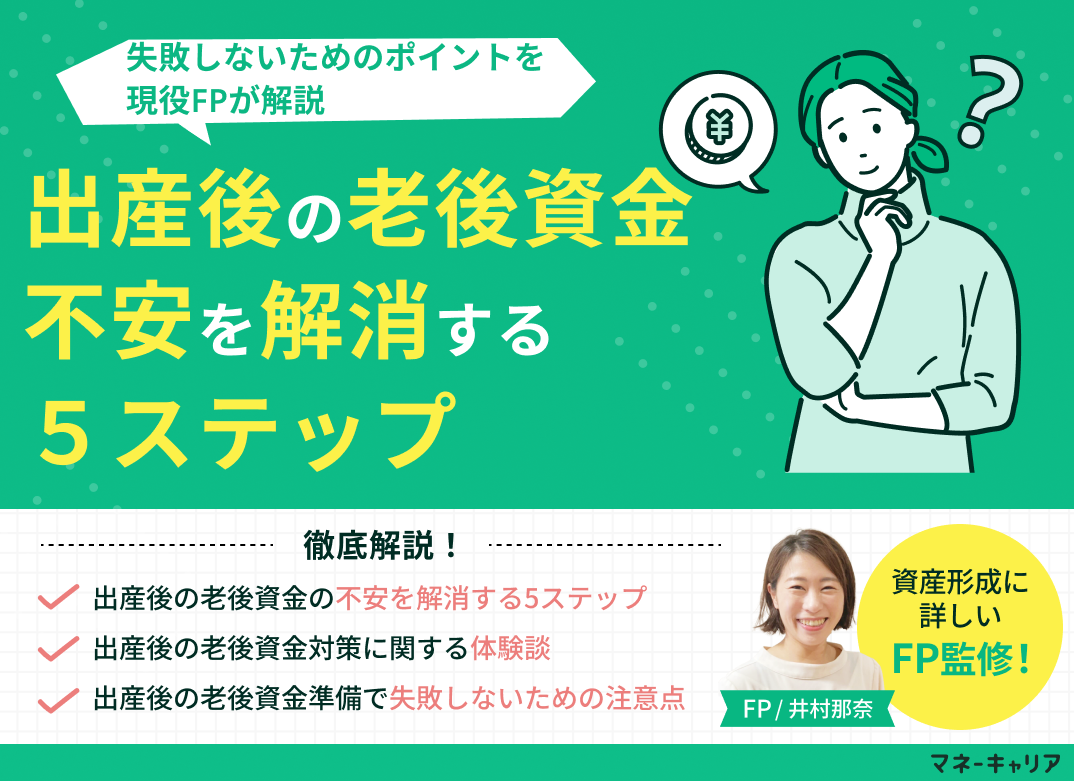この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 老後資金の取り崩し計画の立て方
- ①老後資金を長持ちさせる
- ②取り崩しシミュレーション
- 老後資金の取り崩し方にはどんな方法がある?
- 定率・定額の併用による効率的な取り崩し方
- 定率取り崩しのメリット・デメリット
- 定額取り崩しのメリット・デメリット
- 取り崩しの失敗例と注意点
- 取り崩す順番で資産寿命が変わる!?
- 取り崩しのタイミングを見極めるポイント
- 退職金・預貯金・NISA・iDeCo…どこから崩すべき?
- 年金活を活用した取り崩し
- 老後資金を減らさずに取り崩す方法
- 取り崩しながら資産を増やす戦略とは?
- 新NISA・iDeCoの活用で資産を維持するコツ
- 定年後も資産を減らさないポートフォリオ設計
- 迷ったら専門家に相談!老後資金の取り崩しプランを最適化
- 相談時に用意しておくべき情報とシミュレーションの活用
- 相談できる専門家の種類と選び方 マネーキャリアで、老後資金を安心運用!
- まとめ:老後資金を賢く管理して安心の暮らしを
老後資金の取り崩し計画の立て方

老後資金の取り崩し計画は、豊かな老後生活を実現するために欠かせない重要なステップです。とくに平均寿命が延びている現代では、限られた資産をいかに長く効率的に活用するかが課題となっています。
日本の平均寿命は男性で81.47歳、女性で87.57歳と長寿化が進んでおり、老後の生活資金をどのように計画的に取り崩していくかは多くの人にとって重要な関心事となっています。
①老後資金を長持ちさせる
老後資金を長持ちさせるためには、計画的な取り崩し戦略が必要です。「長寿リスク」と言葉もあるように、予想以上に長生きすると資金が枯渇するリスクに備える必要があります。
まず重要なのは、老後に必要な生活費の把握です。総務省の家計調査(2022年)によると、65歳以上の高齢者無職世帯では月の実収入159,624円に対し、支出合計が209,787円と約5万円不足しているデータがあります。
不足額が30年間続くと計算すると、約2,000万円の貯蓄が必要になる「2000万円問題」が話題になりましたが、実際には個人のライフスタイルや居住地域によって必要額は大きく異なります。
生命保険文化センターの調査(2022年)では、夫婦2人で「ゆとりある老後生活を送るために必要と考える1ヵ月の生活費」の平均額は35.7万円とされていますが、個人の回答は20万円未満から50万円以上まで広く分布しています。
老後資金を長持ちさせるためには、公的年金だけでなく、退職金や企業年金、個人型確定拠出年金(iDeCo)、2024年1月から始まった新NISAなどの税優遇制度を活用した資産形成が効果的です。
②取り崩しシミュレーション
老後資金の取り崩し方法には大きく分けて「定額取り崩し方式」と「変額取り崩し方式」があります。どちらを選ぶかによって、資産の寿命や毎月の生活費は大きく変わってきます。
定額取り崩し方式では、毎月一定額を取り崩す方法で、たとえば1500万円を20年間で使い切る場合のシミュレーションは以下のようになります。
| 予定運用利回り | 0% | 1% | 2% | 3% |
|---|---|---|---|---|
| 取り崩し額(円/月) | 62,500 | 68,583 | 74,949 | 81,571 |
この方法は生活費の計画が立てやすい反面、資産運用の成果によっては予定より早く資金が枯渇するリスクがあります。
一方、変額取り崩し方式では、資産残高に応じて取り崩し額を調整します。取り崩し期間を固定し、運用成果の良し悪しによって毎年の取り崩し額を変動させる方法です。
資産運用をしながら取り崩す場合、リスクと取り崩し額のバランスを考慮するのが重要です。予定運用利回りが高いほど取り崩し額は増えますが、同時に運用リスクも高まります。
さらに、より安心な老後のための戦略として「WPP戦略」も注目されています。これはWork Longer(より長く働き)、Private Pensions(次に私的年金などで賄い)、Public Pensions(その後繰り下げて増額された公的年金を受給)の順序で老後の収入を確保する方法です。
公的年金の繰下げ受給は、65歳から70歳までの間、1ヵ月繰り下げるごとに0.7%増額されるため、長寿の場合には有利になる可能性があります。
シミュレーションと戦略を参考に、自分の資産状況やライフスタイルに合わせた老後資金の取り崩し計画を立てることが、安心した老後生活を送るための鍵となります。
参考データ出典
老後資金の取り崩し方にはどんな方法がある?

老後資金の適切な取り崩し方法を検討するのは、限られた資産で豊かな老後生活を送るために非常に重要です。前章で紹介した定額取り崩し方式や変額取り崩し方式の他にも、さまざまな取り崩し方法があります。
老後資金の効率的な活用のためには、自分のライフスタイルやリスク許容度に合わせた選択が必要です。
定率・定額の併用による効率的な取り崩し方
定率と定額を併用する「ハイブリッド戦略」は、両方のメリットを活かした効率的な取り崩し方法です。基本的な生活費を定額で確保しつつ、残りの資産を定率で取り崩すことで、安定性と効率性のバランスを図ります。
たとえば、公的年金や安定的な不動産収入などの固定収入で基本的な生活費をカバーし、それ以上の生活の質を向上させる支出を金融資産の定率取り崩しでまかなう組み合わせが考えられます。
以下のようなハイブリッド戦略も想定できます。
- 必要最低限の生活費は定額取り崩しで確保
- 余裕資金は定率取り崩しで運用しながら活用
- 市場状況に応じて比率を調整
定率取り崩しのメリット・デメリット
定率取り崩しの例として、かつては資産残高の4%を毎年取り崩す「4%ルール」が広く知られていました。しかし、現在の低金利環境では、この率が高すぎる可能性があります。
最新の研究では、より保守的な3%程度の取り崩し率がより安全だとする見方もあります。実際の取り崩し率は、個人の資産状況や市場環境に応じて慎重に検討する必要があります。
メリットには以下のものがあります。
- 資産寿命の延長市場が低迷している時は取り崩し額が自然と減少するため、資産の温存効果がある
- 市場が回復すると取り崩し額も増加し、生活水準の向上につながる
- 長期的な資産運用と組み合わせることで、インフレにも対応可能
- 市場変動により毎月の取り崩し額が変わるため、生活費の予算計画が立てにくくなる
- 相場下落時に生活費も減少するため、精神的な不安を感じやすくなる
- 残高に応じた取り崩し額の計算が必要で、管理が煩雑になる場合がある
定額取り崩しのメリット・デメリット
定額取り崩しは、毎月または毎年、一定の金額(例:月10万円)を取り崩していく方法です。
メリットには以下のものがあります。
- 毎月の収入が一定なので、家計管理がしやすくなる
- 市場変動に関わらず一定の生活水準を維持できる
- 取り崩し額が固定なので、複雑な計算が不要
- 市場が低迷すると、資産の取り崩しペースが早まり、早期に枯渇する可能性がある
- 物価上昇に対応した取り崩し額の調整が難しい場合がある
- 市場好調時でも取り崩し額が増えないため、恩恵を受けらない
取り崩しの失敗例と注意点

老後資金の取り崩し計画を立てる際には、先人の失敗から学ぶことも重要です。多くの退職者が陥りがちな取り崩しの失敗例と、避けるための注意点を解説します。
取り崩し計画には多くの変数が関わるため、想定外の事態が発生する場合もあります。
運用リスクの誤った評価は大きな失敗要因です。老後資金の取り崩しは過度に安全志向になりすぎる場合と、リスクを取りすぎる場合の両方が問題となります。
安全性重視で低リターン商品だけに投資するとインフレに対応できず、高リスク投資に偏ると市場急落時に大きな損失を被る可能性があります。運用リスクに対しては、年齢や資産状況に応じた適切な資産配分を行い、定期的に見直すことが重要です。
また、インフレを考慮しない取り崩し計画も失敗例の一つです。2022年以降、日本でも2%を超えるインフレが続いています。インフレ対策としては、インフレ連動型の取り崩し計画を立てる、実物資産への投資を維持する、物価スライド機能のある商品を活用するなどが効果的です。
老後の医療・介護費用を過小評価するのも大きな失敗につながります。厚生労働省の「令和3年度 医療費の動向」によると、75歳以上の一人あたり年間医療費は平均約94万円となっています。介護が必要になった場合の自己負担も、要介護度や利用するサービスによっては月額10万円以上になることがあります。
上記の費用に備えるためには、別枠で資金を確保する、民間保険への加入を検討する、公的制度の知識を持つことが大切です。
そして、退職直後に旅行や住宅リフォームなど大きな出費をして老後資金を早期に減らしてしまう例も見られます。反対に、資産枯渇を恐れるあまり必要以上に節約して生活の質を落としてしまうケースもあります。
適切な取り崩し計画は、上記の失敗例を念頭に置きながら、自分のライフスタイルやリスク許容度、健康状態などを総合的に考慮して立てることが重要です。また、環境の変化に応じて定期的に計画を見直すことも忘れてはなりません。
参考データ出典
取り崩す順番で資産寿命が変わる!?

老後資金の取り崩し計画では、どのような方法で取り崩すかだけでなく、「どの資産から取り崩すか」と順序も非常に重要です。税金や運用効率を考慮した取り崩し順序を選ぶことで、同じ資産額でもより長く、より多くの金額を活用するのが可能になります。
最適な取り崩し順序を検討すると、資産寿命が延びる可能性があります。
取り崩しのタイミングを見極めるポイント
老後資金の取り崩しタイミングを見極める際には、いくつかの重要なポイントがあります。まず考慮すべきは税金の影響です。退職後は通常、収入が減少するため税率も下がります。この低税率期間をうまく活用するのが賢明です。
市場環境も重要な判断材料となります。市場が大きく下落している時期に高リスク資産(株式など)を売却すると、その後の回復の恩恵を受けられなくなるため、可能であれば安定資産から取り崩すことが推奨されます。
取り崩しのタイミングは、年間を通じても検討する価値があります。たとえば、配当金や分配金の受取時期を考慮して取り崩しのタイミングを調整したり、税負担を平準化するために複数年にわたって計画的に取り崩すことで、手元に残る金額を増やすことが可能です。
また、生活パターンによっても取り崩しタイミングは変わります。旅行や趣味活動が多い「アクティブシニア期」(65~75歳頃)は支出が多くなりがちで、「安定期」(75~85歳頃)はやや支出が減少し、「介護期」(85歳以降)は医療・介護費用が増加する傾向にあります。この生活パターンの変化も考慮した取り崩し計画が効果的です。
退職金・預貯金・NISA・iDeCo…どこから崩すべき?
多様な金融商品を保有している場合、どの資産から取り崩すべきかの一般的な優先順位は以下のようになります。
- 普通預金や定期預金などの現金性資産(低金利環境下では運用効率が低いため)
- 一般口座の投資資産(とくに含み益の少ないもの)
- 特定口座の投資資産
- NISA口座の投資資産(非課税メリットを最大化するため長期保有が有利)
- iDeCoや企業型DCなどの税制優遇資産(60歳以降でも「加入期間10年以上」などの条件を満たす必要があり、可能な限り後回しが有利)
年金活を活用した取り崩し
公的年金をどのように活用するかも、老後資金の取り崩し計画において重要な要素です。
とくに注目すべきは、年金の繰下げ受給制度です。2022年4月改正で75歳まで繰り下げ可能に(月0.7%×120ヵ月=最大84%増)。ただし基礎年金単独での繰り下げは不可で、厚生年金と同時に手続きが必要です。
長寿化が進む現代において、年金繰下げの増額効果は大きな魅力です。とくに健康状態が良好で、75歳以上まで生きる可能性が高い人にとっては、年金繰下げと資産取り崩しを組み合わせたWPP戦略(Work Longer、Private Pensions、Public Pensions)が効果的です。
たとえば、取り崩し計画では、65~70歳は自身の資産を多めに取り崩して生活費を賄い、75歳まで繰り下げ可能な新制度下では、資産取り崩し期間を65-75歳と設定し、増額年金(最大184%)で長寿リスクに対応する戦略が有効です。
年金と資産取り崩しのバランスを適切に設計すると、老後の収入を安定させつつ、資産寿命を延ばすことが可能になります。とくに長生きリスクへの対策としては、年金で「終身保証の収入源」の価値を最大化する戦略が有効です。
老後資金を減らさずに取り崩す方法

老後資金を取り崩しながらも資産を維持・増加させることは、一見矛盾しているように思えますが、適切な戦略を立てることで実現可能な目標です。
長寿化社会で、資産を減らさずに老後の生活資金を確保する方法を探ることは、多くの退職者にとって大きな関心事となっています。
では、どうすれば取り崩しながらも資産を維持できるのでしょうか?
取り崩しながら資産を増やす戦略とは?
老後資金を取り崩しながらも資産を増やす戦略の核心は、「取り崩し率」よりも「運用リターン」を高く保つことにあります。たとえば、年間3%の取り崩しに対して4%の運用リターンを確保できれば、理論上は資産が減少せず生活資金を引き出すことが可能です。
資産を維持しながら取り崩すためには、インカムゲイン(配当や利息)を重視した投資戦略が有効です。とくに高配当株や優良REITなどは、値動きに関わらず定期的な収入を期待できるため、元本を大きく減らさずに生活資金を確保できる可能性があります。
また、段階的な取り崩し戦略も効果的です。たとえば65~75歳は取り崩し率を低めに設定し、75歳以降は必要に応じて取り崩し率を上げる方法です。初期段階で資産を増やしておくことで、後半の取り崩しに余裕を持たせることができます。
新NISA・iDeCoの活用で資産を維持するコツ
2024年から始まった新NISA制度や継続的に改良されているiDeCoは、老後資金を効率的に維持・増加させるための強力なツールです。制度を活用すると、税負担を抑えながら資産形成を続けることができます。
新NISAでは生涯非課税枠が1,800万円(成長投資枠1,200万円、つみたて投資枠600万円)に拡大され、非課税期間も無期限になりました。
新NISAを活用したポートフォリオ管理のコツは以下のとおりです。
- つみたて投資枠(年間120万円)では、金融庁が指定した基準を満たす長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託のみが対象
- 成長投資枠(年間240万円)では高配当株式やREITなど収益性の高い商品を選択
- 配当や分配金は再投資して非課税メリットを最大化
定年後も資産を減らさないポートフォリオ設計
定年後も資産を減らさないためのポートフォリオ設計では、リスクとリターンのバランスがとくに重要になります。老後のポートフォリオでは「安定収入」「インフレ対策」「成長性」の3要素をバランスよく組み込むことが重要です。
ポートフォリオ構成は個人の状況や市場環境によって異なりますが、一般的な例として以下が挙げられます。。
- 安定収入層(40~50%):国債、社債、元本確保型商品
- インフレ対策層(30~40%):物価連動債、高配当株、REIT
- 成長期待層(10~20%):国内外の株式、新興国資産
迷ったら専門家に相談!老後資金の取り崩しプランを最適化

老後資金の取り崩し計画は、税制や投資環境、個人の状況など複雑な要素が絡み合うため、自分だけで最適解を見つけることが難しい場合があります。
専門家のアドバイスを受けることで、より効率的で安心できる取り崩し計画を立てることができます。
相談時に用意しておくべき情報とシミュレーションの活用
老後資金の取り崩しを専門家に相談する際は、事前に必要な情報を整理しておくことで、より具体的で実用的なアドバイスをえることができます。とくに以下の情報は必須です。
- 現在の資産状況(金融資産の種類・金額、不動産、保険など)
- 収入の見通し(年金見込額、その他収入源)
- 予想される支出(基本生活費、趣味・レジャー費、医療費など)
- 家族構成と相続の希望
- リスク許容度と投資経験
相談できる専門家の種類と選び方 マネーキャリアで、老後資金を安心運用!
老後資金の取り崩しを相談できる専門家には、主に以下のような選択肢があります。
- ファイナンシャルプランナー(FP):総合的な資金計画の専門家
- 税理士:税効率を重視した資産活用のアドバイザー
- 証券会社やバンカー:投資運用に強みを持つアドバイザー
- 保険アドバイザー:保険を活用した資産保全・活用の専門家
- 資格・経験:CFP、1級FP技能士などの上位資格保有者を優先
- 独立性:特定の金融商品に偏らない中立的なアドバイスが得られるか
- 報酬体系:fee-onlyやフィデューシャリー・デューティを重視する姿勢
- 相性:コミュニケーションがスムーズに取れるか
まとめ:老後資金を賢く管理して安心の暮らしを

本記事では、老後資金の効率的な取り崩し方法、リスク管理、資産寿命を延ばすための戦略、専門家活用のポイントなどを解説しました。
老後資金の取り崩しは計画的におこなうことで、より豊かで安心した老後生活を実現できます。しかし誤った方法で進めると、予想より早く資金が枯渇してしまうリスクがあります。
▼老後資金の取り崩しにおける重要ポイント
・資産の取り崩し方式(定率・定額・ハイブリッド)を自分に合わせて選択する
・運用しながら取り崩すことで資産寿命を延ばせる可能性がある
・税制優遇制度(新NISA・iDeCo)を活用した効率的な取り崩し
・取り崩す資産の順番を工夫すると手取り額を増やせる
老後資金の取り崩し計画には、インフレリスク、運用リスク、長寿リスクなどさまざまな要素を考慮する必要があります。とくに長寿化が進む現代では、80代、90代まで資金が持続するような計画が重要です。
資産を効率的に取り崩すには適切な資産配分とポートフォリオ設計が不可欠ですが、自分だけで最適な取り崩し計画を立てるのは難しいものです。独断での判断では資産枯渇のリスクが高まる可能性も否定できません。
「老後資金の取り崩し相談」のように資産形成から取り崩しまでの一貫した戦略を専門家に相談できるサービスを活用する方が増えています。金融機関やファイナンシャルプランナーなど、自分に合った専門家を見つけることで、より安心できる老後資金計画を実現できます。
定期的な見直しと必要に応じた調整を行いながら、自身のライフスタイルに合った取り崩し計画を進めることで、老後の生活をより豊かで安心したものにしていきましょう。