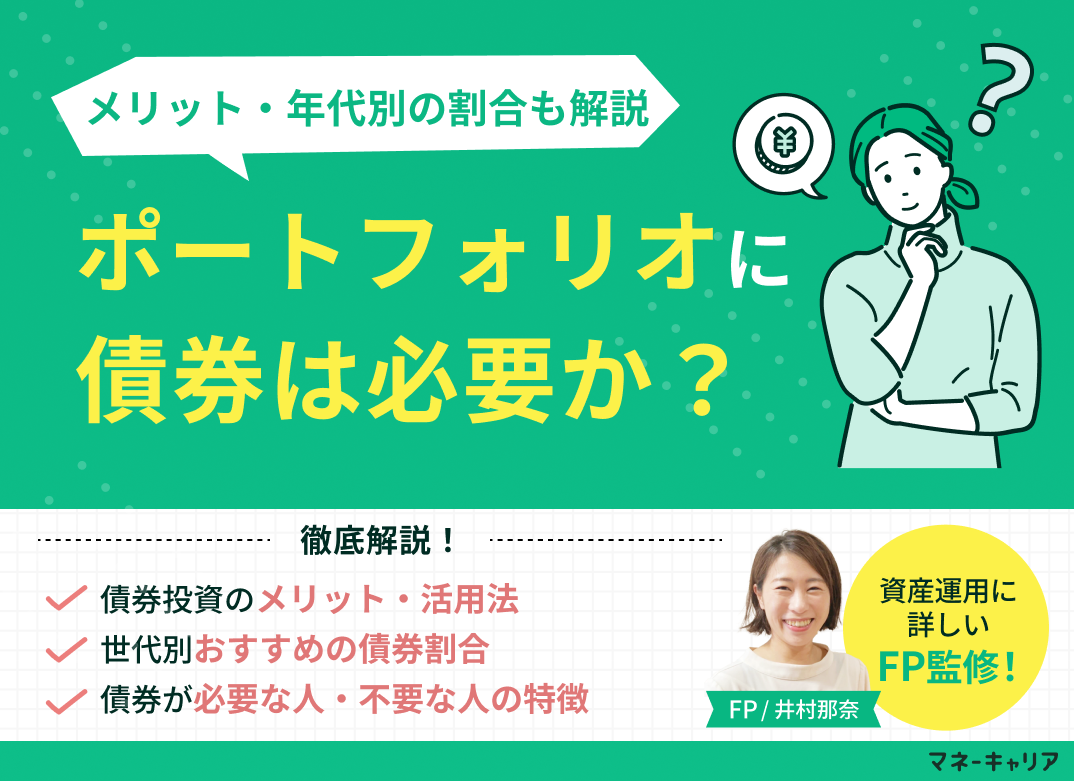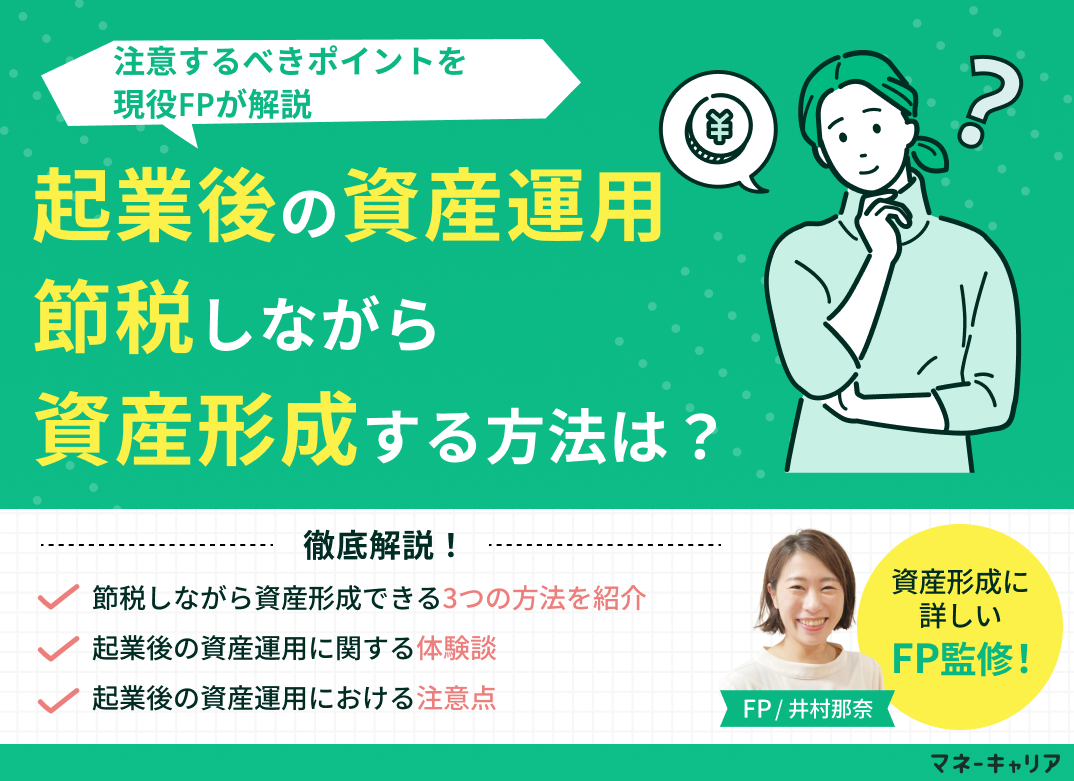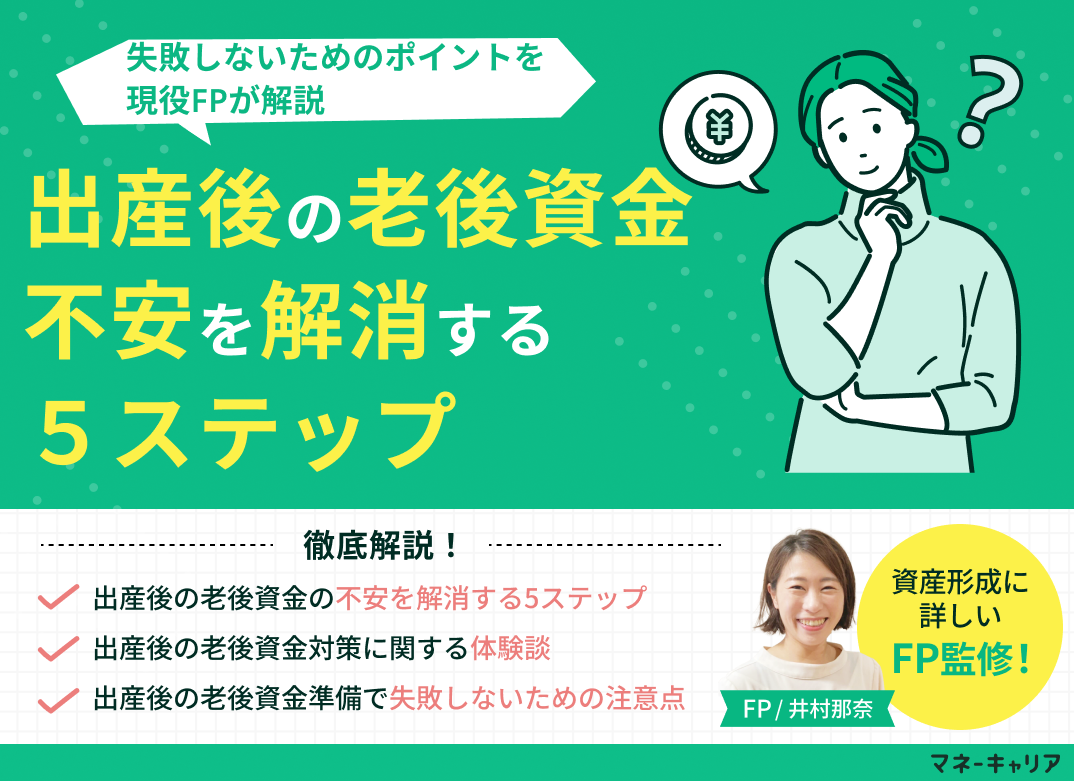「分散投資のポートフォリオについて、おすすめの組み方を知りたい」
「ポートフォリオを最適化して効率よく資産を増やしたい」
とお悩みではないでしょうか。
結論、分散投資のポートフォリオは年齢やリスク許容度、投資目的によって最適な形が変わります。
この記事では年代別のおすすめポートフォリオや作り方のステップを解説します。また、リスクを抑えながら効率的に資産形成するためのポイントについても紹介します。
この記事を読むことで、自分に合った分散投資のポートフォリオを構築できるようになるので、ぜひご覧ください。


この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- おすすめのポートフォリオとは?分散投資の役割から解説
- 分散投資の役割とは?
- 結論・おすすめの資産配分は人によって異なる
- 自分のポートフォリオはどのよう分散投資する?おすすめを知りたい人はFPに相談しよう
- 【年代別】おすすめの分散投資ポートフォリオを紹介
- 20代におすすめのポートフォリオ
- 30代におすすめのポートフォリオ
- 40代におすすめのポートフォリオ
- 50代におすすめのポートフォリオ
- 年齢だけでなく投資目的も重要!
- 【実践編】自分だけの分散投資ポートフォリオを作る5ステップ
- 投資目的と期間を明確にする
- 自分のリスク許容度を正確に把握する
- 基本的な資産配分を決める
- 具体的な金融商品を選定する
- 定期的に見直す
- 分散投資ポートフォリオの注意点は?
- ライフプランの変化に合わせてポートフォリオを見直す
- 定期的な「リバランス」を怠らない
- 長期的な視点で運用する
- 分散投資ポートフォリオを作るのが難しいと感じる人はマネーキャリアに相談してみよう!
- 【まとめ】おすすめのポートフォリオは人による!自分だけの分散投資を見つけよう
おすすめのポートフォリオとは?分散投資の役割から解説
分散投資の役割とは?
結論・おすすめの資産配分は人によって異なる
自分のポートフォリオはどのよう分散投資する?おすすめを知りたい人はFPに相談しよう

「自分に合った資産配分って言われても、どうやって考えればいいの?」「たくさんの金融商品の中から、どれを選べばいいのか分からない…」と、いざ自分でポートフォリオを組もうとすると、多くの疑問や不安が出てくるものです。

【年代別】おすすめの分散投資ポートフォリオを紹介
年代別におすすめのポートフォリオを紹介します。
紹介する年代は以下のとおりです。
ここで紹介するポートフォリオは、あくまで一般的な年代別の特徴に基づいたモデル例です。実際の運用では自身の状況を総合的に考慮し調整をしましょう。
20代におすすめのポートフォリオ
- 国内株式:20%~30%
- 外国株式(先進国):30%~40%
- 外国株式(新興国):10%~20%
- 国内債券:0%~10%
- 外国債券:0%~10%
- その他(REITなど):0%~10%
20代は投資期間を最も長く取れるため、積極的なリスクを取りやすい時期です。
少額からでも積立投資を始めることで、複利効果を最大限に活かせます。また、将来の収入増加も期待できます。
30代におすすめのポートフォリオ
- 国内株式:20%~30%
- 外国株式(先進国):30%~40%
- 外国株式(新興国):5%~15%
- 国内債券:10%~20%
- 外国債券:5%~15%
- その他(REITなど):0%~10%
30代は収入が増え、資産形成を本格化させる時期です。
結婚、出産、住宅購入などライフイベントも多くなるため、ある程度のリスクを取りつつも、将来の資金需要に備えるバランスが求められます。
40代におすすめのポートフォリオ
- 国内株式:15%~25%
- 外国株式(先進国):25%~35%
- 外国株式(新興国):5%~10%
- 国内債券:20%~30%
- 外国債券:10%~20%
- その他(REITなど):5%~15%
40代は収入がピークに近づき、資産額も大きくなってくる時期です。また、子どもの教育費や住宅ローンの返済など、支出も多くなります。
老後資金への意識も高まり、資産を守りながら増やす視点が重要になります。
50代におすすめのポートフォリオ
- 国内株式:10%~20%
- 外国株式(先進国):15%~25%
- 外国株式(新興国):0%~5%
- 国内債券:30%~40%
- 外国債券:15%~25%
- その他(REIT、金など):5%~15%
50代は退職が視野に入り、老後資金の準備が最終段階となる時期です。
大きな失敗は避け、これまで築き上げた資産を減らさない「守りの運用」へのシフトが重要になります。
年齢だけでなく投資目的も重要!
ここまでの解説はあくまで年齢という軸で見た一般的な例です。
年齢だけでなく「何のために」「いつまでに」という投資目的を明確にすることが、最適なポートフォリオを作る上で重要です。
例えば、教育資金を検討する場合、目標時期が10年後など明確であれば目標時期が近づくにつれて安定資産の割合を増やすことが大切です。
また、住宅購入資金を検討する場合、元本割れリスクを極力避けたいのであれば、預貯金や個人向け国債などが中心になります。
このように個々の好みや目的によって異なるため、慎重にポートフォリオを設計しましょう。
【実践編】自分だけの分散投資ポートフォリオを作る5ステップ

自分だけの分散投資ポートフォリオを作る5ステップは以下のとおりです。
- 投資目的と期間を明確にする
- 自分のリスク許容度を正確に把握する
- 基本的な資産配分を決める
- 具体的な金融商品を選定する
- 定期的に見直す
投資目的と期間を明確にする
ポートフォリオ作成には、まず投資の目的を定めることが大切です。
それにあたり、次のことを考えましょう。
- 何のためにお金を増やしたいのか?
(老後資金、子どもの教育費、住宅購入の頭金など) - 具体的にいくら必要なのか?
(老後資金として2000万円、教育費として1人あたり1000万円など) - いつまでにそのお金が必要なのか?
(5年後などという短期か、20年後などという長期か)
自分のリスク許容度を正確に把握する
リスク許容度とは、投資においてどの程度の損失の可能性なら精神的・経済的に受け入れられるかという度合いのことです。
たとえば、若い人なら相場の回復に時間を取れるためリスク許容度は高くなります。
また、扶養する家族が多い人はリスク許容度は低くなる傾向があります。
投資においてはリターンを求めるとリスクも比例するように高くなるため、投資目的とリスク許容度が自身にとって最適なバランスとなるよう見極めることが大切です。
リスク許容度を把握するには、「仮に投資額の20%が一時的に下落したとき、冷静でいられるか」などの質問に自分自身で答えてみると良いでしょう。
基本的な資産配分を決める
次にステップ1で設定した「投資目標・期間」と、ステップ2で把握した「リスク許容度」に基づいて資産配分を決めます。
資産の種類には、株式・債券・不動産(REIT)・預貯金などがあり、リスク許容度に合わせてポートフォリオを調節していきます。
また、調節の際に公的年金の基本ポートフォリオ(国内債券25%、国内株式25%、外国債券25%、外国株式25%)を参考に、自分のリスク許容度に合わせて調整するのも有効です。
ただし、国内資産だけでなく海外資産も組み込む場合は為替リスクに注意しましょう。
具体的な金融商品を選定する
次にステップ3で決めた資産配分に見合った投資対象の、具体的な金融商品を選定します。
商品の選択肢としては、株式や債券などの現物の購入、投資信託やETFなど間接的に投資する商品を購入する方法などが挙げられます。
何に投資するものか、投資対象はしっかり確認しましょう。
選定基準としては、手数料や過去の運用実績、純資産総額などがあります。
特に投資信託を選ぶ際は、運用コストが低いものを選ぶことで、長期的に運用した際のなリターンに大きな差が生まれます。
定期的に見直す
ポートフォリオは市場の変動により、当初設定した資産配分の比率が崩れてくるため、定期的に見直すことが大切です。
例えば株式の価値が上がり比率が高まったら、一部を売却して債券を買い増すなどします。
これにより「気付いたらハイリスクなポートフォリオになり、分散投資の効果が薄れていた」ということを防げます。
見直しの頻度は、年に1回程度が一般的ですが、資産配分が大きく崩れた場合にも実施を検討しましょう。
また、結婚、出産、転職などがあった場合も、投資目的やリスク許容度が変わる可能性があるため、ポートフォリオの見直しが必要です。
分散投資ポートフォリオの注意点は?

分散投資ポートフォリオの注意点は以下のとおりです。
- ライフプランの変化に合わせてポートフォリオを見直す
- 定期的な「リバランス」を怠らない
- 長期的な視点で運用する
ライフプランの変化に合わせてポートフォリオを見直す
ポートフォリオはライフプランを実現するための手段です。
結婚して家族が増えたり、マイホームを購入したり、子どもが生まれたりすると、必要なお金や許容できるリスクの度合いも変わります。
ライフプランが変わったタイミングでポートフォリオの方針を柔軟に見直すことが大切です。
定期的な「リバランス」を怠らない
リバランスとは、崩れた資産配分比率を元の目標比率に戻す作業のことです。
例えば、株式が好調で値上がりすると、ポートフォリオに占める株式の割合が高まります。
その際、値上がりして比率が高まった資産を一部売却し、値下がりして比率が低くなった資産を買い増するなどの方法が取られます。
一般的に年に一度のリバランスが理想的と言われますが、市場が変動したタイミングなどでの見直しも重要です。
また市場が不安定な時期は無理に売買をするのは得策でないので静観するのも一つです。
長期的な視点で運用する
市場は常に変動しており短期的には価格が上下しますが、分散投資や積立投資は長期的な視点で資産形成を目指すものです。
日々の値動きに一喜一憂して、慌てて売買してしまうと、かえって損失を被る可能性があります。
そのため、分散投資の目的を忘れず、投資の目標達成を目指した長期目線での運用を行うことが重要です。
分散投資ポートフォリオを作るのが難しいと感じる人はマネーキャリアに相談してみよう!

「年代別のモデルや作り方のステップは分かったけど、やっぱり自分一人で最適なポートフォリオを組むのは難しそう…」という人も多いはずです。
さらに金融商品の数は無数にあり、自分一人で選び取るのは難しいものです。
マネーキャリアなら資産運用に精通したFPが無料であなたのポートフォリオ作成をサポートします。
ライフプランや投資目的、リスク許容度も踏まえたアドバイスも受けられるので、自分にとって最適な分散投資の方法を見つけましょう。
【まとめ】おすすめのポートフォリオは人による!自分だけの分散投資を見つけよう
ここまで、分散投資のポートフォリオ構築方法やおすすめの資産配分について紹介しました。
分散投資は、将来の資産形成において非常に有効な手段ですが、巷で紹介される「おすすめ」が必ずしも自身にとって最適とは限りません。
大切なのは、自身の年齢、収入、家族構成、そして何よりもライフプランの目的達成のために「いつまでに、何のために、いくら必要か」といった投資目標を明確にすることです。
一人で判断が難しい場合は専門家への相談も選択肢の一つです。
さまざまな情報をもとに、自分だけの分散投資ポートフォリオを作成してみましょう。