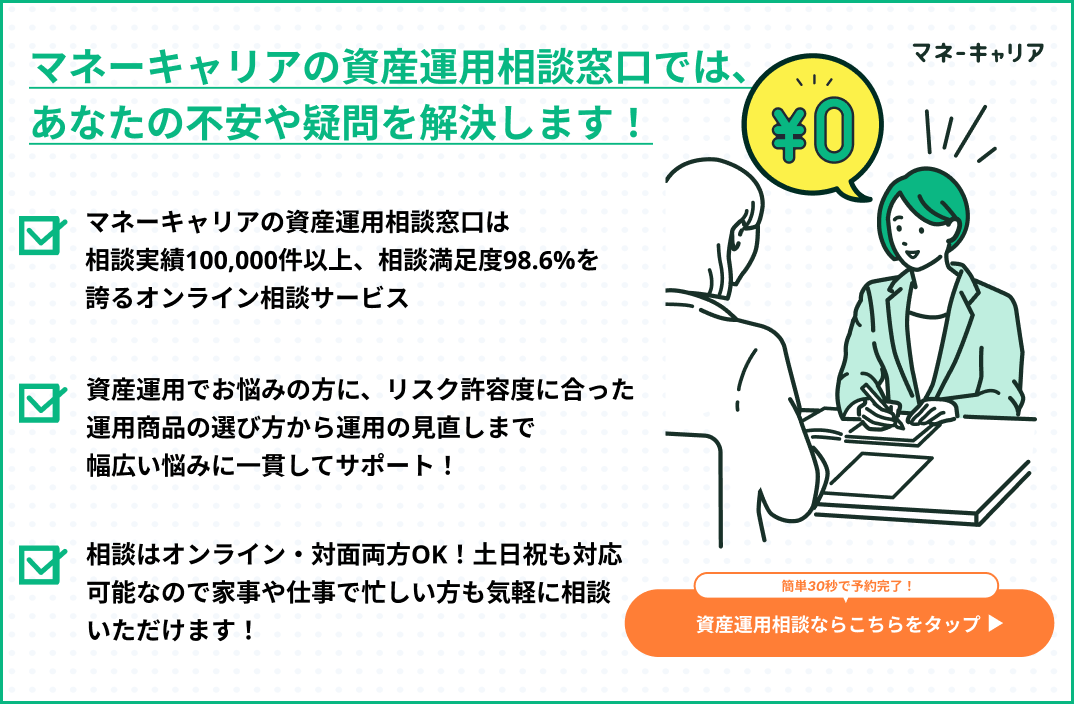・債券ファンドって安全そうだけど、本当に買っても大丈夫?
・“買ってはいけない”って聞くけど、自分には向いているのか分からない…
このような疑問を感じていませんか?
債券ファンドは、価格変動が比較的穏やかでローリスクな運用が可能とされる一方で、元本割れや信託報酬の高さなど、見落とされがちなリスクも存在します。
本記事では、「債券ファンドは買ってはいけない」と言われる理由とその背景、さらに債券ファンドのメリットや向いている人の特徴まで、ファイナンシャルプランナーの視点からわかりやすく解説します。
投資初心者から経験者まで、債券ファンドを検討している方にとって判断材料となる内容をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

井村FP
さらに、マネーキャリアの無料FP相談では、こうした資産運用に関する複雑な悩みにも専門家が丁寧に対応してくれるので、ぜひ一度相談してみてください!

この記事の監修者
井村 那奈
フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
続きを見る
▼
閉じる
▲
債券ファンドを買ってはいけない理由5つをデメリットから解説
資産運用の手段として広く知られる「債券ファンド」。債券を投資対象とするため、リスクが小さいと感じている方も多いかもしれません。
しかし実際には、個人で債券を保有する場合と異なり、元本割れや運用コストの高さなど、見落とされがちなデメリットが存在します。特に、金利変動や分配金の仕組みには注意が必要です。
まずでは、「債券ファンドは買ってはいけない」と言われる主な理由を5つに絞って解説します。
- 債券投資と異なり元本割れする
- 信託報酬が高いファンドが多い
- 期待リターンが低い
- 金利上昇リスクがある
- 分配金が元本の取り崩しになっている
表面的な利回りや商品名だけで判断せず、仕組みを正しく理解した上で自分に合った運用を選択するための判断材料として、ぜひ最後までご一読ください。
債券投資と異なり元本割れする
国債などの個別債券は、償還まで保有すれば原則として元本が返ってくる仕組みです。しかし、債券ファンドは複数の債券を組み入れて運用する投資信託であり、
元本保証はありません。
市場金利の変動や為替リスク、運用方針の変更などにより、基準価額が下落することもあります。
債券投資の最大の魅力である「元本の安全性」が失われる点が、債券ファンドを買ってはいけないと言われる大きな理由の一つです。

井村FP
債券ファンドは元本保証がないため、安定性を重視する投資家には不向きな場合があります。
特に長期保有を前提とするなら、個別債券の方がリスク管理しやすく、計画的な運用が可能です。目的に応じた選択が重要です。
信託報酬が高いファンドが多い
債券ファンドの中でも、ハイイールド債などを組み入れた
アクティブ型ファンドは、信託報酬が高く設定されている傾向があります。
信託報酬は運用期間中に継続的に差し引かれるため、運用成果が報酬を上回らなければ、実質的な利益は得られません。
特に低金利環境下では、信託報酬が運用効率を大きく損なう要因となり、長期的な資産形成に不利に働くことがあります。

井村FP
信託報酬は見落とされがちですが、長期運用では大きな差になります。債券ファンドを選ぶ際は、報酬率だけでなく、運用方針や過去の実績も確認しましょう。
インデックス型など低コストの選択肢も検討する価値があります。
期待リターンが低い
債券ファンドは株式ファンドなどと比べてリスクが低い分、期待できるリターンも限定的です。
特に低金利環境下では、利回りが抑えられ、インフレによる実質価値の目減りも懸念されます。
安定性を重視する投資家には魅力的に映るかもしれませんが、資産形成を目的とする場合には、リターンの低さが大きな障壁となります。
債券ファンドは元本保証がないうえに、リターンも控えめであるため、長期的な運用には不向きとされることがあります。

井村FP
資産運用では、リスクとリターンのバランスが重要です。債券ファンドは安定性を求める場面では有効ですが、インフレや長期の資産形成には不利な面もあります。
目的に応じて、他の資産クラスとの組み合わせを検討しましょう。
金利上昇リスクがある
債券ファンドは金利の変動に敏感です。特に政策金利が上昇すると、既存の債券の利回りが相対的に低くなるため、債券価格は下落します。
これにより、債券ファンドの基準価額も下がる可能性があります。長期債を中心に運用するファンドほど、金利上昇の影響を強く受ける傾向があり、金利上昇局面では運用が不利になります。
債券ファンドは安定的な運用を期待されがちですが、金利環境によっては大きな損失を被ることもあるため注意が必要です。

井村FP
金利上昇局面では、債券ファンドの価格が下落しやすくなります。
特に長期債中心のファンドは影響が大きいため、金利動向を見ながら運用方針を見直すことが重要です。短期債や分散投資もリスク軽減に有効です。
分配金が元本の取り崩しになっている
債券ファンドの分配金は、安定収入を期待する投資家にとって魅力的に映ります。しかし、運用成績が振るわない場合、分配金は利益ではなく元本から支払われることがあります。
これを「特別分配金」と呼び、実質的には資産の取り崩しです。分配金を受け取っているにもかかわらず、基準価額が下がり続けるケースでは、資産の減少が進行している可能性があります。
分配金の仕組みを理解せずに購入すると、長期的な資産形成に悪影響を及ぼすことがあります。

井村FP
分配金の内訳が「普通分配金」か「特別分配金」かを確認することが大切です。高い分配金に惹かれて投資すると、気づかぬうちに元本が減少しているケースもあります。
長期運用を前提とするなら、再投資型も検討しましょう。
債券ファンドは本当に買ってはいけないの?迷う人はFPに相談してみよう
債券ファンドには元本割れや金利変動リスクなどのデメリットがありますが、ローリスクで安定した運用が期待できることから、一定の人気を保っています。
「債券ファンドは買ってはいけない」と一概に言い切ることはできず、投資目的や資産状況、リスク許容度によって適否は異なります。
自分にとって本当に適しているかどうかを判断するには、専門家の意見を聞くのが有効です。迷ったときは、FPに相談してみることをおすすめします。

井村FP
債券ファンドが合うかどうかは、資産全体の構成や将来のライフプランによって変わります。
「なんとなく不安」「他の選択肢と迷っている」といった段階でも、FPに相談することで自分に合った投資スタイルが明確になります。
判断に迷ったら、まずは一度相談してみましょう。
債券ファンドにメリットはある?3つの利点を解説
「債券ファンドは買ってはいけない」といった否定的な意見もある一方で、債券ファンドには他の金融商品にはないメリットも存在します。
特に、少額からの分散投資や安定収入を重視する投資家にとっては、有効な選択肢となり得ます。
ここでは、債券ファンドの代表的な3つの利点を解説します。
- さまざまな種類の債券に投資できる
- ポートフォリオを分散できる
- 分配金が期待できる
さまざまな種類の債券に投資できる
債券ファンドは、個人では購入しづらい海外債券や企業債などにも少額から投資できる点が魅力です。
現物の債券投資ではまとまった資金や取引の手間が必要ですが、ファンドを通じてであれば、手軽に複数の債券に分散投資することが可能です。
これにより、地域・通貨・信用リスクなどを分散しながら、債券市場全体の動向を取り込む運用が実現できます。初心者でも債券投資に取り組みやすい点は、債券ファンドの大きな利点です。

井村FP
債券ファンドは、個人では購入が難しい新興国債や外貨建て債券などにも間接的に投資できる点が強みです。
特にNISAやiDeCoと組み合わせることで、非課税メリットを活かしながら効率的な分散投資が可能になります。
投資対象の債券の種類や地域を確認し、自分のリスク許容度に合ったファンドを選びましょう。
ポートフォリオを分散できる
債券は株式と異なる値動きをするため、債券ファンドをポートフォリオに加えることでリスク分散が可能になります。
たとえば、株式市場が下落する局面では、債券が価格を維持または上昇することがあり、資産全体の安定性を高める効果が期待できます。
特に「S&P500の積立のみ」など株式偏重の運用をしている人にとっては、債券ファンドを組み入れることで、資産の下支えとなる役割を果たします。分散投資は長期運用の基本です。

井村FP
資産運用の基本は「分散投資」です。債券ファンドを組み入れることで、株式市場の変動リスクを緩和し、より安定した資産形成が可能になります。
特にリタイアメントプランや教育資金など、中長期的な目的を持つ方には、債券ファンドの活用が効果的です。
分配金が期待できる
債券ファンドは、保有する債券から得られる利息収入を原資として、
定期的に分配金を支払う仕組みを持っています。
これにより、安定した収入源としての役割を果たすことができ、特に年金生活者やインカム重視の投資家にとって魅力的です。
ただし、運用成績が悪化した場合には、分配金が元本の取り崩しによって支払われるケースもあり、資産の減少につながる可能性があります。
分配金の内容とファンドの運用状況を定期的に確認することが重要です。

井村FP
分配金の「額」だけでなく、「中身」に注目することが大切です。特別分配金が続くファンドは、実質的に資産を取り崩している可能性があります。
安定収入を目的とする場合は、分配方針や過去の実績を確認し、長期的に持続可能なファンドを選ぶようにしましょう。
債券ファンドに関するよくある質問
債券ファンドは比較的リスクが低いとされる一方で、仕組みや種類、制度上の扱いについては誤解されやすい側面もあります。
ここでは、債券ファンドに関して投資初心者から寄せられることの多い代表的な質問を取り上げ、制度や実務の観点からわかりやすく解説します。
- 債券ファンドにはどのようなリスクがありますか?
- 債券ファンドにはどのような種類がありますか?
- NISAで債券ファンドは買えますか?
- 債券ファンドに向いている人は?
債券ファンドにはどのようなリスクがありますか?
債券ファンドには、主に以下のようなリスクが存在します。
- 金利変動リスク:金利が上昇すると既存の債券価格が下落し、ファンドの基準価額も下がる可能性があります。
- 信用リスク:債券の発行体が財政難や倒産に陥ると、利息や元本の支払いが滞るリスクがあります。
- インフレリスク:物価上昇により、債券から得られる利息の実質的な価値が目減りする可能性があります。
- 為替リスク:外国債券を組み入れたファンドでは、為替変動によって円換算の価値が上下します。
債券ファンドに投資する際は、これらの債券特有のリスクを理解したうえで、ファンドの構成や運用方針を確認することが重要です。

井村FP
債券ファンドは「安全資産」と思われがちですが、リスクがゼロではありません。特に金利や為替の変動に敏感な商品です。
投資前には、ファンドの組入債券の種類や平均格付け、デュレーション(残存期間)などを確認し、自身のリスク許容度に合った商品を選びましょう。
債券ファンドにはどのような種類がありますか?
債券ファンドには、投資対象やリスク水準に応じてさまざまな種類があります。
- ソブリン債ファンド:国債を中心に投資。信用リスクが低く、安定性が高い。
- 地方債ファンド:国内外の地方自治体が発行する債券に投資。
- ハイイールド債ファンド:信用格付けの低い企業の社債に投資。高利回りだがリスクも高い。
- エマージング債ファンド:新興国の国債や社債に投資。為替・政治リスクがあるが高利回りが期待できる。
たとえばソブリン債は信用リスクが低い一方、ハイイールド債は高利回りだがリスクも高い傾向があります。目的に応じて適切な種類を選ぶことが大切です。

井村FP
債券ファンドは「どの債券に投資しているか」でリスクとリターンが大きく異なります。
たとえば、ソブリン債は安定志向の方に、ハイイールド債はリターン重視の方に向いています。ファンドの目論見書や月次レポートを活用し、投資対象の内訳を確認しましょう。
NISAで債券ファンドは買えますか?
2024年から始まった新NISA制度では、債券そのものを直接購入することはできませんが、債券を組み入れた投資信託(債券ファンド)であれば、
NISA口座での購入が可能です。
ただし、毎月分配型のファンドは対象外となるため、購入を検討する際は対象商品かどうかを事前に確認する必要があります。
債券ファンドを通じて、NISAの非課税枠を活用しながら安定的な運用を目指すことが可能です。

井村FP
NISAを活用すれば、債券ファンドの分配金や売却益が非課税になります。特に長期保有を前提としたつみたてNISAでは、信託報酬が低く、安定運用を目指す債券ファンドが選択肢となります。
非課税メリットを活かすためにも、分配型より再投資型を検討するのがおすすめです。
債券ファンドに向いている人は?
債券ファンドは、以下のような投資スタイルや目的を持つ人に向いています。
- リスク許容度が低い人:株式よりも価格変動が小さいため、安定志向の方に適しています。
- 分散投資をしたい人:株式中心のポートフォリオに債券を加えることで、全体のリスクを抑えられます。
- 長期運用を考えている人:債券ファンドは中長期での安定収益を目指す商品です。
- 定期的な収入を求める人:分配金を受け取ることで、インカムゲインを得ることができます。
だし、債券ファンドには元本割れや金利変動リスクもあるため、メリットだけでなくデメリットも理解したうえで判断することが重要です。
安定性と収益性のバランスを見極める力が求められます。

井村FP
債券ファンドは「守りの資産」として活用されることが多いですが、金利上昇局面では価格が下落するなどの注意点もあります。
メリットとデメリットは表裏一体。自分の投資目的やライフプランに照らして、適切な商品を選ぶことが大切です。
債券ファンドを買おうか迷っている人はマネーキャリアに相談を
債券ファンドが自分に合っているかどうかは、投資目的やリスク許容度、資産全体のバランスによって判断すべきです。
単体でのリスクやリターンだけでなく、ポートフォリオ全体の中でどう位置づけるかが重要です。
マネーキャリアでは、資産運用に強いFPがあなたの資産状況を俯瞰し、目的に合った運用方法を多角的に提案してくれます。
購入に迷っている人は、一度無料相談を活用して、自分に合った選択肢を見つけましょう。

井村FP
マネーキャリアのFP相談では、債券ファンドのメリット・デメリットだけでなく、他の選択肢との比較や資産全体の最適化まで幅広くサポートします。
無料で何度でも相談できるため、迷っている段階でも気軽に活用してみてください。納得のいく判断ができるはずです。
>>相談料は何度でも無料!マネーキャリアで今すぐ相談する▶︎
【まとめ】債券ファンドはデメリットもあるが向いている人も
債券ファンドを買ってはいけないと言われる理由とその背景、さらに債券ファンドのメリットや向いている人の特徴について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
債券ファンドには
元本割れや金利変動リスク、信託報酬の高さなどのデメリットがある一方で、
分散投資や安定収入といったメリットも存在します。
すべての投資家に不向きというわけではなく、リスクを抑えたい人や長期的な資産形成を目指す人には適している場合もあります。まずは債券ファンドの仕組みやリスクを正しく理解し、自身の投資目的や資産全体のバランスを踏まえて、購入の是非を慎重に検討することが重要です。
迷ったときは、FPに相談して資産全体の視点からアドバイスを受けるのが安心です。マネーキャリアの無料相談を活用して資産形成の最大化にぜひ役立てましょう。