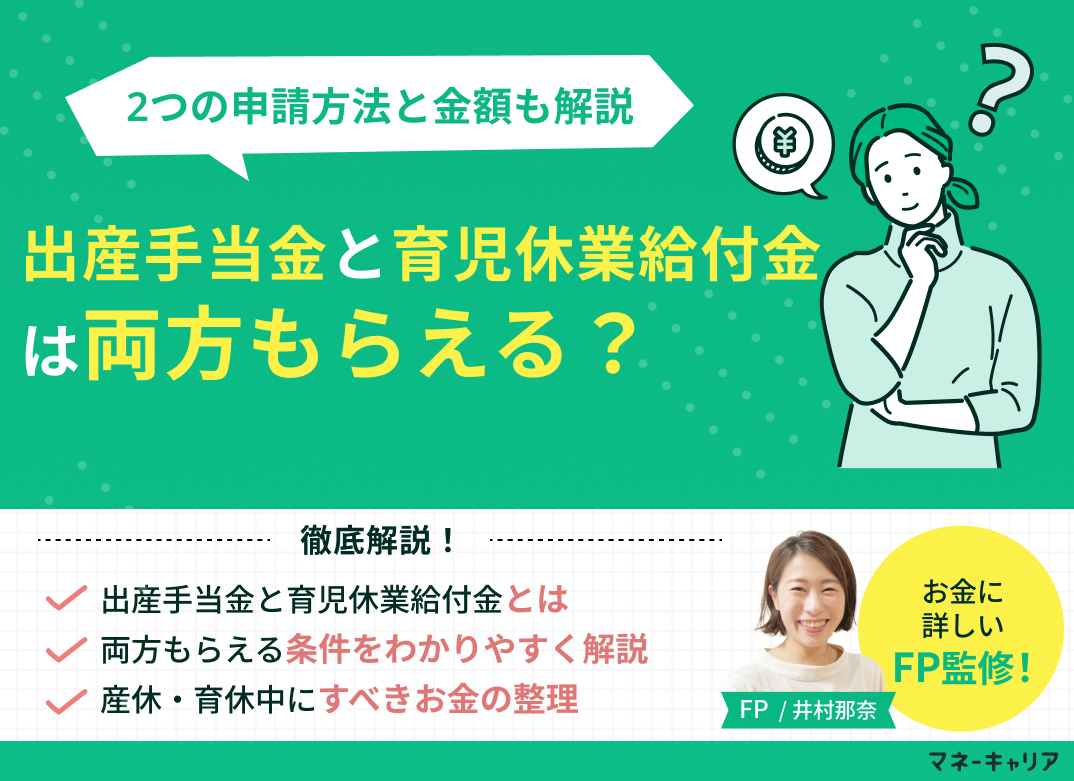
「出産手当金と育児休業給付金って、両方もらえるの?」
「どちらかしかもらえない?受取りのタイミングもよくわからない…」
そんな不安を抱えている妊娠中の方も多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、出産手当金と育児休業給付金は、条件を満たせば両方受け取れます。
ただし、それぞれの支給条件や期間、申請方法は異なるため、正しい知識が必要です。
この記事では、出産手当金と育児休業給付金の違いと受け取りのタイミング、申請方法などをわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
・「今後のお金の流れをしっかり把握したい」
・「申請ミスで損をしたくない」
そんな方は、本記事を読むことで産休・育休中に受け取れるお金を正しく把握し、家計の不安を軽減できます。
内容をまとめると
- 出産手当金と育児休業給付金は両方もらえる
- それぞれ対象者や申請タイミングが違うので要確認
- 産休・育休中は家計を見直し、お金の流れを明確にするのが大切
- マネーキャリアでは、育児期に必要な手当や家計の整え方を無料相談でサポート可能

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 出産手当金と育児休業給付金は両方もらえる?
- 出産手当金とは
- 対象者
- 受け取れる時期
- 申請方法
- 受け取れる金額
- 育児休業給付金とは
- 対象者
- 受け取れる期間
- 申請方法
- 受け取れる金額
- 産休・育休中に整えておくべきお金のこと
- 申請で受け取れるお金をリスト化する
- 生活費の見直しをする
- 将来のお金の見通しを立てる
- 出産手当金と育児休業給付金に関するよくある質問
- 会社を辞めた場合でも出産手当金や育児休業給付金はもらえる?
- フリーランスや自営業者は出産手当金や育児休業給付金の対象外?
- 育児休業中に次の妊娠が分かった場合、給付金はどうなる?
- 産休・育休中に家計を整えるならお金のプロ「マネーキャリア」に相談
出産手当金と育児休業給付金は両方もらえる?
出産手当金と育児休業給付金は、条件を満たしていれば両方もらえます。
どちらも働く方が妊娠・出産・育児に専念できるように設けられた制度です。
ただし、それぞれ支給のタイミングや目的が異なります。
出産手当金は、出産前後の休業期間中の収入を補うもので、産前42日・産後56日の計98日間が対象です。
出産手当金とは
出産手当金は、出産前後の休業期間中の収入を補うための制度です。
正しく活用するために、条件を整理しましょう。
- 対象者
- 受け取れる時期
- 申請方法
- 受け取れる金額
対象者
出産手当金の対象者は「勤務先の健康保険に加入しており、出産のために休業している方」です。
国民健康保険ではなく、会社員が加入する「健康保険」の被保険者でなければなりません。
また、妊娠・出産を理由に働けない状態であることが支給の前提です。
受け取れる時期
出産手当金が受け取れる時期は、出産前42日と産後56日の範囲で休んだ期間です。
双子以上の多胎妊娠の場合は、産前の期間が98日に延長されます。
この期間に実際に会社を休業していれば、その日数分が支給対象となります。
申請方法
出産手当金の申請は、健康保険に申請書を提出することで完了します。
まずは「健康保険出産手当金支給申請書」をダウンロードまたは勤務先から入手しましょう。
受け取れる金額
出産手当金で受け取れる金額は「標準報酬月額の約3分の2」です。
具体的には、過去12ヶ月間の標準報酬月額の平均を30で割り、それに2/3を掛けて日額を計算します。
育児休業給付金とは
育児休業給付金とは、育児のために仕事を休む方を経済的に支える制度です。
出産手当金とは異なる点もあるため、内容を確認してきましょう。
- 対象者
- 受け取れる時期
- 申請方法
- 受け取れる金額
それぞれを詳しく解説します。
対象者
育児休業給付金の対象者は、雇用保険の被保険者で以下の条件を満たす方です。
- 育休開始日前2年間に、11日以上働いた月が12ヵ月以上ある
- 育休休業中に休業開始前の8割以上の賃金が支払われていない
- 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間) 以下である
- 有期雇用なら「1年以上勤務」かつ「1歳6ヵ月まで契約満了が見込まれない」こと
受け取れる期間
育児休業給付金が受け取れる時期は、基本的に子どもが1歳になる前日までです。
ただし、条件によって1歳6ヵ月、さらには2歳まで延長できます。
申請方法
育児休業給付金は、勤務先を通じてハローワークに申請します。
まずは会社に育児休業を取得する意思を伝え、必要な書類を準備しましょう。
書類には自分で記入するものと、会社側が記入する部分の両方があり、どちらも不備なく整える必要があります。
受け取れる金額
育児休業給付金の金額は、休業開始時点の賃金日額の67%です。
具体的には、育休前6ヵ月間の賃金を180で割り、1日あたりの賃金を算出します。
この日額に支給日数(通常30日)を掛け、さらに67%を乗じて計算します。
産休・育休中に整えておくべきお金のこと
出産手当金と育児休業給付金の概要がわかっても、出産後のお金の不安が残っている方は多いのではないでしょうか。
そこで、産休・育休中に今後の家計について考えておきたいことをご紹介します。
- 申請で受け取れるお金をリスト化する
- 生活費の見直しをする
- 将来のお金の見通しを立てる
事前に情報を整理し、生活設計の見直しをしておくことで、安心して育児に専念できます。
ここからは、それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
申請で受け取れるお金をリスト化する
申請で受け取れるお金をリスト化することで、もれなく手続きを進められるでしょう。
出産手当金や育児休業給付金、出産育児一時金、児童手当など、育児期にはさまざまな給付金があります。
生活費の見直しをする
生活費の見直しは、育休中の家計を安定させる重要なポイントです。
育休中は収入が減る一方で、赤ちゃんの育児用品や医療費などの支出が増えやすくなります。
そこで、固定費(通信費・保険・サブスク)や変動費(食費・日用品など)を中心に見直し、無理のない範囲で節約できるところを探しましょう。
将来のお金の見通しを立てる
将来のお金の見通しを立てておくと、育休復帰後の不安を減らせます。
子どもが成長するにつれて教育費や生活費も大きく変化するため、 今後のライフイベント(住宅購入・教育費など)に備え、家計のシミュレーションをしておきましょう。
出産手当金と育児休業給付金に関するよくある質問
出産手当金と育児休業給付金に関する、よくある質問について解説します。
- 会社を辞めた場合でも出産手当金や育児休業給付金はもらえる?
- フリーランスや自営業者は出産手当金や育児休業給付金の対象外?
- 育児休業中に次の妊娠がわかった場合、給付金はどうなる?
それぞれのケースで条件や支給可否が異なるため、誤解のないよう確認しておきましょう。
会社を辞めた場合でも出産手当金や育児休業給付金はもらえる?
会社を辞めた場合、条件を満たせば出産手当金はもらえますが、退職後は原則として育児休業給付金の対象外となります。
ただし再就職後に条件を満たせば対象になることもあります。
出産手当金は、退職前に1年以上健康保険に加入し、退職日に出勤していなければ支給対象となります。
一方、育児休業給付金は雇用保険の被保険者に対して支給される制度です。
フリーランスや自営業者は出産手当金や育児休業給付金の対象外?
フリーランスや自営業者は、出産手当金や育児休業給付金の対象外です。
出産手当金は会社員向けの健康保険に加入している人が対象であり、国民健康保険には出産手当金の制度自体がありません。
また、育児休業給付金も雇用保険に加入している人向けの制度のため、雇用契約のない働き方では対象外です。
育児休業中に次の妊娠が分かった場合、給付金はどうなる?
育児休業中に次の妊娠が分かった場合でも、条件を満たせば再度給付金が受け取れます。
第2子の産前休業が始まる日の前日で第1子の育児休業給付金は終了し、新たに第2子分の出産・育休手当の申請が可能です。
産休・育休中に家計を整えるならお金のプロ「マネーキャリア」に相談
出産手当金と育児休業給付金は両方もらえるのか、それぞれの給付金の対象者・受け取れる時期・申請方法・金額を詳しく解説しました。
これから出産・育児を控えている方は、まず自分がもらえる制度を把握し、必要な手続きを早めに準備しておくことが大切です。
とはいえ、「出産手当金と育児休業給付金をもらっても家計が不安」と感じる方も多いでしょう。
そんな時は、「マネーキャリア」の無料相談を活用してみてください。
出産・育休中に受け取れる給付金の活用法や、生活費の見直し、将来の家計計画まで、何度でも無料で相談できます。
出産や育児に向けて家計を整えたい方は、一度マネーキャリアに相談してみてはいかがでしょうか。





























