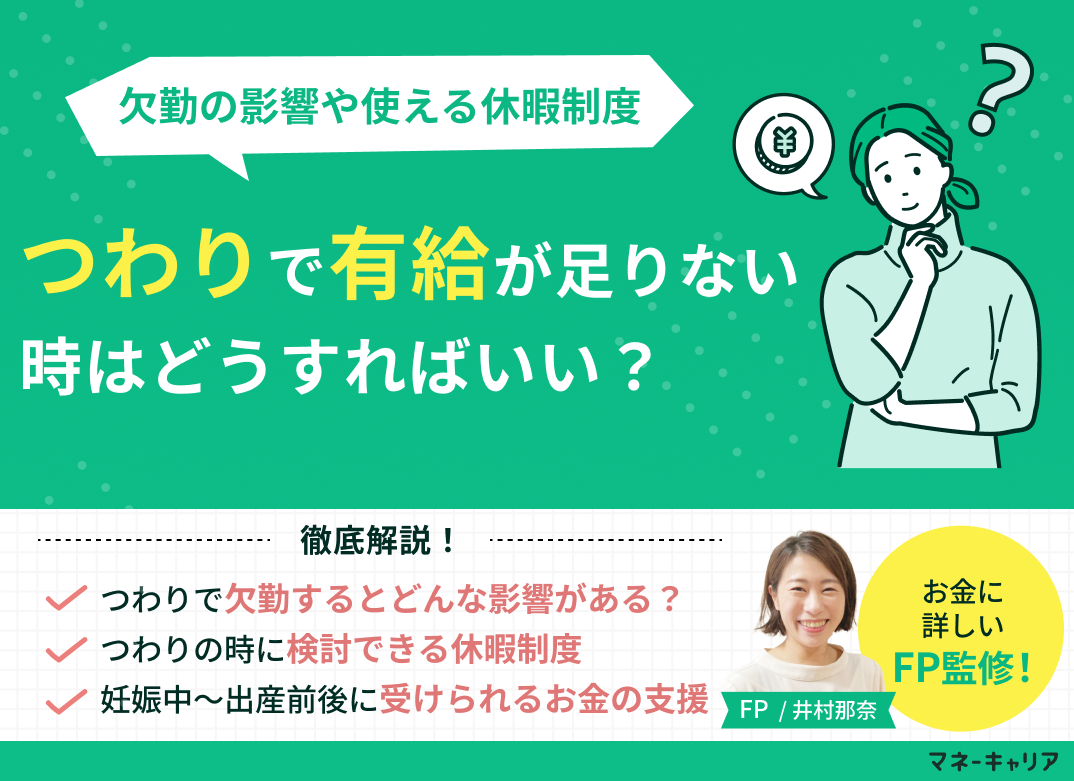
つわりで有給が足りない状況は、多くの妊婦の方が直面する共通の悩みです。
しかし、欠勤や休職、申請できる手当など、関わる制度は種類が多く複雑なため、「どれを使えばいいかわからない」「体調が悪くて調べる余裕もない」と不安を抱えながら、無理をして働く方も少なくありません。
そこで本記事では、欠勤した場合に、有給付与・育児休業給付金にどんな影響があるかや、有給以外で使える休暇制度、妊娠中〜産後に受けられるお金の支援などを詳しく解説します。
・つわりで有給休暇が足りなくなったとき、他に使える休暇制度を知りたい
・欠勤や休業による収入減が家計に与える影響に不安を感じている
上記のような悩みを抱える方は、本記事を読むことで、無理なく働ける調整方法がわかり、今後の見通しを立てやすくなります。
内容をまとめると
- 欠勤が続くと、次年度の有給付与や育児休業給付金に影響が出る場合があるため、他に使える制度を事前に把握しておくことが大切です。
- つわりの重さや勤務先の制度に応じて、欠勤以外には病気休暇・休職・時差出勤などの制度を選べます。
- 職場への伝え方は、上司や同僚など相手別に工夫することで、精神的な負担を軽くしやすくなります。
- つわりによる欠勤や収入不安に悩む方は、相談実績10万件超・満足度98.6%超のマネーキャリアで、家計の整理や見直しについて無料アドバイスを受けられます。

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- つわりで有給が足りない⋯欠勤するとどんな影響がある?
- 欠勤が一定日数を超えると翌年度の有給が付与されないことがある
- 欠勤日数が多いと育児休業給付金が減額される可能性がある
- つわりで有給が足りないときに検討できる休暇制度
- 病気休暇・つわり休暇
- 欠勤・休職
- 勤務調整が可能な「母性健康管理措置」
- 妊娠中〜出産前後に受けられるお金の支援
- 傷病手当金
- 出産手当金
- 育児休業給付金
- つわりで休むときの準備と伝え方
- 上司宛て
- 同僚・部下宛て
- つわりで有給が足りない⋯関連するよくある質問
- 軽いつわりでも仕事を休んでいいですか?
- つわりで吐いた日は仕事を休んだほうがいいですか?
- つわりで有給が足りないときは制度を知って無理しない選択をしよう【まとめ】
つわりで有給が足りない⋯欠勤するとどんな影響がある?
つわりで有給が足りない場合に欠勤すると、どんな影響があるかを、2つ解説します。
紹介する内容は以下のとおりです。
- 欠勤が一定日数を超えると翌年度の有給が付与されないことがある
- 欠勤日数が多いと育児休業給付金が減額される可能性がある
これらの影響をあらかじめ知っておくことで、制度の使い方や働き方を早めに見直す判断がしやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
欠勤が一定日数を超えると翌年度の有給が付与されないことがある
欠勤が一定日数を超えると、翌年度の有給休暇が付与されないことがあります。
その理由は、出勤日数が“所定労働日の8割未満”になると、労働基準法による有給付与の条件を満たさなくなるからです。
例えば、年間の勤務日を250日と仮定した場合、80%にあたる200日以上出勤していれば有給は付与されます。
言い換えると、欠勤が50日を超えると、有給が付与されない可能性があるということです。
ただし、制度上は欠勤日数に余裕があっても、周囲への遠慮から、思うように休めずに精神的な負担を感じる人も少なくありません。
だからこそ、制度の仕組みを知り、「法律上はどこまでなら安心して休めるか」を見極めることが、“無理のない働き方”につながります。
欠勤日数が多いと育児休業給付金が減額される可能性がある
欠勤が多くなると、子どもの誕生後に一定の要件を満たすと支給される“育児休業給付金”の支給額に影響が出る可能性があります。
なぜなら、給付額は"育休前6ヵ月間の賃金"をもとに算出され、その対象月には一定の出勤日数が必要だからです。
具体的には、賃金支払基礎日数が月11日以上ない月は、原則として計算対象に含まれません。
そのため、欠勤が続いて対象月が少なくなると、6ヵ月分の平均賃金が下がり、給付額も減る可能性があります。
まずは自分の出勤状況を確認し、就業規則や制度の条件を早めに把握しておくことが大切です。
つわりで有給が足りないときに検討できる休暇制度
つわりで有給が足りないときに検討できる休暇制度を、3つ解説します。
紹介する制度は以下のとおりです。
- 病気休暇・つわり休暇
- 欠勤・休職
- 勤務調整が可能な「母性健康管理措置」
ある企業が実施した調査では、つわりで1ヵ月に7日以上休んだ・しばらく休職した人の割合は6割以上というデータもあります。
制度ごとの特徴や取得条件を知ることで、自分の体調や状況に合った休み方を選びやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
病気休暇・つわり休暇
病気休暇や"つわり休暇"は、医師の診断書があれば取得できるケースが多く、欠勤扱いを避けて休める可能性があります。
一般的には、申請が通れば数日〜1週間前後の休暇が認められることもあり、症状の重い時期を乗り切る手段になります。
ただし、病気休暇やつわり休暇はすべての会社に共通の制度ではないので、就業規則で定められているかどうかがポイントです。
利用には事前申請や診断書の提出が必要になることが多いので、会社ごとの条件を早めに確認しておきましょう。
欠勤・休職
欠勤や休職は、医師の診断がない場合でも選択できる可能性があります。
特に欠勤は、法律上、診断書の提出が必須ではないため、比較的とりやすい休み方といえるでしょう。
一方で、休職は長期の休みを前提とした制度であり、就業規則によって“診断書の提出”や“期間・理由の制限”が設けられていることが一般的です。
また、どちらのケースでも、休んでいる期間中は給与が支給されないことが多く、家計への影響を事前に確認しておくことも大切です。
制度の条件や支給の有無を事前に把握しておくことで、心身の負担を減らしながら“無理のない働き方”を選びやすくなります。
勤務調整が可能な「母性健康管理措置」
“母性健康管理措置”は、医師の指導があれば勤務の調整ができる制度です。
例えば、時差出勤・勤務時間の短縮・休憩延長・通勤緩和など、体調に合わせて無理なく働くための配慮を受けられます。
この制度は男女雇用機会均等法(第13条)で企業に対応が義務づけられているので、遠慮せずに申し出てみましょう。
申し出の際は、“母性健康管理指導事項連絡カード”を使うと、医師の指導内容が伝わりやすくなります。
就業を続けながら体調を守る手段として、制度の活用を前向きに考えてみましょう。
妊娠中〜出産前後に受けられるお金の支援
妊娠中〜出産前後に受けられるお金の支援を、3つ解説します。
紹介する制度は以下のとおりです。
- 傷病手当金
- 出産手当金
- 育児休業給付金
このあと詳しく解説しますが、傷病手当金は必ずしも妊娠中すべての方が対象になるわけではありません。
それぞれの支給額や申請条件を知ることで、経済的な不安を減らしながら安心して出産・育児に向き合いやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
傷病手当金
傷病手当金は、体調不良などで働けないと医師に診断されたとき、健康保険から支給される制度です。
給与が支払われない状態で会社を休んだとき、連続3日間の待期期間を経て、4日目以降に日給の3分の2相当額が支給されます。
ただし、支給には、"就労不能であること"・"会社から給与の支払いがないこと"など、いくつかの条件を満たす必要があります。
特に妊娠を理由とする休業は、病気として認められにくい場合もあるため、医師の診断内容が重要になります。
体調を最優先にしながら、家計への影響を減らす手段のひとつとして、制度の内容を事前に確認しておきましょう。
出産手当金
出産手当金は、産前産後に仕事を休む間の収入減を補うための、健康保険制度です。
健康保険に加入している被保険者(勤務先で社会保険に加入している人)が対象で、原則として、"出産予定日の42日前から出産後56日目まで"の間に給与の支払いがない場合に支給されます(多胎妊娠の場合は出産前98日から)。
支給額の目安は、標準報酬日額の3分の2相当で、産休中に給与が支給されない場合でも一定の生活費をカバーできます。
申請は、勤務先を通じて加入している健康保険組合に必要書類を提出する方法が一般的です。
手続きが不安な場合は、早めに人事や保険担当窓口に相談して、もらい漏れがないよう準備を進めておくと安心です。
育児休業給付金
育児休業給付金は、1歳未満の子を育てるために育休を取得した方の収入をサポートする制度です。
支給額は、休業開始から180日間は賃金の67%、それ以降は50%が支給されるため、無収入にならずに育児に専念しやすくなります。
受給には、雇用保険に加入していることに加えて、育休開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヵ月以上あることなどの条件を満たす必要があります。
申請は原則として職場を通じておこない、途中で復職した場合は、その時点で給付が終了します。
出産前から制度の仕組みを知っておくことで、収入の見通しが立てやすくなり、安心して育児に向き合う準備ができます。
つわりで休むときの準備と伝え方
つわりで休むときの準備と伝え方を、2つ解説します。
紹介する方法は以下のとおりです。
- 上司宛て
- 同僚・部下宛て
制度を使って休むと決めたとき、悩みやすいのが、職場への伝え方です。
相手の立場に合わせて伝え方を工夫することで、余計な気遣いや誤解を減らし、気持ちよく休職に入る準備がしやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
上司宛て
同僚・部下宛て
つわりで有給が足りない⋯関連するよくある質問
つわりで有給が足りない悩みに関連するよくある質問を、2つ解説します。
紹介する質問は以下のとおりです。
- 軽いつわりでも仕事を休んでいいですか?
- つわりで吐いた日は仕事を休んだほうがいいですか?
体調に応じた判断の幅を知ることで、不安を減らしながら無理のない働き方を選びやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
軽いつわりでも仕事を休んでいいですか?
つわりで吐いた日は仕事を休んだほうがいいですか?
つわりで有給が足りないときは制度を知って無理しない選択をしよう【まとめ】
つわりで有給が足りないときは、制度を知って、自分の体調に合わせた無理のない選択をすることが大切です。
例えば、母性健康管理措置や、会社に制度があれば病気休暇・つわり休暇を使うことで、勤務時間や働き方を柔軟に調整しやすくなります。
さらに、出産手当金や育児休業給付金などの金銭的支援を知っておくことで、欠勤や休職で収入が減ったとしても、安心して休む準備もしやすくなります。
とはいえ、制度の内容や条件を自分だけで調べるのは、負担に感じる方も多いでしょう。
つわりで仕事を休むことによって収入に不安を感じる方や、使える制度の把握に迷っている方は、専門家(FP)への相談をおすすめします。





























