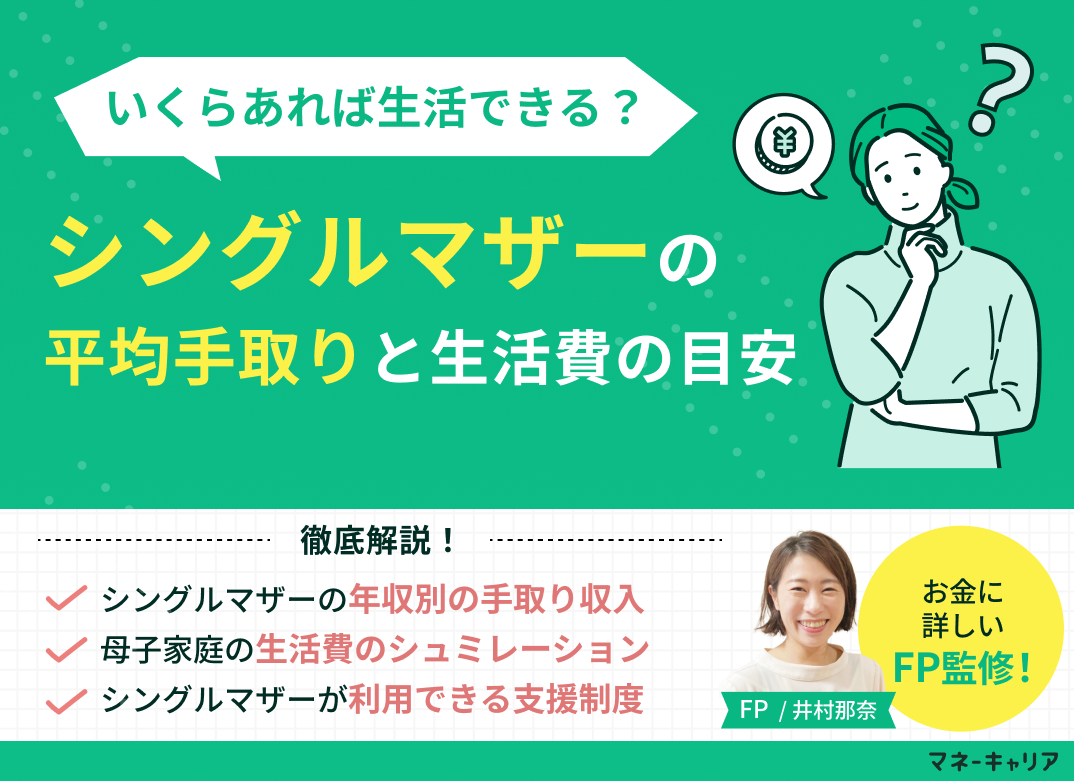
内容をまとめると
- シングルマザーの手取り収入は年収や雇用形態で大きく異なり、生活の安定に向けて正確な手取り額の把握が重要である
- 生活費の適正な割合や子どもの人数別の支出目安を確認し、児童扶養手当や各種支援制度を積極的に利用することで家計の負担を軽減できる
- 手取り収入を増やすためには賢い家計管理と副業やスキルアップによる収入アップが有効であり、長期的な資金計画も必要である
- マネーキャリアは忙しいシングルマザーでも利用しやすいオンライン対応で、多数の経験豊富なFPが手取り計算や支援制度活用法まで幅広い内容を無料相談できる

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- シングルマザーの年収別の手取り収入と計算方法
- 手取り額の計算方法
- シングルマザーの年収別の手取り額の目安
- シングルマザーマザーの手取り額が少ない原因は?
- 母子家庭の生活費のシュミレーションと内訳
- 月々の生活費の適正割合は?
- 子どもの人数別生活費の目安
- シングルマザーが利用できる手当や支援制度
- 児童扶養手当の仕組みと受給条件
- 住宅関連の支援制度
- 医療費関係の助成制度
- 教育関連の支援制度
- その他の支援制度と税制優遇策
- シングルマザーの手取り収入を増やす方法2つ
- 賢い家計管理で支出を減らす
- 副業やスキルアップで収入アップを目指す
- 家計管理や資金計画に悩んだらFP相談窓口を利用しよう
- シングルマザー手取りに関するよくある質問
- シングルマザーの年収はいくらが得ですか?
- シングルマザーの手取り額の平均はどのくらいですか?
- シングルマザーですがお金がなくて疲れました
- まとめ
シングルマザーの年収別の手取り収入と計算方法
シングルマザーの手取り収入は、額面収入から税金や社会保険料を差し引いた後の金額です。
年収に応じて変動し、生活の安定度にも大きく影響します。
ここでは、手取り額の計算方法と年収別の目安を具体的に解説します。
手取り額の計算方法
手取り額は、給与や収入から主に以下を差し引いた後の金額です。
- 所得税
- 住民税
- 健康保険料
- 年金保険料
- 雇用保険料
給与所得者の場合、税金や保険料は源泉徴収として毎月自動的に引かれます。
所得税は所得控除や扶養控除などを考慮して計算され、住民税は前年の所得に基づき課税されます。
例えば年収300万円の場合、合計で約15~20%がこれらの税や保険料として差し引かれ、手元に残るのは240万円前後です。
シングルマザーとして子供を育てるためには、額面年収を気にするのではなく、正確な手取り額を把握して、家計管理や収入アップの戦略を立てましょう。
シングルマザーの年収別の手取り額の目安
シングルマザーの手取りは年収によって異なります。
以下が年収毎の手取り額の目安です。
| 額面年収 | 月の手取り額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 100万円 | 7〜8万円 | 非正規雇用での低収入層 |
| 200万円 | 13万円 | 非正規~正社員初期レベル |
| 300万円 | 20万円 | 正社員の平均的な手取り額 |
| 400万円 | 25万円 | 正社員、中間層 |
| 500万円 | 31万円 | 税・保険料が若干増加し、手取り率は減少傾向 |
| 600万円 | 36万円 | 高収入帯だが税負担増加により手取り率は低下 |
| 700万円 | 41万円 | 税金・保険料の負担がさらに増加 |
| 800万円 | 46万円 | 高収入層、手取り率は年収の55〜60%程度と想定 |
例えば、年収200万円の場合は月の手取りが13万円程で、年収300万円なら20万円前後です。
正社員で年収が400万円を超えると、税金や社会保険料の負担が増えるため手取り率はやや低下しますが、年間の手取り額は300万円程度、月収で25万円前後になります。
一方、パートやアルバイトが中心の非正規雇用の場合、年収はおおむね100万円から150万円程度です。
月々の手取りは8万円から10万円程度にとどまる場合が多く、生活費の確保に苦労するケースが目立ちます。
なお、上記の金額に児童扶養手当や支援制度、養育費は含まれていません。
シングルマザーは児童扶養手当や支援制度を活用すると、さらに手取りが増やせる可能性があります。
シングルマザーマザーの手取り額が少ない原因は?
シングルマザーの手取りが少ない大きな原因の1つに、雇用形態の問題があります。
正社員としてフルタイムで働ける人は限られ、多くはパートやアルバイト、非正規雇用に従事しており、平均年収も低めです。
また、子育てと仕事の両立が難しいため、長時間勤務ができず、キャリア形成やスキルアップの機会も十分ではありません。
さらに一般世帯と比較すると収入に大きな格差があり、生活費や教育費を賄うのが困難なケースも多く見られます。
シングルマザーの手取り額を増やすためには、安定した仕事や多様な働き方、そしてキャリア支援などの社会からの支えがより一層必要だと言えます。
母子家庭の生活費のシュミレーションと内訳
母子家庭の生活費は、家族構成や居住地域、子どもの年齢などによって大きく変わります。
この章では、シングルマザーの月々の生活費の適正な割合や子どもの人数別の生活費目安を知り、支出をシミュレーションしてみましょう。
月々の生活費の適正割合は?
総務省統計局や厚生労働省のデータを基にしたシングルマザーの生活費割合の目安は、以下の通りです。
| 生活費項目 | 適正な割合 | 手取り20万円の場合の金額 |
|---|---|---|
| 住居費 | 10~15% | 2.0~3.0万円 |
| 食費 | 20~25% | 4.0~5.0万円 |
| 水道光熱費 | 7~8% | 1.4~1.6万円 |
| 通信費 | 5~6% | 1.0~1.2万円 |
| 教育費 | 5~10% | 1.0~2.0万円 |
| 医療費 | 3~5% | 0.6~1.0万円 |
| 被服費 | 3~5% | 0.6~1.0万円 |
| 交通費 | 5~7% | 1.0~1.4万円 |
| 娯楽・交際費 | 5% | 1.0万円 |
| その他雑費 | 5% | 1.0万円 |
シングルマザーの生活費の適正な割合は、住居費が約10%から15%で、手取り20万円の場合だと2万円から3万円程度です。
都市部では家賃相場が高く、生活費がさらに3万円以上増えることもあります。
食費は20%から25%で、月に4万円から5万円が目安です。
教育費は5%から10%で、子どもの人数や年齢に応じて1万円から2万円が必要になります。
上記はあくまで目安ですが、参考にして、計画的に支出の割合や金額を決めましょう。
子どもの人数別生活費の目安
子どもの人数が増えると、それに応じて生活費も増加します。
| 子どもの人数 | 月の生活費の目安 |
|---|---|
| 1人 | 19~20万円 |
| 2人 | 22万円 |
| 3人 | 25万円 |
1人の場合は月約19~20万円が目安で、2人になると食費や教育費が増えて月の支出は約22万円になります。
支出項目としては、食費の増加が顕著です。
3人家族の場合は約25万円が目安で、住居も広めが必要になるため家賃も上昇しやすくなります。
加えて、子どもの年齢が上がるにつれて教育費や通信費も増加するため、必要な生活費はさらに増える傾向があります。
これらを踏まえ、家計の見直しや支出の優先順位を考え、将来を見据えた貯蓄計画も合わせて検討することが重要です。
シングルマザーが利用できる手当や支援制度
シングルマザーの生活を支えるため、多くの手当や支援制度が用意されています。
所得や家庭状況に応じた条件がありますが、児童扶養手当や住宅支援、医療費助成、教育支援など多岐にわたります。
条件を理解し、積極的に利用すると家計の負担軽減が期待できます。
ここでは代表的な制度の仕組みと受給条件を詳しく解説します。
児童扶養手当の仕組みと受給条件
児童扶養手当は、ひとり親世帯の生活支援を目的とした手当で、概要は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給対象 | 18歳の誕生日後の最初の3月31日までの子どもを監護するひとり親世帯 |
| 支給額 | 所得に応じて全額支給・一部支給・支給なしの3段階に区分 【全額支給】母子2人世帯:年収約160万円以下 【一部支給】年収365万円以下 【支給なし】それ以上 |
| 支給額 | 第一子:月額約4万3,070円(全額支給の場合)
第二子以降:加算あり(例:第二子は約1万170円加算) |
| 申請方法 | 市区町村役場で申請が必要 |
| 支給日 | ・原則として申請の翌月から支給開始。 ・支給は原則2ヶ月に1回(偶数月)にまとめて支払われることが多い |
18歳の誕生日後の最初の3月31日までの子どもを監護するひとり親が対象で、所得に応じて区分され、支給額が決まります。
例えば、母子2人世帯なら年収約160万円以下で全額支給、365万円以下で一部支給が受けられます。
申請は市区町村役場で行い、同居している祖父母などの所得も影響を受けるため注意が必要です。
支給額は子どもの人数に応じて加算され、シングルマザーにとって経済的に大きな支えになっています。
住宅関連の支援制度
自治体によってはひとり親家庭向けの住宅支援制度があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | ひとり親家庭を含む低所得世帯 |
| 支援内容 | ・家賃補助 ・公営住宅の優先入居 ・収入審査の緩和 |
| 申請条件 | 自治体ごとに異なり、所得制限や居住地域の条件がある場合が多い |
| 募集期間 | 限定されている場合が多く、タイミングが重要 |
住宅関連の支援制度は、ひとり親家庭や収入が少ない世帯が対象の場合が多いです。
家賃の一部を助けてもらえたり、公営住宅に優先的に入れたりする支援があります。
また、収入の審査がゆるくなるケースもあります。
申請条件や支援内容は自治体ごとに異なり、所得制限や居住地域の条件がある場合が多いため、確認は必須です。
募集期間が限定されている場合も多く、募集期間に合わせての申請が重要です。
詳細についてはお住まいの自治体の公式ホームページや役所で確認しましょう。
医療費関係の助成制度
医療費助成は自治体が実施する子どもやひとり親家庭向けの支援制度です。
子どもの医療費が無料または低額になるケースが多く、所得制限がある場合もあります。
さらに、一部の自治体ではシングルマザーの医療費も助成対象になるがところがあります。
費用を気にせず、子供を医療機関で受診させられるのはシングルマザーにとって嬉しい支援です。
助成内容や対象年齢は地域により異なるため、詳細は市区町村役場で確認が必要です。
急な医療費の出費のときはとくに負担軽減に役立ちます。
教育関連の支援制度
幼稚園から高校まで公立学校に通う子どもがいるシングルマザーは、支給条件を満たしていれば、幼稚園から高校までの授業料が無償になる可能性があります。
| 対象学年 | 制度名 | 支援内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 幼児 | 幼児教育・保育の無償化制度 | 幼稚園や保育園の利用料が無料 (一部除く) | 0~2歳は住民税非課税世帯対象 3~5歳は全ての幼児が対象 |
| 小・中学校 | 義務教育 | 授業料無料、教科書代無償 | 公立のみ対象 |
| 高校(公立) | 高等学校等就学支援金制度 | 授業料実質無償化 | 2025年4月から所得制限撤廃で広く利用可能 |
| 高校(私立) | 高等学校等就学支援金制度 | 所得に応じた支援金額 | 所得により支援金額が異なる |
| 小学校~高校 | 学用品費・通学費補助 (自治体による) | 学用品や通学費の補助 | 自治体により有無や条件が異なる |
幼児教育・保育の無償化制度により、3歳から5歳の子どもや、住民税非課税世帯の0~2歳児は幼稚園や保育園の利用料が無料です。
小・中学校は義務教育のため授業料はかからず、教科書代も無償です。
高校では、高等学校等就学支援金制度により公立高校の授業料が実質無償化されており、私立高校に通う場合でも所得に応じた支援金が受けられます。
申請は学校や自治体を通じて行うため、手続きを忘れないことが重要です。
シングルマザーが支給条件を満たし、子どもがずっと公立学校に通う場合、授業料がほとんどかからず教育費の負担を大きく軽減できる可能性が高いです。
公的な支援をフル活用し、子どもの教育にかかる費用を抑えると、将来の資金計画も立てやすくなります。
その他の支援制度と税制優遇策
その他にも、シングルマザーが活用できる支援制度や税制優遇策があります。
| 支援制度 | 内容 |
|---|---|
| ひとり親控除 | ひとり親の納税者に対する所得控除。 最大35万円が所得から差し引かれる |
| 国民年金・国民健康保険料減免 | 収入が低い場合に保険料の減免が受けられる |
| 遺族年金 | 一定の条件を満たす場合に受給できる年金 |
| 公的貸付制度 | 低利または無利子での貸付が受けられる制度 |
ひとり親控除は、ひとり親が所得税の負担を軽くするための制度で、最大35万円が所得から差し引かれます。
国民年金や国民健康保険料の減免は、収入が一定以下の世帯を対象に保険料の減額や免除を受けられます。
もしも何も手続きなく滞納してしまうと、以下の可能性があります。
- 将来年金を満額受け取れない
- 国民健康保険の給付が制限される
- 延滞金が発生する
- 最悪の場合は差し押さえなどの法的措置を受ける
国民年金や国民健康保険料が払えない状況になったら、早めに減免制度の申請を検討しましょう。
遺族年金は、配偶者を亡くした場合に一定の条件を満たすと受給でき、生活の支えになります。
また、公的貸付制度では、低利もしくは無利子でお金を借りることが可能です。
利用可能なものは積極的に使いこなすと、シングルマザーの生活の安定に役立ちます。
シングルマザーの手取り収入を増やす方法2つ
シングルマザーが生活を安定させるためには、手取り収入を増やすことが大切です。
主に、支出を賢く管理して無駄を減らす方法と、副業やスキルアップで収入を上げる方法があります。
ここではそれぞれの具体的なポイントを解説し、具体的な取り組み方を紹介します。
賢い家計管理で支出を減らす
家計管理を見直すことで支出を抑えると、実質的に手取り収入を増やすことが可能です。
まずは収入と支出を正確に把握し、無駄遣いを減らすことが基本ですが、それに加えて各種控除や制度を積極的に利用することも重要です。
| 制度名 | 概要 |
|---|---|
| ふるさと納税 | 自分の住んでいる自治体以外に寄付を行うことで、翌年の住民税や所得税が控除される制度。 返礼品も受け取れる場合が多い。 |
例えば、ふるさと納税を活用すると住民税や所得税が軽減されるため、節税効果が期待できます。
こうした控除を活用しつつ、公営住宅や家賃補助の利用で住居費を抑え、食費は計画的に買い物や特売を利用しましょう。
さらに、光熱費や通信費も格安SIMや電力プランの見直しでも家計の支出の削減が可能です。
家計の見直しと節税を組み合わせて取り組むと、無駄な支出を減らし、必要な支出に賢くお金を使えます。
副業やスキルアップで収入アップを目指す
収入を増やすためには、副業やスキルアップも効果的です。
まず、自分の得意分野や時間に合わせて始められる在宅ワークやフリーランスの仕事を検討しましょう。
未経験でも挑戦できる仕事も多く、生活リズムに合わせて無理なく続けることが可能です。
月に5,000円でも稼げれば、年間で6万円収入を増やせます。
加えて、資格取得や専門スキルの習得をすると正社員へのステップアップも目指せます。
例えば、以下の資格は需要が高く、安定した収入を得やすい分野です。
- IT関連
- 介護福祉
- 保育
複数の収入源を持つと経済的リスクを分散でき、将来の安心にもつながります。
家庭と両立しながら計画的に取り組むことが大切です。
家計管理や資金計画に悩んだらFP相談窓口を利用しよう
家計の見直しや資金計画に迷うときは、専門家への相談が大きな助けになります。
ファイナンシャルプランナー(FP)は、一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面でサポートを行う専門家です。
以下の幅広い知識を持ち、収入や支出のバランスから将来のライフイベントまで総合的にアドバイスしてくれます。
- 家計の収入や支出
- 資産
- 負債
- 保険
- 年金
- 税金
- 住宅ローン
例えば、限られた予算の中で効率よく貯蓄をする方法や保険の見直し、子どもの教育資金の準備計画を具体的に示してくれます。
自分だけでは気づきにくい改善点や活用できる支援制度も教えてもらえるため、経済的な不安を抱える方にとって心強い相談相手です。
シングルマザー手取りに関するよくある質問
シングルマザーの収入や生活状況に関する疑問は多く、年収の目安や実際の手取り額、経済的な疲れについての不安が多く寄せられます。
ここでは、以下の疑問に対してわかりやすく解説します。
- シングルマザーの年収はいくらが得ですか?
- シングルマザーの手取り額の平均はどのくらいですか?
- シングルマザーですがお金がなくて疲れました
シングルマザーの年収はいくらが得ですか?
シングルマザーの年収の目安は、家庭の状況や子どもの人数によって変わりますが、おおよそ300万円から400万円くらいあると暮らしやすいと言われています。
300万円から400万円の収入があれば、毎月の手取り収入は20万円から25万円程度あり、家賃や食費、子育ての費用をまかないつつ、貯金や子どもの教育費の準備も可能です。
税金の控除や手当を上手に活用すると、実質的な手取りが増える場合もあります。
ただし、収入が増えると一部の支援が受けられなくなることもあるため、収入と支援のバランスを考えることも大切です。
自分の家庭に合った資金計画を立て、無理なく収入アップを進めましょう。
シングルマザーの手取り額の平均はどのくらいですか?
シングルマザーの手取り収入の平均は、月約18万円、年収に換算すると272万円です。
これは就労収入だけで、児童扶養手当や養育費などの支援を含めると世帯全体の平均年収は373万円になります。
正社員の平均就労収入は344万円、非正規は150万円と雇用形態で差が大きいのが特徴です。
生活費の平均は月20万円前後で、収入と支出のバランスを考えると、家計管理や支援制度の活用が不可欠です。
シングルマザーですがお金がなくて疲れました
お金の悩みはシングルマザーにとって大きなストレスの元となりがちです。
収入や支出のバランスがうまく取れず、将来の不安が募ることも少なくありません。
そんな時は、一人で抱え込まずに専門家に相談することが重要です。
ファイナンシャルプランナーは、支出の見直しから資金計画の提案、利用可能な公的支援の案内まで、的確にアドバイスしてくれます。
心身の健康を保ちつつ、長期的に安定した生活を送るために、早めの相談が効果的です。




























