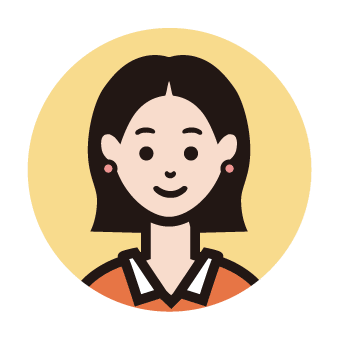▼この記事を読んで分かること
・政府による光熱費支援制度の内容と世間の声
・電気・ガス・水道の負担を減らすための具体的な節約術
・家計全体の見直しと改善策を見つけたい方におすすめのサービス
電気代やガス代の高騰により、支出が増えて家計が苦しくなってきたと感じている方も多いのではないでしょうか。
また、光熱費を抑えるために国の支援制度があると聞いても、「内容がよくわからない」「自分が対象かどうか判断できない」といった不安を抱えている方もいるかもしれません。
そこでこの記事では、政府による光熱費支援制度の概要や申請方法に加え、電気・ガス・水道それぞれの節約方法、さらに家庭ごとの事情に合った見直しポイントについても詳しく解説していきます。
この記事を読むことで、国の制度を正しく活用しつつ、日々の生活でできる無理のない節約を実践することができ、家計の不安を減らし持続可能な暮らし方が見えてきますよ。
内容をまとめると
- 政府はエネルギー価格の高騰を受けて、電気・ガス代を1世帯あたり約45,000円支援する政策を実施しており、電力・ガス会社への補助を通じて光熱費の軽減を図っています。
- ただし、支援策は期間限定のため、電気代の契約プランの見直しや家電の使い方、ガスの給湯・調理方法、水道の節水グッズ活用などの節約術を駆使するのが大切です。
- とはいえ、家庭ごとの最適な対策は異なるため、「何から始めればいいか分からない」と迷う方は、専門家に無料で何度でも相談できる「マネーキャリア」を利用するのがおすすめです。

監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 「光熱費世帯あたり約45,000円の支援」とはどんな施策?
- 電気代の支援
- ガス代の支援
- 家計支援策に対する声とは
- 光熱費の節約方法とは
- 電気代を賢く下げる!契約プラン見直しと家電の節電術
- ガス代を無理なく節約!給湯と調理の簡単テクニック
- 国や自治体による光熱費支援制度・補助金
- 水道代の節約方法とは
- お風呂・シャワーで実践!今日からできる節水習慣
- キッチン・洗濯・トイレで見直せる!効果的な節水術
- 意外と見落としがち?水漏れチェックと節水グッズ活用法
- よくある質問
- 季節ごとの光熱費節約のポイントは?
- オール電化と従来型のガス併用、どちらが光熱費は安くなりますか?
- 電力・ガスの自由化で会社を変更すると本当に安くなりますか?
- 光熱費の支援・家計のやりくりに悩んだら取るべき方法とは?
- 光熱費やガス代・水道代の節約方法まとめ
「光熱費世帯あたり約45,000円の支援」とはどんな施策?
ガソリン補助金の期限延長とともに発表された政策で、電気・都市ガスの小売業者が値下げした分を、政府が補助金で支援する仕組みです。
当記事では、実際にどのような支援があるのか、電気やガスなどの種類ごとに解説していきます。
電気代の支援
ガス代の支援
家計支援策に対する声とは
政府が実施した光熱費支援策には、一定の評価もある一方で、さまざまな課題や不満の声も聞かれます。
中でも「9カ月の期間限定では根本的な解決にならない」といった懸念が多く、支援終了後の生活不安を訴える声が目立ちます。
また、「世帯ごとの状況に応じた支援ではない」との指摘もあり、子育て世帯や単身者など、生活スタイルの違いが考慮されていない点に疑問を持つ人も少なくありません。
さらに、「税負担の軽減を優先してほしい」という意見もあり、今回の施策に対する評価は一様ではないのが実情です。
こうした声から見えてくるのは、支援制度だけに依存せず、自ら光熱費を抑える工夫や、家計全体を見直す姿勢の重要性です。
次章では、家庭で実践できる節約術をご紹介します。
光熱費の節約方法とは
光熱費の負担を軽くするには、国や自治体による支援制度を活用するだけでなく、日常生活の中での工夫や見直しも重要です。
特に電気・ガスは使用量が多く、ちょっとした工夫で大きな節約につながることがあるため、ここでは以下の3つの視点から光熱費の節約方法を具体的に紹介していきます。
電気代を賢く下げる!契約プラン見直しと家電の節電術
電気代を節約する第一歩は、契約プランの見直しです。
電力会社ごとに用意されている時間帯別料金や季節別プランを活用することで、ライフスタイルに合った最適なプランを選べば、年間で数千円〜数万円の節約も可能です。
特に、夜間に使用が多い家庭は「夜得プラン」などの割安なメニューが効果的です。
また、家電の使い方も重要で、待機電力を抑えるためにこまめに電源を切ったり、省エネ性能の高いLED照明や冷蔵庫に切り替えることで、大きな節約につながります。
エアコンの設定温度を夏は28℃、冬は20℃程度に保つことも効果的です。無理なく続けられる工夫で、電気代を上手に抑えましょう。
ガス代を無理なく節約!給湯と調理の簡単テクニック
ガス代の節約には、毎日の給湯や調理の見直しがカギとなります。
例えば、シャワーは短時間で済ませ、追い焚き回数を減らすだけでもかなりの節約になりますし、節水・節ガスシャワーヘッドの導入も効果的です。
調理では、鍋にフタをすることで加熱時間を短縮したり、まとめて下ごしらえして冷凍保存するなど、効率的な方法が節約につながります。
また、ガスコンロの炎が鍋の底からはみ出さないように調整するだけでも、熱効率が上がりガスの無駄を減らせます。
このように、特別な設備投資をしなくても日常の小さな工夫だけで着実にガス代を抑えることが可能ですよ。
国や自治体による光熱費支援制度・補助金
各家庭の負担を軽減するため、国や自治体ではさまざまな光熱費支援策が実施されています。
たとえば、2023年に実施された電気・ガス料金に対する国の補助金制度では、一定の料金を値引きする形で多くの家庭が恩恵を受けました。
一部の自治体では、高齢者世帯や子育て世帯を対象にした追加支援や、光熱費に限定せず家計全体の補助金制度を設けているところもあります。
支援を受けるには申請が必要な場合も多いため、住んでいる地域の自治体ホームページを確認することが大切です。
自分がどの制度の対象になるかを知ることで損をせずに済むので、積極的に情報を収集し、活用していきましょう。
水道代の節約方法とは
水道代は毎月の家計の中でも見落とされがちな出費ですが、実は工夫次第で大きく抑えることができます。
特に家族が多い家庭や、お風呂・洗濯などの水使用量が多い家庭では、ちょっとした習慣の見直しで年間数千円〜1万円以上の節約につながるケースも少なくありません。
ここでは、以下の3つのポイントに分けて水道代の節約法を紹介します。
お風呂・シャワーで実践!今日からできる節水習慣
まず実践したいのは、シャワーの使用時間を短縮することです。
たとえば、シャワーを5分短縮するだけで、1回あたり約60リットルの水が節約できます。
家族全員が意識すれば、月間で数千リットルの削減につながります。
さらに、節水型のシャワーヘッドを使えば、同じ使用時間でも水量を30〜50%削減可能です。
また、湯船にお湯を溜める場合は家族で続けて入浴することで追い焚きの回数を減らし、ガス代も同時に節約できます。
毎日使うお風呂だからこそ、無理なく続けられる習慣で大きな節水効果が期待できます。
キッチン・洗濯・トイレで見直せる!効果的な節水術
水道代を抑えるには、キッチン・洗濯・トイレといった日常的に使用する場所の見直しも欠かせません。
キッチンでは、食器洗いの際に水を出しっぱなしにせず、まとめ洗いを心がけるだけで大きな節水になります。
食洗機を利用する場合は、節水モードを活用するのがおすすめです。
洗濯では、洗濯物を溜めてからまとめて洗う、すすぎ回数を減らす、節水型の洗濯機を活用するなどの工夫が効果的です。
また、トイレは家庭で2番目に水を消費する場所なので、節水型トイレの導入や、タンクにペットボトルを入れるなどの簡易的な方法でも節水が可能です。
こうした工夫を積み重ねることで、毎月の水道代が確実に下がっていきます。
意外と見落としがち?水漏れチェックと節水グッズ活用法
見落とされがちな水道代の原因の一つが「水漏れ」です。
蛇口やトイレのタンクからのわずかな水漏れでも、月単位・年単位で見ると大きな浪費になります。
定期的に蛇口の締まり具合やタンクの水位を確認し、異常があれば早めに修理することが重要です。
また、蛇口に取り付ける節水アダプターや、シャワーヘッドの水量調整機能、トイレの節水コマなど、安価で簡単に導入できる節水グッズの活用も効果的です。
最近ではホームセンターやネットショップでも手軽に手に入りますし、 気づきにくい部分をチェックし、便利なグッズをうまく取り入れることで、無駄な出費を抑えたスマートな水道代節約が実現できます。
よくある質問
光熱費の節約や支援制度の活用に関心が高まる中で、多くの方が共通して抱える疑問があります。
ここでは、特にお問い合わせの多い以下の3つの質問について、分かりやすく解説していきます。
季節ごとの光熱費節約のポイントは?
季節によって光熱費の使い方が変わるため、対策もそれに応じて工夫が必要です。
たとえば、冬は暖房の使用が増えるため、窓に断熱シートを貼る、こたつや電気毛布などの部分暖房を併用することで、エアコンの使用を抑えられます。
また、加湿器を使うと体感温度が上がるため暖房効率も改善します。
一方、夏は冷房対策が中心になります。
すだれや遮熱カーテンを使う、日中は窓を閉めて冷気を逃がさないようにするなどの工夫が有効です。
扇風機とエアコンの併用も省エネにつながります。
春と秋は比較的光熱費がかからない時期ですが、この期間を使って家電の見直しや節約習慣の定着を図ると、年間を通しての光熱費削減に効果的ですよ。
オール電化と従来型のガス併用、どちらが光熱費は安くなりますか?
「オール電化」と「ガス併用」のどちらが光熱費を抑えられるかは、家庭のライフスタイルや住んでいる地域の電気・ガス料金によって変わります。
オール電化は深夜電力の安さを活かし、エコキュートやIHクッキングヒーターなどの高効率機器と組み合わせれば、特に夜間の使用が多い家庭には有利です。
一方で、ガス併用の場合は初期コストが抑えられ、調理の火力や給湯の速さといった利便性も高いという利点があります。
ただし、都市ガスに比べてプロパンガスは単価が高いため注意が必要です。
結論として、各エネルギーの単価、生活パターン、設備の導入コストなどを比較し、シミュレーションを行うことが最適な選択につながります。
電力・ガスの自由化で会社を変更すると本当に安くなりますか?
2016年からの電力自由化、そして2017年からのガス自由化により、契約先を選べるようになりましたよね。
実際、乗り換えによって年間数千円から数万円の節約になるケースもありますが、安さだけでなく契約条件やセット割引、使用量との相性も重要なポイントです。
たとえば、携帯電話やインターネットとセットで契約することで割引が受けられるプランや、ポイント還元のある会社もあります。
使用量が少ない家庭では逆に割高になる場合もあるため、契約前にシミュレーションツールで比較検討することをおすすめします。
また、乗り換えの手続きは比較的簡単で、現在の契約先を解約する必要もなく、新しい会社が手続きを代行してくれるケースがほとんどです。
光熱費の支援・家計のやりくりに悩んだら取るべき方法とは?
光熱費の支援制度や節約術は、家計の負担軽減に大きく貢献する手段ですが、それでも「家計全体のやりくりに不安が残る」という声も少なくありません。
特に最近は物価の上昇や将来への不透明感から、「このままで大丈夫なのか…」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
実際、収入をすぐに増やすことは難しくても、支出の見直しなら今すぐ始められます。
特に光熱費のような固定費は、一度見直せば継続的な節約につながるため、家計改善の第一歩として非常に効果的です。
ただし、「自分に合った節約法が分からない」「何を優先すればいいか判断できない」と感じている方も多いはず。
そんなときに頼れるのが、お金の専門家であるファイナンシャルプランナー(FP)です。
たとえば、無料で何度でも相談ができる「マネーキャリア」では、光熱費はもちろん、家計全体の支出バランスやライフプランまでを踏まえたアドバイスが受けられますよ。

- お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、知見の豊富なファイナンシャルプランナーのプロのみを厳選。
- 資産形成や総合的なライフプランの相談から最適な解決策を提案可能。
- マネーキャリアは「丸紅グループである株式会社Wizleap」が運営しており、満足度98.6%、相談実績も100,000件以上を誇る。

光熱費やガス代・水道代の節約方法まとめ
今回は、政府の光熱費支援制度の内容から、家庭でできる電気・ガス・水道の節約術、さらにはよくある疑問への回答まで、幅広くご紹介してきました
支援制度を活用することはもちろん大切ですが、日常のちょっとした工夫や契約内容の見直しを積み重ねることで、毎月の光熱費を大きく抑えることができます。
特に電気代ではプランの見直しや省エネ家電の使い方、ガス代では給湯と調理の工夫、水道代では節水グッズの活用など、それぞれに具体的な対策があります。
自分に合った方法を選び、無理なく続けることが、家計への負担を軽減するコツです。
とはいえ、家庭によって最適な対策は異なり、「何が一番効果的なのか分からない」と感じる方も多いはず。そんな時は、専門家に家計全体を見てもらえる「マネーキャリア」のような無料相談サービスの活用がおすすめです。