
「つみたてNISAで銘柄をいくつに絞るのが最適なのか」
「複数銘柄に投資することのデメリットやリスクはあるのか」
とお悩みではないでしょうか。
結論として、つみたてNISAで最適な銘柄数は、投資の目的、目標金額、そして最も重要なリスク許容度によって異なります。
いくつかの銘柄に分けて投資する際は、リスクを減らせるメリットと、管理の手間や利益が薄まったりするデメリットを理解した上で、慎重に戦略を立てることが大切です。
この記事では、つみたてNISAにおける最適な銘柄数の見つけ方や、複数銘柄での効果的なリスク分散のコツについて解説します。

 相談者:43歳/女性/既婚子供あり|FP相談の事例を見る▼
相談者:43歳/女性/既婚子供あり|FP相談の事例を見る▼
 相談者:52歳/男性/独身/貯金なし|FP相談の事例を見る▼
相談者:52歳/男性/独身/貯金なし|FP相談の事例を見る▼

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- つみたてNISAの銘柄はいくつ買うべき?
- つみたてNISAで分散投資するメリットとデメリット
- メリット
- デメリット
- つみたてNISAの銘柄の組み合わせ例を紹介
- ひとつの銘柄で運用したい場合
- 複数銘柄で運用したい場合
- つみたてNISAの銘柄数で迷ったらFPに無料相談がおすすめ
- つみたてNISAで複数銘柄を選ぶポイント・分散投資のコツ
- 地域が異なる銘柄を組み合わせる
- 手数料が低い商品を選ぶ
- インデックスファンドを選ぶ
- リスク許容度を確認する
- みんなはつみたてNISAの銘柄はいくつ買った?アンケートで調査
- NISAで保有している銘柄数を教えてください
- 銘柄数を決める際に重視したポイントは?
- 現在の銘柄数に満足していますか?
- 銘柄数を増やしたい・減らしたい理由は?
- NISA初心者の方に向けて銘柄を選ぶ際のアドバイスを教えてください
- つみたてNISAの複数銘柄に関するよくある質問Q&A
- 銘柄数に上限はありますか?
- 銘柄は途中で変更できますか?
- 積立金額は銘柄ごとに自由に設定できますか?
- つみたてNISAで複数銘柄に積み立てるデメリット【まとめ】
つみたてNISAの銘柄はいくつ買うべき?
つみたてNISAにおいて最適な銘柄数は、個人のリスク許容度と投資目的によって変わるため、一律ではありません。
- 初心者の方:投資先の把握が容易な1〜3銘柄程度に絞ることを推奨します
- 経験者の方:管理の煩雑さ(手間)を考慮し、5銘柄程度に抑えることが効果的です
実際に当社で行ったつみたてNISAの銘柄数のアンケート(※)では、以下のような結果が出ています。
| つみたてNISAの銘柄数 | 割合 |
|---|---|
| 1本 | 34.0% |
| 2本 | 22.0% |
| 3本 | 10.0% |
| 4本以上 | 34.0% |
つみたてNISAで分散投資するメリットとデメリット
つみたてNISAにおいて、リスクを軽減し安定したリターンを目指すためには、分散投資が不可欠です。
分散投資とは、複数の異なる資産や地域に投資することで、一つの銘柄が暴落した際の影響を抑える手法を指します。
つみたてNISAの非課税投資枠内(年間120万円)で、どのように分散投資を実行するかが成功の鍵となります。
以下では、つみたてNISAで分散投資を行う際の具体的なメリットとデメリットを解説します。
メリット
つみたてNISAで複数銘柄に投資する最大のメリットは、ご自身のリスク許容度や成長期待に基づき、投資対象やその割合を柔軟かつ細かく調整できる点にあります。
複数銘柄で運用する際は、リスクを効果的に軽減するため以下の3つの要素を分散させることが重要です。
- 資産:株式、債券、現預金など異なる種類の金融商品に分ける
- 地域:日本、アメリカ、新興国など、異なる市場に分ける
- 時間:ドルコスト平均法、つまり定時定額購入を活用し、購入時期を分散させる
デメリット
つみたてNISAで複数の銘柄を保有するデメリットは、投資対象地域が重複する組み合わせを選んだ場合、分散効果が低下する可能性があることです。
分散投資は、値動きの異なる資産や地域を組み合わせることで効果を発揮します。
しかし、以下のような投資対象が重複する組み合わせは、結果的に同じような運用成績になりやすく、リスク軽減効果が薄れてしまいます。
- 全世界株式 + 日本株式:全世界株式に日本株式が含まれるため
- 全世界株式 + 先進国株式:全世界株式に先進国株式が含まれるため
- 先進国株式 + 米国株式:先進国株式の構成比の多くを米国株式が占め、米国市場の動向に大きく左右されてしまうため
つみたてNISAの銘柄の組み合わせ例を紹介
つみたてNISAの銘柄の組み合わせには、投資経験、目標、リスク許容度に応じて様々なパターンが存在します。
ここでは、「ひとつの銘柄で運用したい場合」と「複数銘柄で運用したい場合」の2つのパターンに分けて、具体的な組み合わせ戦略を紹介します。
これらの例を参考に、ご自身の投資目標に最適な銘柄の組み合わせを検討してください。
ひとつの銘柄で運用したい場合
ひとつの銘柄で運用したい場合は、リスク分散されている商品を選ぶことがポイントです。
主な投資対象の種類とリスク水準は以下のとおりです。
| 投資対象 | 特徴 | リスク |
|---|---|---|
| 先進国債券 | 先進国の国債や社債に投資 | 低~中 |
| 国内債券 | 日本国債や社債に投資 | 低 |
| 8資産均等型 | 国内外の株式・債券・リートに均等投資 | 中 |
| 全世界株式 | 世界中の株式市場に分散投資 | 中~高 |
ご自身のリスク許容度に合わせて投資対象を適切に選択することで、長期的に安定した資産形成が期待できます。
特に投資初心者の方は、投資目的や許容できるリスクを明確にしてから最適な商品を選定することが重要です。
複数銘柄で運用したい場合
複数の銘柄を組み合わせて運用する場合、値動きや特性が異なる銘柄を選択することがリスク分散を効果的に行う鍵となります。
主な組み合わせパターンとその特徴は以下のとおりです。
| 投資対象 | 配分例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 先進国株式+新興国株式 | 70%:30% | 成長性重視 |
| 株式型+債券型 | 60%:40% | バランス重視 |
| 国内債券+先進国債券+新興国債券 | 40%:40%:20% | 安定性重視 |
複数の銘柄を組み合わせることで、値動きが反対になったりする商品がお互いを補い合い、よりリスクの少ない効果的な投資ができるようになります。
ただし、銘柄数が増えすぎると管理が煩雑になるため、初心者は2〜3銘柄、経験者でも5銘柄程度に抑えることが推奨されます。
つみたてNISAの銘柄数で迷ったらFPに無料相談がおすすめ
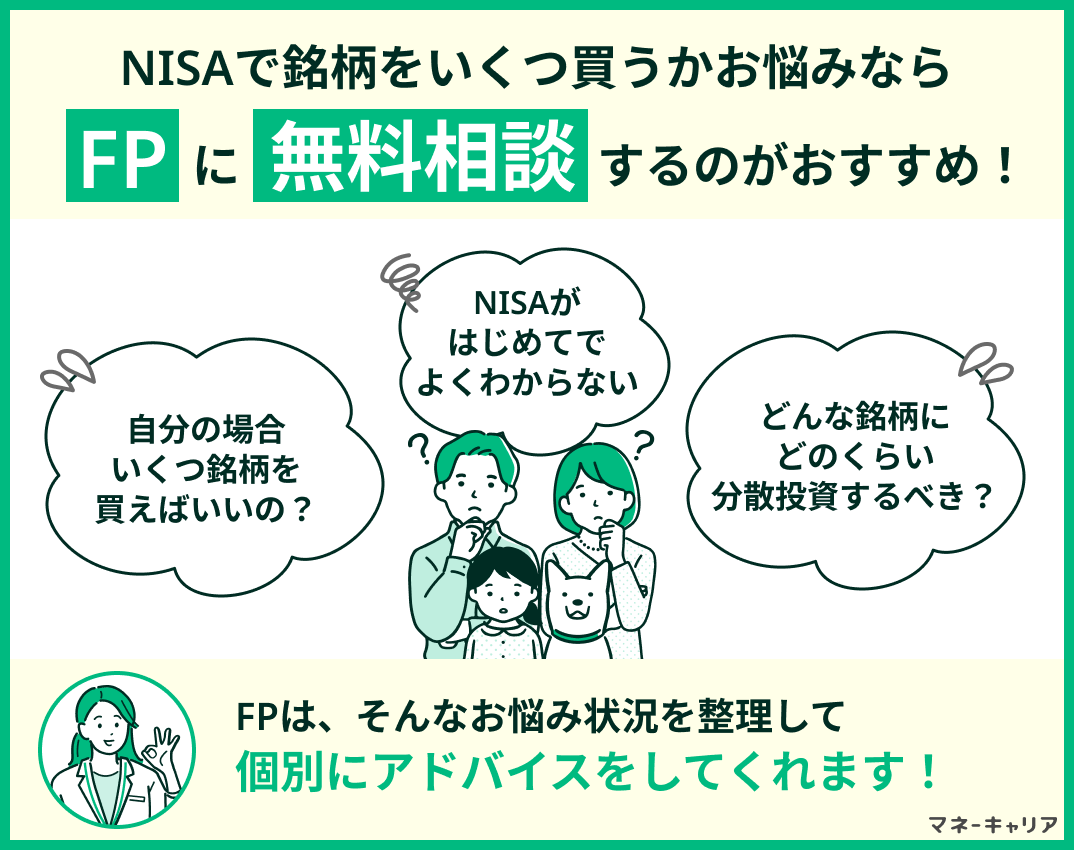
\気になる方は相談事例をチェック!/
 相談者:43歳/女性/既婚子供あり|FP相談の事例を見る▼
相談者:43歳/女性/既婚子供あり|FP相談の事例を見る▼
 相談者:52歳/男性/独身/貯金なし|FP相談の事例を見る▼
相談者:52歳/男性/独身/貯金なし|FP相談の事例を見る▼
つみたてNISAで複数銘柄を選ぶポイント・分散投資のコツ
つみたてNISAで複数銘柄を選定し、効果的な分散投資を行うためのポイントは以下のとおりです。
- 地域が異なる銘柄を組み合わせる
- 手数料が低い商品を選ぶ
- インデックスファンドを選ぶ
- リスク許容度を確認する
これらのポイントを押さえることで、リスクを抑えつつ、長期的なリターンを最大化する分散投資戦略の確立が可能となります。
地域が異なる銘柄を組み合わせる
1つ目は投資先の地域が異なる銘柄を組み合わせることです。
例えば、日本株式だけでなく、米国、欧州、新興国などの株式に分散投資を行うことで、特定の地域の経済状況に運用全体のパフォーマンスが左右されない安定した資産運用が可能となります。
仮に日本経済が停滞する時期でも、米国や新興国が好調であれば、ポートフォリオ全体のリターンを一定の水準に維持できるためです。
地域による分散投資を徹底したい場合は、全世界の株式市場に幅広く投資する「全世界株式」を中心とした投資信託を活用することが推奨されます。
手数料が低い商品を選ぶ
2つ目は、手数料が低い商品を買うことです。
長く投資を続ける場合、たった少しの手数料の違いが将来手に入るお金に大きな差を生みます。
たとえば、毎年0.1%かかる商品と0.5%かかる商品を比べると、20年後には受け取る金額が8%も変わってしまう可能性があります。
つみたてNISAで選べる商品はもともと手数料が安いものが多いですが、その中でも一番安いファンドを選ぶことで、長い目で見て最終的な利益を最大限に増やせます。
複数の銘柄に分けるときも、それぞれの商品の手数料をよく比べて全体の平均手数料を安く保つ工夫が非常に大切になります。
インデックスファンドを選ぶ
3つ目は、インデックスファンドを軸に選定することです。
投資信託には、特定の市場平均指数(例:S&P 500やTOPIX)と同じ値動きを目指すインデックスファンドと、専門家が市場平均を上回るリターンを目指すアクティブファンドの2種類があります。
主な違いは以下の通りです。
| インデックスファンド | アクティブファンド | |
|---|---|---|
| 運用方針 | 特定の指数に連動する | 特定の指数を上回る |
| 信託報酬 | 安い | 高い |
つみたてNISAは長期・積立投資を前提とした制度であるため、低コストで市場平均のリターンを狙えるインデックスファンドと非常に相性が良いと言えます。
複数銘柄を組み合わせる場合でも、異なる指数に連動するインデックスファンドを選ぶことで、コストを抑えつつ効率的な分散投資戦略を構築できます。
リスク許容度を確認する
リスク許容度とは、投資において価格が変動した際や、一時的な損失が発生した際にどの程度まで冷静に受け入れられるかを示す指標です。
投資する期間が長く、そのお金を失っても日々の生活に困らない場合は、リスクを比較的大きく取れる、つまりリスク許容度が高いと判断できます。
逆に、投資期間が短く、近いうちに必要な生活費を充てている場合は、リスクを抑える、つまりリスク許容度が低い状態です。
この許容度に合わせて、株式と債券の割合や先進国と新興国の比率を決めて調整することが、目標達成を目指すための分散投資の秘訣です。
みんなはつみたてNISAの銘柄はいくつ買った?アンケートで調査
今回、つみたてNISA利用者を対象に銘柄数に関するアンケート調査を実施しました。
アンケート項目は以下の通りです。
- NISAで保有している銘柄数を教えてください
- 銘柄数を決める際に重視したポイントは?
- 現在の銘柄数に満足していますか?
- 銘柄数を増やしたい・減らしたい理由は?
- NISA初心者の方に向けて銘柄を選ぶ際のアドバイスを教えてください
実際にみんながどのような考えで銘柄数を決めているのか、その理由や満足度について詳しく解説します。これらの調査結果を参考にして、自分に合った銘柄数を検討する材料にしましょう。
NISAで保有している銘柄数を教えてください
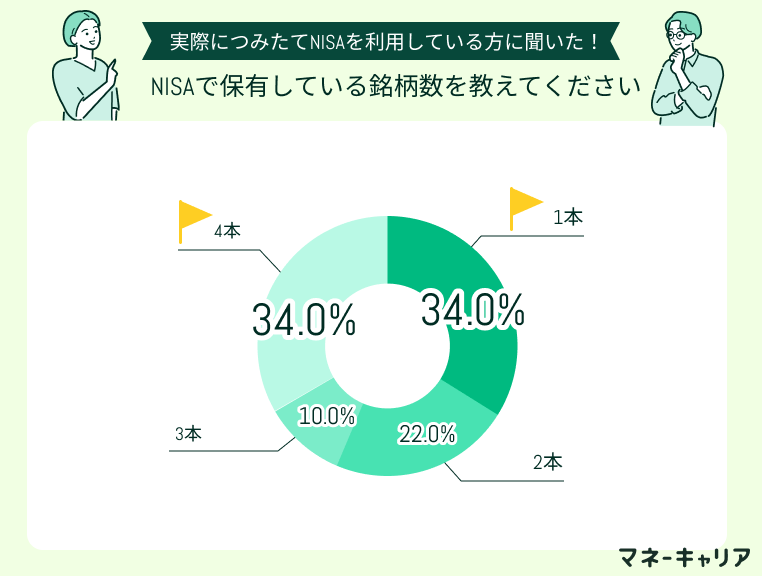
記事冒頭でも紹介しましたが、現在保有している銘柄数についてアンケートを実施した結果、最も多かったのは「1本」と「4本以上」で34%、次いで「2本」が22%という結果になりました。
「3本」は10%となっており、全体の67%の人が3銘柄以下で運用していることが分かります。
この結果から、多くの方が自分が管理しやすい範囲で銘柄数を抑えていることが読み取れます。
銘柄数を決める際に重視したポイントは?
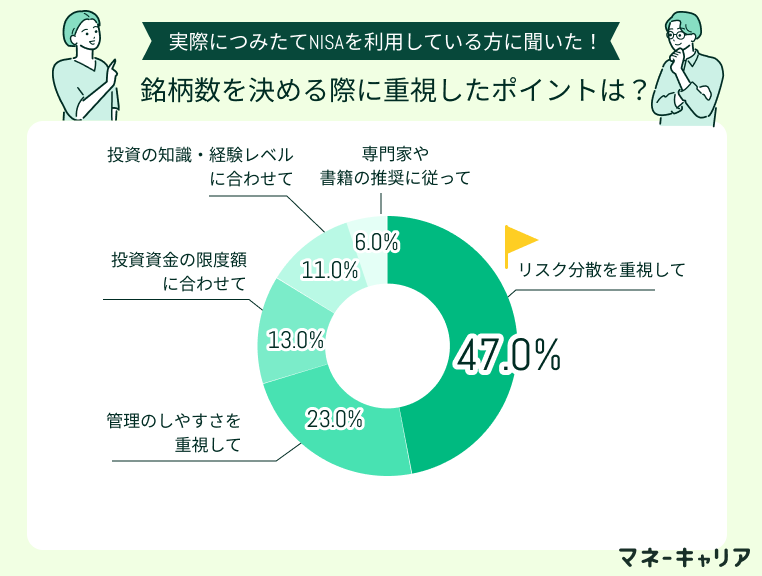
銘柄数を決める際に重視したポイントについて調査した結果、「リスク分散を重視して」が47%で最も多い回答となりました。
次に多かったのは「管理のしやすさを重視して」の23%で、投資資金の限度額に合わせてが13%と続きます。また、投資の知識・経験レベルに合わせてが11%、専門家や書籍の推奨に従ってが6%という結果になりました。
この結果から、投資家の多くがリスク分散の重要性を理解しながらも、管理のしやすさとのバランスを考慮していることが分かります。
現在の銘柄数に満足していますか?
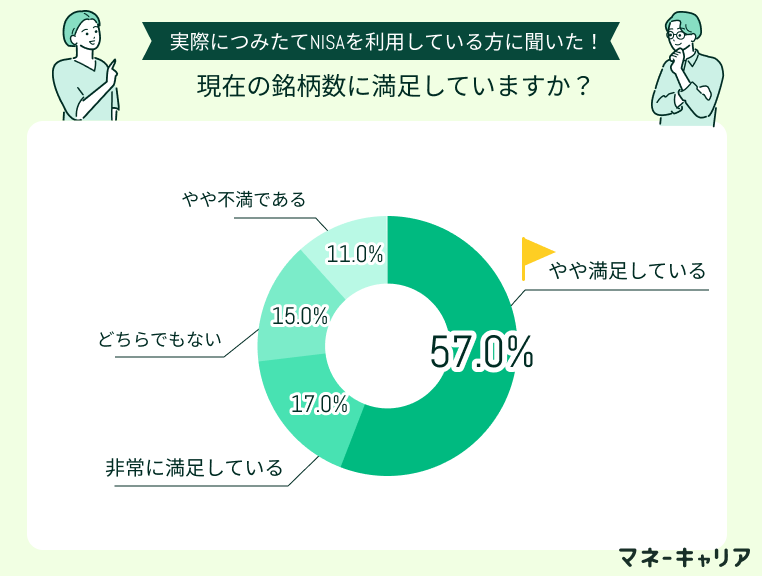
現在の銘柄数に対する満足度について調査した結果、「やや満足している」が57%で最も多い回答となりました。また、「非常に満足している」が17%で、合わせると74%の人が現在の銘柄数に満足していることが分かります。
一方、「どちらでもない」が15%、「やや不満である」が11%という結果になりました。
この結果から、多くの投資家が自分なりに考えて選んだ銘柄数に概ね満足していることが読み取れます。ただし、約4分の1の人が現状に完全には満足していないことも分かり、銘柄数の見直しを検討している人も一定数存在することが明らかになりました。
銘柄数を増やしたい・減らしたい理由は?
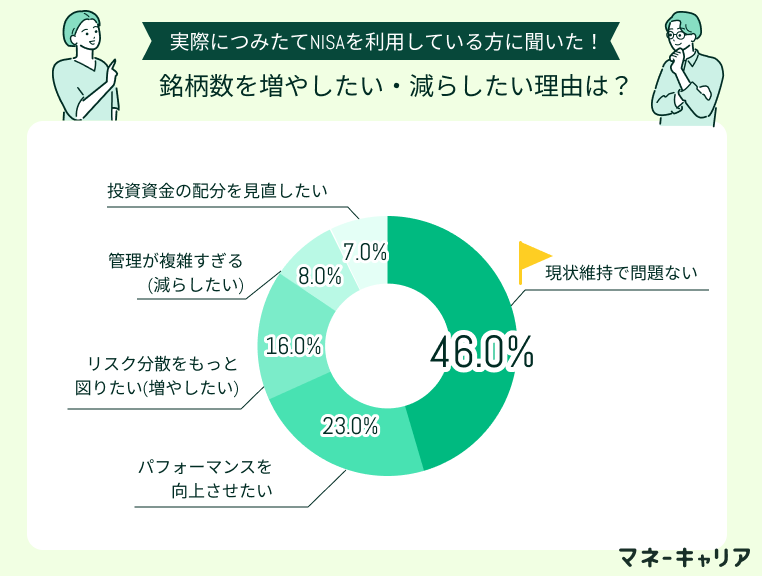
銘柄数を変更したい理由について調査した結果、「現状維持で問題ない」が46件(46%)で最も多い回答となりました。
変更を希望する理由としては、「パフォーマンスを向上させたい」が23件(23%)で最も多く、次いで「リスク分散をもっと図りたい(増やしたい)」が16件(16%)となりました。
この結果から、約半数の人が現在の銘柄数で満足している一方、パフォーマンス向上やリスク分散の観点から変更を検討している人も多いことが分かります。
NISA初心者の方に向けて銘柄を選ぶ際のアドバイスを教えてください

30代男性
人気情報を集めて長期でコツコツ積み立て
YouTubeやネットで情報を集めて、人気があるものや長期的に成長が期待できるものを選ぶと迷いにくいです。まずは少額からコツコツ積み立ててみて、投資に慣れてきたら興味のある銘柄を増やしていくのが良いと思います。

40代女性
分散投資と長期目線を意識して焦らず選ぶことが大切
NISAを始めたばかりの方は、銘柄を1つに絞らず、いくつかに分けて分散投資するのがおすすめです。短期的な値動きに一喜一憂せず、長い目で見てコツコツ積み立てることがいいと思います
つみたてNISAの複数銘柄に関するよくある質問Q&A
つみたてNISAに関するよくある質問を解説します。
解説する質問は以下のとおりです。
- 銘柄数に上限はありますか?
- 銘柄は途中で変更できますか?
- 積立金額は銘柄ごとに自由に設定できますか?
よくある質問への解説を見て、不安や疑問点を解消しましょう。
銘柄数に上限はありますか?
組み合わせや個数の上限はありません。
新NISAの非課税投資枠1,800万円の範囲内であれば、制限なく買うことができます。
ただし、複数の銘柄を購入すれば、その分管理も煩雑になります。銘柄をいくつ買うか迷う際は、購入の目的を明確にし、目的に沿った個数を購入しましょう。
銘柄は途中で変更できますか?
銘柄は途中で変更できます。
ただし、銘柄を途中で変更する際には以下の注意点があります。
- 「値上がりしている」という理由だけで銘柄を買い替えない
- 銘柄数が少ない時は金融機関の変更も視野に入れる
値上がりしている銘柄を見つけたとしても、直近だけでなく長期的な成績を見て成長が期待できるか判断しましょう。
また、銘柄の取扱本数は 金融機関によって大きく異なります。あるネット証券では200本近くの取り扱いに対し、ある銀行では20本も取り扱っていないケースもあります。
積立金額は銘柄ごとに自由に設定できますか?
銘柄ごとに異なる積立金額を設定することが可能です。
例えば、リスクの高い銘柄には毎月5,000円、リスクの低い銘柄には毎月10,000円というように、自分の投資戦略に合わせて配分を調整できます。
ただし、各証券会社によって最低積立金額が設定されている場合があるので注意が必要です。
つみたてNISAで複数銘柄に積み立てるデメリット【まとめ】

ここまで、つみたてNISAにおける最適な銘柄数と効果的な分散投資のコツを解説してきました。
つみたてNISAで複数銘柄に投資する場合、管理の煩雑化や銘柄の重複による分散効果の低下というデメリットがある一方で、リスク許容度や投資目的によって最適な銘柄数は大きく異なります。
最適な銘柄選びやリスク許容度の判断が難しいと感じる方は、マネーキャリアの利用をぜひご検討ください。
専門家が、あなたの資産状況や目標を分析し、最適な銘柄数や組み合わせ戦略について個別にアドバイスを提供します。
何度でも無料で相談できて、相談予約は30秒で完了するため気軽にご利用ください。






























NISAの口座を開設してみたものの、どんなもの銘柄をいくつ選べばいいのか悩んでいる。分散投資をどれくらいすればいいのかも気になる。