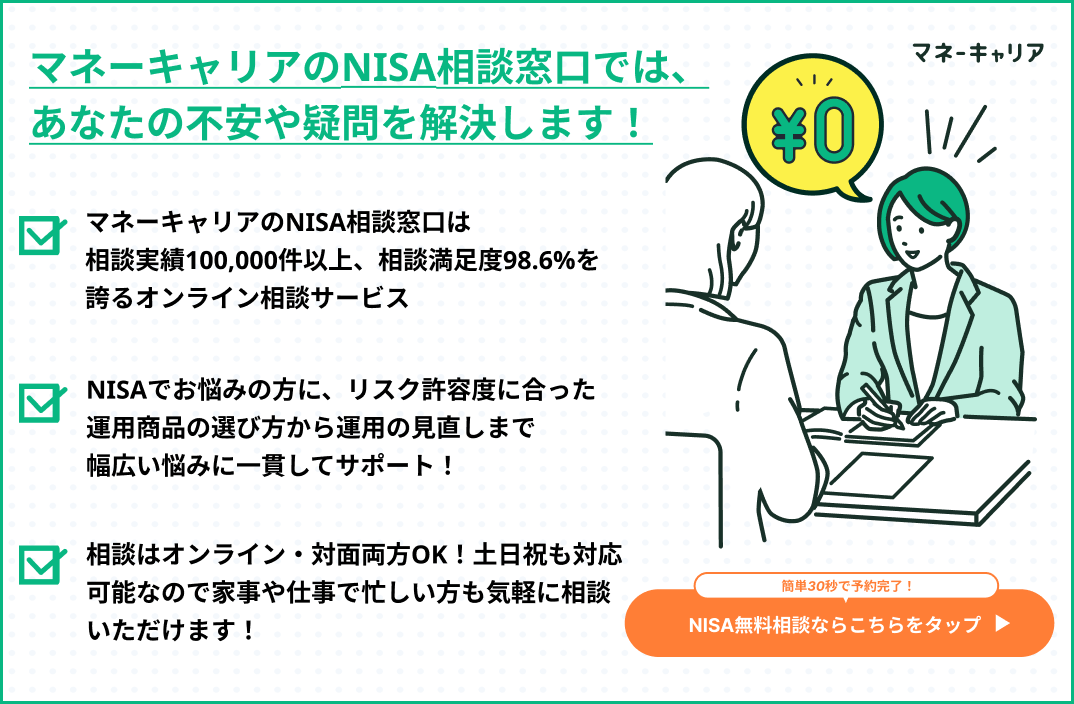この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
「NISAの長期保有は意味ない」と言われる理由とは?

- 値上がりしない・含み損が続いているため
- 非課税メリットを実感しづらいため
- 投資商品が長期保有向きでなかったため
値上がりしない・含み損が続いているため
NISAで投資を始めてから数週間、または数か月経ってもあまり値上がりしないと、意味がないと感じてしまうかもしれません。
短期的な値動きを気にしすぎると一喜一憂してしまい、ストレスになる可能性も高いです。
非課税メリットを実感しづらいため
通常の投資では運用益が出ると20.315%の割合で課税されますが、NISAは運用益が非課税となるお得な制度です。
NISAの非課税メリットをiDeCoと比較すると、iDeCoは掛け金が全額所得控除の対象となるため、運用益に関わらず減税メリットがあります。NISAの場合には運用益が出ないと非課税の恩恵は受けられないため、メリットを実感しにくいかもしれません。
では、投資で100万円の利益が出た場合、NISA口座と通常の課税口座で手元に残る金額にどれほどの差が出るかシミュレーションしてみましょう。
| 口座の種類 | NISA口座 | 特定口座など |
|---|---|---|
| 運用益 | 100万円 | 100万円 |
| 課税額 | 0円 | 20万3,150円 |
| 受け取れる金額 | 100万円 | 79万6,850円 |
運用益が大きければ大きいほど、非課税メリットは大きくなります。
投資商品が長期保有向きでなかったため
NISAで購入した商品が長期保有に向いていない銘柄だった、という可能性もあります。
値動きが激しい個別株やテーマ型ファンドを選ぶと、長期で安定成長しないことで「長期保有は意味ない」と感じるかもしれません。
長期的にほったらかし投資をするなら、バランス型やインデックス型の商品がおすすめです。
NISAのお悩みは無料FP相談で解決しよう!

- NISAで失敗しないためにはどうすればいい?
- 投資初心者でも安心して使う方法は?

NISAの長期保有で失敗しないためのポイント3つ

次の3つの点にしぼって解説します。
- 長期保有に適した商品を選ぶ
- 分散投資を意識する
- 定期的にリバランス・見直しをする
長期保有に適した商品を選ぶ
まずは、長期保有に適した金融商品を選びましょう。
バランス型の商品やインデックスファンドなど、長期的に見て成長が見込める商品がおすすめです。
長期保有する場合にはコストも重要で、投資信託の信託報酬ができるだけ低いものを選ぶようにしてください。
分散投資を意識する
投資の原則の1つ、分散を意識して商品選びをします。
特定の国や企業、産業に一点集中せず、地域や資産クラスを幅広く分散して保有しましょう。分散投資をすることでリスクを低減できるからです。
定期的にリバランス・見直しをする
長期保有には放置が重要ですが、完全に何もしないわけではありません。
半年または1年に1度のペースでポートフォリオを確認し、資産配分を見直していきましょう。
例えば、当初は金融商品Aを50%、金融商品Bを50%購入して運用していたとしましょう。価格変動によりAが70%、Bが30%の割合に変化していました。リバランスするには、次回の積み立てからBを多めに購入することで当初のポートフォリオに近づけていきます。
【まとめ】NISAは長期保有が正解!リスク許容度に合わせた運用をしよう

この記事で解説した通り、運用状況がよくなかったり、選んだ商品が長期保有に向いていなかったりするとNISAの長期保有は意味ないと感じてしまうことがあります。
実際にはNISAは長期保有に向いている制度で、長期保有に適した商品を選んである程度ほったらかすことで、複利効果によっていつの間にか資産が増えているでしょう。
NISAで積み立てる際の疑問点は、マネーキャリアのFP相談で解決できます。自分に合った積立額や運用方法について知ることで、安心してNISAを利用できるでしょう。