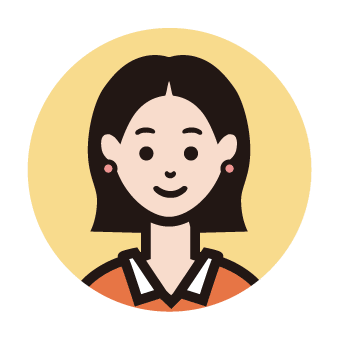▼この記事を読んでわかること
・自分の場合は医療費控除を受けられるか知りたい方におすすめのサービス
医療費控除の申請を検討している方の中には
「家族が世帯分離していても医療費は合算できるの?」
「同居していない親や扶養に入っていない子どもの医療費も対象になるの?」
といった不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
特に、親の介護や子どもの独立などで家族の暮らし方が多様化する中、「生計を一にする」の意味があいまいで、自分のケースが対象になるのか判断しづらいという声も少なくありません。
そこでこの記事では、 世帯分離していても医療費控除の対象となるケースや、 「生計を一にする」と判断される基準、 実際に申告する際のポイントや注意点などをわかりやすく解説します。
この記事を読めば、自分や家族の状況でどこまで医療費控除を活用できるかが明確になり、損せず申告できるようになります。
内容をまとめると
- 医療費控除では、たとえ世帯分離していても「生活費を支援している」「医療費を実際に負担している」などの実態があれば、「生計を一にしている」とみなされ、医療費を合算して申告できます。
- 具体例として、①世帯分離した親の医療費を子が負担した場合、②別居中でも婚姻関係がある配偶者の場合、③扶養に入っていない高収入の家族にかかった医療費などを紹介しています。
- こうした複雑なケースに対応するために、「相談実績10万件・満足度98.6%」のマネーキャリアで、何度でも無料相談できる専門家と一緒に判断することで、自分に最適な申告方法を見つけて損せず制度を活用できます。

監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 医療費控除は世帯分離していても合算できる?
- 医療費控除の合算は「生計を一にする」かどうかがポイント
- 「生計を一にする」の意味を解説!
- 「生計を一にする」ことと家族が同居・別居かは関係なし
- 「生計を一にする」ことと税制上の扶養家族かも関係なし
- 医療費控除を合算する時の申告書は1つでOK
- 医療費控除の対象となる家族・親族の範囲は?
- 世帯分離していても医療費控除を合算できるケースを解説!
- ①世帯分離した親の医療費を子供が支払った場合
- ②子供の医療費を世帯分離した親が支払った場合
- ③別居しているが婚姻状態にある配偶者の医療費を支払った場合
- 【注意】医療費控除は複数の世帯からは申請できない
- 医療費控除は家族の中で所得が一番多い人が申請しよう
- 医療費控除は納税者の所得税率によって金額が変わってくる
- 夫婦共働きの場合は所得が多い方でまとめて申告するとお得
- 医療費控除を申請するには確定申告が必要なので注意!
- 医療費控除に含まれるものを解説!
- 【参考】医療費控除を受けるなら世帯分離をした方がいい?
- 医療費控除を受けられるか知りたい方におすすめのサービス
- 【まとめ】「生計を一にする」なら医療費控除はまとめて申告!
医療費控除は世帯分離していても合算できる?
先日、50代の男性から次の相談をされました。
「数ヵ月まえ、母親が病気を患ってしまい、かなりの医療費がかかっています。母とは世帯分離をしていますが、実際のところ家計は一緒です。この場合、医療費控除は適用されますでしょうか。医療費がかさんでしまい大変なので、負担を少しでも減らせたら嬉しいです。」
こちらのご相談内容について結論を述べると、世帯分離をしているお母さまにかかった医療費も控除の対象になります。
それは、お母さまは息子さんと「生計を一にしている」からです。 ご相談者様とお母さまは生活費、光熱費などを共有しているとのことでしたので、生計を一にしているとみなすせことができます。
医療費控除に関する正しい知識がなければ、医療費控除の対象であるにも関わらず、申告せずにそのまま節税メリットを享受する機会を逃してしまいます。
そこで、本記事では、世帯分離をしている家族にかかった医療費を医療費控除で合算できるケースを解説していきます。 本記事が、医療費控除について知りたい方のお手伝いになれば幸いです。
医療費控除の合算は「生計を一にする」かどうかがポイント
医療費控除とは納税者の税負担を軽減させるための制度で、年間にかかった医療費が一定額を超えた場合に適用されます。
たとえば、以下に当てはまる場合は、医療費控除を受けられます。
- 1年間に支払った医療費の合計額が10万円を超える
- 医療費の支払い額が合計所得金額の5%を超えている
医療費控除が適用されれば、医療費にかかった金額をもとにして所得税・住民税が還付されます。
医療費控除は納税者本人にかかった医療費のみならず、生計を一にする家族にかかった医療費を合算して計算できます。
つまり、生計を一にする家族の1年間においてかかった医療費を合算し、10万円を超えたら医療費控除を利用することができます。
以下、医療費控除を受ける際の「生計を一にする」の意味・ポイントを詳細に解説していきます。
「生計を一にする」の意味を解説!
「生計を一にする」とはどのような意味なのか、その判断基準を確認していきましょう。
ひとつの家計で生活している人たちのことを「生計を一にしている」といいます。
生計を一にするかの判断基準は、以下の通りになります。
- 収入状況
- 生活費の状況
- 水道、光熱費、通信費の支払状況
- 家賃の支払状況
- 建物の構造
- 不動産登記の内容
- 住民票、社会保険における世帯に関する記載内容
「生計を一にする」ことと家族が同居・別居かは関係なし
「生計を一にする」の判断基準は、家族が同居しているか、別居しているかは関係しません。
たとえば、以下の場合は生計を一にすると見做されます。
- 父親が単身赴任の家庭
- 地方から大学進学を機に上京し、一人暮らしをしている大学生
- 療養などの理由から一人離れて暮らしている母親
国税上の公式サイト(「生計を一にしているもの」の意義)において、「生計を一にする」について詳しく説明されていますので参考にしてみてください。
「生計を一にする」ことと税制上の扶養家族かも関係なし
生計を一にするかの判断基準は、税制上の扶養家族かどうかは関係ありません。
扶養家族ではなくとも生計を一にしている場合は、医療費を合算できます。
医療費控除の合算には年収は関係しませんので、高額な所得を得ている家族の医療費も医療費控除の対象であり、かつ合算の対象です。
たとえば、以下の場合は、扶養家族でなくとも医療費控除の合算を行えます。
- 配偶者控除適用外の共働きの夫婦で、妻が夫の医療費を支払った場合
- 父親が一定以上の収入のある同居中の息子の医療費を支払った場合
- 妻子に生活費を送っている単身赴任の夫が子供の医療費を支払った場合
医療費控除を合算する時の申告書は1つでOK
医療費控除を合算するときの申請書は1つで問題ありません。
ご自身の就業形態にあわせて、確定申告書A、確定申告書Bのいずれかを提出しましょう。
確定申告書Aは会社員、年金受給者が利用するのに対し、確定申告書Bは不動産所得がある方、個人事業主などが利用します。
確定申告書A、確定申告書Bのいずれも税務署に行かずとも、インターネット上で入手可能です。
医療費控除の対象となる家族・親族の範囲は?
医療費控除の対象となる家族・親族の範囲は定められています。
医療費控除の対象となる家族・親族の範囲は次の通りです。
- 配偶者
- 6親等内の血族
- 3親等内の姻族
- 養子縁組をしている親子関係
世帯分離していても医療費控除を合算できるケースを解説!
医療費控除とは、納税者本人、もしくは生計を一にする家族の年間の医療費が一定以上に達した時に受けることのできる税控除です。
医療費控除の合算は、世帯分離していても合算できるケースがあります。
世帯分離とは、一つの世帯を複数の世帯に分けて住民票登録することをいいます。
世帯分離では住居を共にしているかは関係なく、一つ屋根の下に世帯主が二人以上いるケースもあります。
たとえば、世帯分離は以下のケースが該当します。
親夫婦+息子夫婦→親夫婦/息子夫婦
上記は、二世帯が同居しているケースです。
世帯主は、父親と息子になります。
父+子A+子B→父+子A/子B
上記は、子供一人が独立して、世帯を分離したケースです。
父と子Bが世帯主になります。
世帯分離をしていても医療費控除を合算できるケースがありますので、確認していきましょう。
①世帯分離した親の医療費を子供が支払った場合
世帯分離をした親の医療費を子供が支払った場合、親と子が生計を一にしていれば、医療費控除を合算できます。
たとえば、同居中の母親にかかった医療費を子が支払った場合、親子の生計の状況によっては医療費控除の合算対象になります。
子が母親に金銭的支援を日常的に行っていれば、生計を一にするとみなすことができるのです。
世帯分離をしていても、医療費を誰が支払ったか、生計を一にしているかが、医療費控除の合算を考える上でポイントになります。
詳しく知りたい方は、国税庁の公式サイト(同居していない母親の医療費を子供が負担した場合)をご参照ください。
②子供の医療費を世帯分離した親が支払った場合
子供の医療費を世帯分離した親が支払った場合、医療費控除は合算できます。
世帯分離をした子供の医療費を親が支払った場合、医療費控除の合算が可能です。
子供に一定以上の収入があるケース、子供が正社員として働いているケースにおいても、親と子が生計を一にしている場合は、世帯分離していても医療費控除を合算できます。
③別居しているが婚姻状態にある配偶者の医療費を支払った場合
医療費控除の合算において、配偶者とは法的に婚姻関係にあることを大前提とします。
医療費控除は婚姻状態にある場合はまとめて申請を行うことが可能ですが、離婚、婚姻前の場合はまとめて申請することはできません。
事実婚の場合も医療費控除の対象にはならないので注意してください。
別居しているが婚姻状態にある配偶者の医療費を支払った場合、控除の合算ができるかは、夫婦の生計のたて方によります。
別居しているといっても法的には婚姻関係にありますので、一緒に暮らしているかは問題になりません。
別居していたとしても生計を一にしている場合は、医療費控除を合算できます。
【注意】医療費控除は複数の世帯からは申請できない
医療費控除は、医療費を支払っている世帯主が子・親の分もまとめて申請を行います。
世帯主といっても、実際に誰が医療費控除を申請するかについては家族で話し合う必要があります。
1つの世帯のなかで誰が医療費控除を受けるかについて、法的規定はありません。
家族間での話し合いによって最善の方法を決めましょう。
医療費控除は家族の中で所得が一番多い人が申請しよう
家族のなかで医療費控除を行う際は、課税所得が多く、所得税率の高い人にまとめるのが最も有効な方法です。
所得税の税率は年収ではなく、課税所得によって決まるということを覚えておいてください。
家族にかかった医療費を所得税率の高い人に集約することによって、 節税効果が最も大きくなるからです。
たとえば、父(年収700万円)、母(年収200万円)、息子(年収300万円)という世帯の場合、年収が最も高い父にまとめることで、節税効果を最大限に得ることができます。
医療費控除は納税者の所得税率によって金額が変わってくる
医療費控除は納税者の所得税率によって金額は異なります。
以下の速算表を参照してください。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円超900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円超1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
参考 国税庁「所得税の税率」
<医療費控除シミュレーション Bさんの場合>
年間所得が400万円のBさんの場合を例に考えてみましょう。
医療費控除は10万円を超える部分に適用されます。
適用される税率は、所得税20%、住民税10%となります。
Bさんは病気の治療のために、年間で15万5千円使ったとします。
この場合、医療費控除の対象となるのは5万5千円です。
計算式は以下になります。
・所得税の節税額:55000円×20%=1100円
・住民税の節税額:55000円×10%=5500円
夫婦共働きの場合は所得が多い方でまとめて申告するとお得
夫婦共働きの場合は、医療費控除を所得が多い方にまとめることで節税につながります。
医療費控除を行う際に着目する箇所は年収ではなく、課税所得額であることに注意してください。
税率を少しでも下げて節約したい夫婦は、所得が多い方でまとめて申告することをおすすめします。
夫婦共働きの場合、年間で支払った医療費が10万円に満たなくても、夫婦のどちらかの所得が200万円を下まわっていれば、医療費控除が適用されることもあります。
医療費控除を申請するには確定申告が必要なので注意!
医療費控除を受けるには、自分で確定申告をする必要があります。
確定申告の時期は、例年2月~3月15日頃までとなっています。
確定申告の正確な時期は社会情勢などによって変動するので、医療費控除を希望する方はその年の確定申告の期間を遅くとも年明けまでには確認するようにしましょう。
サラリーマンの方が「確定申告」という言葉を聞くと、確定申告とは個人事業主やフリーランスに関係するものとして考える方も多いです。
しかし、医療費控除を受ける場合は、年末調整を済ませた会社員も申告する必要があります。
確定申告を行うことに面倒くささを感じる方もいらっしゃいますが、自分・家族の医療費、及び通院にかかった交通費も対象になるため、節税効果がかなりあります。
確定申告を行う際は、以下の物が必要になります。
- 病院・薬局から受け取った領収書
- 医療費のお知らせ
- 健康診断の結果など
医療費控除に含まれるものを解説!
医療費控除の恩恵を最大限活かし、節税するためには、医療費控除に含まれる費用をしっかりとおさえておく必要があります。
医療費控除に含まれる費用は多岐にわたるため、医療費控除の対象として認められる費用を確認しておきましょう。
<医療費控除に含まれる費用>
- 病院での診療費、治療費
- 入院費
- 入院時の食事代
- 医師の処方箋をもとに購入した医薬品の代金
- 医師の指示を受けて購入した治療に必要な医療器具(松葉杖、車椅子など)の購入費用
- 通院に使った公共交通機関の代金
- 緊急時の通院に使ったタクシー代金
- 歯の治療費(保険適用外の費用も可)
- 医師の指示を受けて行ったリハビリ、整体にかかった代金
- 出産費
<医療費控除に含まれない費用>
- 人間ドックなど健康診断の費用(病気が発見され、治療を開始した場合は医療費控除の対象になります)
- 予防注射の費用
- 美容整形の治療費用
- 美容、もしくは健康維持を目的にした漢方薬、ビタミン剤などの費用
- 通院時のマイカーのガソリン代
- 自己都合によるタクシーの乗車賃(緊急時にタクシーに乗った場合は、医療費控除の対象になります)
- 入院時に自己都合で利用した個室代、ベッド代など
- 未払いの医療費
- リラクゼーション、健康維持を目的にしたマッサージ、整体
通常、医療費控除が適用されるものは、病気の治療を目的とした診察・医療行為に支払った費用に限定されます。
美容目的の治療費、自分の判断で健康維持を目的にした整体などの費用は、医療費控除に合算できません。
また、入院時に、自己都合でベッドを代えたことによって生じる差額、院内の売店で購入した菓子類の代金なども控除の対象外となります。
【参考】医療費控除を受けるなら世帯分離をした方がいい?
医療費控除を受けるにあたって世帯分離をした方が良いかは、所得、及び生活状況によって異なります。
世帯分離をするメリットは、世帯分離によって所得が下がるため、自己負担の上限が下がり控除を多く受け取れる可能性があることです。
たとえば、扶養している父親が入院した場合、世帯分離を行うことで医療費、介護費が安くなる可能性は高いです。
一方、世帯分離を行うことで生じるデメリットもあります。
世帯分離を行ったことによって、自分の子供、親などを扶養していたことで減額されていた所得額、住民税などが増額するケースも珍しくありません。
医療費控除を受けるにあたって世帯分離をした方が良いかは、所得、家族の状況によって大きく異なります。
ご自身、もしくはご家族で判断がつかない場合は、ファイナンシャルプランナーに相談してみることをおすすめします。
医療費控除を受けられるか知りたい方におすすめのサービス
医療費控除は条件さえ合えば大きな節税につながる制度ですが、「うちは対象になるのか」「申請し忘れたら損するのでは」といった不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
特に、家族が世帯分離していたり、扶養に入っていないケースでは判断が難しく、制度を正しく理解していないことで本来受けられるはずの控除を逃してしまうこともあります。
また、医療費控除は申告のタイミングや申請書類の種類なども関わるため、「なんとなく不安だけどよく分からないまま放置してしまう」という方も少なくありません。
そんな時に頼りになるのが、税制や家計管理に精通した専門家への相談です。たとえば、「マネーキャリア」では医療費控除や世帯分離に関する疑問を、無料で何度でも専門家に相談することができます。
「世帯分離している親の医療費は合算できる?」「うちの場合は誰が申請すべき?」といった具体的なケースにも対応してもらえるため、不安や疑問をその場でスッキリ解消できますよ。

▼マネーキャリアの概要
- お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、年収や節税について知見の豊富な、ファイナンシャルプランナーのプロのみを厳選。
- 資産形成や総合的なライフプランの相談から最適な解決策を提案可能。
- マネーキャリアは「丸紅グループである株式会社Wizleap」が運営しており、満足度98.6%、相談実績も100,000件以上を誇る。

【まとめ】「生計を一にする」なら医療費控除はまとめて申告!
この記事では、「世帯分離していても医療費控除は合算できるのか?」という疑問に対し、制度の仕組みや判断基準を詳しく解説してきました。
ポイントとなるのは、「同居しているか」「扶養に入っているか」ではなく、実質的に生活を支え合っている=『生計を一にしている』かどうかです
たとえ世帯を分けていても、生活費や医療費を日常的に支援していれば、合算は可能です。 特に、以下のようなケースでは医療費控除が認められることがあります。
- 世帯分離した親の医療費を子供が負担している場合
- 別居中の配偶者の医療費を支払っている場合
- 扶養に入っていないが生活費のやり取りがある家族間での支払い
こうした重要な判断に迷ったときは、「マネーキャリア」の無料相談を活用するのがおすすめです。世帯分離や扶養の状況に応じて、専門家があなたに合った最適な申告方法をアドバイスしてくれます。