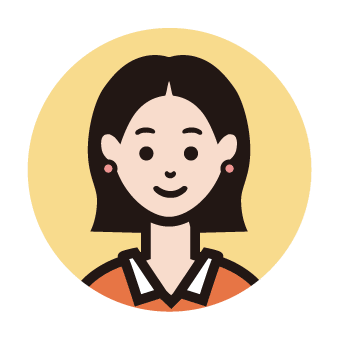内容をまとめると
- シングルマザーが利用できる主な支援制度には、年収204万円以下で住民税が非課税になる措置や、年収385万円未満で児童扶養手当や医療費助成が受けられる制度があります。
- ただし、支援に頼りすぎると収入の上限が固定化され、将来的な生活設計や教育費確保に不安が残るため、年収を上げる選択も視野に入れる必要があります。
- 今と将来を見据えて最適な判断をしたいなら、無料で何度でもFPに相談できる「マネーキャリア」の活用が有効で、家計や働き方を客観的に見直す第一歩として多くの人に選ばれています。

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- シングルマザーの年収はいくらがお得?所得制限の基準額の例を紹介
- 【年収204万円以下】住民税の非課税措置の対象
- 【年収385万円未満】児童扶養手当の対象
- 【年収385万円未満】ひとり親家庭等医療費助成の対象
- 【地域により異なる】ひとり親家庭の住宅手当の対象
- 【結論】年収385万円を超える場合はどんどん稼いだ方がいい
- シングルマザーの年収が上がるとどんな影響・デメリットがある?
- 保育料が上がる可能性がある
- 所得税の増加
- 社会保険料の増加
- 公的支援や手当の変化
- シングルマザーの年収が上がるとどんなメリットがある?
- 経済的な安定・安心感を得られる
- 子どもの習い事・塾などの教育費を確保できる
- 全体的な生活の質が上がる
- 将来に備えた貯蓄・投資がしやすくなる
- シングルマザーで年収や家計に悩みがある方におすすめのサービス
- まとめ;シングルマザーの年収はいくらが得?
シングルマザーの年収はいくらがお得?所得制限の基準額の例を紹介
シングルマザーとして働く場合、年収はどのくらいが適当なのでしょうか。所得制限の基準額を参考に、具体的な例を紹介します。
【年収204万円以下】住民税の非課税措置の対象
まず一つ目は、住民税の非課税措置です。住民税は、低所得世帯向けに非課税措置が設けられており、ひとり親世帯の場合は、前年の年収が204万円以下、合計所得で見ると135万円以下の場合において非課税になります。扶養家族がいる場合は、所得が135万円を超えたとしても非課税になる場合もあります。
住民税の非課税を維持したい場合は、年収204万円が一つの目安と考えても良いでしょう。住民税非課税世帯になると、国民健康保険や国民年金保険料など、社会保険料も減免されます。
【年収385万円未満】児童扶養手当の対象
児童扶養手当は、ひとり親世帯の生活安定と自立を支援する国の制度です。18歳以下の児童(一定の障害がある場合は20歳未満)を養育するひとり親が対象で、所得に応じて支給額が決定します。
支給額は、全部支給と一部支給の2段階制です。全部支給の月額は、児童1人の場合45,500円、一部支給は所得に応じて10,740円~45,490円です。2人目以降は、所得に応じて加算されます。
【年収385万円未満】ひとり親家庭等医療費助成の対象
ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭の医療費負担を軽減する制度です。ひとり親家庭の親と18歳以下の児童(一定の障害がある場合は20歳未満)を対象としています。
ひとり親家庭等医療費助成制度では、医療機関で支払った医療費の自己負担分が助成されます。所得制限や助成対象となる医療費の範囲は自治体によって異なるため、詳細はお住まいの市区町村の窓口で確認する必要があります。
【地域により異なる】ひとり親家庭の住宅手当の対象
ひとり親家庭向けの住宅手当は、経済的な負担を軽減し、安定した住居を確保するための支援制度です。支援内容は全国一律ではなく、住んでいる自治体によって内容が大きく異なります。
支給金額は自治体ごとの差が大きく、数千円から数万円までの幅があります。家賃の一部を補助する形式が多いものの、市営住宅など公営住宅への入居を斡旋する自治体もあります。
自治体 | 手当の金額 | 収入 | 所得制限 |
|---|---|---|---|
| 東京都世田谷区 | 4万円 | 480万円 | 329万8,000円 |
| 東京都武蔵野市 | 1万円 | ー | 274万円 |
| 千葉県君津市 | 5,000円 | ー | 274万円 |
| 千葉県浦安市 | 1万5,000円 | ー | 230万円 |
【結論】年収385万円を超える場合はどんどん稼いだ方がいい
ひとり親世帯が受けられる恩恵を考慮した上で働く場合、目安となる各制度の所得制限をピックアップしました。
- 住民税非課税世帯の年収204万円
- ひとり親家庭等医療費助成の年収240万円台〜270万円台
- 児童扶養手当の年収385万円
シングルマザーの年収が上がるとどんな影響・デメリットがある?

ひとり親世帯の年収が上がると、具体的にどのようなデメリットが考えられるのでしょうか。想定される4つのデメリットをピックアップしてみました。
保育料が上がる可能性がある
0歳〜2歳の住民税非課税世帯の子供は、認可保育園や認定こども園の保育料が無料になります。つまり、現在、住民税非課税世帯のひとり親世帯では、年収204万円を超えると保育料が上がる可能性があります。
子供の年齢や所得に関係なく保育料を無料としている自治体もあるものの、一般的には、保育料のアップはシングルマザーが年収を上げるデメリットの一つとして考えても良いでしょう。
保育料は住民税非課税世帯でなくとも、無料となるケースがあります。それぞれの施設で保育料無償となる条件を一覧表にまとめました。
保育所・認定こども園
| 年齢 | 無償化の範囲 |
|---|---|
| 3歳〜5歳 | すべての子供が無料 |
| 0歳〜2歳 | 住民税非課税世帯の子供が無料 |
認定外保育施設
| 年齢 | 無償化の範囲 |
|---|---|
| 3歳〜5歳 | 保育が必要な児童を対象に月額37,000円まで無料 |
| 0歳〜2歳 | 保育が必要かつ住民税非課税世帯を対象に 月額42,000円まで無料 |
所得税の増加
ひとり親世帯には、ひとり親控除として35万円の所得税控除が適用されます。ひとり親とは、その年の12月31日時点で、婚姻していない人、もしくは配偶者の生死が不明な人のいずれかの条件が当てはまる人です。さらに、次の3つの条件を満たすとひとり親控除が適用されます。
- 内縁関係や事実婚の相手がいない
- 生計を一つにする子供がいる
- 合計所得金額が500万円以下
社会保険料の増加
社会保険料は、主に「標準報酬月額」に基づいて決定されます。標準報酬月額は、毎月の給与(基本給、残業代、各種手当などを含む)を一定の範囲ごとに区分したものです。年収が上がると、標準報酬月額も上がる可能性が高いため、社会保険料も増加します。
実際の保険料額は、標準報酬月額に保険料率をかけて算出されるため、年収の増加と保険料の増加が必ずしも比例するわけではありませんが、一般的に年収が多い人ほど負担額は大きくなります。
シングルマザーとして自立するために、一生懸命働いて年収を上げると社会保険料の負担額も増加する可能性があることを認識しておきましょう。
公的支援や手当の変化
前述の通り、年収を上げると住民税の非課税措置や児童扶養手当、医療助成や住宅手当など、至れり尽くせりのひとり親支援制度の恩恵が受けられなくなる、もしくは少なくなる可能性があります。
公的な支援を受けつつ子供との時間を重視するのか、シングルマザーとして自立した生活を目指して、より年収のアップを目指すのか、悩みどころです。現在の状況を鑑みて、転換点をどこに設定するのかなど、将来を見据えた計画が必要です。
シングルマザーの年収が上がるとどんなメリットがある?

年収を上げるとひとり親世帯をサポートする支援制度は受けられなくなりますが、必ずしも損をすることばかりではありません。年収を上げることで想定されるメリットを4つ、ピックアップしてみました。
経済的な安定・安心感を得られる
年収を上げて全ての支援を受けずに生活できると、心の荷物を下ろしたような安堵感が得られます。公的な支援が受け続けていても安心感はありますが、税金で養ってもらっている感覚がどこかにあるため、少なからず後ろめたさを感じてしまう人もいます。
長い目で見た場合、制限のない経済的な自立を選択した方が、自分に使えるお金も増えることから豊かな生活を送れる可能性が高いです。
子どもの習い事・塾などの教育費を確保できる
公的な支援制度はひとり親世帯の経済的負担を緩和するための、重要な役割を果たしています。しかし、支援金額には上限が設けられており、全ての教育費をカバーできるわけではありません。子供にとって、より良い教育環境を用意するには、ずっと公的な支援頼みでいるわけにもいかないでしょう。
経済的な自立を果たすと、子供を習い事へ通わせたり、塾へ行かせたりなど一定の教育環境を整えることができます。
全体的な生活の質が上がる
経済的な自立を果たすと、生活の質を底上げできます。少し家賃を上乗せして、より快適な住環境を確保することもできますし、休みの日のレジャーやたまの外食なども、それほど無理することなく実現可能です。
生活の質を底上げすることで、日々の幸福感や満足感を得られるため、ストレスや不安の軽減から、心の平穏を保ちやすくなる効果もあります。何か新しいことに挑戦してみようというチャレンジングな精神も芽生えてくるでしょう。
将来に備えた貯蓄・投資がしやすくなる
公的な支援を受け続けている状況では、貯蓄や投資はままなりませんが、経済的な自立を果たせば、将来に備えるための貯蓄や投資を考えられるようになります。
貯蓄や投資はできるだけ早くからスタートした方が、良い効果を得やすいです。子供の教育費のための学資保険など、できるだけ早い段階から準備しておきたいところです。そのほか、昨今ではNISAなどの積立投資も、将来の資産形成のためのより良い選択肢も提供されるようになりました。
シングルマザーで年収や家計に悩みがある方におすすめのサービス
年収を上げたい気持ちはあっても、支援制度が受けられなくなる不安や、家計への影響を考えると、踏み出しづらいという声は多く聞かれます。特に、制度の「壁」がある中で、どのタイミングで動くべきかの判断は難しいものです。
そんなときこそ意識したいのが「収入」だけでなく「支出」を見直すことです。支出の管理を徹底することで、現在の年収のままでも家計の安定を図ることができるケースも少なくありません。
とはいえ、支出の見直しや制度の活用法をすべて自分で把握するのは簡単ではないため、何を優先すべきか・どの支援が自分に適しているのか迷う方も多いでしょう。
そこで活用したいのが、FP(ファイナンシャルプランナー)への相談です。家計の状況や希望を踏まえて、今の収入でできること、これから備えるべきことを一緒に考えてくれます。
「マネーキャリア」なら、相談実績10万件以上・満足度98.6%の信頼あるFPに何度でも無料で相談できるので、家計の見直しや将来の備えに、最初の一歩として気軽に活用してみることをおすすめします。

- お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、年収や節税について知見の豊富な、ファイナンシャルプランナーのプロのみを厳選。
- 資産形成や総合的なライフプランの相談から最適な解決策を提案可能。
- マネーキャリアは「丸紅グループである株式会社Wizleap」が運営しており、満足度98.6%、相談実績も100,000件以上を誇る。

まとめ;シングルマザーの年収はいくらが得?
シングルマザーが受けられる支援制度には、住民税の非課税となる年収204万円や、児童扶養手当の対象となる年収385万円など、いくつかの「壁」が存在します。
これらの基準を踏まえると、年収は204〜385万円の間に抑えるのが一つの目安といえるでしょう。
ただし、支援を優先して年収を抑えることが、必ずしも得とは限りません。収入が増えることで支援は減る一方、自立に向けた資金計画や生活の選択肢が広がるというメリットもあります。
大切なのは、目先の制度にとらわれず、家計全体と将来設計をふまえて判断すること。人それぞれ家庭の事情やライフプランが異なるからこそ、収入と支出のバランスを丁寧に考える必要があります。
このような複雑な事情を含めて考える時は、専門家の力を借りて冷静に整理してみるのも一つの手です。 「マネーキャリア」の無料FP相談を活用すれば、無理なく前向きな選択ができるようサポートしてくれますよ。