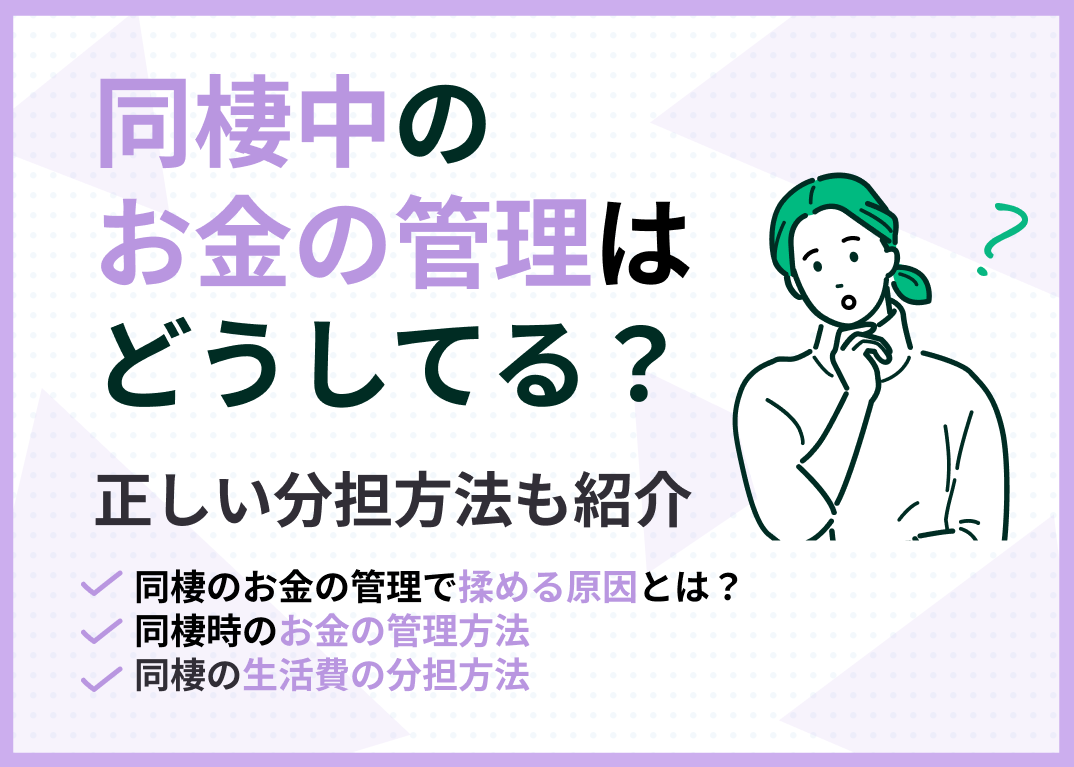
内容をまとめると
- 揉めないための同棲時のお金の管理方法は最初にルールを作ることです。収入や負担割合で不公平にならないよ話し合うことが大切である。
- また、貯金や将来設計の不一致をなくしておくことで、結婚も見据えたお付き合いが期待できる。
- 将来について不安がある方や同棲のお金のルールを2人で決められない、という方は、お金のプロであるFPへの相談がおすすめである。
- 「マネーキャリア」なら経験豊富なFPにオンラインで気軽に無料相談できるため、話ずらいお金の悩みも安心です。

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 同棲のお金の管理はどうしてる?揉める原因とは
- 揉めないための同棲時のお金の管理方法
- お金の使い方のズレを解消する
- 生活費の負担割合で揉めないためのルールをつくる
- 貯金や将来設計の不一致をなくす
- 同棲の生活費|分担方法の3パターンを比較
- 共同財布で生活費を管理する方法
- 項目別にお金を分担する方法
- 完全折半で平等になるようにする方法
- 同棲にかかるお金の内訳を解説
- 家賃や食費の内訳
- 同棲カップルの平均生活費
- 見落としがちな同棲の雑費
- 同棲解消時のお金トラブルを防ぐ方法
- 同棲のお金に関するよくある質問
- 同棲するための貯金はいくらが理想?
- 同棲のお金で揉めないためのルールは?
- 共同口座は作るべき?
- 同棲のお金の悩みを解決するために使える方法とは?
- 同棲のお金をどうするかが分かる正しい分担方法のまとめ
同棲のお金の管理はどうしてる?揉める原因とは
同棲生活が始まると、家賃・食費・光熱費・日用品といったさまざまな出費が発生します。
最初は「とりあえず折半で」とざっくり決めていても、時間が経つにつれて金銭感覚の違いや負担の偏りが目立ち、思わぬトラブルに発展することもあります。
たとえば、収入差を考慮せず完全な折半にしてしまうと、負担の重さに不満を感じる人も多くいるのが現実です。
さらに、共同財布でやりくりしている場合でも「何にどれだけ使ったのかわからない」「自分ばかりが払っている気がする」といった不公平感が生まれやすくなります。
また、「貯金はどうする?」「将来のライフプランに向けた備えは必要?」といった重要なお金の話を避けてしまうカップルも多く、そこから価値観のズレが明るみに出るケースも少なくありません。
同棲中の金銭トラブルは、話し合いのきっかけさえあれば未然に防げることがほとんどです。まずはお互いの考え方を確認し、無理のない分担方法を探ることが大切です。
揉めないための同棲時のお金の管理方法
同棲生活を円満に続けるには、お金の管理ルールを明確にすることが不可欠です。
ここでは、揉めないための具体的なポイントを3つご紹介します。
- お金の使い方のズレを解消する
- 生活費の負担割合で揉めないためのルールをつくる
- 貯金や将来設計の不一致をなくす
お金の使い方のズレを解消する
同棲中によくあるのが、「お金の使い方」に対する価値観の違いです。
たとえば、節約を重視する人と、趣味や交際費にお金をかけたい人とでは、日々の支出のバランスに不満が生まれることがあります。
こうしたズレを小さくするには、お互いの金銭感覚や優先順位について一度しっかり話してみるのが大切です。
そのため、週に一度、家計について軽く話し合う時間をつくったり、家計簿アプリを一緒に使って支出を見える化するのがおすすめです。
ストレスを減らすためにも、お金の使い方のズレは早めに解消しておくべきです。
生活費の負担割合で揉めないためのルールをつくる
生活費の負担については、同棲時以下の問題が起こりやすい傾向にあります。
- どちらが多く払っているか
- 家賃や光熱費はどう分けるのか
お金と負担の割合は、不公平感を抱きやすい部分でもあるため、注意が必要です。
例えば、収入に差がある場合は、折半ではなく収入比で分担する方法のほうが納得しやすいです。
また、生活費の支払い方についても、「項目ごとに分担する」「共通の財布を作る」など、の方法を一緒に考えてみるのもおすすめです。
2人にとって無理のないやり方を見つけておけると、気持ちよく過ごせる時間を増やすことが期待できますよ。
貯金や将来設計の不一致をなくす
同棲生活が落ち着いてきたら、目の前の支出だけでなく、先のライフプランについても話し合っておくべきです。
たとえば「いつまでにいくら貯めたいか」「結婚や出産をどう考えているか」など、将来に関わるお金のことは、ふたりで暮らすうえで避けて通れないテーマです。
貯金に対する意識や、人生設計のイメージが大きくズレていると、あとになってお互いの気持ちがすれ違う原因になることもあります。
特に、片方だけが不安を感じている場合、話し合いのきっかけがないまま時間が過ぎてしまうケースも少なくありません。明確なゴールを決める必要はなくても、まずは「どう考えているか」を共有しておくことが大切です。
互いの考え方を知っておくだけで、将来に向けた準備もしやすくなり、同棲生活の安心感につながります。
同棲の生活費|分担方法の3パターンを比較
同棲を始めるとき、多くのカップルが最初につまずきやすいのが「生活費の分担方法」です。 収入や価値観の違いによって、最適なやり方は人それぞれ異なります。
ここでは、実際によく選ばれている3つのパターンをご紹介します。
- 共同財布で生活費を管理する方法
- 項目別にお金を分担する方法
- 完全折半で平等になるようにする方法
お互いが無理なく納得できる形を選ぶことが、長く心地よく暮らすためのポイントになります。
共同財布で生活費を管理する方法
共同財布で生活費を管理する方法とは、ふたりで決めた金額を毎月同じ財布や口座に入れ、その中から生活に必要なお金を出していく方法です。
家賃や光熱費、食費、日用品の購入など、すべてをまとめて管理することができるため、支出の全体像を把握しやすくなるのが特徴です。この方法は「ふたりで一つの家計」という感覚を育みやすく、一体感が生まれやすいというメリットがあります。
一方で、どちらが何にいくら使っているかが曖昧になりがちなので、定期的な見直しやルール作りが必要です。
項目別にお金を分担する方法
項目別にお金を分担する方法とは、家賃は彼氏、光熱費と食費は彼女、といったように、生活費の項目ごとに分担するシステムです。役割がはっきりしているため、お互いの責任が明確になりやすく、それぞれの金銭管理の自由度を保ちやすいのが特長といえます。
この方法は、自分のペースでお金を管理したい人に向いています。ただし、項目によって金額の差が大きくなることもあるため、定期的に見直してバランスを整えることが求められます。
不公平感を相手に与えないためにも、最初にそれぞれの負担額をおおまかに試算しておくと安心です。目に見える金額の差がある場合は、どこかでバランスが取れるように調整するなど、歩み寄る姿勢を持つべきといえます。
「なんとなく」で分けるのではなく、お互いが納得したうえで決めることが、長く無理なく続けていくためのポイントになります。
完全折半で平等になるようにする方法
完全折半で平等になるようにする方法を選ぶ場合、全体の生活費を毎月合計し、2人でぴったり半分ずつ負担するようにするぼがベターです。
こちらの方法は、「公平でわかりやすい」「不満が出にくい」と感じる人も多く、特に収入が近いカップルに選ばれやすいスタイルです。
ただし、収入に差がある場合は、同じ金額を出すことがどちらかの負担になることもあるため注意が必要です。支出の内容や金額によっては、柔軟にルールを変えていくことも大切になってきます。
また、結婚も考えている場合は、将来の家計のあり方もふまえて話し合っておくべきです。完全折半が今はうまくいっていても、今後どちらかが仕事を変えたり、育児や家事の負担に差が出てきたりする可能性もあります。
長い目で見たときに、どうすればお互いに納得できる関係でいられるかを一緒に考えておくと、結婚後のお金のトラブルを防ぎやすくなります。目の前の負担だけでなく、ライフステージの変化に合わせて柔軟に対応していく姿勢が大切です。
同棲にかかるお金の内訳を解説
同棲を始める際に気になるのが、「毎月どのくらいお金がかかるのか」という点ではないでしょうか。
初期費用や生活費の感覚がつかめていないと、無理な家計管理になったり、思わぬ出費に戸惑ったりすることもあります。ここでは、同棲カップルにかかる主な費用について、具体的な内訳を以下3つの観点からご紹介します。
- 家賃や食費の内訳
- 同棲カップルの平均生活費
- 見落としがちな同棲の雑費
家賃や食費の内訳
同棲生活の中でも、家賃と食費は大きな割合を占める項目です。家賃については、地域や物件の条件によって大きく差が出ますが、都心部では月8〜12万円前後、地方では5〜8万円程度が一つの目安となることが多いようです。
総務省などの統計によると、二人暮らし世帯の家賃は、手取り月収の25~30%が望ましいと言われています。
また、賃貸契約時には敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用も必要となるため、最初にまとまった資金を準備しておく必要があります。一方で食費は、ふたり分とはいえ、外食やコンビニの利用が多いと月5〜6万円を超えることもあります。
自炊中心にすることで月3〜4万円に抑えることも可能ですが、食材の購入頻度やライフスタイルによって変動しやすい項目でもあります。このように、家賃と食費だけでも家計の大部分を占めるため、同棲を始める前に無理のない金額での見積もりをしておくと安心です。
参照:総務省
同棲カップルの平均生活費
実際に同棲しているカップルが、どれくらいの生活費を使っているのか気になる方も多くいます。総務省の「家計調査」では、家賃を除く2人暮らし世帯の支出平均は約241,372円との報告があります(食費約70,550円、光熱費約21,708円など)。
この中には、家賃や食費に加え、水道光熱費(電気・ガス・水道)、通信費(Wi-Fi・スマホ代)なども含まれています。
ただし、生活スタイルや収入、暮らす地域によってこの数字は大きく変わることがあります。 たとえば車を所有している場合や、ペットを飼っている場合は、その分の維持費や医療費がプラスされます。
また、ふたりとも外食やレジャーが好きな場合には、交際費も高くなる傾向があります。平均額はあくまで目安としてとらえ、自分たちの生活に合わせて予算を組み立てていくことが大切です。
毎月の出費をある程度把握しておくことで、無理のない家計管理や貯金の計画も立てやすくなります。
参照:総務省
見落としがちな同棲の雑費
同棲を始めたとき、意外と見落としがちなのが「雑費」の存在です。たとえば、トイレットペーパーやティッシュ、洗剤、シャンプー、ゴミ袋などの消耗品は、少額とはいえ毎月確実にかかる支出です。
また、キッチン用品や掃除道具、収納アイテムなど、最初のうちは生活環境を整えるための出費も少なくありません。
さらに、結婚式のご祝儀やお互いの誕生日・記念日のプレゼント代、衣替えのための衣類や寝具の購入費なども、雑費として定期的に発生するため、考慮しておくべき点です。
小さな出費の積み重ねだからこそ、事前に雑費用として月3,000円〜5,000円程度の枠を確保しておくと安心です。このような細かな支出は、家計簿をつけていないと見えづらく、いつの間にか予算をオーバーしていることもあります。
生活費をざっくり把握するだけでなく、こうした雑費まで含めてお金の流れを意識することで、より安定した同棲生活を送ることができますよ。
同棲解消時のお金トラブルを防ぐ方法
同棲を解消する際は、感情面だけでなく、お金に関する問題が表面化しやすくなります。特に家賃や光熱費、家具・家電の所有権、敷金の返還など、共同生活で生じた費用の精算は、曖昧なままにしておくとトラブルの原因になりがちです。
トラブルを防ぐためには、まず「お金の整理」と「気持ちの整理」を分けて考えることが大切です。話し合いの場では、感情に流されすぎず、いつ・何に・どれだけお金を出していたかを整理したうえで、冷静に分担の方向性を話し合う必要があります。
家賃の清算や敷金の扱い、購入した家具や家電の引き取り方などは、可能であれば事前にリストアップし、書面に残しておくと安心です。
また、片方だけが引越しをする場合、その費用や新生活にかかる初期費用なども含めて、お互いにできる範囲で配慮し合えると、後味のよい別れにつながります。
別れる理由がどんなものであっても、お金のトラブルが残ってしまうと、せっかくの思い出に影を落とすことにもなりかねません。
円満な同棲解消のためには、「最後まで誠実に向き合うこと」がなによりの鍵です。感情と経済的な負担の両方に目を向け、話し合いを重ねることで、互いに納得できるかたちで前に進むことを目指すのがおすすめです。
同棲のお金に関するよくある質問
「同棲を始めたいけれど、実際いくらかかるの?」「生活費はどうやって分ければいい?」 そんな疑問を抱く方はとても多く、実際に同棲を始めてからもっと事前に話し合っておけばよかった、と感じるカップルも少なくありません。
そこでここでは、実際に多くのカップルが気になる「お金にまつわるよくある質問」を3つピックアップし、わかりやすく解説していきます。
- 同棲するための貯金はいくらが理想?
- 同棲のお金で揉めないためのルールは?
- 共同口座は作るべき?
同棲するための貯金はいくらが理想?
結論、同棲するための貯金は100万円程度あると安心です。
同棲を始める際は、物件契約時の敷金・礼金・仲介手数料、引越し費用、家具・家電の購入など、さまざまな初期費用がかかります。
特に賃貸契約の初期費用は家賃の4〜6ヶ月分程度が相場とされており、東京都内で家賃10万円なら40万〜60万円かかることも少なくありません。さらに、ベッドや冷蔵庫、洗濯機、調理器具などの生活用品を一から揃えると、追加で10〜20万円は見ておきたいところです。
また、生活が始まったあとの毎月の支出(家賃・光熱費・食費など)も発生するため、生活費の3ヶ月分程度を別に確保しておくと、より安心してスタートできます。余裕を持った準備をすることで、金銭的な焦りや不安なく新生活を始められます。
同棲のお金で揉めないためのルールは?
結論、同棲のお金で揉めないためには、支払いルールを事前に決め、定期的に見直すことが大切です。
同棲中によくあるトラブルの原因は、「お金の分担が曖昧」「自分ばかりが多く払っている気がする」など、金銭面のすれ違いによるものです。
だからこそ、同棲を始める前に、家賃・光熱費・食費・日用品などを誰がどう負担するのか、具体的なルールを決めておく必要があります。収入が近い場合は折半でもよいですが、収入差があるなら負担割合を調整するほうが不満が溜まりにくくなります。
また、「家賃は彼氏、食費は彼女」などの項目別分担や、共通財布・共通口座を使う方法もあります。どれが正解というより、ふたりにとって納得できる方法を選ぶことが大切です。
一度決めたルールも、生活スタイルの変化や収支バランスによって見直す機会を設けておくと、より長く快適な同棲生活を送れるでしょう。
共同口座は作るべき?
共同口座は、管理を一本化したいならおすすめできる方法です。ただし、無理に作らず段階的に検討をすることが大切です。
共同口座は、ふたりの生活費をまとめて管理できるため、家賃・光熱費・食費などの支払いがスムーズになります。口座の明細を見れば支出の全体像が把握しやすく、「どちらがどれだけ出しているか」が可視化される点でもメリットがあります。
一方で、片方が口座を多く使っていると感じたときに「不公平だ」と思いやすくなるなど、信頼関係や使い方のルールが曖昧なまま運用するとストレスにつながることも考えられます。
そのため、はじめから共同口座をつくらず、家計簿アプリや共通財布を使って「共有する」経験を重ねてから、本格的に導入を考えるのもひとつの方法です。
また、結婚を視野に入れているカップルなら、将来的な家計管理の練習として共同口座はとても有効です。 ただし、お金のスタイルは人それぞれであるため、無理のないタイミングと方法で進めることが大切です。
同棲のお金の悩みを解決するために使える方法とは?
ここでは、同棲中に生まれやすいお金の不安や迷いを、プロのサポートで解消する方法を紹介します。
「生活費の分担ってこのままでいいの?」「将来に向けて、貯金や保険ってどう考えたらいいの…」と悩む方も少なくありません。今後のライフプランや万が一のリスクも踏まえるなら、ひとりで抱え込まずにお金の専門家と一緒に考えることが安心への近道です。
そこで役立つのが、無料でファイナンシャルプランナー(FP)に相談できる「マネーキャリア」です。マネーキャリアでは、同棲カップルのお金の悩みにも親身に寄り添いながら、ふたりに合った家計管理や保険・貯蓄のアドバイスが受けられます。
また、マネーキャリアの魅力は、特定の保険会社に属さない中立的な立場のFPが対応することです。相談は何度でも無料で、収入やライフスタイルに応じたオーダーメイドの提案が受けられることができます。

家計やお金の悩み全般を無料でオンラインで解消
マネーキャリア:https://money-career.com/
マネーキャリアのおすすめポイントはこちら
- お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、年収や節税について知見の豊富な、ファイナンシャルプランナーのプロのみを厳選
- 資産形成や総合的なライフプランの相談から最適な解決策を提案可能
- マネーキャリアは「丸紅グループである株式会社Wizleap」が運営しており、満足度98.6%、相談実績も100,000件以上を誇っています

同棲のお金をどうするかが分かる正しい分担方法のまとめ
本記事では、同棲を始めるにあたって避けて通れない「お金の分担」について、よくある悩みや3つの分担方法(共同財布・項目別分担・完全折半)を紹介しました。
それぞれの方法にはメリット・デメリットがあり、大切なのは「ふたりの収入や価値観に合ったスタイルを見つけること」です。
結論として、同棲中のお金のトラブルを防ぐためには、最初にルールを決め、定期的に見直すことが何より重要です。また、将来の結婚やライフプランを視野に入れて話し合うことで、お金に対する価値観のすり合わせもしやすくなります。
とはいえ、「本当にこの分け方でいいのか不安」「ふたりに合ったやりくり方法をプロに相談したい」と感じる方もいるかもしれません。そんなときに頼れるのが、無料で何度でも相談できるファイナンシャルプランナーサービス「マネーキャリア」です。
マネーキャリアでは、保険会社などに属さない中立的な立場のFPが対応し、家計や将来の悩みに寄り添ったオーダーメイドの提案が受けられます。同棲カップルの相談実績も豊富なので、初めてでも安心して利用できます。
マネーキャリアを利用して、同棲のお金どうする?の悩みを解決に導き、安定した同棲生活を目指していきましょう。





















