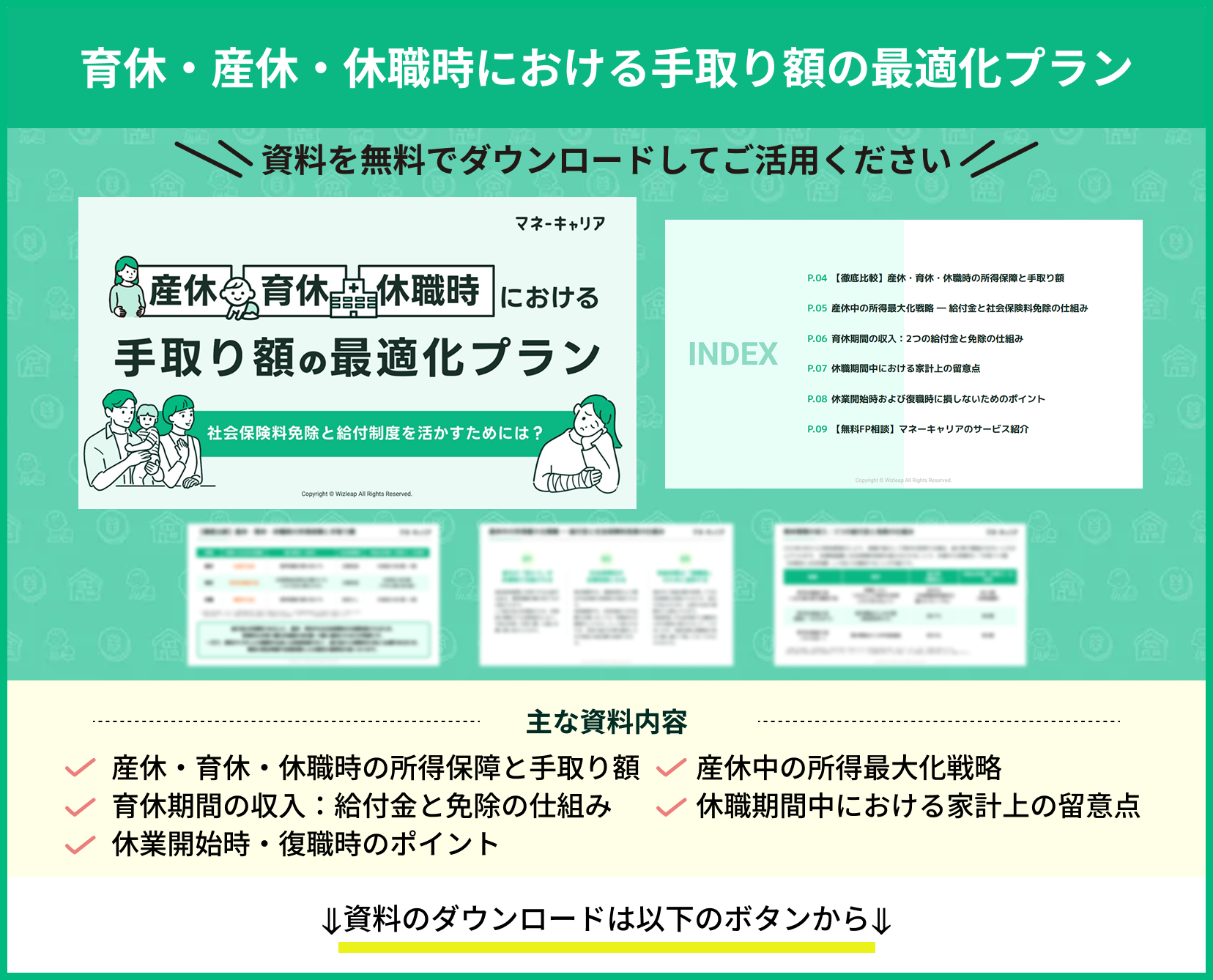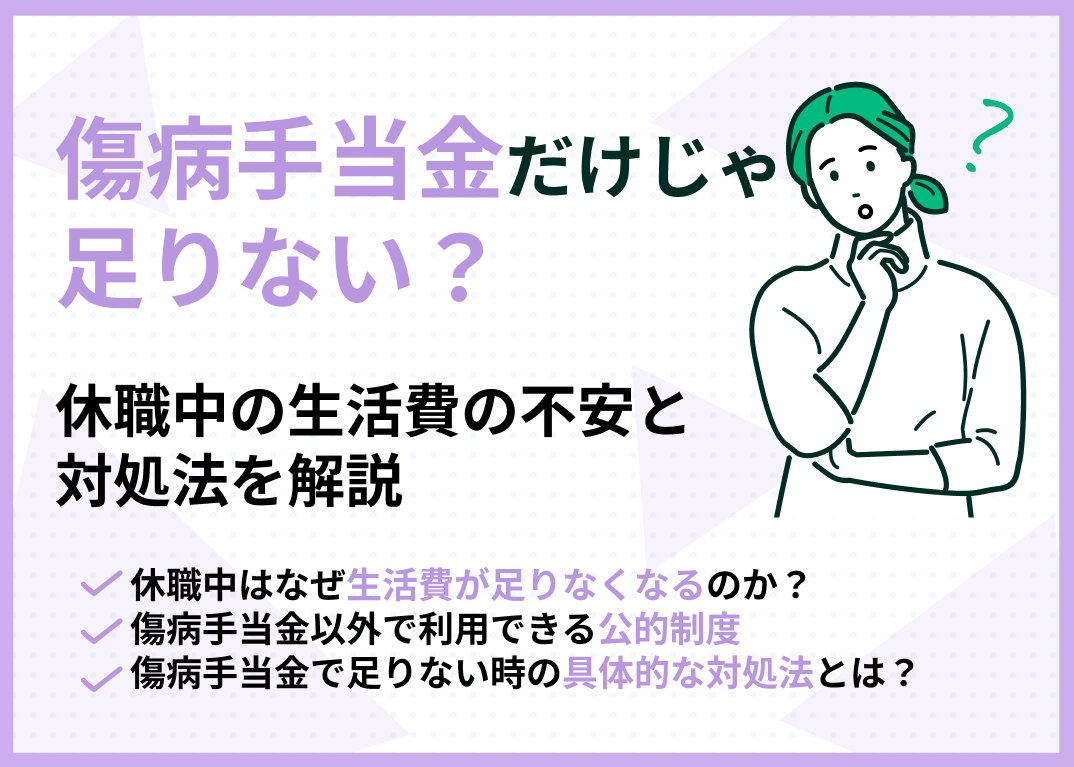
内容をまとめると
- 休職中に生活費が不足する主な理由は、傷病手当金が月給の約2/3にとどまる一方で、社会保険料や税金、医療費などの支払いが続くためです。
- そうした状況に備えるには、「高額療養費制度」や「住居確保給付金制度」などの公的支援を活用しつつ、家計の見直しや副業の検討、傷病手当金の確実な申請などの対策を講じることが大切です。
- とはいえ、制度の条件や手続きは複雑で、自己判断が難しいケースが想定されるため、相談実績10万件・満足度98.6%を誇る「マネーキャリア」で、何度でも無料相談できるFPと一緒に、自分に合った対策を見つけていくのがおすすめです。

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 休職中はなぜ生活費が足りなくなるのか?
- 傷病手当金の支給額が月給の約2/3であるため
- 社会保険料や住民税、医療費などの支払い負担
- 傷病手当金以外で利用できる公的制度とは
- 医療費負担を軽減する制度
- 住居確保給付金制度の活用方法
- 傷病手当金で足りない時の具体的な対処法とは
- 家計の見直しと支出の削減
- 生活福祉資金貸付制度の活用検討
- 休職中の副業や内職の可否確認と選択
- 傷病手当金支給期間終了後に取るべき方法とは
- 障害年金への切り替えを検討
- 失業給付金の特例受給要件
- 休職中の傷病手当金申請のポイント
- 申請書類の記入と医師の診断書取得
- 会社との円滑な連携方法
- 休職中の傷病手当に関するよくある質問
- 傷病手当金はいつ振り込まれるのか
- 適応障害で休職しても手当はもらえるのか
- 傷病手当金は退職後も継続受給できるのか
- 休職中にお金に困った際におすすめのサービス
- 休職中の傷病手当の概要と対処法まとめ
休職中はなぜ生活費が足りなくなるのか?
休職中に生活費が足りなくなる主な理由は、収入が減少する一方で、社会保険料や税金、医療費などの固定費の支払いが続くためです。
具体的には、以下の点が生活費の不足につながります。
- 傷病手当金の支給額が月給の約2/3であるため
- 社会保険料や住民税、医療費などの支払い負担
傷病手当金の支給額が月給の約2/3であるため
休職中に生活費が足りなくなる原因のひとつは、傷病手当金の支給額が月給の約2/3であるためです。
これは、健康保険法に基づき定められた支給基準であり、傷病手当といっても月給の全額が支給されるわけではないのです。
例えば、月給30万円の方が休職した場合、傷病手当金として支給されるのは、だいたい月に20万円程度になります。
つまり、月々10万円の収入減少に繋がり、今までと同じ生活レベルを維持しようとすると、この差額がそのまま生活費の足りない部分として現れてしまうのです。
そのため、休職が決定したらまずは傷病手当金の具体的な支給額を確認し、家計の状況を把握することが重要です。
社会保険料や住民税、医療費などの支払い負担
たとえ収入が減少しても、それに伴い支出が自動的に減少するわけではありません。
休職中であっても社会保険料や住民税、医療費などの支払い負担は続きます。
特に、健康保険料や厚生年金保険料などの固定費は、給与が支払われなくても支払い義務が生じます。
また、住民税は前年度の所得に基づいて課税されるため、休職中でも納税通知書が届きます。
さらに、病気やケガで休職している場合、通院費や薬代などの医療費が追加で発生します。
これらの支出が収入から差し引かれることで、利用できる生活費はさらに足りなくなってしまうのです。
そのため、休職する前にこれらの支出がどのくらいかかるのかを把握し、対策を立てておくことが重要です。
傷病手当金以外で利用できる公的制度とは
休職中に利用できる公的制度は、傷病手当金だけではありません。
生活費の不安を軽減するためには、様々な公的支援制度を理解し、活用することが重要です。
特に以下2つの制度は、休職中の家計を助ける上でとても役立ちます。
- 医療費負担を軽減する制度
- 住居確保給付金制度の活用方法
医療費負担を軽減する制度
休職中に医療費の負担が足りないと感じる場合、いくつかの公的制度でその負担を軽減できます。
最も代表的なのは「高額療養費制度」です。
これは、1ヶ月の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超えた分が払い戻される制度です。
また、難病指定されている疾患の場合や、精神疾患による継続的な通院が必要な場合には、「自立支援医療制度」の利用も検討できます。
この制度を利用すると、医療費の自己負担割合が1割に軽減されるため、長期的な治療が必要な方にとっては大きな助けとなります。
住居確保給付金制度の活用方法
住居確保給付金は、離職や廃業、または個人の都合によらない休業などにより経済的に困窮し、住居を失うおそれがある方に、家賃相当額を支給する制度です。
休職によって収入が大幅に減少し、家賃の支払いが足りない状況に陥った場合に活用できます。
支給期間は原則3ヶ月ですが、一定の条件を満たせば最長9ヶ月まで延長が可能です。
ちなみに、この制度を利用するにはハローワークでの求職活動を行うことなどが条件に含まれます。
つまり、給付金を受け取りながらも、症状の回復に合わせて社会復帰を目指すことが求められるということです。
これらの制度をしっかりと活用し、安心して治療に専念しながらも復職に向けた準備を進めましょう。
傷病手当金で足りない時の具体的な対処法とは
傷病手当金だけでは生活費が足りない場合、具体的な対策を講じることが重要です。
経済的な不安を解消し、安心して療養に専念するためには、様々な選択肢を検討する必要があります。
主な対処法としては、以下の3つの方法が挙げられます。
- 家計の見直しと支出の削減
- 生活福祉資金貸付制度の活用検討
- 休職中の副業や内職の可否確認と選択
家計の見直しと支出の削減
傷病手当金だけでは生活費が足りない場合、まず家計全体を見直し、支出の削減を検討することが最も基本的で効果的な対処法です。
まずは、固定費と変動費に分けて、無駄がないかを確認しましょう。
例えば、スマートフォンのプランを見直したり、不要なサブスクリプションを解約したりするだけでも、毎月の負担を減らせます。
また、食費や娯楽費といった変動費も、予算を決めて管理することで使いすぎを防げます。
さらに、家計簿アプリなどを活用して支出を「見える化」すると、削減できる項目が明確になり、効率的に生活費の足りない部分を補えるでしょう。
生活福祉資金貸付制度の活用検討
生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者、障害を持つ方などを対象に、生活再建に必要な資金を貸し付ける公的な制度です。
休職によって収入が大幅に減少し、傷病手当金だけでは生活費が足りない場合に活用を検討できます。
この制度には、生活費をまかなう「総合支援資金」や、緊急的な支出に対応する「緊急小口資金」など、目的に応じた様々な種類があります。
特に、一般的な金融機関からの借り入れに比べて、低金利または無利子で利用できる点が大きなメリットです。
お住まいの市区町村の社会福祉協議会が窓口となっているため、まずは自分が利用できるかどうか相談してみることをおすすめします。
休職中の副業や内職の可否確認と選択
休職中の収入が足りないと感じる場合、体調が許す範囲で副業や内職を検討することも一つの方法です。
ただし、休職の理由や会社の就業規則によっては、副業が認められないケースもあります。
そのため、まずは会社の担当者や産業医に相談し、副業が可能かどうか、また可能な場合はどのような範囲での活動が許容されるのかを確認することが必要です。
許可が得られた場合でも、体調への影響を最優先に考え、webライティングやアンケートモニターなど、無理のない範囲で始められる在宅ワークを選ぶことが大切です。
※ただし、会社の許可とは別に、労働の対価として収入を得ることで保険者(健康保険組合等)から「労務可能」と判断され、傷病手当金が支給停止となるリスクがあります。副業を検討する際はその点を十分に留意し、慎重に判断してください。
傷病手当金支給期間終了後に取るべき方法とは
傷病手当金の支給期間は最長1年6ヶ月と定められています。
この期間が終了した後も病状が続き、すぐに仕事に復帰できない場合、生活費が足りないという問題がさらに深刻化する可能性があります。
しかし、以下のように傷病手当金以外にも利用できる公的制度が複数存在します。
- 障害年金への切り替えを検討
- 失業給付金の特例受給要件
障害年金への切り替えを検討
傷病手当金の受給が終了した後も病状が継続し、就労が困難な場合、障害年金への切り替えを検討することが重要な選択肢となります。
障害年金には、国民年金に加入している方が対象の「障害基礎年金」と、厚生年金に加入している方が対象の「障害厚生年金」があります。
支給額は、障害の程度や加入期間によって異なります。
また、同一の傷病により障害年金(障害厚生年金など)が受給できる場合、原則として傷病手当金は支給されません。
ただし、障害年金の額を360で割った日額が、傷病手当金の日額より低い場合は、その差額分が傷病手当金として支給される調整が行われます。
そのため、自身の病状や加入状況を確認し、受給要件を満たしているかを早めに確認しましょう。
失業給付金の特例受給要件
病気や怪我で働けない場合、通常の失業給付金(雇用保険の基本手当)は受給できません。
しかし、傷病手当金の受給終了後も病状が回復せず、すぐに働くことが困難な場合、「失業給付金の受給期間延長」や「特例受給」が適用される可能性があります。
通常、失業給付の受給期間は離職の翌日から1年間ですが、病気などにより30日以上働けない場合は、その期間に応じて最長3年間まで延長可能です。
また、傷病手当金を受給していた方が、その後も就労が難しい状況であれば、ハローワークで特例として基本手当の受給を申請できる場合があります。
この手続きには医師の診断書などが必要となるため、自分が支給の対象となる方は、まずハローワークに相談し、詳細な要件や手続きを確認することが重要です。
休職中の傷病手当金申請のポイント
休職中に傷病手当金を確実に受け取るためには、申請プロセスを正しく理解し、適切な対応をとることが重要です。
特に、必要書類の準備や会社との連携は、スムーズな受給の鍵となります。
ここでは、以下2つの主要なポイントについて説明します。
- 申請書類の記入と医師の診断書取得
- 会社との円滑な連携方法
申請書類の記入と医師の診断書取得
傷病手当金の申請で最も重要なのは、申請書類の正確な記入と医師の診断書(意見書)の取得です。
申請書には、ご自身の基本情報や療養状況、仕事内容などを詳しく記載する必要があります。
特に、病気やケガで「労務不能であった期間」を正確に記入することが重要です。
また、医師の診断書は、病状や治療経過、そして労務不能であることの医学的な根拠を示すために不可欠な書類です。
診断書は、傷病手当金の申請期間ごとに医師に作成してもらう必要があります。
そのため、通院の際に忘れずに依頼し、早めに準備を進めるようにしましょう。
会社との円滑な連携方法
傷病手当金の申請には、会社との円滑な連携が不可欠です。
まず、休職の決定後すぐに人事担当者や総務担当者へ連絡を取り、傷病手当金の申請に必要な手続きや書類について確認しましょう。
申請書には、会社が記入する欄があるため、担当者に協力を依頼する必要があります。
この際、社会保険料の取り扱いや、休職期間中の給与支給の有無についても確認しておくと良いでしょう。
会社によっては、健康保険組合への提出を代行してくれる場合もあります。
不明な点があれば遠慮なく質問し、相互に協力しながら手続きを進めることで、生活費が足りないという状況を避けることに繋がりますよ。
休職中の傷病手当に関するよくある質問
休職中の傷病手当金については、多くの疑問や不安を抱える方がいらっしゃいます。
特に、生活費が足りないかもしれないという状況では、支給のタイミングや対象となる病気、退職後の受給可否などは非常に気になる点でしょう。
ここでは、傷病手当金に関してよくある質問とその回答をまとめました。
- 傷病手当金はいつ振り込まれるのか
- 適応障害で休職しても手当はもらえるのか
- 傷病手当金は退職後も継続受給できるのか
傷病手当金はいつ振り込まれるのか
傷病手当金がいつ振り込まれるのかは、多くの方が気にされる点です。
申請から実際に支給されるまでの期間は、概ね2週間から2ヶ月程度が目安とされています。
これは、健康保険組合や協会けんぽが申請内容を審査する期間が必要となるためです。
特に、初めての申請や内容に不備がある場合は、審査に時間がかかることがあります。
しかし、一度支給が開始されれば、その後は原則として月に一度、指定の金融機関口座に振り込まれることが一般的です。
そのため、申請が遅れると生活費が足りない期間が長くなる可能性があるため、早めの申請が大切です。
適応障害で休職しても手当はもらえるのか
適応障害で休職した場合でも、傷病手当金は支給対象となります。
重要なのは、適応障害と診断され、その病状によって労務不能であると医師が判断していることです。
つまり、診断書において「労務不能である」旨が明記されている必要があります。
精神疾患による休職であっても、身体的な病気と同様に、健康保険の支給要件を満たせば傷病手当金を受け取れます。
そのため、適応障害で休職を検討している場合は、まずは医師に相談することが大切です。
適切な診断と診断書の発行を依頼することが、生活費が足りないという不安を解消する第一歩となりますよ。
傷病手当金は退職後も継続受給できるのか
傷病手当金は、一定の条件を満たせば退職後も継続して受給できる場合があります。
この「継続給付」の条件は、主に以下の2点です。
- 退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
- 退職日に傷病手当金を受給しているか、または受給できる状態であること。
つまり、退職日の時点で病気やケガのために労務不能である必要があります。
退職後に継続給付を受けるためには、健康保険組合や協会けんぽに必要書類を提出し、改めて手続きを行う必要があります。
具体的には、医師の診断書や退職証明書などが求められるため、これらの条件と手続きを事前に確認しておくことが大切です。
休職中にお金に困った際におすすめのサービス
ここでは、休職中に生活費が足りなくなってしまったときに頼れるサービスを紹介します。
「傷病手当金だけでは家計がまわらない…」
「支出はそのままなのに、収入が大幅に減って不安…」と感じる方も多いはずです。
実際、収入減と固定費の支払いが重なることで、予想以上に金銭的な余裕がなくなり、日々のやりくりに頭を悩ませる方が少なくありません。
しかし、そんな時こそ今後の生活や回復までの期間を見据えて、お金のプロである専門家と一緒に対策を考えることが重要です。
家計の見直しや制度の活用、副業の判断など、どれをどう進めればいいのかを一人で決めるのは難しいものです。
そのような悩みを抱える方に支持されているのが「マネーキャリア」です。ファイナンシャルプランナー(FP)に何度でも無料で相談でき、自分の状況や悩みに合わせた最適なアドバイスを受けられます。
また、相談前にFPの経歴や口コミを確認できるため、安心して相談相手を選べる点も高評価です。中立的な立場からの提案が受けられるのも、「売り込みがない」と好評の理由の一つです。
「どこから手をつければいいか分からない…」と感じたら、まずは気軽にマネーキャリアに相談してみましょう。生活不安を少しでも軽減し、安心して療養に専念する第一歩になります。
<マネーキャリアのおすすめポイントとは?>
- お客様からのアンケートを元にプロのファイナンシャルプランナーのみを厳選しています。
- もちろん、住宅ローンだけではなく、資産形成や総合的なライフプランの相談から最適な解決策を提案可能です。
- マネーキャリアは「丸紅グループである株式会社Wizleap」が運営しており、満足度98.6%、相談実績も100,000件以上を誇ります。

休職中の傷病手当の概要と対処法まとめ
ここまでご紹介してきたように、休職中は収入が減る一方で、社会保険料や医療費などの支出は継続するため、生活費が足りなくなるケースが非常に多く見られます。
そんな時に頼りになるのが「傷病手当金」ですが、その制度内容や支給条件を正しく理解しておくことが、安心して療養を続けるための第一歩です。
また、傷病手当金だけでは生活が成り立たない場合もあるため、制度の賢い活用や支出の見直し、副業の可否といった対策も合わせて検討していく必要があります。
ただし、制度ごとの条件や手続きは複雑なため、一人で判断するのは難しいこともあります。
そんな時は、専門家に無料で何度でも相談できる「マネーキャリア」のようなサービスを活用することで、自分に合った最適な対策を見つけることが可能になります。