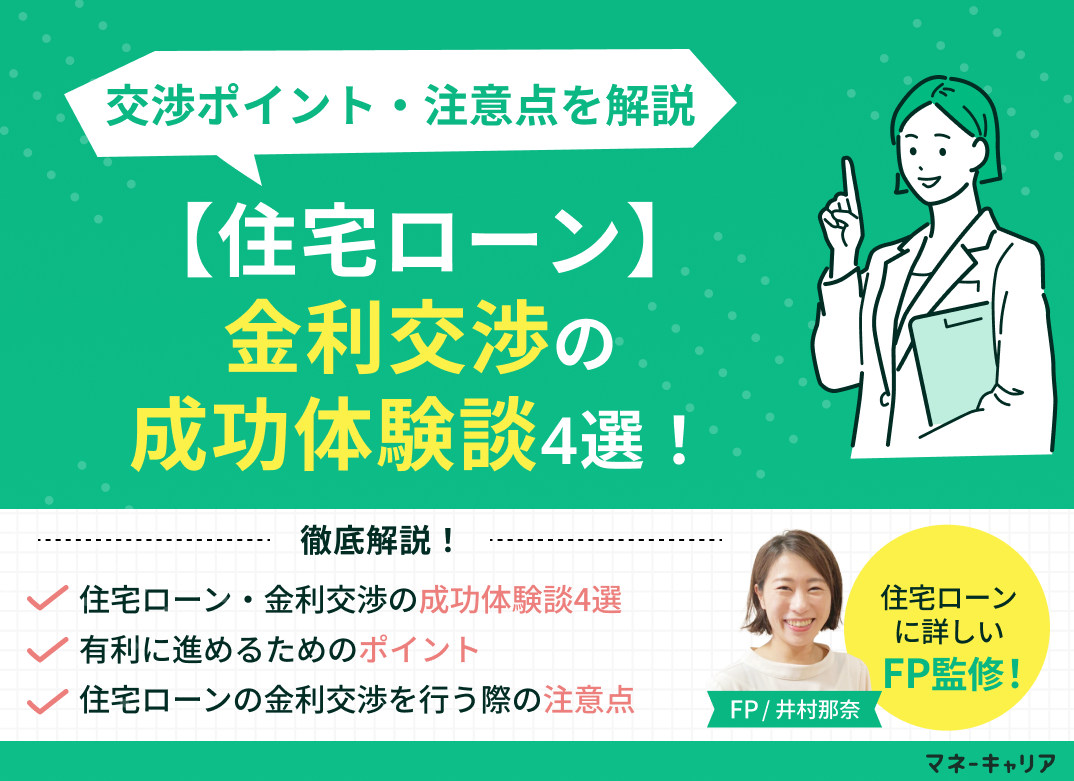NEW ARTICLES新着記事
-
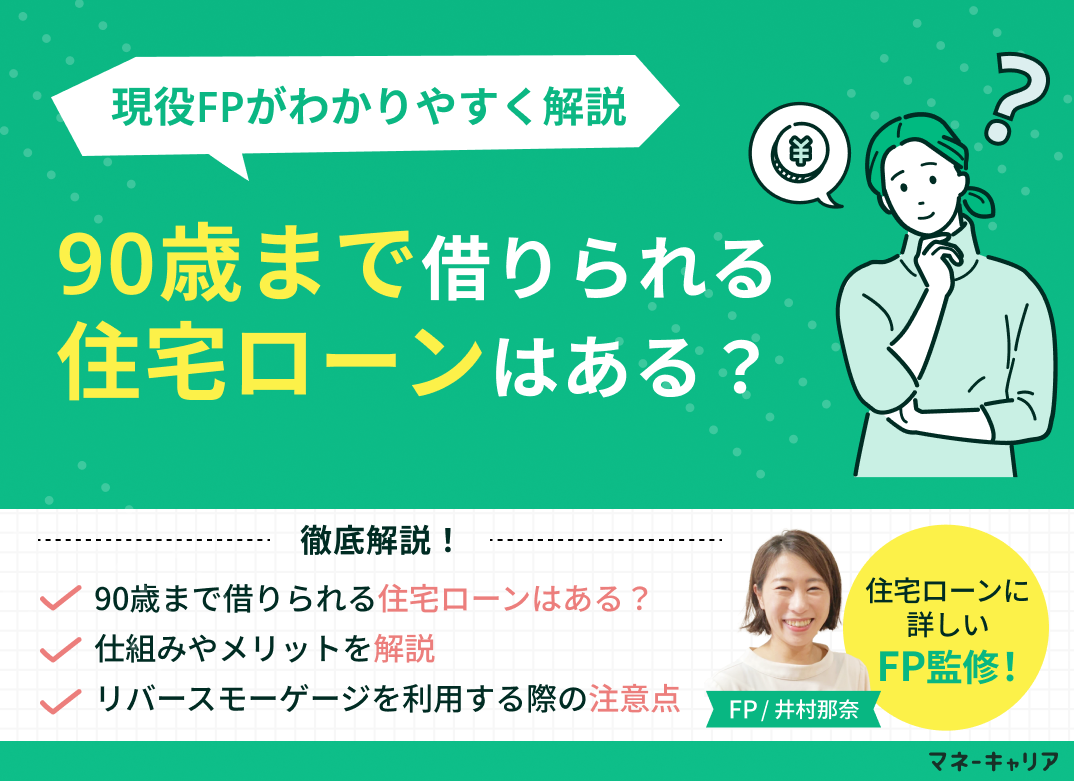 90歳まで借りられる住宅ローンはある?現役FPがわかりやすく解説
90歳まで借りられる住宅ローンはある?現役FPがわかりやすく解説2025-09-18
-
 転職で住宅ローンの金利は変わる?返済中に気をつけたい注意点を解説
転職で住宅ローンの金利は変わる?返済中に気をつけたい注意点を解説2025-09-18
-
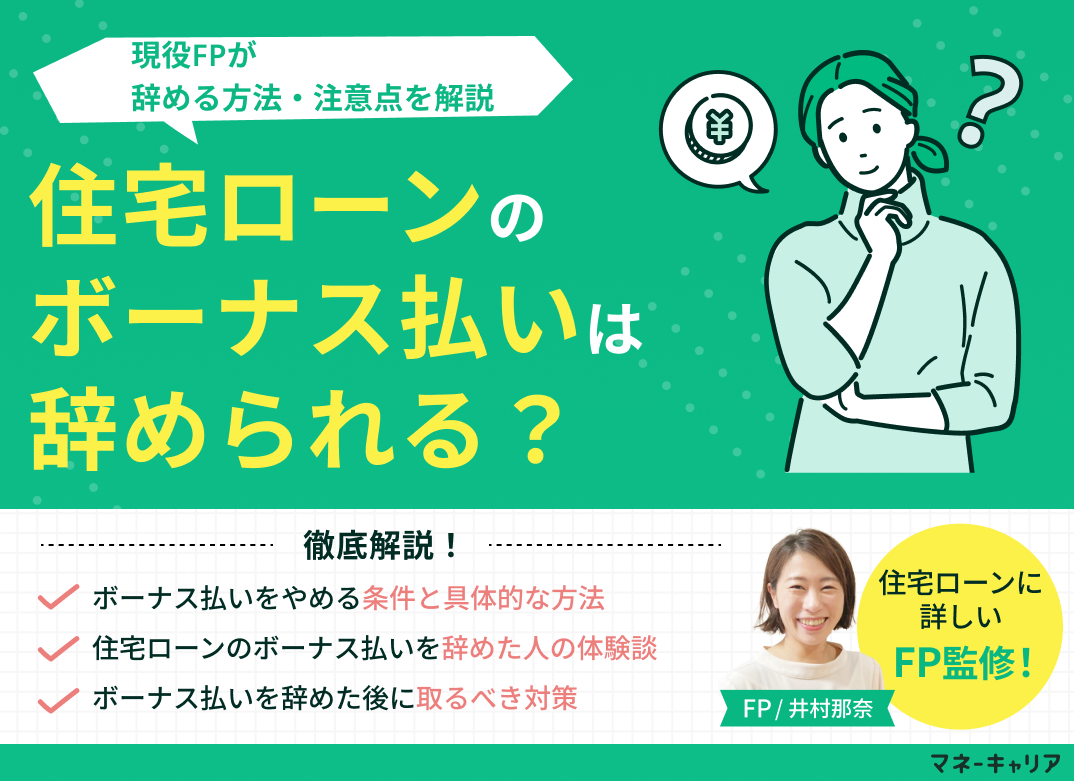 住宅ローンのボーナス払いを辞められる?辞める方法・注意点を解説
住宅ローンのボーナス払いを辞められる?辞める方法・注意点を解説2025-09-17
-
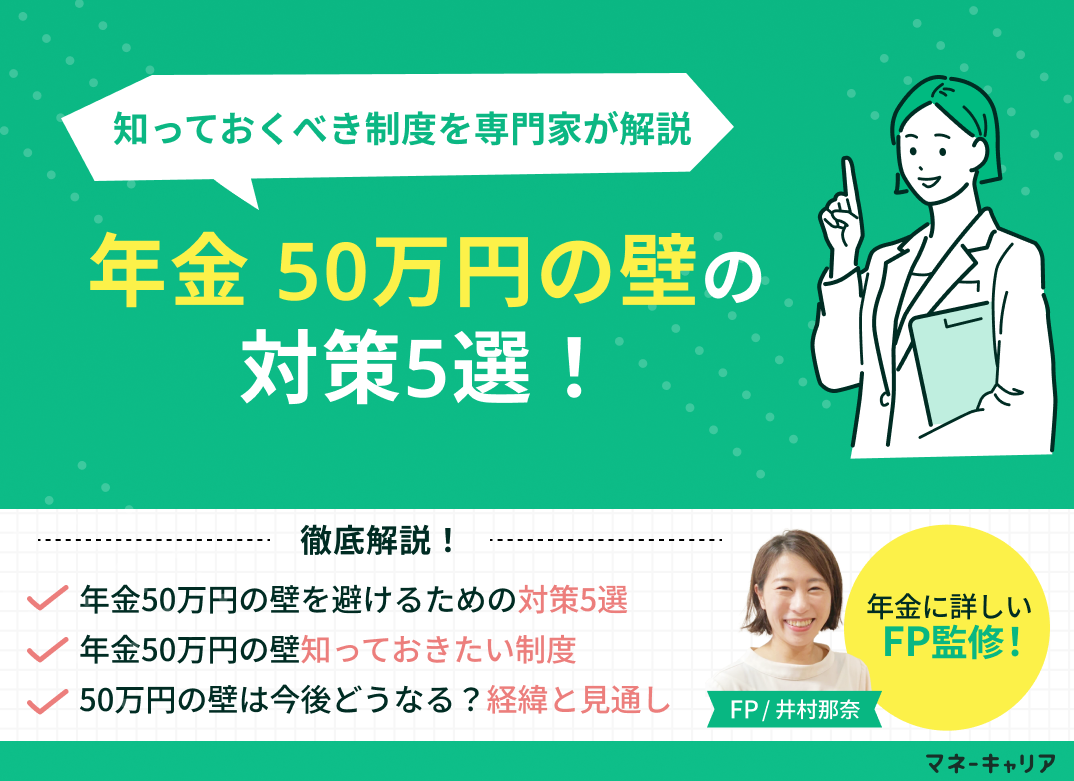 年金「50万円の壁」の対策5選!知っておくべき制度を専門家が解説
年金「50万円の壁」の対策5選!知っておくべき制度を専門家が解説2025-09-17
-
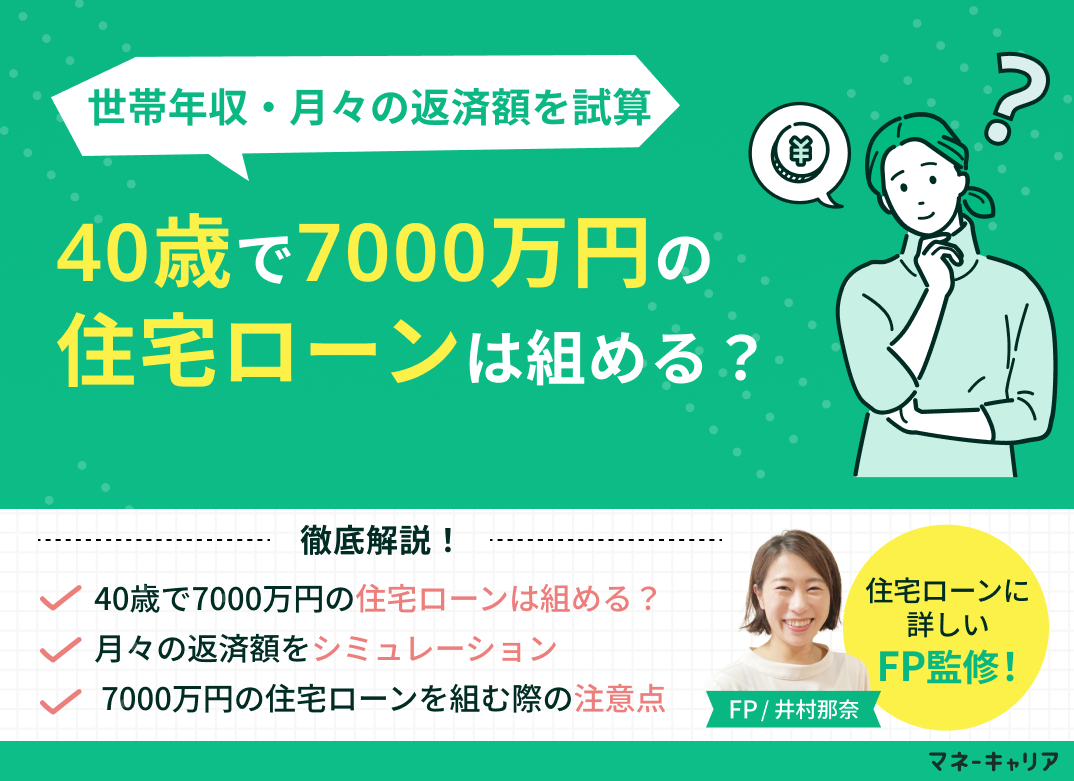 40歳で7000万円の住宅ローンは組める?世帯年収・月々の返済額を試算
40歳で7000万円の住宅ローンは組める?世帯年収・月々の返済額を試算2025-09-17
-
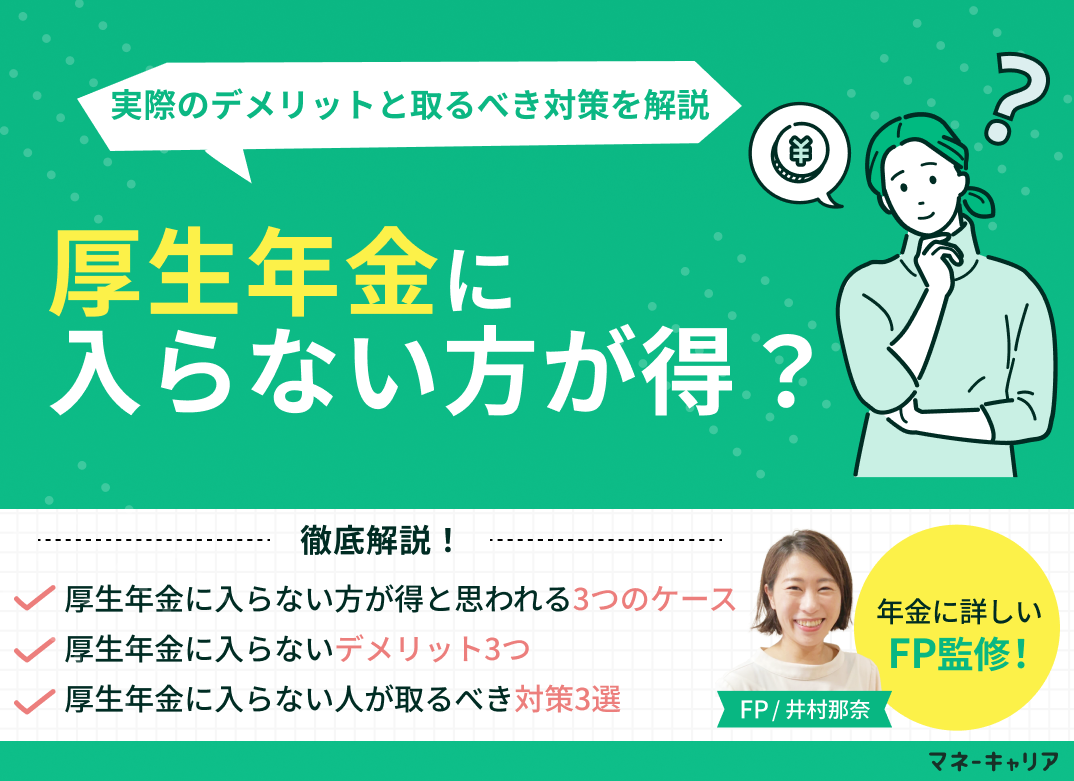 厚生年金に入らない方が得?実際のデメリットと取るべき対策を解説
厚生年金に入らない方が得?実際のデメリットと取るべき対策を解説2025-09-17
-
 住宅ローンで火災保険に入らないのは可能?必要性・保険料を抑えるコツを解説
住宅ローンで火災保険に入らないのは可能?必要性・保険料を抑えるコツを解説2025-09-17
-
 再雇用で厚生年金に加入しないのは可能?加入しないデメリットや対策も解説
再雇用で厚生年金に加入しないのは可能?加入しないデメリットや対策も解説2025-09-17
-
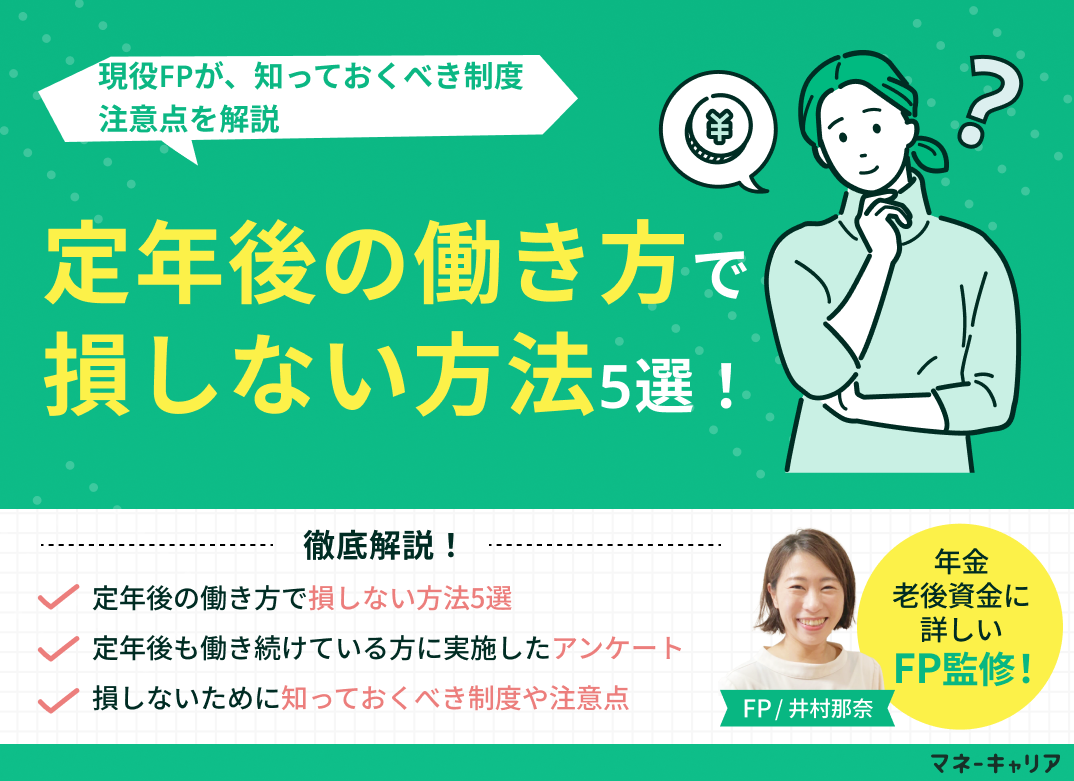 定年後の働き方で損しない方法5選!知っておくべき制度・注意点を解説
定年後の働き方で損しない方法5選!知っておくべき制度・注意点を解説2025-09-17
-
 転職1年目で住宅ローンは組める?審査に通りやすいケースと対策を解説
転職1年目で住宅ローンは組める?審査に通りやすいケースと対策を解説2025-09-17
-
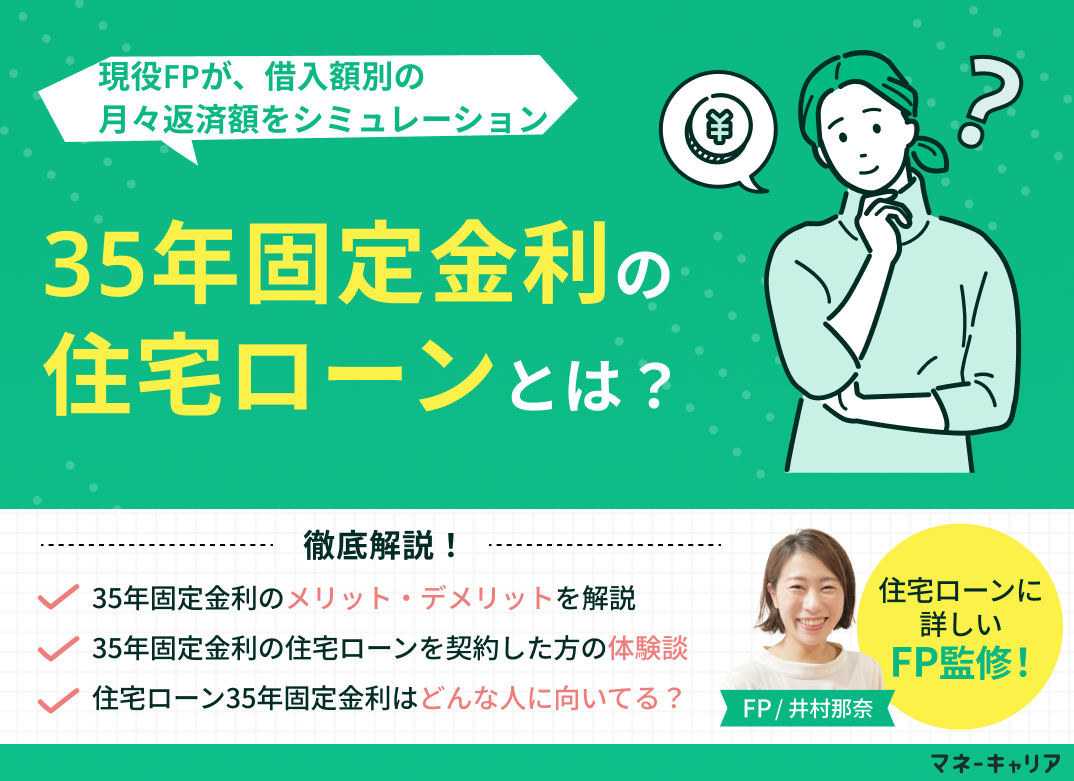 住宅ローン35年固定金利とは?借入額別の月々返済額をシミュレーション
住宅ローン35年固定金利とは?借入額別の月々返済額をシミュレーション2025-09-12
-
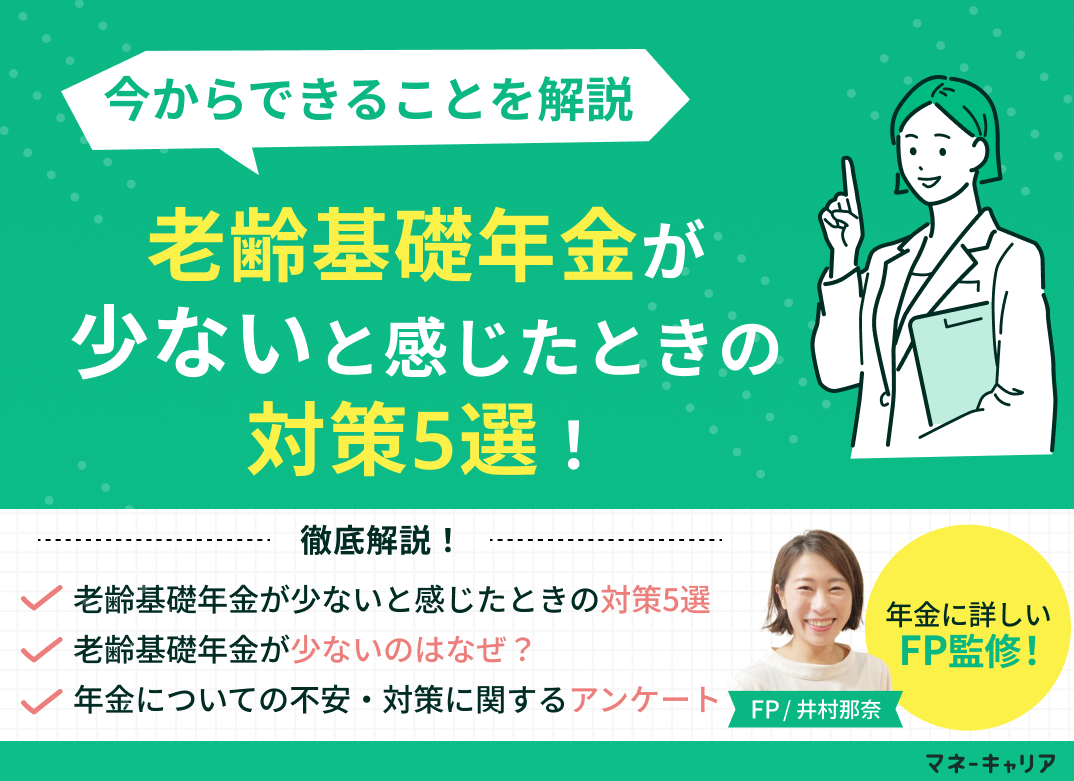 老齢基礎年金が少ないと感じたときの対策5選!今からできることを解説
老齢基礎年金が少ないと感じたときの対策5選!今からできることを解説2025-09-12
-
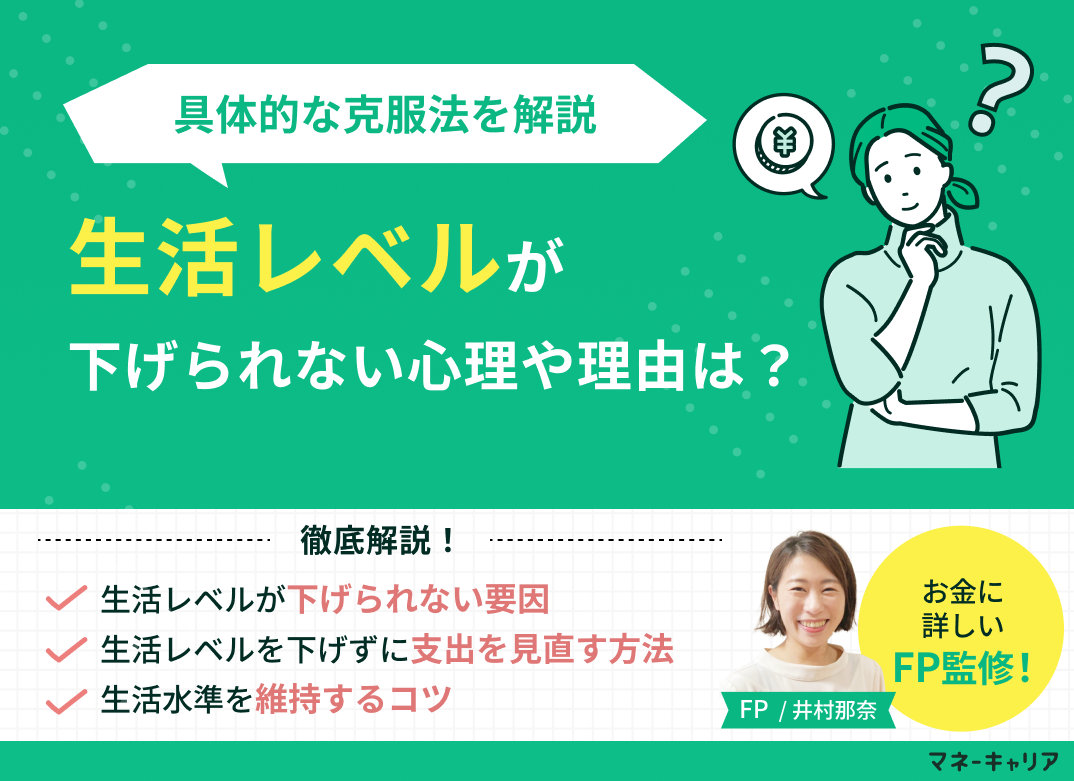 生活レベルが下げられない人の心理や理由とは?具体的な克服法を解説
生活レベルが下げられない人の心理や理由とは?具体的な克服法を解説2025-09-11
-
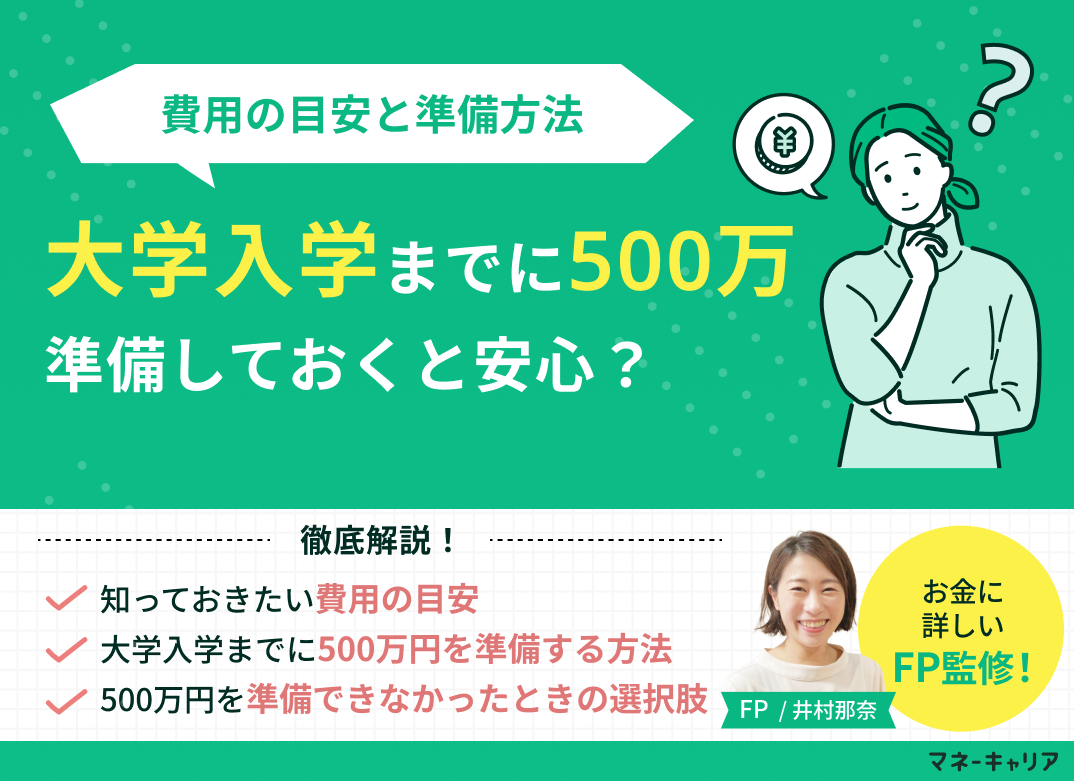 大学入学までに500万円準備しておくと安心?費用の目安と準備方法
大学入学までに500万円準備しておくと安心?費用の目安と準備方法2025-09-11
-
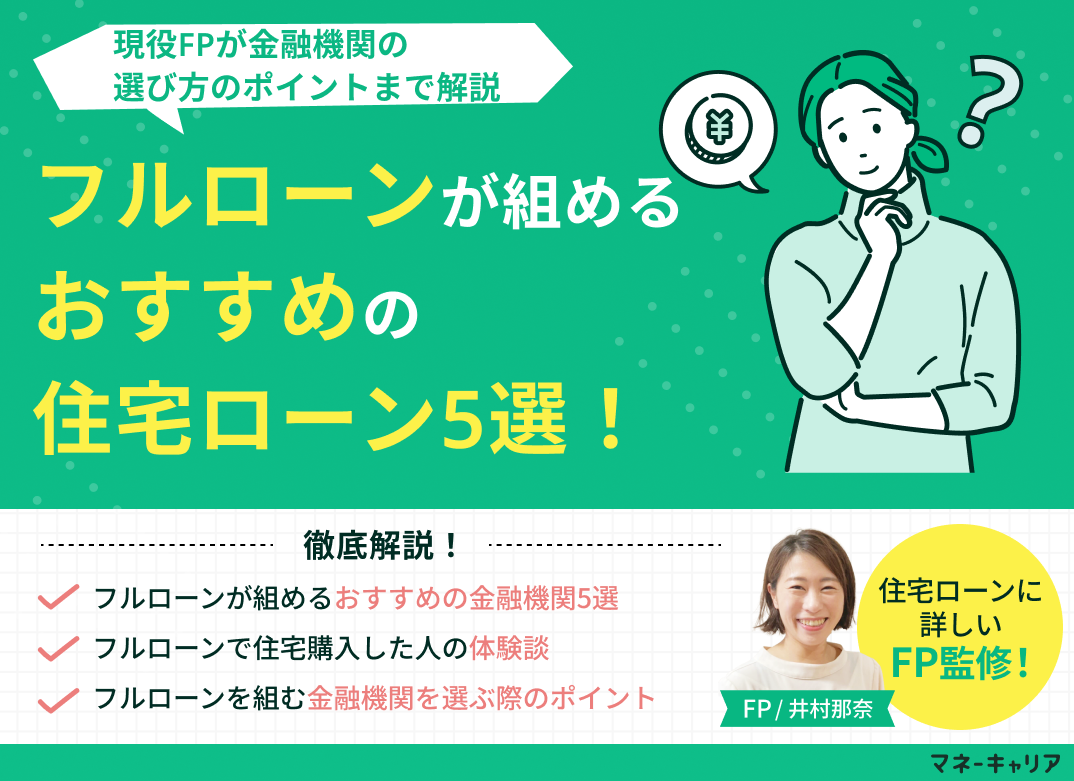 フルローンが組めるおすすめの住宅ローン5選!選び方のポイントも解説
フルローンが組めるおすすめの住宅ローン5選!選び方のポイントも解説2025-09-11
-
 【住宅ローン】オーバーローンはいくらまで借りられる?諸費用込みのリスクも解説
【住宅ローン】オーバーローンはいくらまで借りられる?諸費用込みのリスクも解説2025-09-11
-
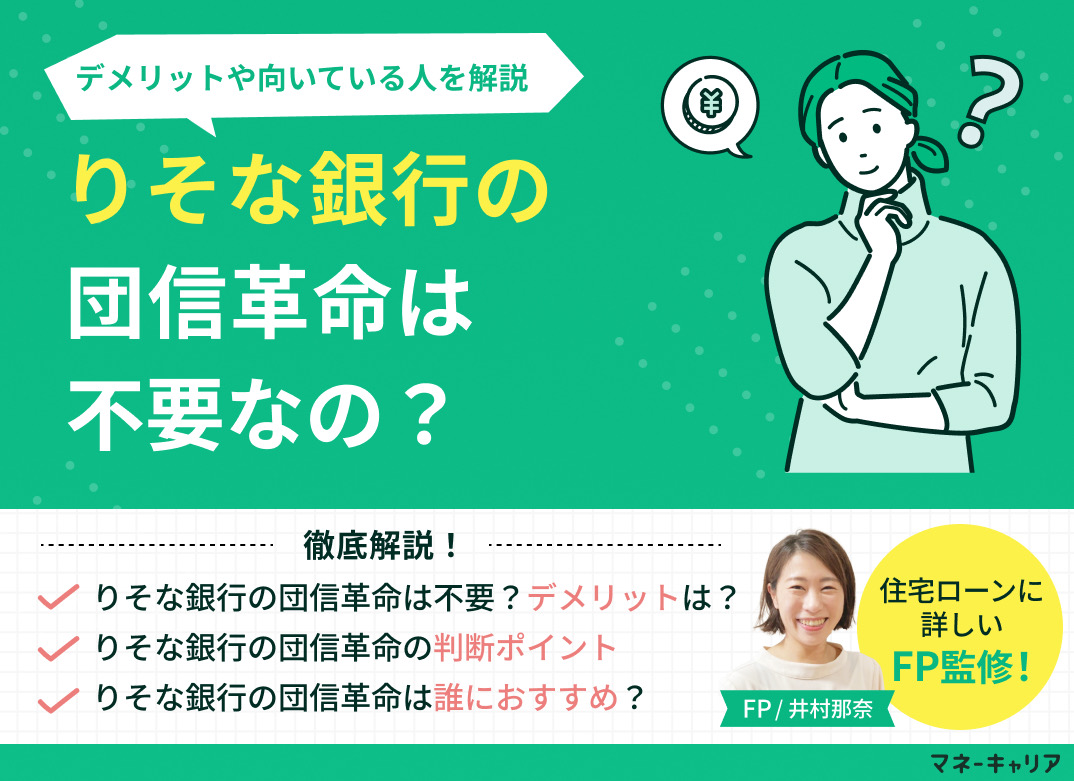 りそな銀行の団信革命はいらない?デメリットは?向いている人を解説
りそな銀行の団信革命はいらない?デメリットは?向いている人を解説2025-09-11
-
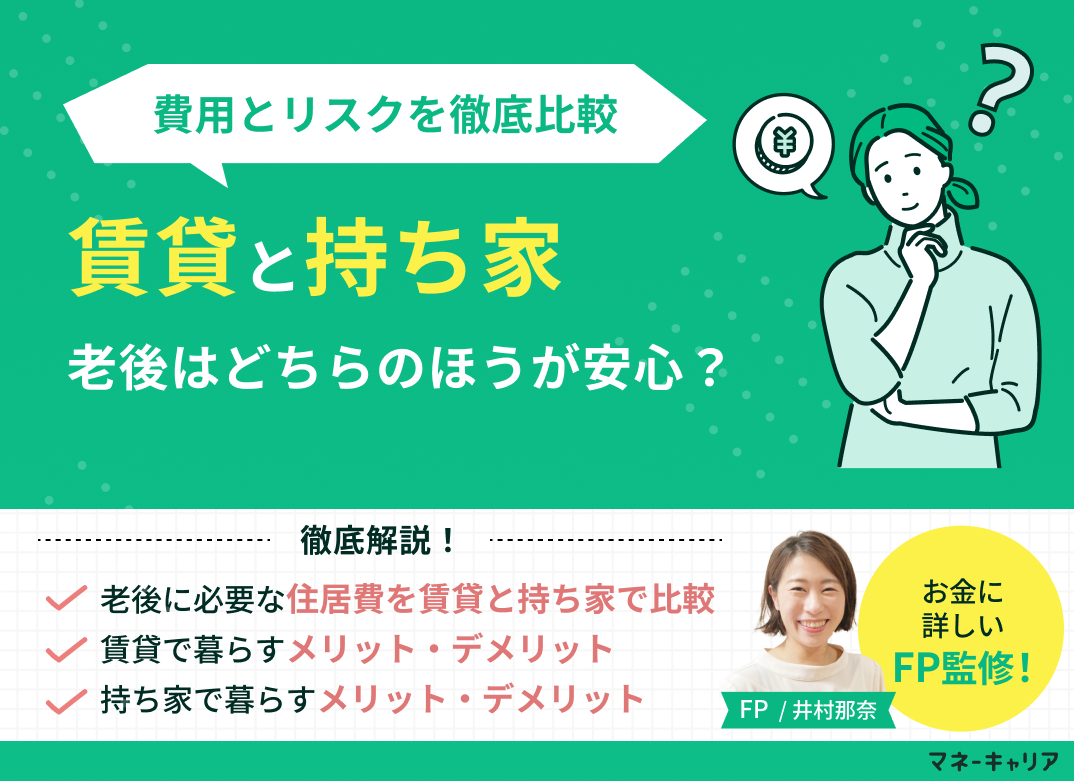 老後は賃貸と持ち家どちらが安心?それぞれの費用とリスクを徹底比較
老後は賃貸と持ち家どちらが安心?それぞれの費用とリスクを徹底比較2025-09-11
-
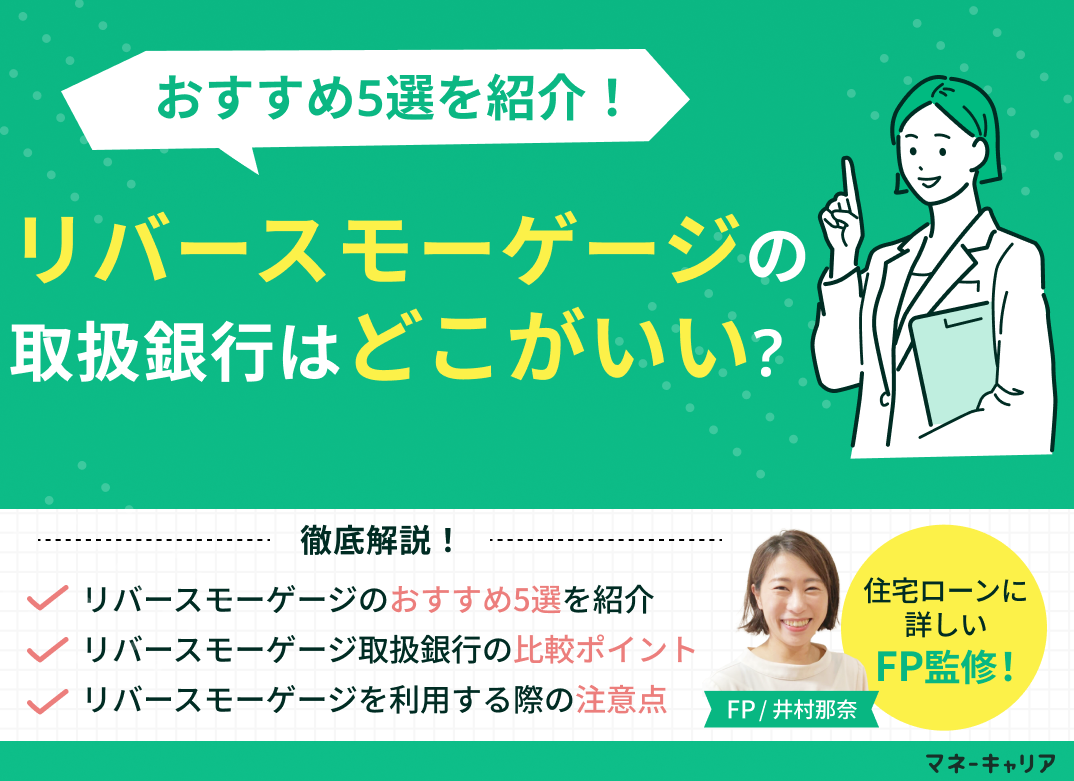 リバースモーゲージの取扱銀行はどこがいい?おすすめ5選を紹介
リバースモーゲージの取扱銀行はどこがいい?おすすめ5選を紹介2025-09-10

人気記事
-
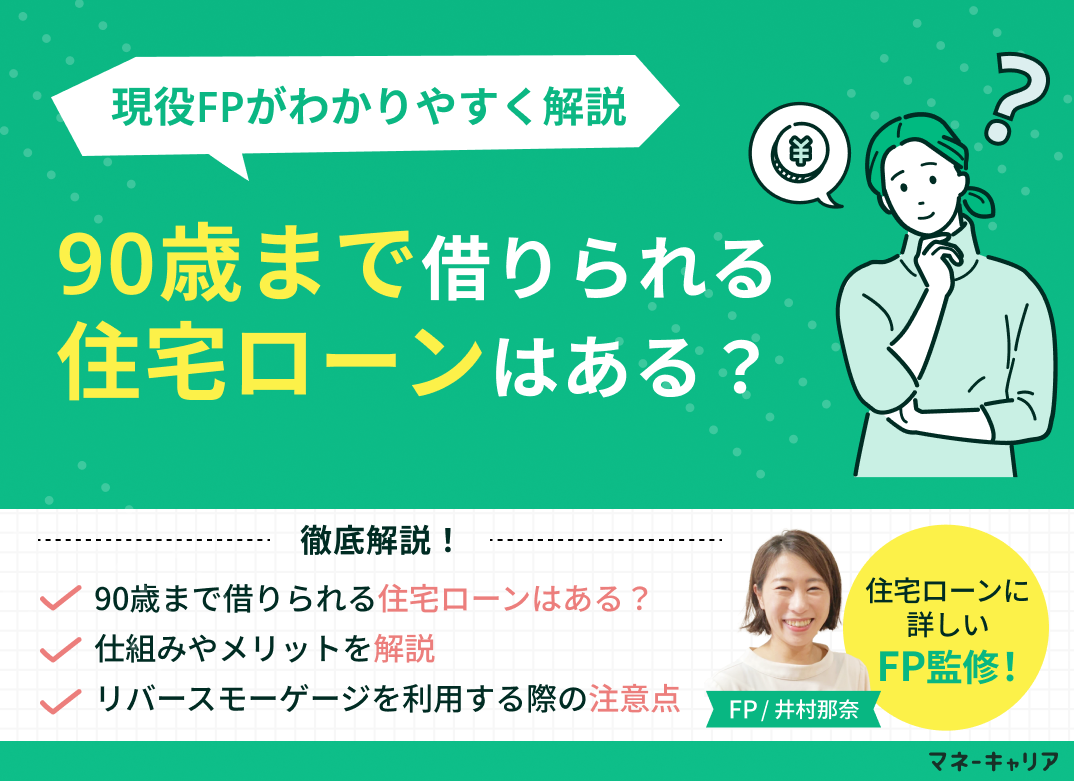 90歳まで借りられる住宅ローンはある?現役FPがわかりやすく解説
90歳まで借りられる住宅ローンはある?現役FPがわかりやすく解説2025-09-18
-
 転職で住宅ローンの金利は変わる?返済中に気をつけたい注意点を解説
転職で住宅ローンの金利は変わる?返済中に気をつけたい注意点を解説2025-09-18
-
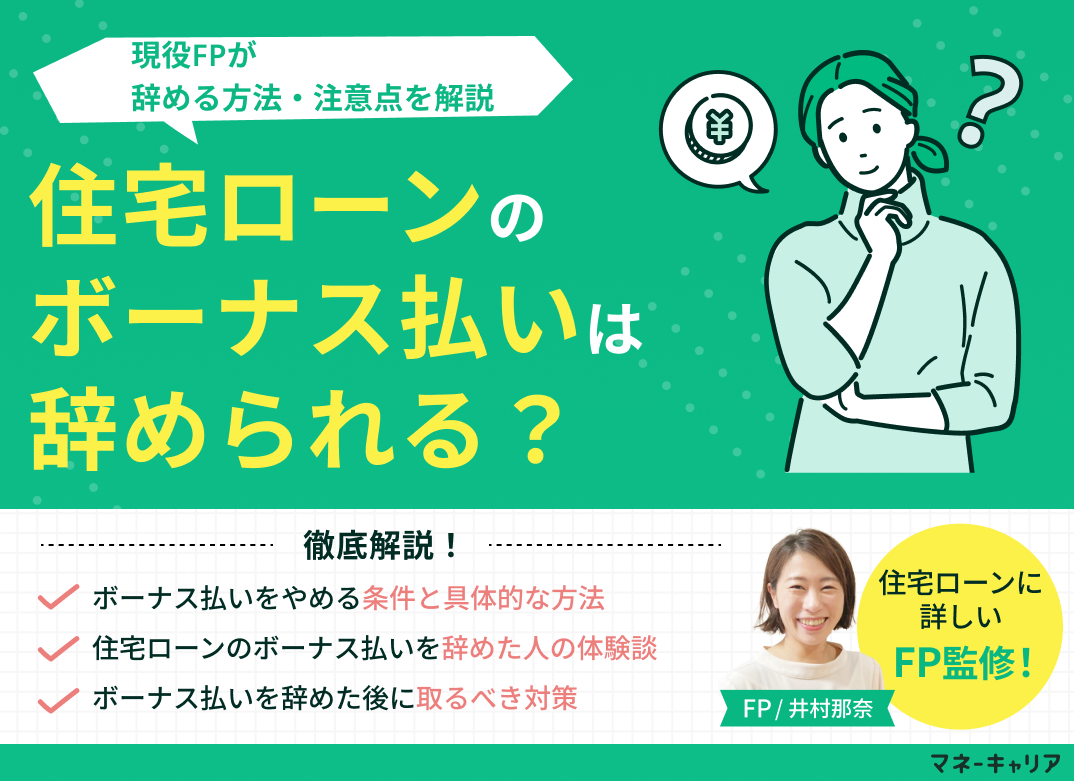 住宅ローンのボーナス払いを辞められる?辞める方法・注意点を解説
住宅ローンのボーナス払いを辞められる?辞める方法・注意点を解説2025-09-17
-
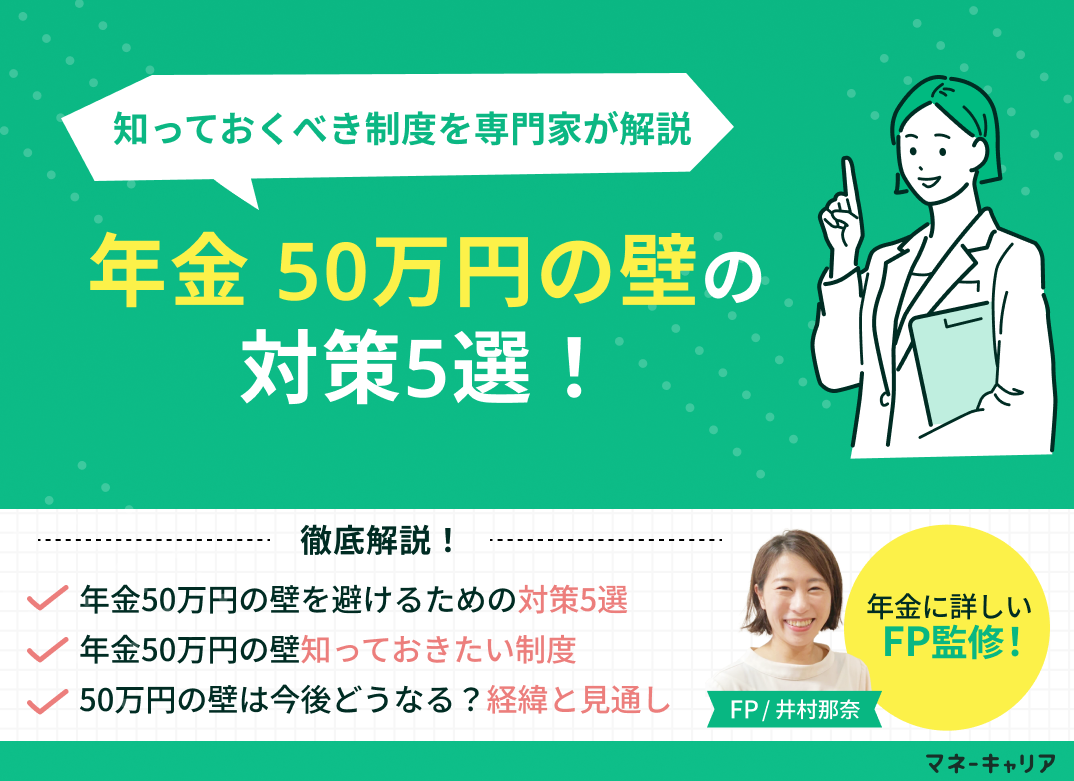 年金「50万円の壁」の対策5選!知っておくべき制度を専門家が解説
年金「50万円の壁」の対策5選!知っておくべき制度を専門家が解説2025-09-17
-
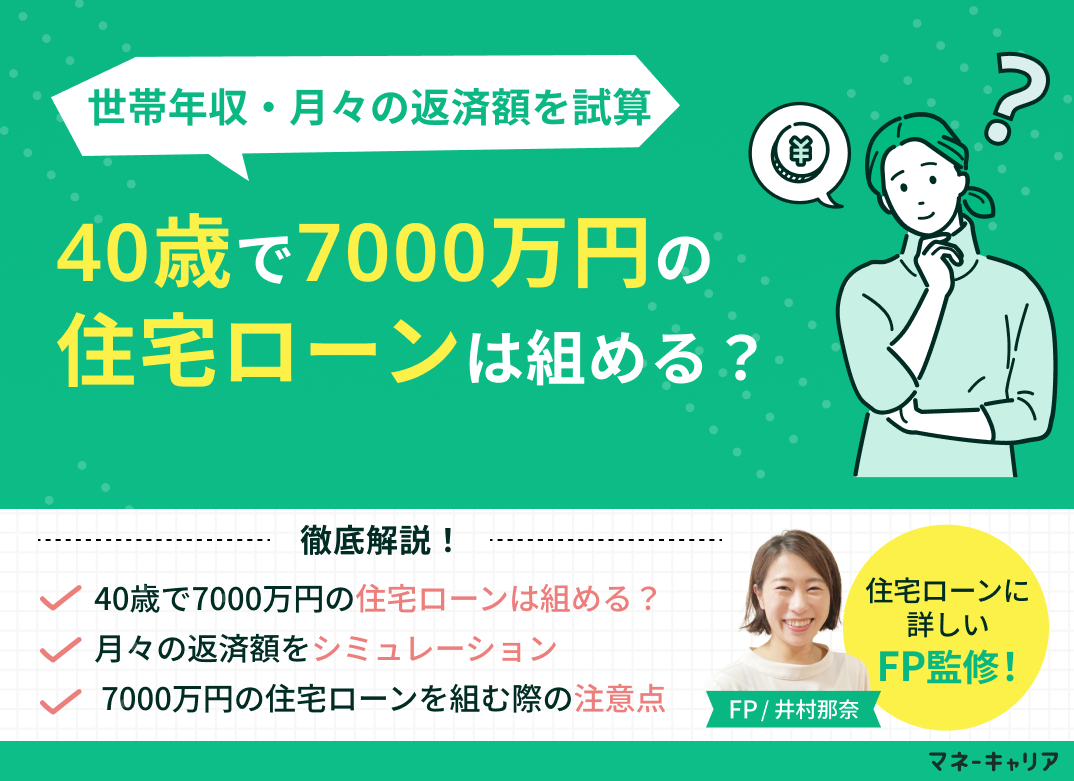 40歳で7000万円の住宅ローンは組める?世帯年収・月々の返済額を試算
40歳で7000万円の住宅ローンは組める?世帯年収・月々の返済額を試算2025-09-17
-
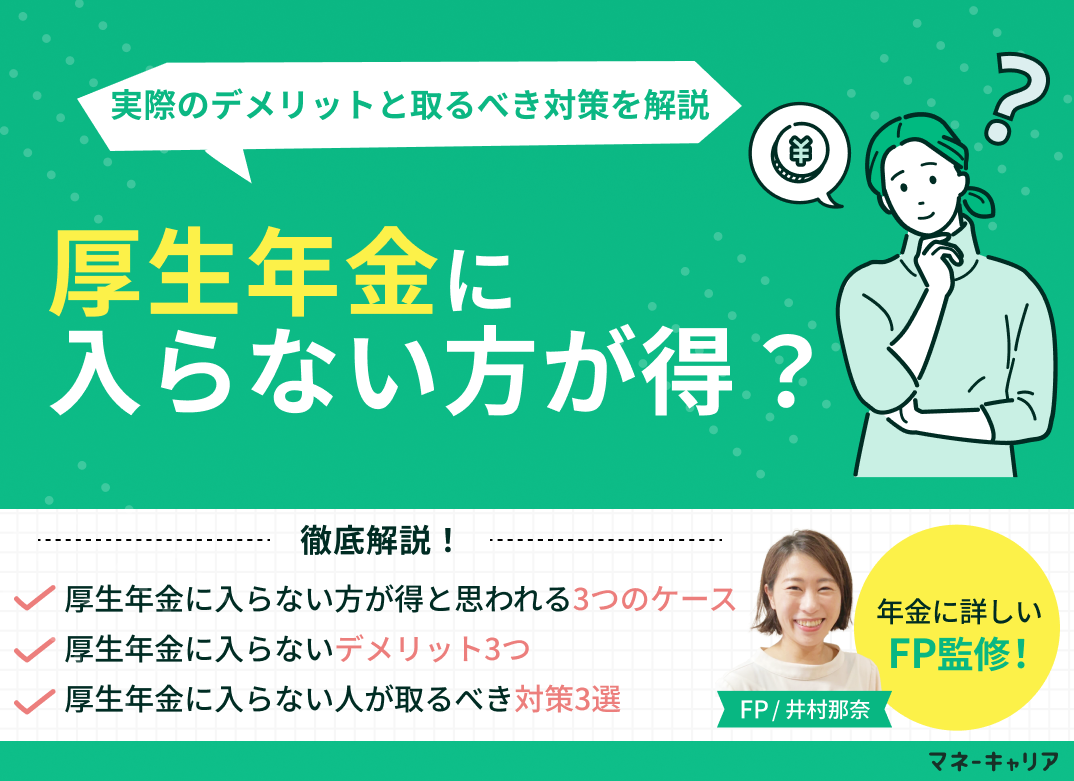 厚生年金に入らない方が得?実際のデメリットと取るべき対策を解説
厚生年金に入らない方が得?実際のデメリットと取るべき対策を解説2025-09-17
-
 住宅ローンで火災保険に入らないのは可能?必要性・保険料を抑えるコツを解説
住宅ローンで火災保険に入らないのは可能?必要性・保険料を抑えるコツを解説2025-09-17
-
 再雇用で厚生年金に加入しないのは可能?加入しないデメリットや対策も解説
再雇用で厚生年金に加入しないのは可能?加入しないデメリットや対策も解説2025-09-17
-
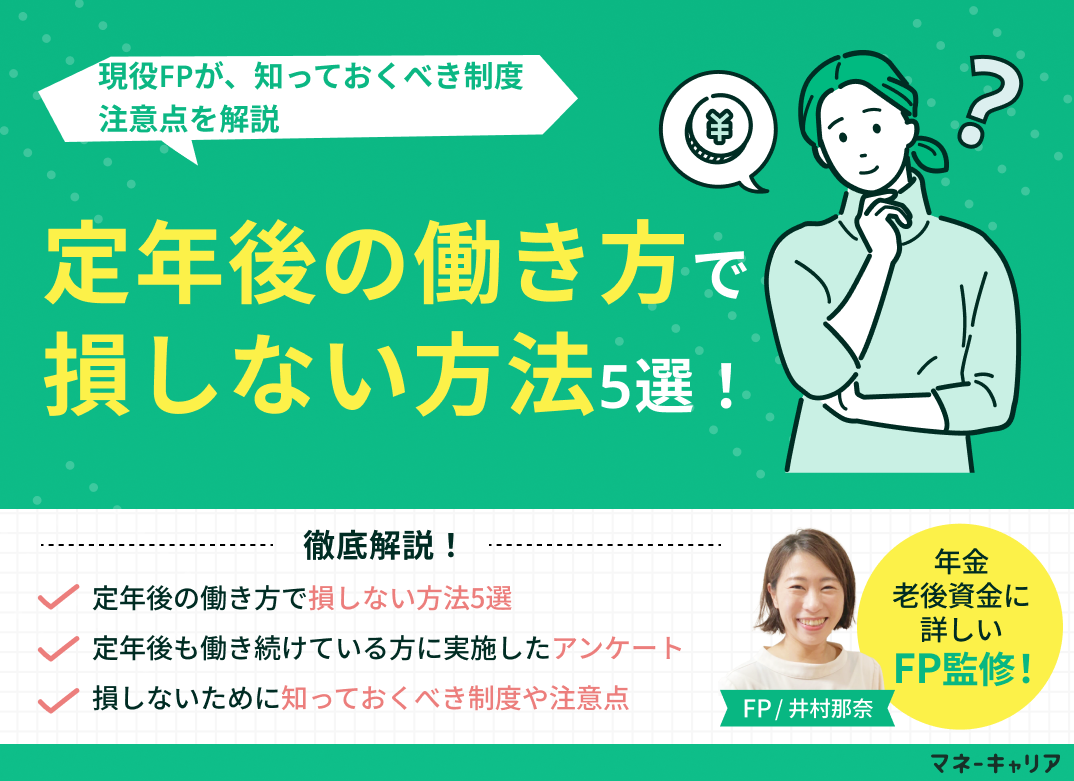 定年後の働き方で損しない方法5選!知っておくべき制度・注意点を解説
定年後の働き方で損しない方法5選!知っておくべき制度・注意点を解説2025-09-17
-
 転職1年目で住宅ローンは組める?審査に通りやすいケースと対策を解説
転職1年目で住宅ローンは組める?審査に通りやすいケースと対策を解説2025-09-17
-
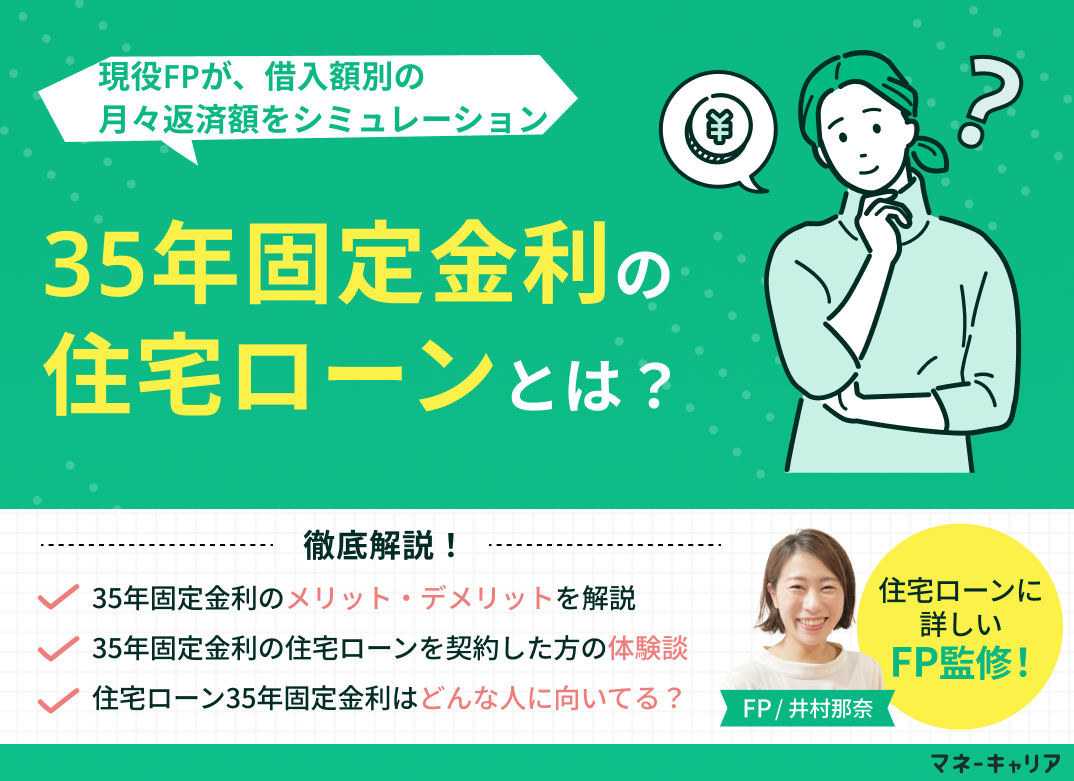 住宅ローン35年固定金利とは?借入額別の月々返済額をシミュレーション
住宅ローン35年固定金利とは?借入額別の月々返済額をシミュレーション2025-09-12
-
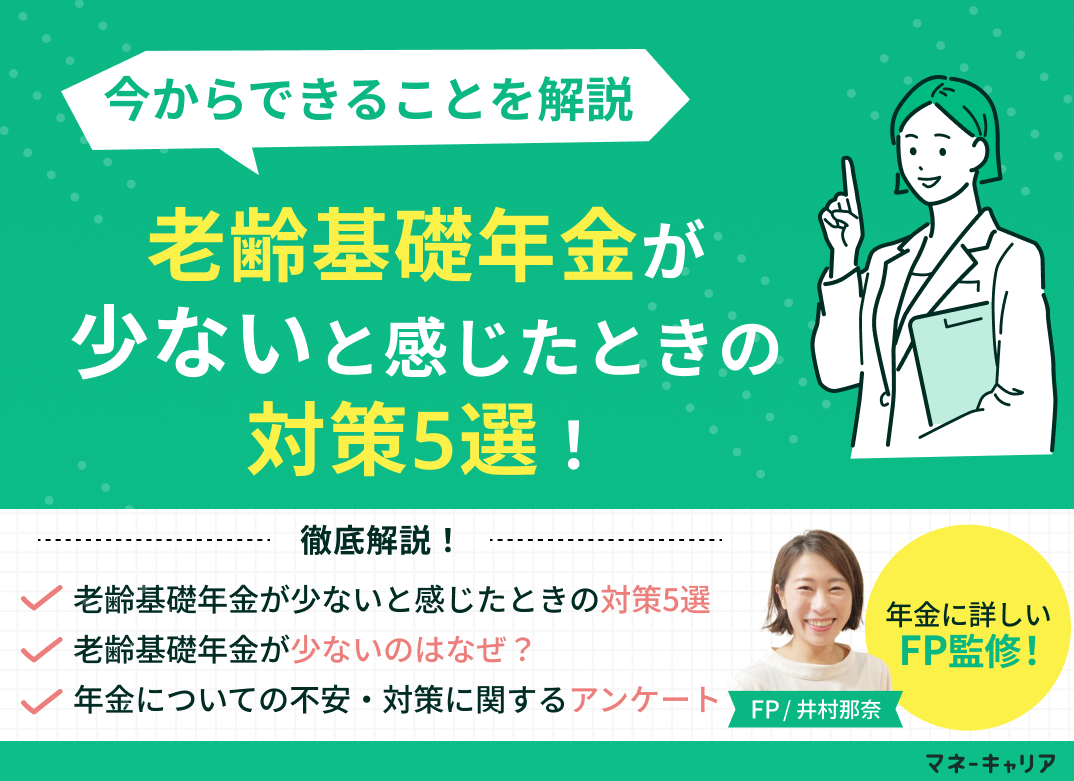 老齢基礎年金が少ないと感じたときの対策5選!今からできることを解説
老齢基礎年金が少ないと感じたときの対策5選!今からできることを解説2025-09-12
-
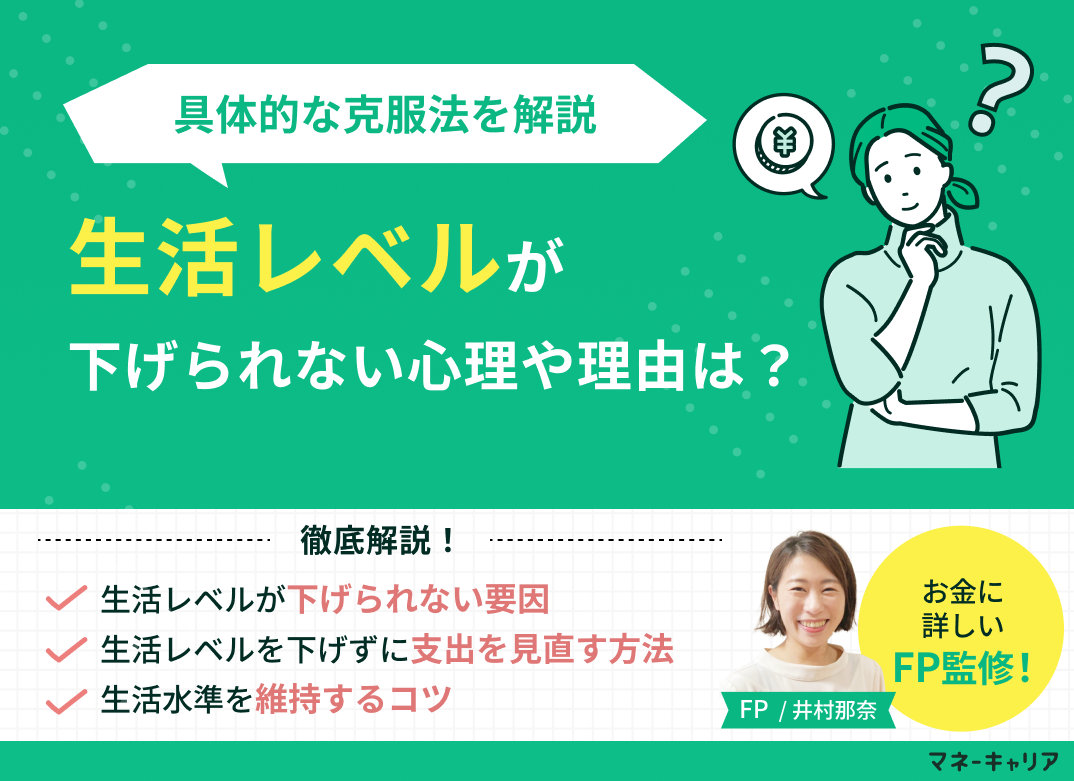 生活レベルが下げられない人の心理や理由とは?具体的な克服法を解説
生活レベルが下げられない人の心理や理由とは?具体的な克服法を解説2025-09-11
-
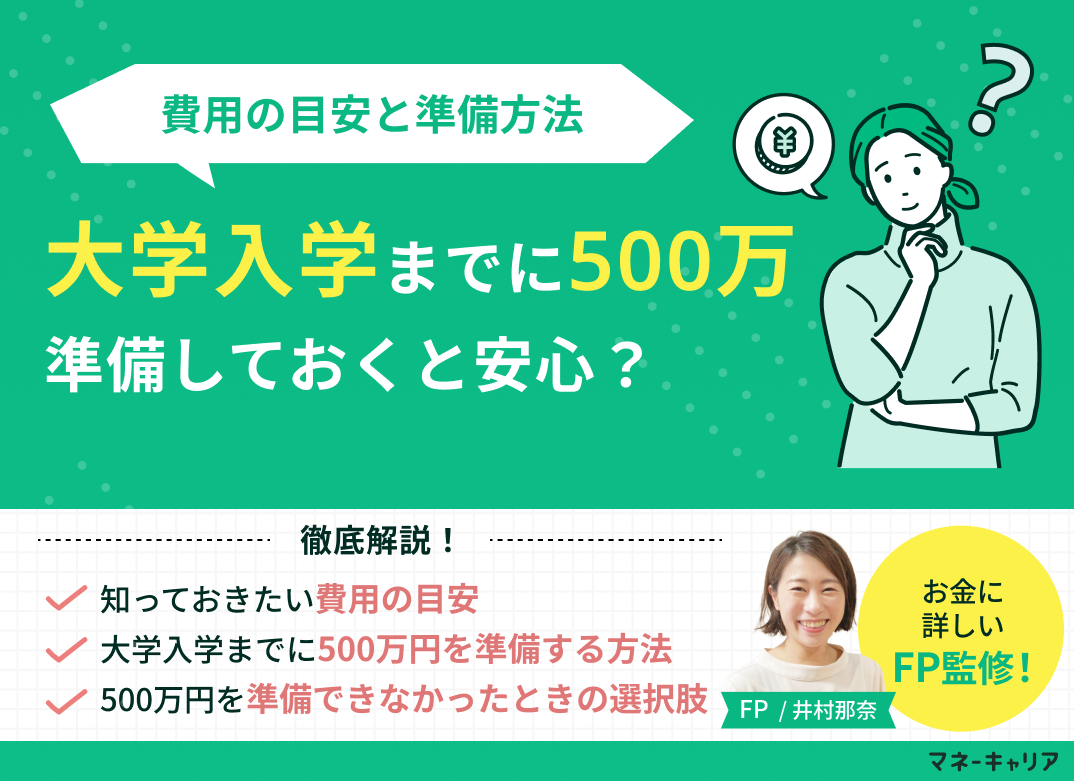 大学入学までに500万円準備しておくと安心?費用の目安と準備方法
大学入学までに500万円準備しておくと安心?費用の目安と準備方法2025-09-11
-
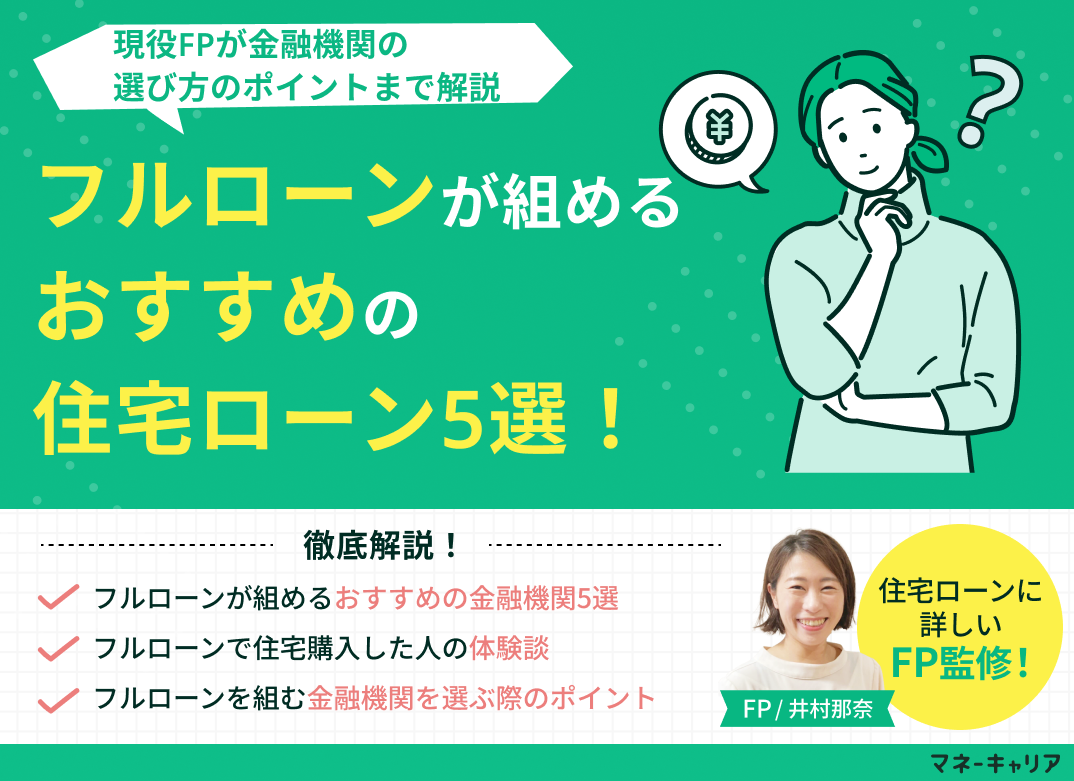 フルローンが組めるおすすめの住宅ローン5選!選び方のポイントも解説
フルローンが組めるおすすめの住宅ローン5選!選び方のポイントも解説2025-09-11
-
 【住宅ローン】オーバーローンはいくらまで借りられる?諸費用込みのリスクも解説
【住宅ローン】オーバーローンはいくらまで借りられる?諸費用込みのリスクも解説2025-09-11
-
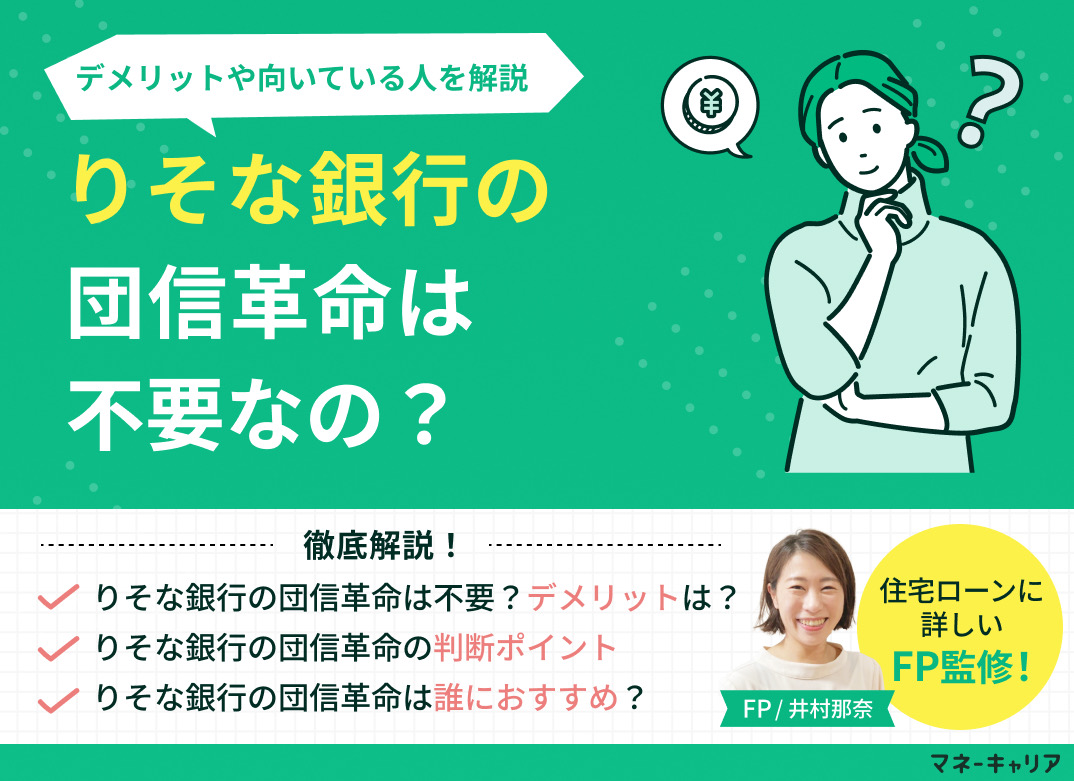 りそな銀行の団信革命はいらない?デメリットは?向いている人を解説
りそな銀行の団信革命はいらない?デメリットは?向いている人を解説2025-09-11
-
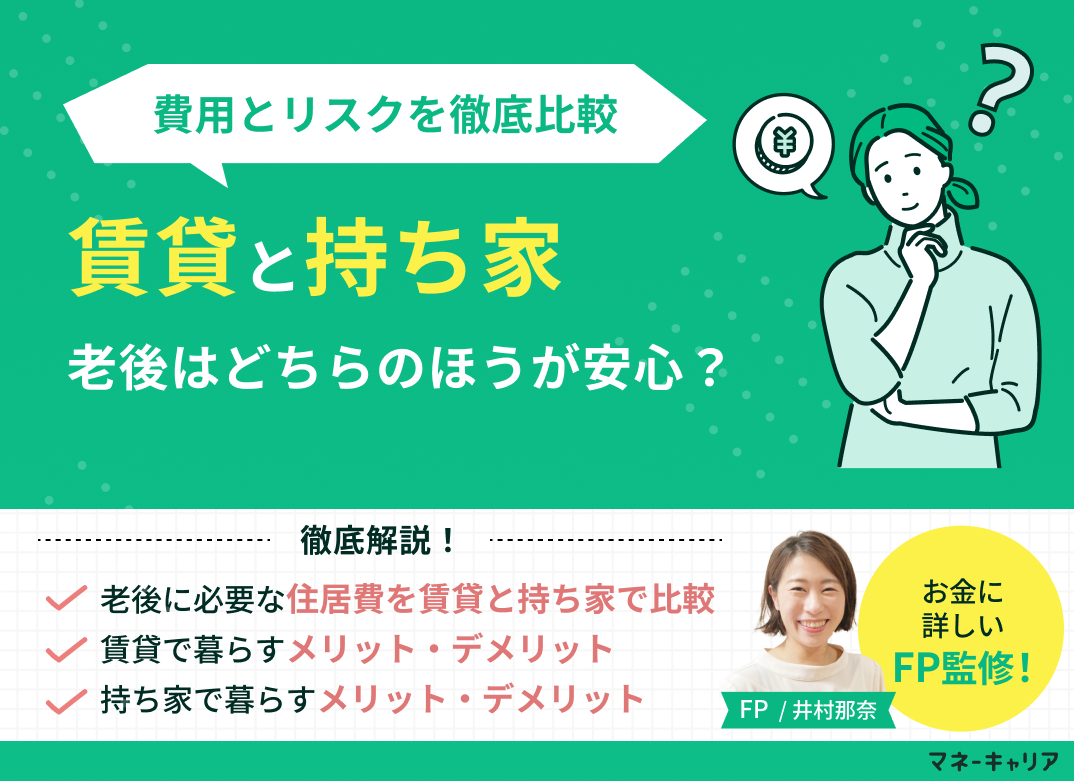 老後は賃貸と持ち家どちらが安心?それぞれの費用とリスクを徹底比較
老後は賃貸と持ち家どちらが安心?それぞれの費用とリスクを徹底比較2025-09-11
-
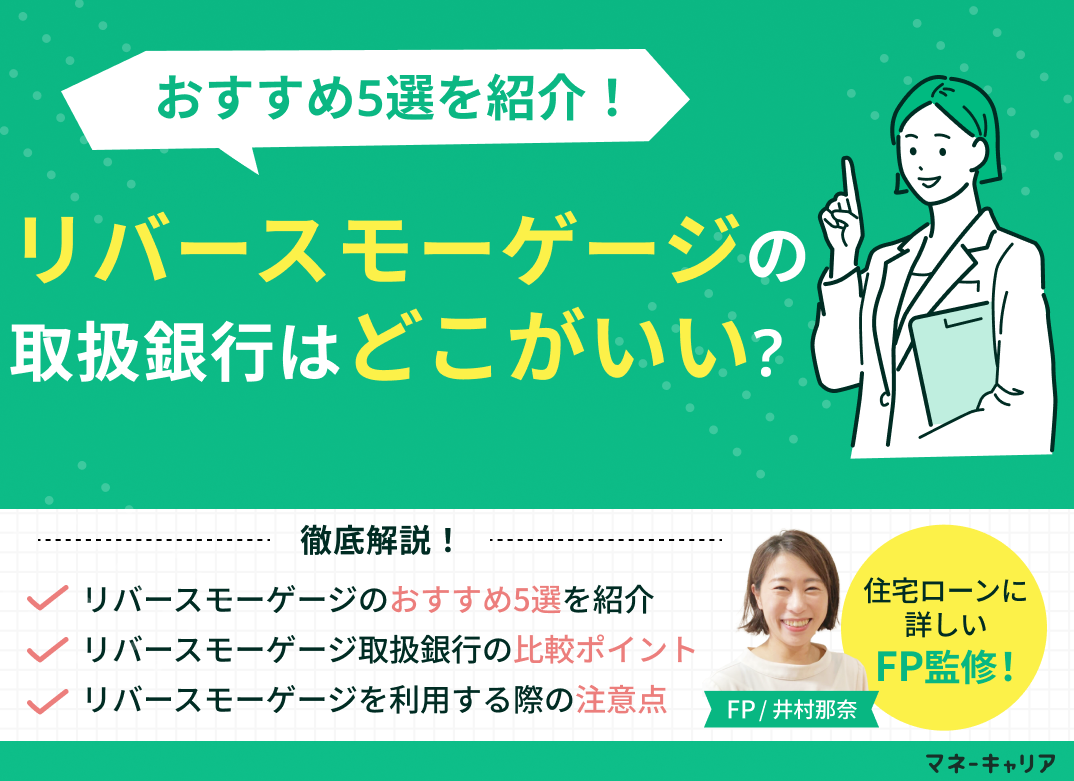 リバースモーゲージの取扱銀行はどこがいい?おすすめ5選を紹介
リバースモーゲージの取扱銀行はどこがいい?おすすめ5選を紹介2025-09-10