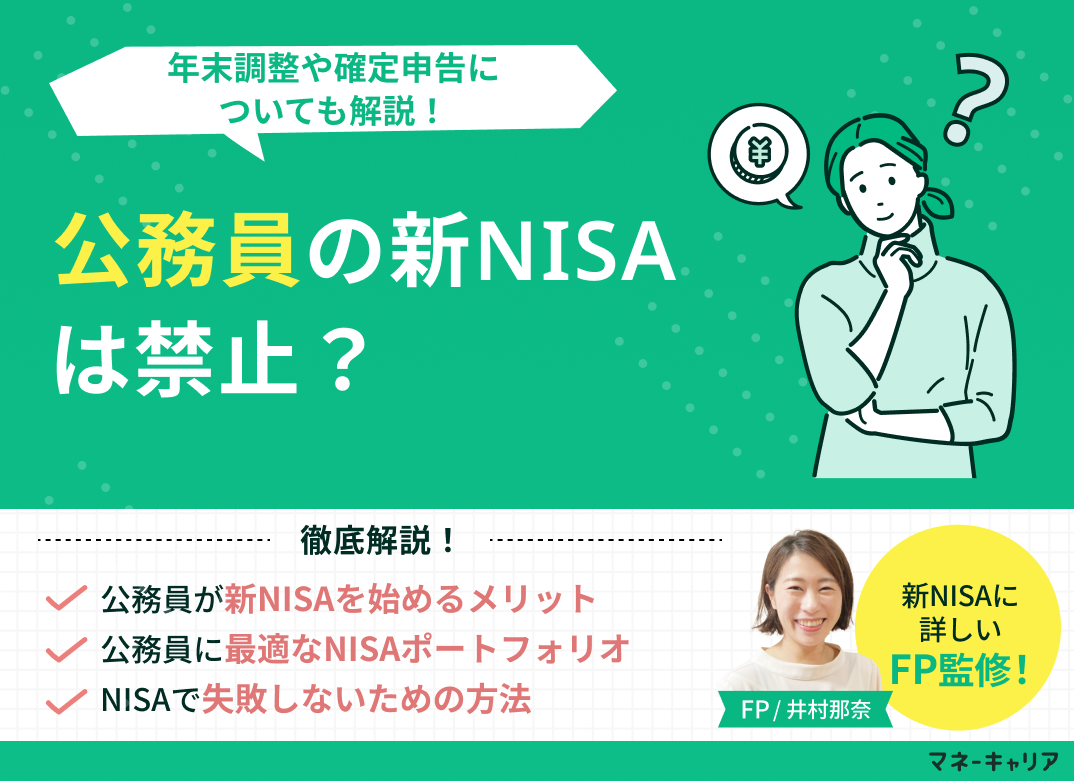
「公務員だけど新NISA(つみたてNISA)は利用できるの?」
「公務員の新NISA(つみたてNISA)は禁止されていないか心配」
とお悩みではないでしょうか。
- 結論、公務員でも新NISA(つみたてNISA)は利用でき、副業には該当しないため安心して始められます。ただし公務員特有のNISAの注意点があるため慎重に検討することが重要です。
この記事では公務員のNISA利用における注意点や最適な運用方法を解説します。
この記事を読むことで、公務員でも安心してNISAを活用した資産形成ができるようになり、将来の資産作りに役立てられるので、ぜひご覧ください。
内容をまとめると
- 公務員でも新NISAは利用可能で、年末調節や確定申告も必要ないため積極的に利用していきたい資産運用方法
- 「NISAを効果的に活用したい」「公務員ならではのNISAの始め方を知りたい」そんな方はマネーキャリアのプロ(FP)に無料相談して、将来どれくらいお金が増えそうかシミュレーションしてもらおう!
- 初めての資産運用でも0から教えてもらえるから安心。今のうちに一度チェックしておくことが、老後の安心につながります!
- FP相談で、あなたの老後資金計画が”足りるか足りないか”がはっきり見えます!

監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
NISAは公務員でも利用できる!
結論、NISAは公務員でも利用できる制度です。
公務員法や地方公務員法では、株式投資などの営利目的の活動に一定の制限がありますが、NISAを利用した資産形成は問題ありません。
NISAは個人の資産形成を支援する国の制度であり、公務員の副業規制の対象外とされています。
頻繁な売買を繰り返すデイトレードのような取引は、本業に支障をきたす可能性がありますが、長期的な資産形成を目的とした積立投資であれば、公務員でも安心してNISAを活用できます。
以下では、NISAの仕組みや公務員が運用するメリットについて詳しく解説します。
NISAの仕組み・メリット
公務員にとってNISAは非常に有効な資産形成手段です。
NISAは「少額投資非課税制度」の略称で、投資で得た利益が非課税になる国の制度です。
以下の表でNISAの詳細をまとめました。
| 項目 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
|---|---|---|
| 年間投資上限額 | 120万円 | 240万円 |
| 生涯投資上限額 | 1,800万円 | 1,200万円 |
| 非課税期間 | 無期限 | 無期限 |
| 対象商品 | 投資信託・ETF | 株式・投資信託・ETF |
公務員にとってNISAの最大のメリットは、安定した収入を活かした長期積立投資ができることです。
通常の投資では利益に20.315%の税金がかかりますが、NISA口座なら非課税のため、公務員の堅実な資産形成に最適です。
また、公務員は退職金制度が充実しているため、NISAを老後資金の上乗せとして活用することで、より豊かな老後生活を実現できます。
年末調節や確定申告は必要ない
NISAでは年末調整や確定申告は原則不要です。
確定申告とは1年間に得た所得と、所得に対する課税額を計算し、税務署に報告・納税する作業のことであり、NISA口座での投資による利益は非課税のため、確定申告の対象外となります。
これは公務員にとって大きなメリットで、複雑な税務手続きを気にすることなく投資を始められます。
ただし、NISA口座以外での投資や、年間20万円を超える副業収入がある場合は確定申告が必要になる場合があります。
公務員の方は副業規制もあるため、NISA以外の投資を行う際は事前に職場の規定を確認することをおすすめします。
公務員に最適なNISAポートフォリオ(資産配分)
公務員に最適なNISAポートフォリオは、安定性を重視した資産配分がおすすめです。
公務員は収入が安定している一方、大幅な昇給は期待しにくいため、リスクを抑えた長期的な資産形成が適しています。
具体的には、国内株式30%、先進国株式40%、国内債券20%、先進国債券10%といったバランス型の配分が考えられます。
また、公務員は退職金制度が充実しているため、老後資金の一部は既に確保されていると考え、NISAではややリスクを取った運用も可能です。
年代別では、20~30代は株式比重を高め、40代以降は債券比重を増やすなど、ライフステージに応じた調整も重要です。
公務員がNISAを始めるための準備3ステップ
公務員がNISAを始めるための準備は、以下の3つのステップで進められます。
まず、口座開設する金融機関を決めることから始めます。
ネット証券は手数料が安く商品ラインナップも豊富なため、初心者にはおすすめです。
次に、必要書類を揃えて口座開設を行います。
本人確認書類とマイナンバー確認書類があれば、オンラインで簡単に手続きできます。
最後に、購入したい商品を選び投資金額を設定します。
初心者の場合は、リスクを分散できる投資信託から始めることをおすすめします。
これらのステップを踏むことで、公務員でも安心してNISAを始められます。
公務員のNISAでお悩みならFP相談で解消しよう!
公務員のNISA活用については、個人の状況によって最適な方法が大きく異なります。
年齢、家族構成、将来の計画、リスク許容度などを総合的に考慮して、適切な投資戦略を立てる必要があります。
また、公務員特有の退職金制度や共済年金との兼ね合いも考慮しなければなりません。
このような複雑な判断を一人で行うのは難しく、専門家のアドバイスを受けることで、より効率的で安全な資産形成が可能になります。
NISAで失敗しないための方法
NISAで失敗しないためには、適切な資金管理とリスク分散が重要です。
具体的な方法は以下のとおりです。
投資は元本保証がないため、生活に必要な資金と投資資金を明確に分けて管理する必要があります。
また、一つの商品や地域に集中投資するのではなく、複数の資産に分散投資することでリスクを軽減できます。
以下では、NISA投資で失敗を避けるための具体的な方法を解説します。
生活資金と投資資金を分けて管理する
NISAで失敗しないためには、生活資金と投資資金を分けて管理することが重要です。
投資は元本保証がないため、生活に必要な資金まで投資に回してしまうと、急な出費や市場下落時に困ることになります。
一般的に、生活費の3~6ヶ月分は緊急時資金として預貯金で確保し、それ以外の余裕資金で投資を行うことがおすすめです。
公務員の場合、収入が安定しているため、緊急時資金は3ヶ月分程度でも十分な場合があります。また、投資資金も一度に大きな金額を投資するのではなく、毎月一定額を積み立てる方法がリスクを抑えられます。
リスク分散を意識する
NISA投資では、リスク分散を意識することが失敗を避けるために重要です。
一つの商品や地域、業種に集中投資すると、その分野で問題が起きた時に大きな損失を被る可能性があります。
例えば、日本株だけに投資していると、日本経済の低迷時に資産価値が大きく下がるリスクがあります。
そのため、国内外の株式や債券、不動産投資信託(REIT)など、異なる資産クラスに分散投資することが重要です。
また、時間分散も効果的で、毎月一定額を積み立てることで購入タイミングのリスクを軽減できます。
FPに相談して最適な運用プランを決める【おすすめ】
NISAで失敗しないための効果的な方法は、FPに相談して最適な運用プランを決めることです。
専門家のアドバイスを受けることで、自分の状況に合った投資戦略を立てることができ、感情的な判断による失敗を避けることができます。
特に公務員の方は、退職金制度や共済年金などの特殊な制度があるため、それらを考慮した総合的な資産形成プランが必要です。
FPは、あなたのライフプラン、リスク許容度、投資目標などを総合的に分析し、最適なポートフォリオを提案してくれます。また、定期的な見直しやリバランスのアドバイスも受けられるため、一度利用してみるのがおすすめです。
公務員にもNISAはおすすめ【まとめ】
ここまで、公務員のNISA利用の可否、制度のメリット、最適なポートフォリオ、失敗しないための方法などを紹介してきました。内容をまとめると以下のとおりです。
- 公務員でもNISAは利用可能で、職業による制限はない
- NISA口座での投資は年末調整や確定申告が不要
- 安定収入を活かした長期積立投資が公務員に適している
- リスク分散と生活資金の確保が失敗しないポイント
- 専門家のアドバイスを受けることで最適な運用が可能
しかし、NISA投資では商品選びの失敗や過度なリスクを抱えることによる損失などのリスクがあります。
そこでおすすめなのが、マネーキャリアのNISA無料相談窓口への相談です。
マネーキャリアでは、公務員の方に特化した資産形成プランの提案、最適な投資商品の選び方をアドバイスいたします!
相談料は無料なのでお気軽にご相談ください!




















